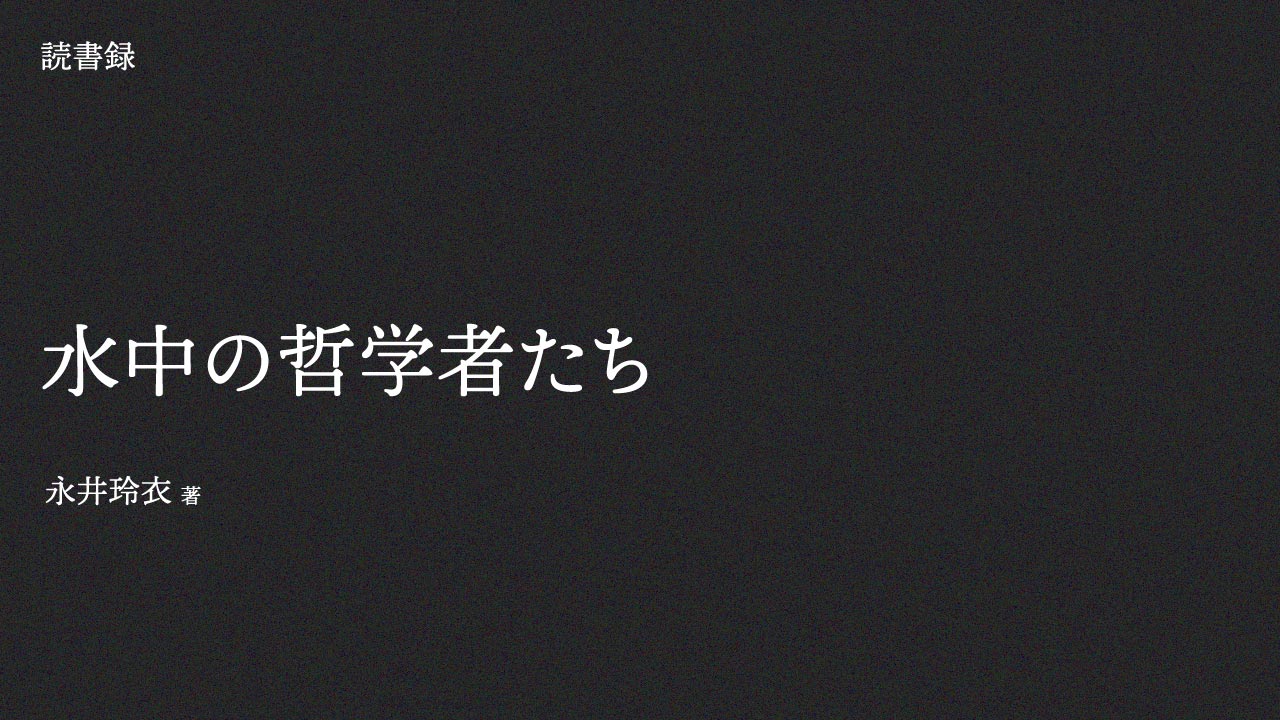「問いは、偉大である。もろく小さなわたしでは到底かなわないほどに、堅固で美しい。人々の口からまろび出る問いは、いろいろなかたちをしている。」
本書の冒頭に記された一節です。
私たちは、「本当は分かりあえない」ということをどこかで知っていながらも、それでもなお「分かりあおうとする」ことを手放すことができません。
分かりあえなさに打ちひしがれるのではなく、分かりあおうとする姿勢そのものが、人間の柔らかさや危うさ、そして時に深い共感の可能性を育むのではないか。本書を読みながら、そんなことを考えさせられました。
永井さんの言葉は、どこまでも静かでやさしいのに、ときおり心の奥深くを射抜くような強さを持っていました。その穏やかで澄んだ筆致に導かれながら、「問い」や「対話」という行為のもつ力について、私なりに思いを巡らせてみたいと思います。
恐れをともなう営みとしての対話
対話というのはおそろしい行為だ。他者に何かを伝えようとすることは、離れた相手のところまで勢いをつけて跳ぶようなものだ。たっぷりと助走をつけて、勢いよくジャンプしないと相手には届かない。あなたとわたしの間には、大きくて深い隔たりがある。だから、他者に何かを伝えることはリスクでもある。跳躍の失敗は、そのまま転倒を意味する。ということは、他者に何かを伝えようとそもそもしなければ、硬い地面に身体を打ちつけることもない。もしくは、せっかく手を差し伸べてくれた相手を、うっかりバスから引き倒して傷つけてしまうこともない。
〜
他者とわかりあうことはできません、他者に何かを伝えきることはできません、という感覚は、広く共有されているように思う。わかりあうことができないからこそ面白い、とか、他者は異質だからこそ創造的なものが生まれる、とかいう言説もあふれている。その通りだ。その通り。全くもって、完璧に、同意する。だがわたしはあえて言いたい。 それでもなお、わたしはなお、あなたとは完全にわかりあえないということに絶望する。
〜
完全に通じあわなくてもいい。わかりあうことはゴールではない。わかりあうのではない、わかりあおうとしあうこと。互いに空を飛ぶことを夢見ること、それだけでいい。
〜
信頼できるひとに向けてならまだしも、見知らぬひとに向けて飛翔するのは、本当にこわいことだ。無防備で、無謀で、おこがましいことだ。だからこそ、対話はおそろしいものでありつづける。
私はこれまで、対話は積極的に行うべきものであり、そこにリスクがあるということについては深く考えたことはありませんでした。もちろん、相手への敬意や誠実さをもって語り合うことが大前提であると信じてきましたし、その姿勢さえあれば、対話はおおむね健やかに成立するものだと思っていたのです。
しかし、対話という行為が本質的に「跳躍」であり、失敗や痛みの可能性をはらんだものであることに、あらためて気づかされました。対話とは、こちらの思いや考えを、助走をつけて相手のもとへ飛ばすようなこと。届くかどうかはわからないし、うっかり相手を傷つけてしまうこともある。そう考えると、対話を恐れて距離をとってしまう人がいるのも、無理のないことなのかもしれません。
対話はたしかに、恐ろしいものです。けれども、そこから逃げていては、何も始まりません。ときには、自分自身の内側の脆さがあらわになるような、不意に感情の地雷を踏んでしまうような瞬間もあります。あるいは、こちらの意図が届かず、誤解され、拒まれてしまうかもしれない。そんな不安や怖れが、対話の場には常につきまとっています。
それでもなお、私たちは誰かと話し、聞き、考えようとします。完全に通じ合うことはできなくても、「分かりあおうとする」姿勢にこそ意味があるのだと、本書を通じて深く感じました。見知らぬ誰かに向かって、無防備なまま跳ぼうとするその勇気こそが、対話という営みの本質なのかもしれません。
相手を尊重することと、怖れずに飛ぶこと。その両方を携えて言葉を交わすとき、対話はただの意見交換ではなく、何かもっと根源的な「つながり」を生む場になるのだと思います。たとえ何も解決しなくても、たとえ完全に理解しあえなくても、「跳ぶ」という行為そのものに、かすかな希望が宿る。そんなふうに、今では感じています。
「対話」と「問い」
対話が跳躍であるならば、その起点には、いつも「問い」があります。問いこそが、対話のはじまりをつくるものだと思うのです。
「どうしてそう思うのか」「本当にそうだと言えるのか」「なぜ、それを選ぶのか」。こうした問いは、ただ相手を詰問するためのものではなく、自分自身の思考を揺り動かし、また相手の内側をそっとたぐり寄せるための手がかりになります。
本書冒頭の一文に戻ります。
問いは、偉大である。もろく小さなわたしでは到底かなわないほどに、堅固で美しい。
問いは、どこか自分の手には余るような存在でありながらも、私たちが世界とつながるためのもっとも原初的な、そして根源的な方法なのだと感じました。
問いは、知識の量や語彙の豊かさとは無関係に、誰もが差し出すことのできる贈り物のようなものです。問いを発するという行為には「私はあなたに関心がある」「私はまだ、わかっていない」という誠実な姿勢が宿っています。問いとは、断定でもなく命令でもなく、呼びかけです。それは、相手の自由を前提にした関わり方であり、だからこそ、おそろしくもあり、しかし同時に限りなく美しい行為でもあります。
問いを持ち続けるということは、答えを急がないということでもあります。すぐに結論を出すのではなく、ゆっくりと、何層にも折り重なる感情や考えを丁寧にほどいていく時間を許すこと。その時間のなかで、私たちは互いに変化していきます。問いとは、他者とともに「変わっていくことを引き受ける」態度なのかもしれません。
問いを立てる。問いを受け取る。そして、ともに考える。その静かで、しかし深く根を張る営みのなかに、哲学的な対話の核心があると私は思います。
攻撃的な「問い」は「問い」なのか
しかし、今の私たちの言葉の世界には、何かを問うふりをしながら、実は相手を追いつめたり、裁いたりするような「問いもどき」があふれているように感じます。
勝ち負けを決めるのは簡単だ。こっちのほうがわかりやすいです、とか、論理的、面白い、声が大きい、とか。傷つけあうことが認められた中で、闘うことはもっと楽ちんだ。本当に、簡単だ。
そのような問いは、一見すると対話の入り口のように見えて、実は答えを求めてはいません。ただ、自分の立場の正しさを確認するために、あるいは相手の不備を暴くために使われているような「問い」のようなもの。これは「問い」の形をした攻撃にすぎません。
それは本当に、問いなのでしょうか。
本来の問いとは、相手に興味を持ち、理解しようとする動きの中から自然と立ち上がるものではなかったかと思います。問いは、本来、関係を結ぶための手段であり、誰かと「ともに考える」ための入り口のはずです。それなのに、いつの間にか問いが「正しさ」をめぐる戦いの道具になってしまうとき、言葉の地盤は大きく崩れてしまうように思います。
「相手を理解すること、相手を認めること、その上で問うこと」。たったそれだけのことなのに、私たちはとても簡単に、その考えを吹き飛ばしてしまいます。
問いとは、本来とても繊細なものです。それは、他者の中にある世界に分け入る行為だからです。自分の考えを押しつけるのではなく、相手の持つ前提や価値観に、そっと光を当ててみる。問いとは、その人のなかにある「まだ言葉になっていないもの」に手を差し伸べるようなものなのだと思います。
つまり、問いには「まなざし」が必要です。
相手をどう見ているのか。理解しようとしているのか、それともただ正したいのか。問いのあり方は、まなざしのあり方そのものにほかなりません。
問いを投げかけるとき、私たちは問われてもいるのでしょう。自分がどんな関係を結びたいのか、どんな姿勢でそこにいるのか。問いとは、相手に向けるものに見えて、実は自分の足元を照らすものでもあります。
だからこそ、問いを使うときには、慎重でありたいと思います。問いは武器にもなるし、灯火にもなりうる。問いの使い方次第で、対話は戦いにも、まなざしの交換にも変わるのだと、この本を通して強く感じました。
「問い」から逃げないこと
わたしたちはひとと集まって話すことが苦手である。うまく考えられたとしても、それを適切にひとに伝えたり、話を聞いたりすることが本当に下手だ。考えを闘わせて、誰が一番強いのかを決めることが好きで、ひとと協力して意見を練り上げていくことがとても苦手だ。
私はもともと、人と積極的に関わるのが得意なタイプではありません。誰かと話すより、一人で黙って考えているほうが落ち着くのです。心のどこかでそう感じながら大人になりました。
正直に言えば、誰かに投げかけたい「問い」などほとんど持っていなかったのです。
誰かが夢中になって話していることにも、社会が盛り上げようとしているトピックにも興味を持つことができませんでした。それは傲慢でも冷淡でもなく、ただただ、自分のまなざしの位置が定まっていなかったからだと思います。
一方で、誰かと意見を戦わせたいとも思いませんでした。議論で勝ち負けをつけることに、ある種の暴力性を感じてしまうのです。
言葉を武器にするような場では、自分の声が遠ざかっていくように感じられたし、何より、相手の言葉を聞こうとする余裕を失ってしまう気がしていました。
ただ、今になって思うのです。私は「問い」を持たなかったのではなく、問いを持つことをどこかで避けていたのではないかと。
問いとは、自分が世界とどう向き合っているかを問われることでもあります。何に興味を持ち、何に怒り、何に喜ぶのか。自分自身の姿勢を掘り返されるようなその行為から、私はずっと目をそらしていたのかもしれません。
思考すること、分かろうとすること、問うこと。それらの営みから少しずつ距離を取っていたのは、自分の未熟さを直視するのが怖かったからでしょう。
そして同時に、誰かに無関心であることのほうが、安全だったからなのだと思います。
この本に触れたことで、私はようやく、そのことを言葉にできるようになった気がしています。問いは、世界に差し出す手でありながら、自分自身の輪郭を静かに探し直す行為でもあるのだと感じます。問いを持つとは、やわらかく、でもしっかりと、誰かと生きるということを受け止めることなのかもしれません。
相手を認め、問い、対話する
問いは、相手を理解するためにあるべきものです。まず相手の存在を一人の人間として認めること。そこに立脚しなければ、どんな問いも単なる攻撃や操作にすぎません。
問いとは、相手に向けたまなざしです。その人がどんな考えを持ち、どんな背景を背負い、どんな言葉で語ろうとしているのか。それらを知ろうとする姿勢がなければ、問いはすぐに暴力的なものになります。相手を「答えるべき存在」としてだけ見てしまえば、対話は成立しません。
問いを発するとき、私たちは自分の姿勢もまた問われています。その問いは、ほんとうに「相手に届いてほしい問い」なのか。相手と関係を築くための跳躍なのか。それとも、自分の正しさを証明するための方便にすぎないのか。
問いを立てる前に、自分自身に問うてみたいと思います。私は本当に、この人の話を聞こうとしているのか。この問いは、分かりあおうとする態度にふさわしいものなのか。
問いは、相手を認めることからしか始まりません。そして、問いを通じてつながる対話は、いつもそこから生まれるはずです。
問いは鋭くなくていいし、整っていなくてもいい。たどたどしくても、未完成でも、その問いが「あなたのことを知りたい」という願いから生まれているのなら、きっと言葉は届くのではないかと思うのです。
そのことを、私はこの本から教わった気がします。