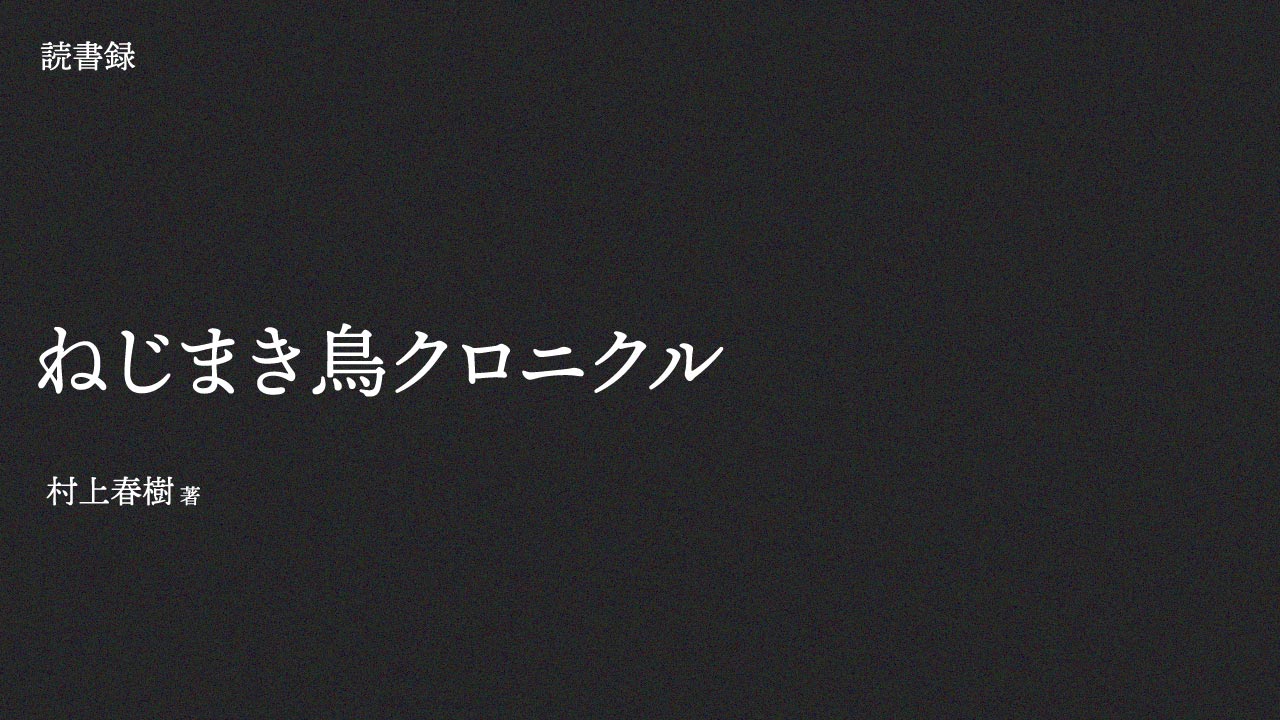『ねじまき鳥クロニクル』を最初に読んだのは高校生の頃でした。
学校でも、家の中でも夢中で読みふけっていた記憶があります。
あの時、私は物語のすべてを理解できていたわけではありません。けれど、ページをめくるたびに何か大切なものが胸の奥に沈んでいくような、そんな感覚を何度も味わいました。
本の裏表紙のあらすじを読むだけで、泣きそうになってしまうほどです。
人生のさまざまな季節にそっと寄り添ってくるような、あまりにも深い物語についての読書録です。
物語を超えて潜るもの
『ねじまき鳥クロニクル』の凄みは、物語の巧妙さや伏線回収の見事さにあるわけではないと感じています。
もちろんプロットも独創的で、異界と現実を行き来する構造には心を奪われますが、それ以上に私が強く感じるのは、「世界はどうしようもなく不条理である」という感覚と「それでも生きていくしかない人間の悲しさと祈りのようなもの」が、全編にわたって貫かれていることです。
たとえば、井戸の底という場所。
そこには物語的な意味もありますが、もっと根源的な「思考の構造」「自己との対峙」「世界との断絶」そのものが描かれているように思えてなりません。人はただ生きているだけでは、自分が何者かを深く理解することはできない。けれど、沈黙の時間、暗闇の中に沈み込む時間の中でしか、触れられない何かがある。井戸とは、その象徴のように思えるのです。
そして「ねじまき鳥」の存在。
これは物語に現れる「異様な存在」として捉えるよりも、「誰かの人生が軋み始めた瞬間」というメタファーとして捉えました。その音に耳を澄ませることでしか、私たちは自分の生の構造や世界の歪みを理解することができないのかもしれません。
また、この作品は「善悪の二元論」からも「成功・幸福の定義」からも距離をとっています。物語がどんなに進んでも、基本的には何も解決しないし、華々しい勝利もありません。しかしその中で、どうしようもなく不確実で残酷な現実に抗わずに生きるという選択を、丁寧に描いています。
何かを断罪するのではなく、そこに「何かがある」という事実をそっとすくい上げるような、その態度こそがこの作品の強さだと思います。
ねじまき鳥について
ねじまき鳥の姿は見えませんが、確かに「音」として物語の中に現れる存在です。
ねじを巻くような音を響かせながら、どこかで世界を巻き直している。姿は描かれず、話すこともない。それなのに、その音を聞いた瞬間に、読者もまた物語の中の静けさと歪みに引き込まれていきます。
この鳥は明らかに比喩として存在していますが、何のメタファーかと問われれば、それはひとつではありません。
世界が歪み始めた時。時間や記憶が綻び始める予兆。人間の心に走る小さな亀裂。運命を巻き戻すことのできない不可逆性。
これらすべてが、ねじまき鳥の「音」に集約されています。
それは災いの予兆ではなく、すでに破綻しかけている世界の断末魔でもなく、もっと静かで冷ややかで、言い換えれば「世界の軋みの象徴」なのかもしれません。
まるで「正常に見える世界」そのものが、じつはもう壊れ始めているのだという事実を、そっと教えてくれるような不気味さがあります。
狂気的な暴力の語り口
本作の中で語られる最も印象的な歴史的背景の一つが、「ノモンハン事件」(1939年)を含む日本軍とソ連軍の満洲国境での戦闘、そしてその中で起きた極限状態の人間の暴力です。
特にボリスや間宮中尉の語る戦争体験は、本当に凄惨で強烈です。
作中に登場する間宮中尉の拷問では、人間が他者に対して行いうる暴力の極致とでも言いますか、極めて凄絶なシーンが描かれます。ただしそれは大声で叫ばれるわかりやすい暴力ではなく「皮膚を剥がされる」という静かで陰惨な描写でした。
第二次大戦における加害・被害の区別を越えて「戦争という状況そのものが人間をいかにして壊していくか」という主題を内包しているように思えます。
このような歴史は、日本社会において長く語られることなく放置されてきた記憶です。まさに「沈黙の暴力」とでも言うのでしょうか。
国としてはもう終わったこととして片づけられていても、そこに生きた人間たちには終わらせることのできない闇が残り続けている、そんな重さを物語は声高ではなく、むしろ静かに、恐ろしいまでの冷たさで語っています。
「見えない権力」と「正しさ」。支配の構造について
もうひとつの歴史的背景は、戦後の高度経済成長と権力構造の変質でしょう。
綿谷ノボルという人物は、その象徴ともいえる存在です。彼は戦後の混乱をくぐり抜け、冷静に制度を利用し、政治的・社会的な影響力を築いていきます。彼の正しさは常に制度や結果によって保証されているように見えますが、その背後には見えにくい形の支配があります。
これは現代社会の構造的暴力の一形態だと感じます。
「何もされていない」のに傷ついている人がいる。「誰も暴力を振るっていない」のに自由を奪われている人がいる。「合理的な判断のもと」に人が押しつぶされている。
こうした暴力は、声にならない痛みとして日常に潜みます。
「あまりに静かな暴力」であり、その暴力性はボリスとはやや異なります。
社会的には語られることのない個人の痛み。
それは、歴史の教科書には載らず、マスメディアも触れようとしない種類の暴力です。
『ねじまき鳥クロニクル』が描く暴力は、爆音を立てて迫るものではありません。むしろ、「日常に紛れてしまうほど静かなもの」だからこそ、より深く人を蝕む。
それは語られなかった戦争の記憶であり、構造のなかで巧妙に正当化される支配であり、声を持たない者たちの沈黙であり、それらが生み出す闇です。
何よりこの作品が恐ろしいのは、闇が「誰か特定の悪人」だけに宿っているのではなく、ごく普通の人間、そして社会の仕組みそのものにある種の「正しさ」として深く組み込まれているという点です。
そうした暴力に対して、主人公はただ耳を澄まし、沈黙の底に降りていきます。その行為と勇気に何度も胸を打たれました。
岡田亨という「無色透明」の歩み
主人公・岡田亨のことを考えてみます。
彼は一見するとあまりに「何もしない」人物と言ってもいいかもしれません。勤めていた法律事務所を辞め、主夫のように暮らし、家の猫がいなくなっても、妻が姿を消しても、彼はただ考え、待ち、沈黙し続けます。
でも彼は、ただ立ち止まっていたわけではないのです。
彼の歩みは、外から見れば動きのないものに見えるかもしれません。けれど内側では、深い井戸に何度も潜っていくような「内的な探求」が、ひたすら続けられていました。
彼は、自分の中にある音を聞こうとしていたように写ります。
電話の音、不快な音、記憶の軋み、愛した人との断絶、世界の歪み。それらに蓋をせず、耳を澄ませ、待ち、時に自らその場所に降りていく。誰にも見えない戦場を、たったひとり静かに歩いているような姿でした。
彼は特別な能力を持っているわけでも、英雄的な決断を下すわけでもありません。しかしただ諦めず、ただ逃げない。それだけのことが、どれだけ難しいか。
もしかすると彼は、社会の中で失われていく個人性の象徴かもしれません。そして同時に、無色透明であることの強さ、静かで透明な信念のあり方を教えてくれる存在でもありました。
誰もが答えを求めて右往左往するこの時代に、彼のように「ただ考え、ただ待つ」ことができる人間がいたということは、この物語が示すひとつの希望だったのかもしれません。
本稿では言及しませんが、本編後半での暗闇の激闘は本当に胸が打たれました。今でもあのシーンまでの流れを読むと泣いてしまいます。
2023年のもうひとつの「ねじまき鳥」
2023年、『ねじまき鳥クロニクル』は舞台としても上演されました。
私が観に行ったのは、友人・山中桃子さんがチラシデザインを担当したことがきっかけでした。好きな作品が舞台になるというだけでも特別なのに、身近な人がその世界観の一端を担っているとなれば、やはり足を運ばずにはいられません。
舞台の演出は、映像と肉体表現を巧みに組み合わせた構成で、あの幻想的で深淵な物語を、抽象度を保ったまま立ち上げようとしている意志を強く感じました。原作がもつ言葉にならない部分、井戸の沈黙、ねじまき鳥の気配、心が軋む音、歴史の影それらを言語以外の方法で伝えようとする試みは、とても勇敢で、そしてどこか美しくもありました。
原作の精緻で重層的な構造をすべて再現することは非常に難しいと思うのですが、むしろ舞台は「描けなかった部分の余白」によって、逆に『ねじまき鳥クロニクル』という作品の本質、言葉では掴みきれないどこまでも沈んでいく世界の断片のようなものを浮かび上がらせていたようにも感じます。
観劇を終えて思ったのは、村上春樹という作家が描こうとしたのは「意味のある物語」ではなく「意味に触れようとする沈黙の運動」だったのではないかということでした。そして舞台は、その運動を別のかたちで再現しようとしていたのかもしれません。あれはもうひとつのねじまき鳥の声だったのだと思います。
人は闇から帰ってくることができるのだろうか
『ねじまき鳥クロニクル』を読むなかで、ずっと心に残り続けている問いがあります。
「この世界の深い闇に触れてしまったとき、人はなお人でいられるのか」という問いです。
本作には、戦争の記憶、拷問の痕、性的支配、制度的暴力、沈黙の断絶といった、さまざまな「闇」が登場します。
それらは単なる「嫌な出来事」として描かれているのではなく、人間の尊厳が失われる瞬間や、社会に組み込まれた静かな暴力の構造として、物語のなかに静かに漂っているのです。
ボリスや綿谷ノボルのようにその闇を理解し、支配のために使う人物もいれば、クミコや加納姉妹のように沈黙のうちに傷を抱え、消えていく存在もいます。
では、岡田亨はどうだったのでしょうか。
彼は、何度も何度も闇の場に足を踏み入れますが、闇に触れることから決して逃げませんでした。
愛する人が去り、世界の輪郭が崩れ、日常の静寂が軋み始めても、声を荒げることなく、ただ見つめ、受け入れ、沈黙のなかに身を置いていきます。
井戸の底へと降りていく場面は、その象徴だったと思うのです。
目を閉じ、音のない暗闇のなかで、世界の奥にある何かと向き合おうとする姿勢。そこには、安易な希望や即席の救いはありません。ただ「逃げない」という、誠実な選択だけがありました。
そして、最も重要なのは、彼が闇に触れてもなお、闇に染まらなかったことです。
綿谷ノボルのように力を手にすることもなく、怒りにまかせて誰かを傷つけることもなく、彼は人としての在り方を崩しませんでした。それは、決して弱さではなく、むしろ強さの証だったのだと思います。
多くの人は、闇に触れると壊れてしまいます。あるいは、その闇を取り込むことでしか生き残れないと考えてしまう。
しかし主人公は沈黙のなかに立ち、誰かを打ち倒すのではなく、壊れずにいることそのものを自分の抵抗としたように見えます。
この物語において、それは最も美しく、最も強い人間の姿だったと私は思います。
もしかすると勇気とは、闇を払いのけることではなく、闇に触れたまま正しい人であり続けることなのかもしれません。もしくは傷を知りながら、誰にもその傷を押しつけずにいることなのかもしれません。
それこそが主人公が選んだ生き方であり、読者である私たちがこの物語のなかで何度も胸を打たれる理由なのだと思います。
結びに:静かな音に耳を澄ますように
『ねじまき鳥クロニクル』を読み終えるたび、いつも少しだけ現実の輪郭が変わって見える気がします。
風の音が違って聞こえたり、人の沈黙がやけに重く感じられたり、あるいは日常のひとつひとつに、微かな軋みのようなものを感じたりするのです。
その感覚は、不快ではありません。
むしろ、ようやく自分が何かと「同じ地平」に立ったような不思議な安堵があります。痛みも矛盾も暴力も、等しく人生の底に確かに横たわっていて、それを無視しないという態度だけが何かを照らす小さな灯火になると、そんな気がしてなりません。
高校生のときには言葉にできなかったものが、少しずつ言葉に近づいてきている気がします。
でも、どれほど言葉を尽くしても、『ねじまき鳥クロニクル』という本のすべてを語り切ることはできないでしょう。それだけは確信しています。
きっと、また何年かしたら、この本をもう一度開くことになるはずです。その時に自分が何を思うのか、楽しみでもあり怖くもあります。