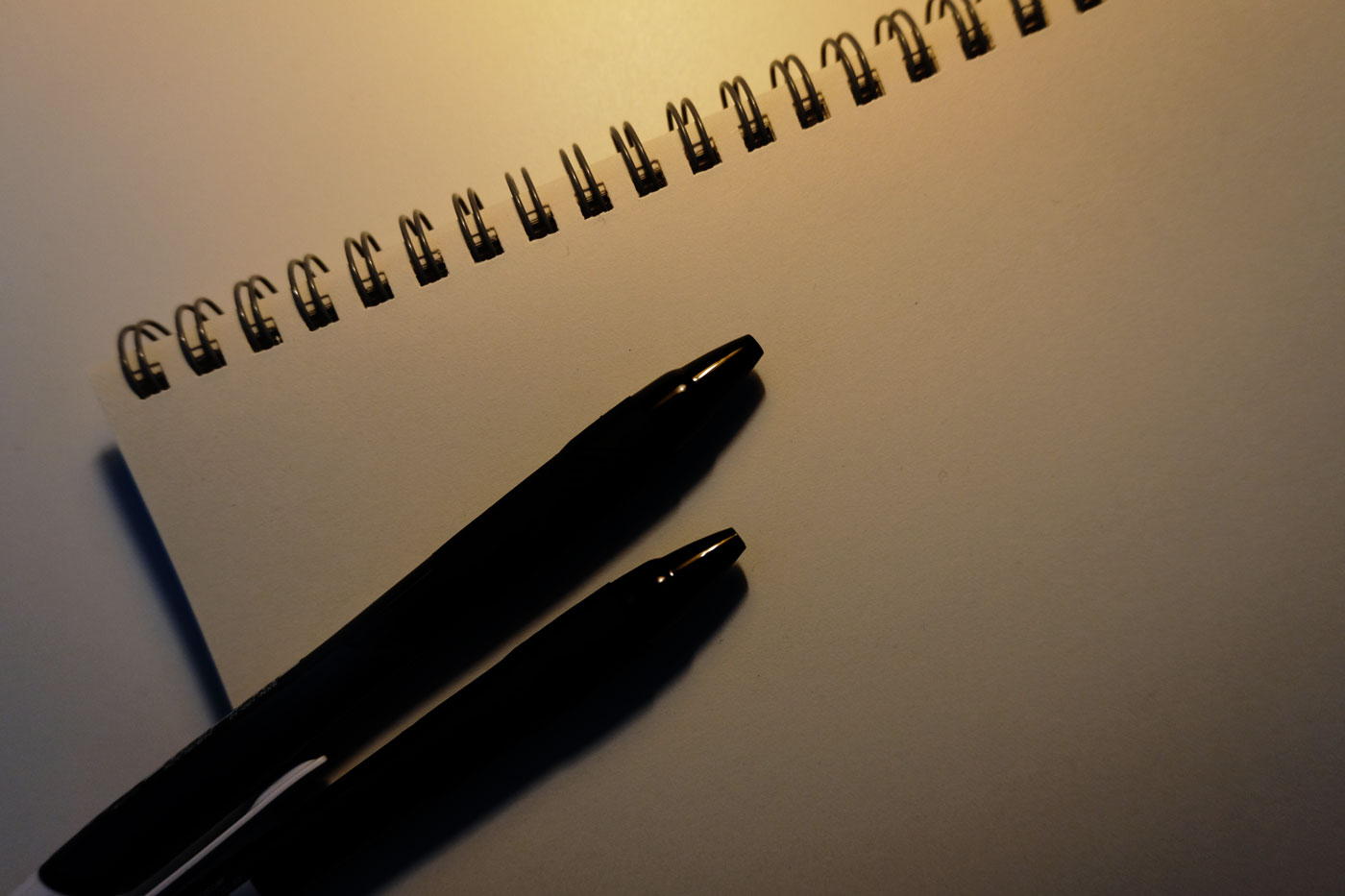文章で人に想いを伝える方法はいくつもあります。
現代では、メールやSNSといった手段が主流ですが、手紙もまた大切な伝達手段のひとつです。メールとは異なり、書き手の温度感がより鮮明に伝わるのが手紙の魅力です。
相手を思い浮かべながら言葉を選び、下書きをし清書するといった、その過程そのものが、受け取る人の心に届きます。
私自身、仕事ではネットでの執筆を日常的に行っていますが、手紙を書く機会は人生の中でも数えるほどしかありません。
そんな「手紙」を題材にし、映画化されたのが、2025年3月に公開された「35年目のラブレター」です。今回は、そのあらすじをたどりながら、作品を通して感じたことを綴っていきます。
読み書きできなかった夫が、妻に送った35年越しのラブレター
本作は実話をもとに描かれた作品で、モデルは奈良市に暮らす西畑 保(たもつ)さん。幼少期に十分な教育を受けられず、読み書きができないまま大人になった保さんは、職場でのいじめや転職を繰り返す日々を送っていました。
転機は、奈良市のお寿司屋に勤めたこと。そこでの真面目な働きぶりが縁となり、お見合いで出会ったのが皎子(きょうこ)さんでした。
やがて二人は結婚しますが、保さんは読み書きができないことを打ち明けられずにいました。ある日、回覧板のサインを求められたことをきっかけに告白。
皎子さんは「一緒に頑張ろう」「これからは私があなたの手になるから」と支える決意を示します。この一言が、保さんの人生を大きく変えることになります。
定年後、保さんは妻への感謝をラブレターで伝えるため、夜間中学校に入学。「あいうえお」から学び直し、初めてのラブレターを書き上げます。初回は誤字脱字が多く不完全でしたが、翌年のクリスマスには納得の一枚を完成させます。
しかし、不運な出来事が重なり、その手紙を皎子さんに直接渡すことは叶わなかったのです。
結びに
本作を見終えて感じたのは、チャレンジに年齢は関係ないということです。
定年後から読み書きを学ぶことは、並大抵の努力ではありません。それでも保さんは、奥様への感謝の気持ちを手紙で伝えたいという一心で学び続けました。その情熱は本当に素晴らしく、胸を打たれます。
同時に、保さんを支え続けた皎子さんの愛情にも深く心を動かされました。読み書きができないことを打ち明けられたときに、「これからは私があなたの手になるから」と応えたのは、無償の愛なくしてはできないことです。
初めてラブレターを受け取ったときの皎子さんの喜びは、きっと言葉にできないほど大きなものだったでしょう。
保さんは幼少期から読み書きができないことでいじめを受け、大人になってからも苦労を重ねてきました。
1936年、和歌山県に生まれた西畑さんの幼少期は太平洋戦争のさなか。生活は決して豊かではなく、小学生の頃から兄弟のために働き、少しずつお金を貯めていました。
しかし、その大切なお金を学校の教室で失くしてしまいます。後に見つかったものの自分のものであると信じてもらえず、泥棒と呼ばれ、いじめを受けるようになります。やがて学校へ通うことをやめ、読み書きはもちろん、勉強の方法すら学ばないまま成長しました。
現代でもいじめの問題はなくなりませんが、もし戦争という時代背景がなければ、西畑さんの人生は大きく違っていたかもしれません。戦争が子どもたちの未来や可能性をいかに奪ってしまうのか、その恐ろしさを改めて痛感させられます。
保さんは寿司職人として腕を磨き、やがてかけがえのない皎子さんと出会うことで幸せをつかみます。
皎子さんと共に過ごし、自分の想いを文字にして贈るために費やした時間は、何にも代えがたい宝物なはずです。それは、ふたりにとって温かい時間だったに違いありません。