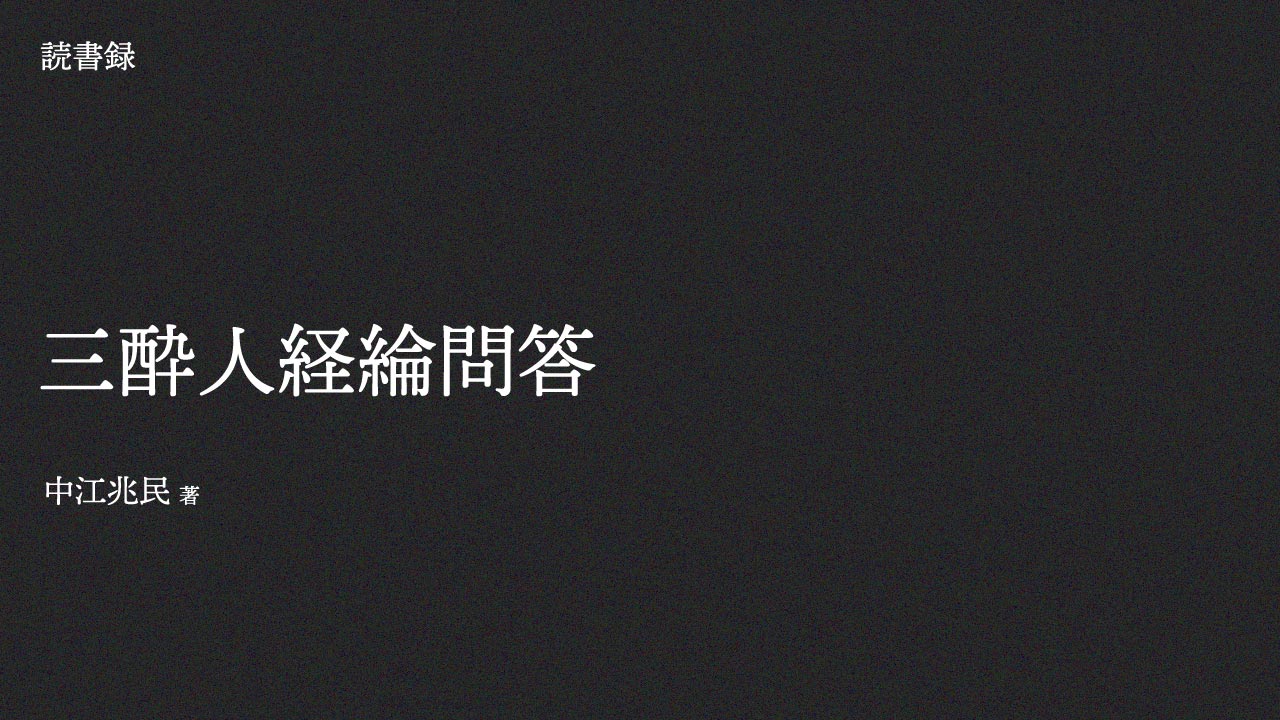中江兆民の著作『三酔人経綸問答』。
明治の半ばに世に問われた一風変わった思想書です。立場の異なる三人の酔っぱらいが政治論議を交わすという風変わりな設定が特徴的であり、さらに対話形式で綴られているという点でも独創的な作品ですね。
一見難解に思える題名ですが、その実態は「三人の酔った人物が国家経営について問答する」という意外にも平明で、その内容は軽妙で砕けた筆致で風刺的な政治談義が展開されていくというもの。まるで兆民が遊んでいるかのような親しみやすい展開です。
しかし、この「遊び」の仮面の下には、彼の真摯な思索が隠されています。
本作には当時の日本が直面していた国際情勢や国内政治の諸問題に対する兆民の深い洞察が反映されており、明治期の日本が直面していた重大な政治課題に対する兆民の深い考察が凝縮されていると感じます。
彼は自らの理想と現実認識を三者の対話に託し、「小国」日本が世界の中でいかに生き延びるべきかという国家的課題を読者に問いかけています。酔った三人の議論を通じて、日本の進むべき道を模索するという手法は、古典的な対話篇の伝統を踏まえながらも、日本の思想書としては極めて斬新な試みでした。
対話形式で掘り進められる様々な思考。
私はこの本から「対話」というものの本質を少しだけ学べたような気がします。
土佐の知性、中江兆民
中江兆民は土佐(現・高知県)出身の思想家であり、幕末の志士・坂本龍馬から明治末期に活躍した幸徳秋水へと続く「土佐の革新的な思潮」の中心的存在として位置づけられます。
土佐が育んだこのリベラル的思想の特質は、その前向きな気質と徹底した現実主義的姿勢にあるような気がします。
しばしば歴史家が指摘するように、坂本龍馬が同時代の志士たちと一線を画していたのは、将来の政治体制を具体的に構想する先見性と、実務的な経済感覚を併せ持っていた点でした(坂本龍馬をリベラリストとしていいのかはさておき…)。
イデオロギー的純粋さよりも実践的な社会変革の方法を模索した龍馬の精神性。それを継いだのが中江兆民でした。
また、後に大逆罪に問われて悲劇的な最期を迎えることになる幸徳秋水も、その思想の根底には土佐のリベラリズムの実践的性格が息づいていたのかもしれません。
兆民は明治初期にフランスへ留学し、急進的民主主義者の哲学者エミール・アコラースから多大な影響を受けました。
アコラースを通じてルソーの思想に触れた兆民は、帰国後の明治15年(1882年)に『社会契約論』を漢文体で翻訳した『民約訳解』を世に送り出します。以降、日本における代議制政治の確立を目指して言論活動を展開し、自らも政治家として奔走しました。
明治維新の際、兆民はまだ20代前半の若者でした。
同郷の土佐藩からは坂本龍馬、板垣退助、後藤象二郎、中岡慎太郎といった維新の立役者が輩出されていましたが、彼らはいずれも兆民より上の世代でした。もしかすると「もう少し早く生まれていれば、あの激動の時代に自分も一翼を担えたのではないか」そうした微妙な時代的ずれへの意識が兆民の心の底にあったかもしれません。
この「生きるべき時代にやや遅れて生まれた」という少し傾いた感覚と、西洋の理想と現実の両面を知悉していた兆民独自の複眼的視点が、『三酔人経綸問答』には色濃く反映されています。
明治中期において兆民が描いた現実主義的とは具体的にどのようなものだったのか。そして当時の日本においてはどのような思想潮流が交錯していたのか。
この問いに対する回答として、兆民は『三酔人経綸問答』という作品を著しました。この作品は単なる思想書を超え、異なる政治観を持つ三者の対話という劇的形式を通じて、明治日本の進むべき道を巡る知的格闘を描き出します。
『三酔人経綸問答』に登場する3人
物語は梅雨の鬱陶しい一日から始まります。「南海先生」が憂さ晴らしに酒を傾けていると、酔いがほどよく回った頃、思いがけず二人の訪問者が現れます。洋学の教養を身につけ論理的思考に長けた「紳士君」と、豪胆で冒険心に富み軍事を好む「侵伐家」の「豪傑君」です。
西洋の民主主義に共鳴する「洋学紳士」、軍事力による国威発揚を唱える「豪傑君」、そして両者の議論を聞きながら現実的な落としどころを探る「南海先生」。
三つの異なる政治思想を体現する人物たち。
兆民は当時の日本社会に存在した政治的立場の対立を、この三者に象徴させています。西欧的価値観に基づく平和主義、国家拡張を目指す好戦的ナショナリズム、そして理想と現実の間で実行可能な政策を模索するプラグマティズム。
これらの視点が酒の力を借りて率直にぶつかり合います。
酔いの状態だからこそ、建前を脱ぎ捨て、本音で語り合える。形式的な政治論文では表現できない思想の葛藤や矛盾を、酔った三者の対話という文学的装置を通して浮き彫りにしているようです。
ではざっと登場人物の説明を。
洋学紳士(紳士君)
「洋学紳士」(紳士君)は東西の哲学・学問に精通した博識の士として描かれており、論理的な議論展開によって自らの主張を組み立てる理論派です。彼の政治的立場は、理想主義的な民主主義・平和主義に集約されます。
紳士君は人類の歴史を文明の発展段階として捉え、社会進化論の影響下に「進化こそが進歩の原動力である」という信念を持っています。
彼は欧米列強による侵略的植民地政策を徹底的に批判し、日本が歩むべき道は民主政治の完全な実現による国内改革と武装放棄(軍備撤廃)にあると力説します。
戦争を根本的に否定する非戦論を展開し、自由と平和によってこそ真の文明開化が達成されるというユートピア的信念の持ち主です。
極言すれば、「周囲の国々が帝国主義的行動を取ろうとも、日本は理想を貫き非武装中立の平和国家として存立すべきだ」という革新的な立場であり、これは明治期の民権派知識人が抱いた理想の延長線上に位置づけられる思想といえるでしょう。
豪傑君
「豪傑君」は作品中、まさにその名の通りの剛勇豪胆な気質の持ち主として描かれます。
洋学紳士の理想主義とは正反対の現実路線を主張する彼の政治姿勢は、当時勃興しつつあった国家主義・軍国主義の先駆けと言えるものかもしれません。
彼が繰り返し力説するのは「理想論では国家は守れない」という現実認識です。
欧米列強による植民地争奪戦のただ中にあって、日本が独立を維持し国際社会で生き残るには、武力を背景とした強い国家建設が不可欠だと断言します。
彼の視線は内向きではなく、むしろアジア大陸、特に清国への膨張主義的進出を積極的に推進すべきとしているように映ります。
洋学紳士の掲げる平和理想主義に対しては「弱肉強食の国際秩序において道徳や理想を説いても無駄であり、むしろ国家の危機を招くだけだ」と喝破します。その言葉は時に粗暴ですが、当時の国際情勢を冷静に分析する鋭さも兼ね備えています。
豪傑君の思想は、明治初期から台頭してきた征韓論者や大陸進出論者の主張と重なり、後の日露戦争から太平洋戦争へと至る日本の軍事路線を先取りするかのような不気味な先見性を持っているように感じます。
兆民はこの人物を通して、理想と現実の緊張関係、そして軍事力に依存した国家建設の危うさを読者に問いかけていたのかもしれません。
南海先生
高齢で隠居生活を送る土佐出身の学者という設定で、酒席の風雅を愛する温厚な人物として描かれています。
対照的な二人の来客、理想に燃える「洋学紳士」と好戦的な「豪傑君」の間に立ち、両極端な政治思想の調停者としての役割を果たします。硬直した教条主義を避け、状況に応じた柔軟な現実主義に基づいた、量より質的発言が目立ちます。
決して長広舌を振るうわけではありませんが、論争が過熱したタイミングで投じる短い言葉には鋭い洞察と豊かな経験が凝縮された重みを感じます。
彼の発言は「理想も大事。でも現実も大事。どう折り合いをつけるかを話し合おう」というもので、抽象的理念と具体的現実のバランスを模索し、穏やかなリアリズムの立場をとります。
例として、彼は非武装平和主義の崇高さを認めつつも、列強の覇権争いという厳しい国際環境で完全非武装では国家存続が危うくなると指摘します。同時に、他国への侵略や武力拡張主義にも警鐘を鳴らし、「防衛のための最小限の備えを維持しつつ、決して覇権追求には走らない中庸の道を探るべき」という抑制の効いた国家運営を示唆します。
文学的解釈としては、この南海先生のキャラクターに作者・中江兆民自身の政治的均衡感覚が色濃く反映されているとされます。
実際、研究者の中には「三人全てが兆民自身の内面の投影であり、なかでも南海先生には兆民の鋭い分析力や常識的な現実主義が特に反映されている」と指摘する者もいるようです。
「南海」という名前自体、兆民の故郷・土佐が属した「南海道」に由来するという解釈もあり、作者との同一性も垣間見れます。
紳士君の理想主義、豪傑君の現実主義
ルソーとフランス革命を熱烈に支持する紳士君。
彼は自由と平等を基調とする「民主の制」こそが社会進化の必然的帰結だと主張します。彼の思想は徹底した合理主義と純粋なデモクラシー信奉に根ざしており、政治的進化の理論によれば、民主制の確立は自由・平等・友愛の原理を社会の基盤とし、究極的には軍備の撤廃をも実現するとされます。
紳士君の展望によれば、諸国家が民主体制へと移行するにつれ、世界は自ずと平和への道を歩むことになるようです。彼はルソーやカントの思想を援用しながら、世界平和の可能性について熱弁します。
これに対して豪傑君は、理論と現実の乖離を指摘します。彼の視点からすれば、十九世紀の国際政治の現状は紳士君の理想とは大きく異なっています。紳士君が崇める西洋「文明国」も実態は軍事力の拡充と植民地獲得に邁進する「強国」にすぎないと断じるのです。
豪傑君は、ポーランドやビルマの国家主権喪失の歴史を引き合いに出しながら、国力の充実と軍備の拡張、そして影響圏の拡大こそが国家の生存条件であると主張します。この反論は、国際関係における冷徹なリアリズムの立場を体現するものと言えるでしょう。
二人の対立は、理想主義と現実主義、普遍的価値と国家利益、進歩史観と力の政治という、近代政治思想の根本的な緊張関係を浮き彫りにしています。
南海先生が示す「間」という道
未来の理想社会を直線的に目指す紳士君と、武士的伝統への回帰を説く豪傑君。この対照的な二極の間に位置するのが南海先生です。
この人物のみが「先生」の敬称で呼ばれ、年長者として描かれていることからも、その調停者的役割は物語の構造において必然だったと解釈できます。
南海先生は、社会進化のコースが単一直線的だとする紳士君の単純な図式に観点を与えます。彼の視点では、進化の道筋は各国固有の歴史的背景によって多様に分岐するものであり、アジア諸国においては「専制」から直接「民主制」へと飛躍することは社会的混乱を招くだけだと指摘します。
南海先生が提示する道筋は慎重かつ段階的です。
まず君主と宰相が主導して人々に「自由権」を付与する「恩賜的の民権」を基盤とした「立憲制」の確立から始まります。この体制下では、貴族院を含む二院制議会が設立され、統制された形で徐々に自由化が進行します。その過程を経て民権思想が社会に十分に浸透した後に初めて、英国やフランスが歩んだような「恢復的の民権」に基づく政治体制へと移行すべきだと説くのです。
この三者の対立図式は、現代社会にも通底するように思えます。
理想を掲げて突き進むべきか、伝統的価値観を守るべきか、あるいは現実を踏まえた漸進的変革を選ぶべきか。
組織運営においても、ビジョン重視かシェア拡大優先かという二項対立を超えた第三の道を模索する姿勢が、時に最も困難でありながら賢明な選択となり得るのかもしれません。
理想主義的な価値観の追求か、それとも国力の増強か、或いは
洋学紳士(理想主義)、豪傑君(現実・国力主義)、南海先生(調和・中庸)という三者の対照的な立場を通して、兆民自身の内なる思想的葛藤を劇的に表現したような本作。
当然ながら、この作品については「登場する三人の人物のうち誰の主張が兆民自身の思想としてみなすか?」という問いがしばしば投げかけられ、また三者の対話が兆民自身の思想的多面性を表現したものではないかという解釈も提示されてきました。
三人の登場人物は明確な思想的対立軸を形成しています。
一方が「民主主義・平和主義」という普遍的理想を高らかに掲げ、他方が「国家主義・武力主義」という冷徹な現実論を主張し、そしてその間に立つ南海先生が両極端な立場の調停を試みるという構図です。
この三者の対立は、明治日本が直面した根本的な政治的ジレンマを象徴しているようです。
西洋の理想主義的な価値観を追求するのか、それとも国際社会の厳しい現実に適応するために国力増強を優先するのか。近代化の過程で日本が避けて通れなかった根源的問いがここに凝縮されています。
三人の激論は明確な決着をみることなく展開しますが、それぞれの主張の強みと弱点を浮き彫りにすることで、読者に安易な結論ではなく、深い思索を促す仕掛けとなっています。
兆民自身の内面的葛藤も作品に投影されており、理想に殉じたい心情と現実を直視する知性との緊張関係が対話の随所に表れています。
「対話の精神」とは自己変容を厭わない態度にあるのではないか
三者三様の価値観を持つ彼らの対話は、思想的交流の本質を映し出しています。
ここで思い出したいのが、西洋思想の伝統においてプラトン以来の対話の根幹をなす「弁証法」という概念です。
これは、AとBという相反する見解が存在するとき、それらを創造的に融合させてCという新たな認識を生み出す思考法です。この視点から見ると、対話と対論(ディベート)の差異が明確になります。
「対論」では、相手の主張を論破することが主眼となるため必然的に勝者と敗者が生まれます。AとBが対論を行い、Aが優位に立った場合、Aの立場は不変のまま、BがAの見解を受け入れることになります。これはある意味で思想的降伏を意味します。
これに対し「対話」は、参加者全員の変容を前提としています。
AもBも互いに影響し合い、双方が変化することで、Cという新たな思想的地平が開かれる。
これこそが弁証法的対話の真髄ですが、日本の文化的文脈では「自らの信念を曲げること」として抵抗感を抱く傾向があります。
しかし、真の対話の精神とは、異なる価値観を持つ者同士が互いの見解を摺り合わせる過程で、自己変容を厭わない態度にあります。さらに進んで、自己の変化そのものに積極的価値を見出す姿勢こそが、対話がもたらす最も豊かな恵みなのです。
この認識は、現代の多様化する社会において、異なる背景や価値観を持つ人々が共存し、創造的な解決策を模索する上で、ますます重要性を増しているような気がします。
解のない世界、対話という態度
この作品は一国の政治や文明化を論じる際の視点の多様性を、その構造自体によって巧みに提示しています。こうした文学的手法が展開される本書からは、「中庸の価値」という今日的な教訓も浮かび上がってきます。
洋学紳士と豪傑君の極論対決は、それぞれが単独では脆弱な思想基盤に立っていることを浮き彫りにしました。
理想主義と現実主義、いずれか一方に傾倒すれば問題解決の道筋を見誤る危険性があります。
南海先生が体現する中庸の立ち位置、すなわち「理想を保持しつつ現実と折り合う」という姿勢は、今日の政策形成においても示唆に富んでいます。
例えば、不安定な安全保障環境の中で平和国家を標榜する日本は、理想(平和主義)と現実(抑止力の必要性)の均衡を絶えず追求せざるを得ません。本書はこの難問に対し、極端な結論に飛びつくのではなく、対話と熟慮によって解を模索する知恵を私たちに伝えています。
現代日本、そして世界では、過激な思想やイデオロギーが声高に主張され、インターネットがそれを増幅し、そうした極端な言説に引き寄せられる人々が増加しています。このような状況下で、立場を異にする人々の意見に耳を傾け、「君の気持ちは理解できるが」と寄り添いながら中庸の道を提示しようとした中江兆民の著作を再読することには、大きな現代的意義があると考えます。
もちろん、南海先生の一見するとまるで結論のような主張であっても、そのテクストの語り手、受け手によっては相対化されてしまうでしょう。
真の対話を実現するためには、相手の見解を打ち負かすのではなく、異なる意見の存在を認め、互いが変容することを厭わないという前提が不可欠です。この過程を通じてこそ議論は新たな地平へと到達できるのです。この基本的理解なくして対話を基調とする社会の構築は不可能でしょう。
この文章を執筆している私は現在36歳。良くも悪くも「現代の若者は」と感じてしまう事もある年になりました。しかし嘆くばかりではいけません。正しく向き合い、社会と自己の変化を直視していく必要があるのです。
異なる立場や意見に向き合い、自己変容を受容するという「対話の本質」を理解しなくてはなりません。
自律的思考と対話の実践。
社会的分断が深まる現在、時間と労力を要するこの二つの営みの重要性を一貫して説いた中江兆民の遺産を再読することは、極めて意義深い時間となりました。