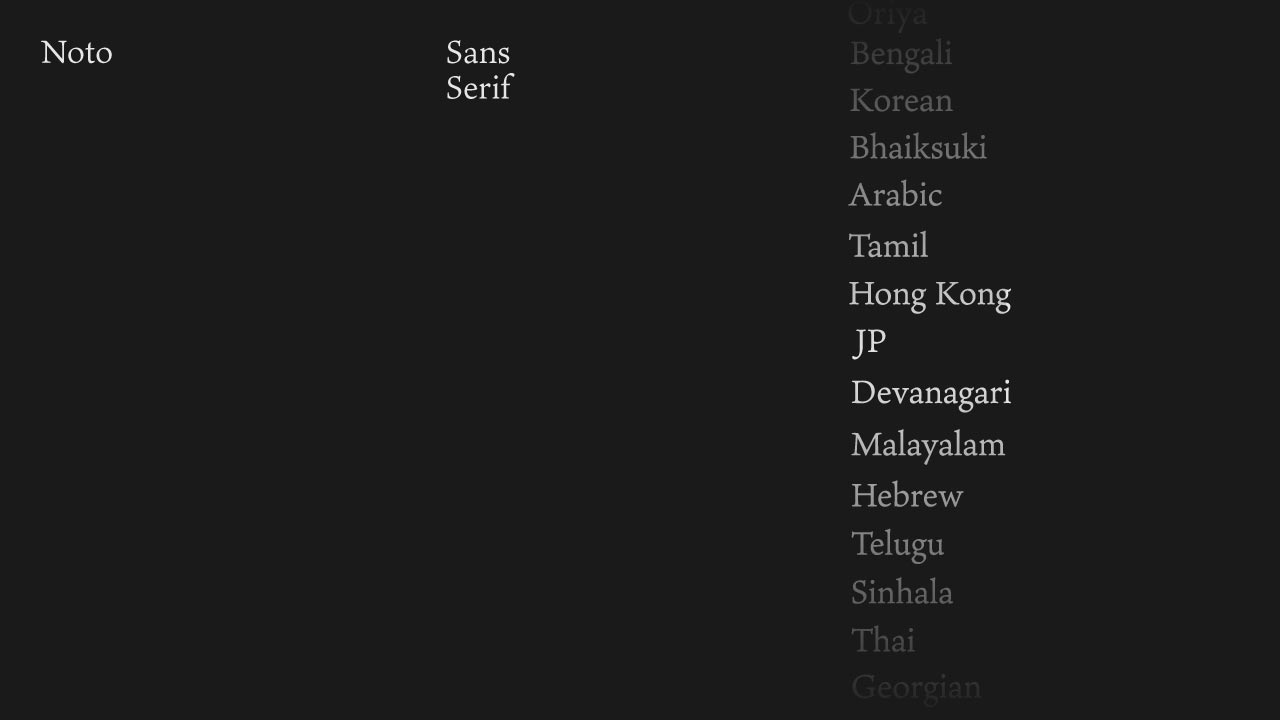ここ数年のウェブサイト制作において「フォントはNoto Sans JPで(またはNoto Serif JPで)」という選択が多くなりました。
デザイン提案の際も「安全で読みやすい日本語フォント」として、採用する機会が多いのも事実です。
無料で使える高品質な日本語フォントとして制作現場に革命をもたらしたNoto Sans JPは、今や私たちデザイナーの「定番」と言っても過言ではないと思います。
ただ、ふと立ち止まって考えてみると、その選択は本当にベストなのでしょうか。「とりあえずNoto」という習慣が、知らず知らずのうちに身についてしまっていることもあるかもしれません。
提供開始から約10年が経過した今、改めてNotoとの付き合い方を見直してみたいと思います。
気づけば「定番」になっていたNoto
最近、気になるWebサイトをデベロッパーツールで覗いてみると、「あ、ここもNoto Sans JP使ってるなー」ということが本当に多くなりました。
実際に弊社の過去1年間の案件を振り返ってみると、多くのプロジェクトでNoto Sans JPを採用しています。
サブスクリプション型の有償フォントと比べるとクライアントへの説明もしやすく、表示も安定しており、そして何よりも無料である点。制作者としてはメリットばかりのフォントである一方、競合他社のサイトを調査した際に「またNotoか」と感じる場面も増えているのも事実です。
同じ業界の企業サイトが軒並みNoto Sans JPを使用している状況を目にすると、差別化の機会を逸しているのではないかという疑問が頭をよぎります。
デザイナーとして、フォント選択という重要な判断を「定番だから」という理由だけで済ませてしまって良いのでしょうか。
そもそも、なぜNotoだったのか?
Noto Sans JPが登場した2014年頃の制作環境を振り返ってみます。
当時、私たちデザイナーは日本語Webフォントの選択肢の少なさに本当に苦労していました。
游ゴシックという選択肢もありましたが、レンダリングが不安定で、特にWindows環境では細すぎて読みづらくなる問題で頭を抱えていたのは記憶に新しいのではないでしょうか。
一方、ユニークなフォントの多くは商用利用時のライセンス制約があり、クライアントへの説明も複雑になりがちです。結果として、多くのサイトが環境依存のフォント表示に頼らざるを得ない状況でした。
そんな中でのNoto Sans JPの登場は、まさに「救世主」。
Google Fontsとして配信される安定性、CDNによる高速読み込み、そして何より商用利用可能なオープンソースライセンス。これらすべてが無料で提供されるという事実は、当時の制作現場にとって革命的だったのです。
私自身も初めてNoto Sans JPを使った時の「やっと安心して提案できる日本語フォントが手に入った」という安堵感を今でも覚えています。
当時の選択は、間違いなく合理的なものでした。
Notoプロジェクトの目指す理想
ここで重要なのは、私たちが日常的に使用しているNoto Sans JPが、実は壮大なグローバルプロジェクトの一部だということです。
Notoプロジェクトは「No More Tofu」(文字化けをなくそう)という理念のもと、世界中の1,000以上の言語、150以上の文字体系をカバーすることを目指しています。
デジタル環境における言語格差の解消、つまり「すべての人が自分の言語で情報にアクセスできる世界」の実現を目指した取り組みなのです。
Noto Sans JPは、この壮大な理想の中で日本語話者のために開発された一つのピースに過ぎません。ラテン文字、アラビア文字、漢字、ひらがな、カタカナ、これら異なる文字体系が視覚的に調和するよう細部まで調整が施されています。
私たちが「使いやすいフォント」として何気なく選択しているNoto Sans JPの背景には、「文化的多様性を尊重しながらも統一されたデザインシステムを構築する」という、非常に高い技術的・デザイン的挑戦があるのです。
Notoが変えたもの、変えられなかったもの
Noto Sans JPおよびNoto系フォントの普及は、確実に制作現場を変えました。
フォント選択にかける時間が短縮され、クライアントへの説明も「Googleが開発した無料の高品質フォント」として安心して提案できるようになりました。特に多言語サイトの制作では、Notoファミリー内で統一できることの恩恵は計り知れません。
一方で、変えられなかった、あるいは新たに生まれた課題もあります。最も大きいのは、日本語タイポグラフィの画一化です。
タイポグラフィはデザインにおいて極めて重要な要素の一つであるにも関わらず、多くのサイトが同じフォントを使用することで、ブランドごとの個性や差別化が困難になっているのが現実です。
また、「Notoなら安全」という意識が強すぎるあまり、フォント選択における創意工夫や、プロジェクトの性格に応じた最適化の検討がおろそかになってしまうことも時にあると思います。
他の選択肢と比較してみる
現在の日本語Webフォント環境は、Noto登場時と比べてかなり充実してきています。
Adobe Fontsでは小塚ゴシックやりょうゴシック、FONTPLUS、TypeSquareなどの有料サービスでは、より多様な選択肢が提供されています。
例えば、高級感や上品さを演出したいプロジェクトでは「筑紫明朝」や「源ノ明朝」、信頼性や専門性を重視する場合は「小塚ゴシック」や「貂明朝」、親しみやすさを表現したい場合は「M PLUS Rounded 1c」といった具合に、プロジェクトの性格に応じた最適解が存在します。
重要なのは、これらの選択肢をクライアントに提示し、ブランドイメージや目的に最も適したフォントを選定することです。
「Notoで十分」という判断も時には正しいと思います。ただ、その判断をする前に、他の選択肢にも少し目を向けてみても良いのかもしれません。
これからのNotoとの付き合い方
Noto Sans JPが「定番」になったからこそ、私たちデザイナーには改めて問われることがあります。
それは、フォント選択における専門性と責任です。
まず大切なのは、Notoを選ぶ理由を明確にすることです。「無料だから」「安全だから」ではなく「このプロジェクトの目的とターゲットに最も適しているから」という積極的な理由があるかどうか。
手癖で選ぶことなく、他の選択肢も検討するよう心がけることはとても大切だと思います。余談ですが、Google Fontsで提供されている日本語フォントは執筆時点で約50種類存在します。以下はその一例です。
可読性・視認性に優れたUD書体も提供されているため、フォント選定時の選択肢の一つとして入れてみるのも良いと思います。
「とりあえずNoto」から脱却し、複数の選択肢を総合考慮した上で意識的にNoto Sans JPを選択できるようになること。それが、制作現場に革命をもたらしてくれたこのフォントへの、私たちなりの敬意なのかもしれません。