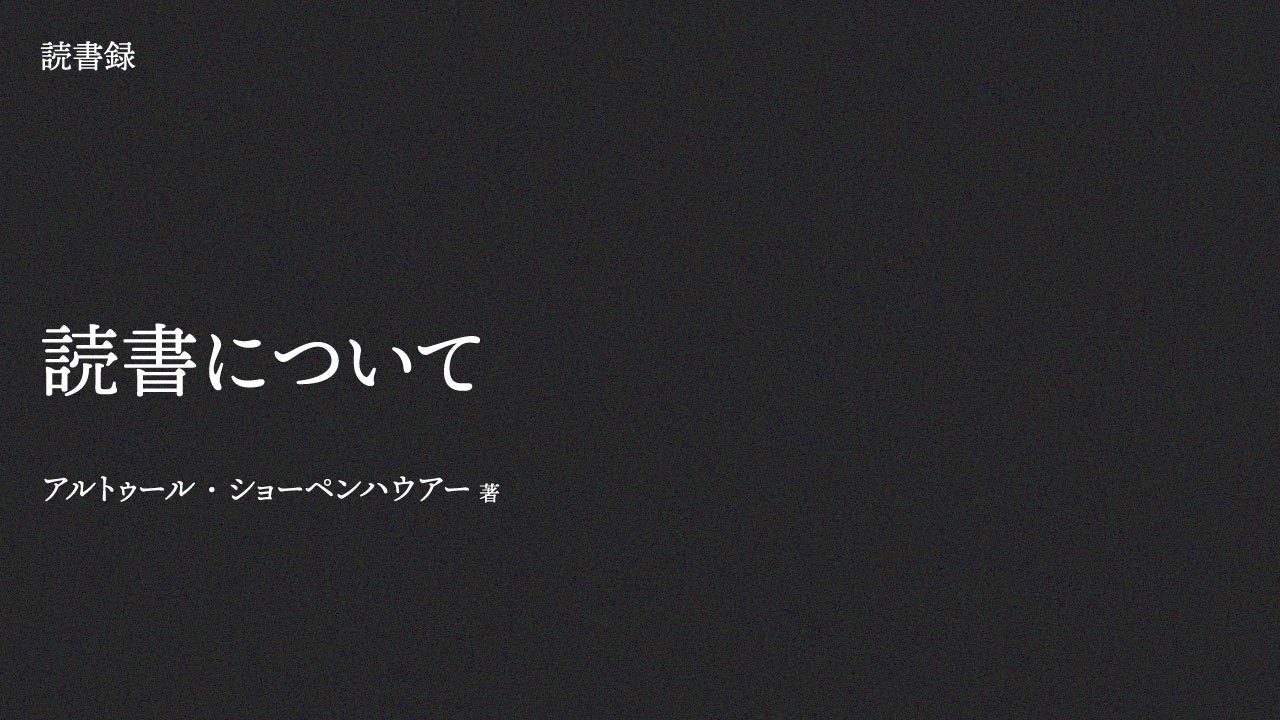1851年に初版が出た、ショーペンハウアーの小論集『読書について』。
読了後、まず最初に思ったのは、「執筆や編集に関わるすべての人が読むべきだな」ということ。次に湧いてきたのは、「いや、むしろ現代を生きる全員が読んだ方がいいのでは?」という感情でした。
AIによる文章生成、Xやnoteのインスタントな情報摂取、SEOライティング全盛の今。
書くことの価値や意味が、かつてないほど変質している感覚があります。
しかし最近、むしろ「書くこと」の価値は相対的に上がっているのではないか?と感じる場面が増えました。
手軽に情報を得られる今だからこそ、「何をどう書く」のか、そして「何をどう読む」のか。その質が問われているのではないかと思ったのです。
そう思って手に取ったのがこの本でしたが…。読んでみたら、想像の数倍、「読む」と「書く」の本質にぶん殴られたような読書体験になりました。
正直、かなりの精神的ダメージを負いました。笑
今回はそんな本、『読書について』の読書録です。
読むことは良いこと?それとも悪いこと?
「本を読むことは良いことだ」。
私は人生を通してそう信じていましたし、疑ったことがありませんでした。
知識を増やすこと、読書という豊かな体験そのものが「良いこと」であるのは当然だと、どこか盲目的に思っていたのです。
そんな私に、ショーペンハウアーは鋭すぎる言葉で切り込んできます。
「博覧強記の愛書家は文献から出発し、本から拾い集めた他人の意見を用いて、全体を構成する。それは異質な素材を寄せ集めて作られた自動人形のようなものだ。」
「本を読むとは、自分の頭ではなく、他人の頭で考えることだ。たえず本を読んでいると、他人の考えがどんどん流れ込んでくる。これは、一分のすきもなく完璧な体系とまではいかなくても理路整然たる全体像を展開させようとする、自分の頭で考える人にとって、マイナスにしかならない。なぜなら他人の考えはどれをとっても、ちがう精神から発し、ちがう体系に属し、ちがう色合いを帯びているので、決して思想・知識・洞察・確信が自然に融合してひとつにまとまってゆくことはなく、むしろ頭の中にバベルの塔 のような言葉の混乱をそっと引き起こすからだ。他人の考えがぎっしり詰め込まれた精神は、明晰な洞察力をことごとく失い、いまにも全面崩壊しそうだ。」
このような言葉が並びます。読んだ瞬間、言葉を失いました。
これはまさに、日々「知識のインプット」に追われ、読んだ端から忘れていく現代人の姿そのものではないかと思ったのです。
さらに、彼はこうも言います。
「人生を読書についやし、本から知識をくみとった人は、たくさんの旅行案内書をながめて、その土地に詳しくなった人のようなものだ。こうした人は雑多な情報を提供できるが、結局のところ、土地の実情についての知識はバラバラで、明確でも綿密でもない。」
「読書するとは、自分でものを考えずに、代わりに他人に考えてもらうことだ。他人の心の運びをなぞっているだけだ。」
あまりの辛辣さに、読んでいて悲しくなってしまったほどです…。しかし、だからこそこの本は、本質を突いているのだと思います。
「思考停止状態で本を読むな」と言われているようで、ただただ背筋が伸びる思いです。
書き手として学ぶべきこと
読むことの本質をこれでもかと突きつけられたあとに、次にやってくるのは、書くことへの猛烈な批評です。
弊社は日々、言葉を選び、構成を考え、丁寧に推敲を重ねながら原稿を書いているつもりです。
しかし、そんな営みに対してもショーペンハウアーは一切容赦がありません。
「まず物書きには二種類ある。テーマがあるから書くタイプと、書くために書くタイプだ。第一のタイプは思想や経験があり、それらは伝えるに値するものだと考えている。第二のタイプはお金が要るので、お金のために書く。書くために考える。できるかぎり長々と考えをつむぎだし、裏づけのない、ピントはずれの、わざとらしい、ふらふら不安定な考えをくだくだしく書き、またたいてい、ありもしないものをあるように見せかけるために、ぼかしを好み、文章にきっぱりした明快さが欠けることから、それがわかる。」
まるで現代の一部のコンテンツ大量生産システムを予見していたかのような描写です。
前者は、自らの思想や経験に価値を見出し、伝えるべき何かがあって筆を執る人。
後者は、書くという行為そのものを目的とし「何かを書かねばならない」状況に身を置く人。
これは非常に身に沁みました。
自分は第二のタイプになっていないだろうかと…。
自分の浅はかさを見透かされている気がして、読んでいてなんだか身震いするほどです。
「書くべきテーマがあるから書く人だけが、書くに値することを書く。」
彼の論は一貫しています。書き手として価値があるのは、たった一つ。「書くべきテーマがある」こと。そして、それを可能にする条件は、
「すぐれた文体であるための第一規則、それだけでもう十分といえそうな規則は、「主張すべきものがある」ことだ。これさえあれば、やっていける。」
のようです。
さらに、こんな言葉も続きます。
「ふつうの言葉を用いて、非凡なことを語りなさい。」
この言葉に、私は本当に打ちのめされました。
「うまく書こう」とすることの前に、「何を語るべきか」が問われている。そんな当たり前すぎることすら日々忘れがちだったような気がしています。
読めば読むほど最も本質的な問いが突き刺さってくるのです。
さて、この本が書かれたのは1851年、日本にペリーが来航する前の時代です。
200年近く前に書かれたこの文章が、デジタルやAIを駆使して文章を書こうとする現代の私たちに、これほどまでに鋭く響いてくるという事実に、ただただ震えます。
良書を読むこと
インプットは「毒」にも「糧」にもなると、ショーペンハウアーは言います。
「書くとき、素材をじかに自分の頭から取り出す人物だけが、読むに値する書き手だ。」とも言っています。
では、書き手である私たちは、何も読まずに書けというのでしょうか?そう反発したくなるところですが、彼の主張はもう少し複雑です。
たとえば彼はこうも言っています。先ほど引用した言葉をもう一度。
人生を読書についやし、本から知識をくみとった人は、たくさんの旅行案内書をながめて、その土地に詳しくなった人のようなものだ。
つまり、読書で得た知識は、実体験とは別物であり、あくまで断片的で寄せ集めのものだということ。
では私たちは、インプットなどせず、ただ「自分の頭」だけで考え続ければよいのでしょうか?
その問いに対し、ショーペンハウアーは次のように釘を刺します。
「無知は人間の品位を落とす。」
読書そのものを否定しているわけではないようです。むしろ、読書には正しいあり方があるのだと繰り返し説いているように思えました。
次の一文を。
「良書はどんなに頻繁に読んでも、読みすぎることはない。悪書は知性を毒し、精神をそこなう。」
ここで彼が言う「悪書」とは何か?
それは、おそらく「自分の頭で考えられていない本」であり、ただ儲けや話題性のために生成されたような文章のことを指しているのだと思います。
そしてもう一つ、印象的な一節を。
「読んだものをすべて覚えておきたがるのは、食べたものをみな身体にとどめておきたがるようなものだ。〜身体が自分と同質のものしか吸収しないように、私たちはみな、自分が興味あるもの、つまり自分の思想体系や目的に合うものしか自分の中にとどめておけない。〜思想体系がないと、何事に対しても公正な関心を寄せることができず、そのため本を読んでも、なにも身につかない。なにひとつ記憶にとどめておけないのだ。」
つまり、知識とは、読むことそのものではなく、選び、咀嚼し、自分の思想体系の中に溶かし込むプロセスを通してはじめて身になるということ。
読むという行為は、それ自体に価値があるのではなく、「何を読み、どう考え、どう自分の言葉に昇華するか」という態度が重要なのです。
この本を通じて、ショーペンハウアーはこう言っているのではないかと思いました。
「金儲けのために書かれた駄文を読んで読書した気になるな。真に思考する者の、重厚で、美しく、思想に裏打ちされた言葉にこそ耳を傾けろ。そして自らの頭で考える力を、鍛えろ。そして金儲けのための駄文を書くな。哲学を磨け。」
と。
「わかりました。ごめんなさい。」意外の言葉が出てきませんでした。
引用の中で、彼がシュレーゲルの次の言葉を引いているのも印象的でした。
「古人の書いたものを熱心に読みなさい。 まことの大家 を。 現代人が古人について論じたものは、たいしたことはない」 (シュレーゲル『古代の研究』)
現代の本ではなく、自ら古典に触れよと。原典を読むこと、それ自体が知性を鍛える道であることが、力強く語られています。
結びに:この時代だからこそ良い知識を大事に、自らの糧にし、自ら考えることを大事にする
現代は、誰もが「情報の発信者」になれる時代です。
ChatGPTのような生成AIは、リサーチも下書きもあっという間にこなしてくれます。SEO記事は定型化され、文体や構造を量産する手法も高度に洗練されています。
だからこそ「自分の頭で考える力」こそが、かつてないほど重要になっていると私は思います。
もちろん、よく設計され、調査されたSEO記事には価値があります。AIも、的確に使えば強力な補助線になることは論を待ちません。
でもそれらはあくまで手段であって、「書くこと」の本質は、あくまで何をどう考え、どう伝えたいかという意思から始まるべきでなのでしょう。
ショーペンハウアーが生きた19世紀と、私たちの生きる2020年代。情報のスピードも量も桁違いに変わりましたが、「書く人の姿勢」や「読むことの意味」は、案外何も変わっていないのかもしれません。きっと、ショーペンハウアーの時代のもっと昔から。
彼は、ホラティウスのこんな言葉を引用しています。
「正しく書く秘策は賢くあること」
本当に残る言葉とは、本当に伝わる文章とは、「正しく書かれたもの」以上に、「賢く考え抜かれたもの」なのだと思います。
『読書について』は、そんな当たり前のことを、骨の髄まで突きつけてくる一冊でした。
読むことも、書くことも、何気なくやりすごせばすぐに消費されていくこの時代において、改めて「言葉と向き合うことの重み」を思い出させてくれた本でした。