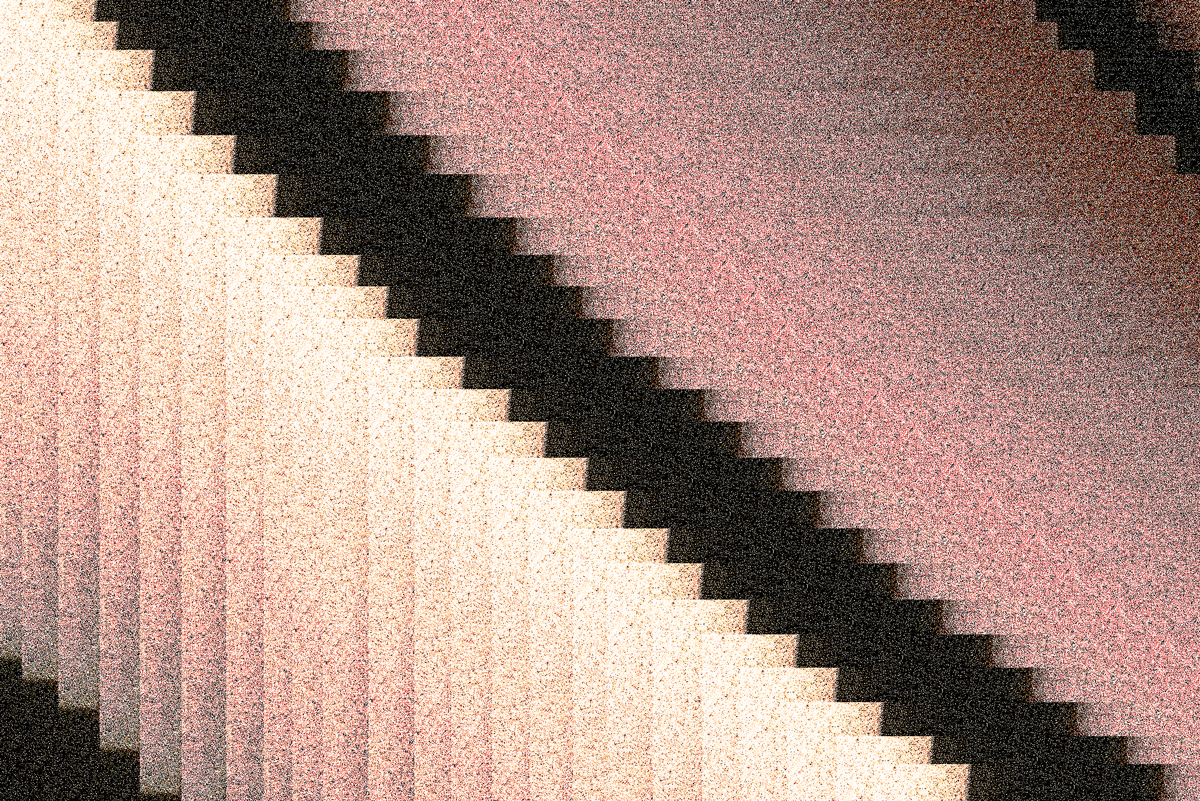今日は「自分の学び」についての振り返りにお付き合いください。
いきなりですが私は10代の頃から社会学やら哲学やら歴史やら古典やらといった、どちらかといえばちょっと抽象的な世界に心を奪われてきました。
しかし最近、足元の経営をもっと理解しなくてはならないと強く思いました。
例えば経営学、市場のことや会計や財務、税金や投資。
文化や思想を大事にしながらも、まず自分の生活と事業の基盤をきちんと知らなくてはいい経営はできません。当たり前の話なんですけどね…
しかし私にとっては深い反省を伴う気づきでした。
経営と文化。数字と思想。
これらは対立するものではなく、むしろ互いを照らし合う関係にあると思うんです。
数字を理解することは文化の仕組みを理解することにもつながり、哲学を学ぶことは経営の判断軸を支える「背骨」をつくる。
「足元を照らす知」と「遠くを照らす知」、その両方を学ぶことが、より良く生きるということだと、最近では思っています。
そんなお話です。
まず自分の学びの地図を描きなおすところから
私はこれまで、いわゆる「勉強が得意な人間」ではありませんでした。むしろ苦手です。
その時々で興味を持ったことを深掘りするのは好きでしたが「今必要なこと」を地道に学ぶ習慣はどこかで避けてきた気がします。
「好奇心は旺盛でも持続的な学びは不得意」というのが自己理解です。情けない自己理解ですね。
その特性が自分の成長をどこかで止めていたのだと、最近ようやく実感しています。
経営を始め、組織を背負い、家庭を築き、以前よりも多くの責任を持つようになってから「知らないことの怖さ」と「知ることの強さ」を身をもって感じるようになりました。
学ぶとは、単に知識を増やすことではありません。それは、自分の行動を支える“軸”を持つための行為のように思えます。
だからこそ「今自分は何を学ぶべきなんだっけ?」ということを考え直してみました。
私が改めて描き直したところ「学びの地図」は次の5つになりました。
- 経営を支える学び
- 実務を磨く学び
- お金と向き合う学び
- 人文知を深める学び
- 趣味と遊びの学び
どれもが人生の異なる方角を指しています。
ちょっと変な感覚かもしれませんが、このロードマップを描いた時、私の頭の中には自分の分身が5人生まれた感覚になりました。
主たる自分は中心にいながらも、それぞれの方向にそれぞれの自分が少しずつ歩みを進めることで、“今の自分”と“これからの自分”のあいだに橋が架かっていく感覚があります。
それぞれの方向で何を学ばなくてはいけないのか、さらにもう1階層整理してみました。
1 経営を支える学びについて
「経営をしている」という言葉は、なんだか曖昧だなと昔から思っていました。
会社を立ち上げ、売上を上げ、請求書を出していれば経営なのか?と聞かれるとなんだか違う気がします。
「自分は経営できてる?」と自問自答してみたところ、違和感がありました。「経営しているようで、経営していなかったのではないか…?」と素直に思ったのです。
経営とは、数字の管理や人の采配に留まるものではありません。それは「何を目指すのか」という意志を形づくるところに本質があると感じています。
会社という器の中に、どんな思想を流し込むのか。日々の判断を導く軸を、どんな理念で支えるのか。
この「骨格」を持たないまま走ると、どんなに努力をしても形だけが大きくなり、中身のない“空洞化した経営”に陥ってしまうと思うのです。
恥ずかしながら、私自身がそうでした。
数字に追われ、現場に追われ「なぜこの仕事をしているのか」という問いを置き去りにしていたことは否定できません。
そのため、まず1から経営学や会計や財務や税務や補助金制度などなど、経営の「基礎体力」を鍛える学びを積み直しています。
本を読み、歩きながら音声を聞き、とにかく今は常に経営にまつわる情報に触れるようにしています。
2 実務を磨く学びについて
実務に関する学びはこれまで劣後してしまっていました。「今まで通用してきたから、きっとこれからも大丈夫」という思い込みが少なからずあった気がしています。この態度が学びを遅らせてしまっていました。
大反省ですね。
技術も、デザインも、時代とともに凄まじい速さで変化します。昨日の成功は、今日の停滞に容易く変わってしまう。
気づけば、自分が一番嫌っていた“形骸化”の渦中に立っていたのです。
Webデザイン、グラフィック、SEO、広告、アクセス解析などなど。
それらは単なる技術ではなく、「世界との接点をどのように編集するか」という技術そのものです。
もはや会社の根幹そのものですね。
最近までちょっと停止してしまっていましたが、弊社では週に一度、朝の勉強会を開いています。
それぞれの専門領域を持つメンバーが、最新の技術や知見を共有する会です。
その場を借りながらも改めて、実務に関する技術をつけていかなければならないと思っています。
3 お金と向き合う学びについて
きっかけは、老後や家族の将来を具体的に考え始めたことでした。
自分の人生を、どう設計すればいいんだ?という問いは、理想の話ではなく、極めて現実的な問いです。
そしてその現実を支えるのが、お金という“構造”でした。
すごく無知だったこともあり、この数ヶ月間とにかく様々な本を読み漁り、勉強し、投資・資産運用・経済の仕組みを貪るように学んでいきました。
学べば学ぶほど、お金という存在が単なる数値でも欲望の象徴でもなく、「時間と選択の自由度」をつくる装置であるように思えてきます。
また、企業の決算書を読むようになると、それが経営の学びにもつながっていきます。
企業という生き物が、どんな思想で資本を動かしているのか。どんな哲学を、収支の裏に忍ばせているのか。それを読み解くことは、人間そのものの理解にも近いのかもしれません。
結局のところ、お金の学びとは、“生の有限性”を自覚するための訓練なのかもしれませんね。
限られた時間、限られた資源のなかで、何を守り、何を育て、何に投資するのか。
その問いの積み重ねが、人生設計となるのかなと思います。
4 人文知を深める学びについて
私が最も長く心を寄せてきた学びは、やはり人文の領域です。
哲学、美学、文学、歴史、宗教、文化…。
それらは実用とはほど遠く、すぐに成果をもたらすものでもありません。「投資」という観点で見ると、あまり魅力的な商品ではないかもしれませんね。
しかし私は、創作に向き合うとき、あるいは人に向き合うとき、この「無用の知」がどれほど重要かを、何度も思い知らされてきました。
編集やデザインの本質とは、結局のところ「人をどう理解するか」です。
人間を知らずして、美しさも、機能も、言葉も成り立ちません。人文知とは、人間という“不可解な存在”を観察し、その中に潜む秩序や欲望を、静かに見つめ直すための道具だと思うのです。
例えば哲学を学ぶことは、物事を一つの角度から見ない訓練でもあります。
「なんでそう考えるの?」と問い続ける姿勢は、経営やデザインの判断においても強力な武器になります。
また、歴史を学ぶことは、短期的な成功や失敗を超えて、人間の営みそのものの連続性に気づくことができます。
文化や芸術の理解は、感性を磨くことにとどまらず、「私たちが何を大切にしてきたのか」「なぜそれを美しいと感じるのか」などの社会の“記憶”を辿ることができます。
その問いを繰り返すうちに、少しずつ自分の中の「人間らしさ」が再び輪郭を取り戻していけるような気がするのです。
成果を急ぐこの時代において、人文知を学ぶということはとても非効率で、とても贅沢な行為です。
けれど、その贅沢こそが、社会に温度を取り戻すための“知の灯”なのだと信じています。
5 趣味と遊びの学びについて
私はあまり多趣味な人間ではありません。
ただ、お酒や音楽、アートの世界に触れているとき、なぜか心が少しやわらかくなるのを感じます。
新しいお酒に出会えば、その産地や哲学、どんな風土の中で育まれたものなのかを調べてみたくなります。
それは単なる情報収集ではなく、「この味の背後には、どんな人の時間が流れていたのだろう」という想像の旅のようなものです。
音楽やアートも同じです。
気になる作品に出会えば、その背景を辿りたくなりますし、作者がどんな時代を生き、どんな痛みや歓びを抱えていたのかを知りたくなります。
それを「勉強」と呼ぶのは少し違う気もしますが、その積み重ねが、私の中の“教養の地層”を形づくっている気がします。
ただの凝り性という言葉で片付けられるかもしれません。
しかし本当の豊かさは、「何のためでもなく、ただ好きだから続けること」の中に宿るのかもしれないなと思ったりします。
好きなことを深める時間は、社会的には無駄かもしれません。しかしその無駄こそが心に余白をつくり、他者への感受性を育ててくれます。
お酒を味わいながら世界を想う時間、音楽を聴きながら沈黙に身を委ねる時間。
その静かな瞬間瞬間の中に「学ぶとは本来こういうことなのかもしれない」と思うのです。
趣味的な学びとは、好きなものへの敬意のかたちなのかもしれません。
近い学びと遠い学びの間で
というわけでざっと5つの領域の学びを心がけるようになりました。
私はこれまで、どちらかというと“遠い射程の学び”を好んできました。
哲学、思想、文化などの学びは、時間の流れを越え、人間という存在を深く掘り下げるための時間でした。
が、「今を生きるための学び」が、あまりにも足りていなかったのではないかと思います。
いくら思想を語っても会計の仕組みを知らなければ、会社は回りません。
いくら歴史を学んでも明日の給与を払えなければ、仲間の生活をを守れません。
この世界をより良くしていくためには、理想と現実の両方に手を伸ばす必要があります。
遠くを見すぎれば足を取られ、足元ばかり見れば視野を失う。
だからこそ、今私が求めているのは「遠い学び」と「近い学び」をつなぐためのバランス感覚です。
遠い学びは、人生の方向を定める“北極星”のようなものです。
対する近い学びは、その星に向かって歩くための“羅針盤”のようなもの。
どちらか一方では、航路を見失ってしまうと思うのです。
近い学びが日々を豊かにし、遠い学びが人生を深くする。
この二つが重なったとき、人はようやく進むことができるのかもしれません。
学ぶことに終わりはありません。が、決してそれは苦行ではありません。
昨日より少しだけ深く世界を理解できること。誰かと語る言葉が、ほんの少しだけ豊かになること。その小さな積み重ねが大事なのです。
昨日より今日、今日より明日。近い学びと遠い学び。
私はこれからも、この“遠近の呼吸”を大切にしながら、学びを重ね、仕事を磨き、そして世界を少しでも美しく眺められる人間でありたいと思います。