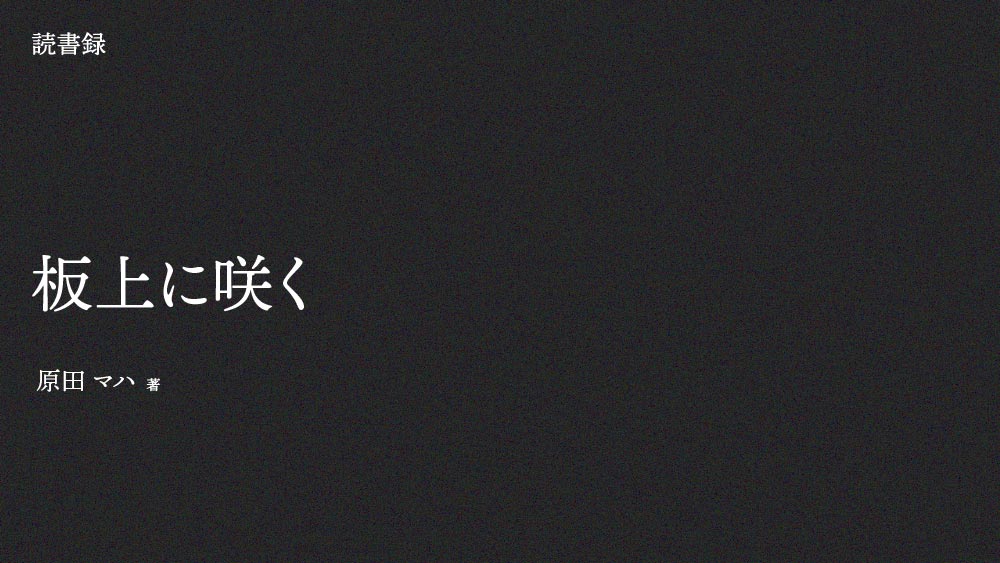現代日本では多くの小説家が活躍していますが、原田マハさんもその内の一人。アートや美術をテーマにした小説を数多く執筆している作家さんです。
私はアートや美術に関しては知識がなく、有名なアーティストの名前を片手で数える程度しか知りません。
そんな私が、ある一冊の小説と出会います。それが原田マハさんが執筆された「板上に咲く」。
これは棟方志功を題材に書かれた作品で、世界のムナカタになるまでのストーリーを妻のチヤ目線で語られる史実に基づいた物語です。
ページをめくるほどに、芸術家としての情熱と、それを支えた家族の愛の深さが描かれており、読者に勇気と感動を与えてくれます。
棟方志功の人生を愛と芸術、そして時代の激動をテーマにした作品
原田マハさんの小説「板上に咲く」は、版画家棟方志功の人生を妻の視点から描いた作品であり、愛と芸術、そして時代の激動をテーマにした作品です。
棟方志功はゴッホに憧れ、1924年に故郷である青森から上京。
しかし、絵を教えてくれる師もおらず、画材を買うお金もない中で棟方は木版画と出会います。弱視でありながらも、彼のひたむきな努力と妻との絆が、彼を「世界のムナカタ」へと導く物語です。
妻のチヤは、志功の苦悩や成功を見守りながら、彼を支える存在として描かれています。
本編では、チヤが志功に対する深い愛情が垣間見えます。棟方志功の人生を描いた小説で、彼の芸術活動と私生活に焦点を当てています。
稼ぎがない時代を支えてくれた松木夫妻の存在
本書では志功とチヤとの出会いから綴られており、結婚のきっかけから最後は世界のムネカタになるまでの半生を描いています。
まだ無名だった志功が単身で東京にでていき、友人である松木満史の自宅に間借りしていました。そして青森にいるチヤと手紙でやり取りしていた際に、一緒に住みたいと志功に頼み込みます。
しかし、志功は首を縦には振ってくれません。理由はまだまだ自分は模索中で、とてもじゃないが一緒に住むなどの余裕はないとのこと。
ただ、いつかきっと画家として成功し、その際はきっと呼び寄せるから、それまでは辛抱してほしいとチヤに伝えます。
しかしながら、画家としての成功はそう簡単にはいきません。志功はお金が稼げないことから、一緒に住むことは無理だと手紙に綴ります。
それを受けたチヤは、返事の手紙を書かずに志功がいる東京行きを決意します。
「こうなったら押しかけるしかない。」「なんと言われても行ってやる。」その一心がチヤを突き動きました。
結果的に志功と出会うことができますが、間借りしていた松木には妻がおり、ただでさえ稼ぎがない志功だけでも生活は厳しい。さらに志功とチヤには一人の子供がおり、同居となればさらに生活は逼迫してしまう。
そんな中でも松木夫妻はチヤと子供を受け入れ、一緒に住むことを承諾してくれました。
ゴッホを目指し油絵に取り組む棟方志功が木版画を選んだ理由
志功はゴッホの「ひまわり」を雑誌で見たことで、感銘を受けます。そしてゴッホに憧れ、ゴッホになりたいと油絵を描きますが、木版画との出会いを果たします。
それは川上澄生という版画家の木版画に触れ、その明瞭で詩情あふれる作風に志功はすっかり心を奪われます。
いづれ木版画に夢中になりますが、友人の松木が諭します。
「本気で職業画家で成功を目指すのであれば、版画ではなく油絵に注力しろ」と。
それを聞いた志功は、ゴッホが夢中になった浮世絵を引き合いにだし説得します。
浮世絵は筆で描いた肉筆画と木版画に分類されます。ゴッホは、北斎、広重、歌麿、英泉といった日本の浮世絵をこよなく愛しました。浮世絵の魅力にはまったゴッホは、研究を重ねた結果それまでとは違った絵として生まれ変わったのです。
そんなゴッホが愛した浮世絵の道へと進みたいと。ゴッホの後を追いかける道ではなく、ゴッホが進もうとしたその先を目指したのです。
弱視を乗り越え独自のスタイルを確立した棟方志功
棟方志功は幼い頃から弱視だったこともあり、地を這う体勢で版木に覆い被さり板に顔を接近させて舐めるように掘る姿が印象的です。
本書では、視力が低下してきていることに気づく志功がチヤに手拭いで目隠しをするように伝える描写が描かれています。
心配そうに見守るチヤを尻目に、ザクッ、ザクッと版木を彫る音が響き、彫り目を手の感触で確かめながら少しづつ前進していきます。
勢い余り、右手に持っていた彫刻刀が左指をえぐりますが、血にまみれながら前進を続けました。チヤは吐息とともに涙が溢れますが、版画こそが志功なのだと実感します。
志功とチヤの睦まじさと家族に対する深い愛情
本書の中で、チヤが志功に対する深い愛情が垣間見える描写が何度か表現されています。
友人の松木夫妻の家に居候し、その後に家を借りることになりますが、当然ながら稼ぎはありません。
ただ、チヤは幸せでした。
離れ離れで暮らさなくてよく、これから先もどんなに辛くても、苦しくても志功とならばきっと乗り越えられる。ずっとついていこう。何があっても二人一緒に歩いていこうと。
また志功も家族愛に溢れた人間だった描写が描かれています。
徐々に画家としての才能を開花しつつある棟方志功。
そして単身、京都に向かい念願だったゴッホの「ひまわり」の実物を見に行くチャンスが訪れます。
しかし子供が高熱を出してしまうのです。医師からは大変危険な状態だと告げられ、このまま熱が下がらなければ命に関わると。
チヤは一瞬、見果てぬ夢の一つでもあったゴッホの「ひまわり」を見られるチャンスを邪魔したくないと伝えるのをためらいますが、自分の子供のために電報を打つことを決心します。
志功はゴッホに会いに行くはずの日に夜汽車を乗り継ぎ、自宅へと帰ってきました。
チヤは申し訳ない気持ちと嬉しい気持ちが入り混じります。
そして志功は、チヤに家族全員、元気でいる。そしていつか必ず、ふたりで会いにいこう。ほんものの「ひまわり」にと。
志功とチヤ夫妻の睦まじさと、家族に対する愛情が伝わるシーンでした。
戦争をきっかけに諦めかけた画家への道を、チヤの強い信念が世界のムナカタへと導く
第二次世界大戦が開戦され、空襲警報が不気味に鳴り響くなか、棟方一家は最低限の荷物を持って東京から富山への疎開を決定します。
ただ、志功が大切にしていた板木は東京の自宅に残したままでした。
それを知ったチヤは怒りを抑えられず、空襲警報が鳴り響く東京へ向かうことを決意します。
当然ながら志功は反対し、自分が東京に行くことを提案しますが、チヤの気持ちは変わりません。
「志功に何かあったらどうするの?誰が版画を創るの?誰が日本のゴッホになるの?」と、志功に詰め寄ります。
チヤは東京に出向き、棟方夫妻は離れ離れになります。
志功が大切にしていた板木を梱包し、手続きを済ませました。チヤは富山方面に向かう電車に乗り込みますが、その時に大空襲が起こります。
燃えている東京の街を見ながら、チヤの背中を怖気が駆け上がります。
鳴り響く空襲警報、爆撃音、逃げ惑う人々の悲鳴。聞こえるはずのない音を電車の座席で想像しながら、板木が燃え尽きてしまったかもしれないと後悔の念に苛まれました。
志功にとって命に等しい板木を失ってしまったことで、チヤは志功に対し、別れて欲しいと懇願します。志功の答えは「よく帰ってきてくれた。自分にとって最も大切なのは板木ではなくチヤ」だと。
結果として板木は奇跡的に志功の手元に届きます。
そこから、志功の代表作でもある「二菩薩釈迦十大弟子」の制作に着手。
1930年のサンパウロ・ビエンナーレ国際美術展で版画部門最高賞を受賞し、翌1931年のヴェネツィア・ビエンナーレ国際美術展ではグランプリの国際版画大賞を受賞しています。
日本のゴッホを目指した棟方は、ゴッホを超えて世界の「ムナカタ」となったのです。
結びに
原田マハさんのおかげで、私にとって棟方志功さんが特別なアーティストの一人となりました。
棟方志功はどんな状況であっても、挑戦することをやめませんでした。どんなにどん底でお金がなくても、誰かにダメだと言われても、おかしな人だと思われても、物がよく見えなくても、志功は諦めませんでした。
それは彼の強い信念も見受けられますが、妻のチヤの存在が大きかったのではないかと思います。
志功を支えるチヤの献身的な姿も象徴的ですが、家族を想うシーンも印象的です。
また現代では、夢を語ることに対して後ろ向きな意見も少なくありません。棟方志功のように純粋に夢を語り、取り組む姿勢は忘れてはいけない気がします。
あくまでも史実を基にしたフィクションではありますが、アートに触れるきっかけだけではなく夫婦の在り方を考え直す一冊とも言えるでしょう。