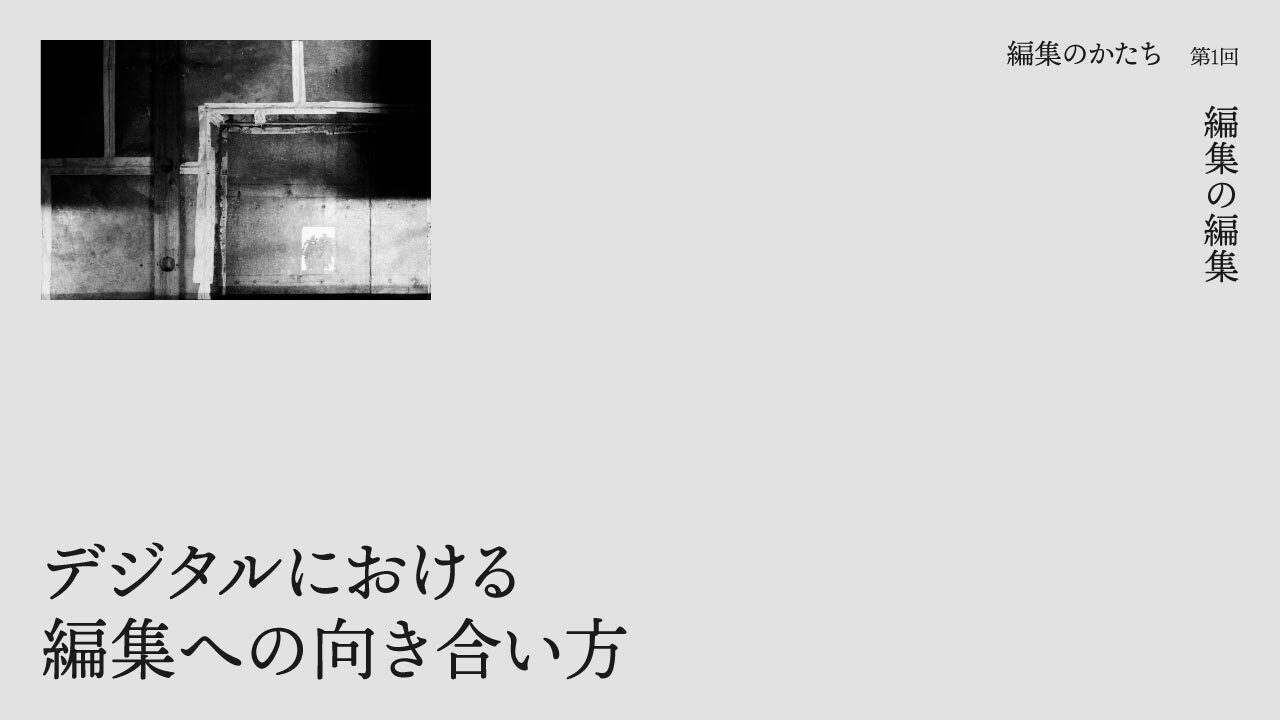編集 / デザインプロダクションである私たちは、日々どのように「編集」という営みに向き合っているのか。
その内側を少しずつ言葉にしていくために、今回から「編集のかたち」という連載を始めたいと思います。
「編集」という仕事は、非常に体系化しづらい領域です。
この仕事は単に文章を直したり構成を整えたりすることではないと思っています。それらはあくまで結果として現れる「技法」の一部にすぎません。
編集という態度を端的に表すなら「伝えるべき価値と向き合い、それをどう届けるかを考え抜くこと」だと私たちは捉えています。
決まりきった手順や明快なマニュアルがあるわけではなく、常に思考を巡らせながら、時には手探りで、時には直感に頼りつつ、ストイックに取り組み続ける必要がある仕事です。
それに「編集」と一口に言ってもその関わり方は実に多様です。デザインと編集、写真と編集、記事と編集、SEOと編集、メディアと編集……。デジタル空間で織りなされるコンテンツにおいては、編集の持つ意味や可能性がもはや単一の定義では捉えきれないほど広がっています。
そこでこの連載では、多角的な視点から「編集」について考えてみたいと思います。
第一回のテーマは「編集の編集」。
「編集」という概念そのものをどのように捉え、どのように考えるのかという問いに向き合っていこうと思います。
そのため、今回は具体的な技法や即効性のある方法論は扱いません。「こうすれば上手くいく」という安易な答えを提示するのではなく「編集という営みとどう向き合うべきか」という精神性に焦点を当てるつもりです。
私たちは普段、オウンドメディアや企業ブログ、SEO文脈のコンテンツ設計など、時に雑誌などの出版物に関わることもあれど、基本的にはデジタル空間における執筆と編集を主な業務としている企業です。
だからこそ、この連載でも「紙の編集」というよりは「デジタル空間における編集」を中心に思考を深めていきたいと考えています。
しかし、連載では「これが正解だ」ということを提示するつもりはありません。人や会社、現場や目的によって、編集のかたちは実に多様だからです。お伝えできるのは、あくまで私たち自身が日々の実践のなかで模索し続けている編集との対話の一断面にすぎません。
「編集ってなんだろう?」
改めてこの問いを、私たちなりに掘り下げてみたいと思います。
この連載が、いつかどこかで誰かの問いかけや思考の一助となれば、これに勝る喜びはありません。
私たちにとって編集とは何か
編集という響きから具体的にどのような仕事を連想するでしょうか?
100人いれば100通りの答えがあるかもしれませんね。
文字を添削する人。原稿に赤字を入れる人。書籍や雑誌を作る人。動画を調整する人。音をサンプリングする人。
様々な実践が「編集」という言葉で括られています。
私の周りでは「場を編集する人」「スポーツを編集する人」「チームを編集する人」などもいて、もはや何が何だか判然としない状況にあります。
編集とは何かふわりとした「輪郭しか持たない概念」のようです。
では私たちは「編集」をどう捉え直せばよいのか。
前提となる思考は「情報と情報を繋げて新たな情報を生成すること」。これが編集の根幹にあると考えています。
そして、そこから生まれた意味や情報の集合体が「コンテンツ」として現れます。
私たちが生きる現代では、高度な思想も大衆的な娯楽も、様々な文化的要素を吸収しながら変容し続けています。
本が電子と結びつき、映像技術がSNSと融合する。あらゆる様式が他の様式と結合するこの時代において、その複雑な編み目を読み解き、再構成する営み、それこそが「編集」という実践の核心なのかもしれません。
松岡正剛の「情報はひとりではいられない」という言葉は、編集という行為の本質を見事に言い表しています。情報は常に他の情報との関係性の中でこそ、その価値を発揮するからです。
あらゆる情報を「編集可能なもの」として捉える視座
さて、梅棹忠夫の『知的生産の技術』。この1969年に出版された先見的著作の中に、私は編集の本質を垣間見た気がします。
この本には次のような一節があります。
ここで知的生産とよんでいるのは、人間の知的活動が、なにか新しい情報の生産にむけられているような場合である、とかんがえていいであろう。
この場合、情報というのは、なんでもいい。 知恵、思想、かんがえ、報道、叙述、そのほか、十分ひろく解釈しておいていい。
つまり、かんたんにいえば、知的生産というのは、頭をはたらかせて、なにかあたらしいことがらー情報ーを、ひとにわたるかたちで提出することなのだ、くらいに考えておけばよいだろう。この場合、知的生産という概念は、一方では知的活動以外のものによる生産の概念に対立し、他方では知的な消費という概念に対立するものとなる。
人間の生産活動には、いろいろの種類のものがある。たとえば、肉体労働によって物質やエネルギーを生産する。ところが、知的活動というものは、もしなにかを生産しているとすれば、それはいつも情報を生産しているのである。その情報が、物資やエネルギーの生産に役立つものであるにせよ、とにかく第一次的に知的活動の結果として生産されるのは、情報である。
さらにこう続きます。
ところが一方では、情報はいつでも知的活動の結果として生産されるとはかぎらない。 情報生産のなかにも、さまざまなものがあって、なかには知的生産とはいえないような情報生産もある。 たとえば、ピアノやバイオリンの演奏とか、舞踊の上演とか、おいしい料理をつくるとか、こういうものはいずれも情報生産にはちがいないが、知的情報生産とは区別したほうがいいだろう。いうならば、感覚的あるいは肉体的情報生産とでもいうべきであろうか。
知的生産とは、知的情報の生産であるといった。既存の、あるいは新規の、さまざまな情報をもとにして、それに、それぞれの人間の知的情報処理能力を作用させて、そこにあたらしい情報を作り出す作業なのである。 それは、単に一定の知識をもとでにしたルーティン・ワーク以上のものである。そこには、多少ともつねにあらたなる創造の要素がある。知的生産とは、かんがえることによる生産である。
現代における「編集」の本質を鋭く言い表していると感じます。
梅棹はこの著作で、すべての人間が情報の生産者となる社会の到来を予見していました。
情報過多の時代だからこそ、編集という営みには新たな価値が宿る。これは情報社会を主体的に生きるための知的態度であり、創造的技法だということは昔から変わっていないようです。
私たちは、あらゆる情報を「編集可能なもの」として捉える視座を持つべきでしょう。世界の価値観に絶対的なものはなく、常に別の角度から編み直す可能性に自覚的であるべきです。
世界は複雑で多様な文化が織り成す多層的な織物です。
それを表現するための「複雑で多様な物語を紡ぐ編集力」が今日求められていると感じるのです。
拡大するデジタルの世界、真に価値ある情報を生み出すためには
デジタル世界の拡大とAIの台頭は「即答」や「速報」の価値を高めました。しかし、その陰で情報を作るための思索や探究、身体を使った情報収集の優先度や重要性が相対的に低下してしまっているように思われます。
AIの活用自体は推奨すべきことですが、その出力を考えなしに受容したり、AIが生成した情報だけで「コンテンツ」を成立させようとする姿勢には慎重であるべきというのが私たちの考えです。
真に価値ある情報を生み出すためには、しばしばデジタルの世界を超えた経験や知見が不可欠だと思っているためです。
そのために古往今来、四方八方、あらゆる角度から対象に迫り、必要な情報を徹底的に収集する。時には狂気に近い情熱で対象と向き合う。そこに妥協の余地はありません。
端的に言えば「優れたコンテンツを創出するためならあらゆる知的努力を惜しまない」という姿勢。これこそが編集者に求められる職業倫理だと思うのです。
デジタル上のリサーチだけでコンテンツを作ろうとする姿勢が必ずしも間違いとは言えませんが、それは編集という深遠な知的実践の一部分に過ぎません。安易に情報を生産し流通させる責任感の薄さは、情報社会の質を低下させる危険をはらんでいるように感じてならないのです。
総じて、編集とは「情報をより意義ある形で結合、再構成し、より良く表現するための知的営為の総体」だと言っていいかもしれません。情報と情報を結びつけるというその実践には、知的誠実さと創造的情熱、そして何より対象への敬意が不可欠です。
明示化されていない知的資源、文化資源に独自性を付与するために
情報と情報を結びつけることは編集において極めて重要な観点ですが、ただ結びつけるだけではなかなか良い情報は生まれません。編集という営みによって情報に「独自性」「希少性」という付加価値を与えることが重要だと思っています。
この人の、あるいはこの会社のどこをどう見せれば本質が浮かび上がるだろうか。どのような視点と結びつければ新たな物語が生まれるのか。
その人や会社にしか持ち得ない独自の文化や知恵をまず見抜く眼差しが、編集者には求められます。
AIによる技術革新と編集の変容
さて、毎日のように生成AIの話題が取り沙汰される昨今。この技術の登場は編集という営みにとって大きな転換点となりました。
AIによる自動編集、自動文章生成が身近になり、ビッグデータ活用や機械学習、仮想現実を提示する力などなどに日々驚かされています。
しかし、新しい技術が社会を一変させることは人類史において特段珍しいことではないのです。
少しだけ歴史を遡ってみます。
まず、古代神話やアレクサンドリアの時代には、人類史上初の大規模な知識の集積と体系化が行われました。
飛んで15世紀、グーテンベルクの活版印刷。文芸復興、宗教改革、近世社会に大きく貢献したことは言うまでもありません。
ライプニッツやデカルト、ニュートンが活躍した17世紀のヨーロッパでは、科学革命とともに論理的思考と計算技術が飛躍的に発展。人間が自らの思考過程を形式化し、外部化する手段(論理記号や計算装置)を獲得した時代でした。
18〜19世紀の産業革命期には、人類は蒸気機関という新たな動力を手に入れ、機械による労働の自動化が本格化。蒸気機関の力により移動と通信の革命が引き起こされ、鉄道によって人や物資はかつてない速度で遠方へ運ばれます。都市と地方、国と国が密接に結ばれる「時間・空間の縮減」が生じました。
19世紀後半から20世紀初頭にかけては、人間の視覚や聴覚の体験をそのまま記録・複製する技術が次々と発明されました。写真(1839年のダゲレオタイプ)、音声録音(1877年のエジソンの蓄音機)、映画(1895年のリュミエール兄弟によるシネマトグラフ)といった技術の誕生がそれです。
20世紀後半から21世紀にかけて、人類はついに生命の設計図である遺伝子に直接手を加える技術を獲得しました。1970年代に出現した遺伝子操作(遺伝子工学)は、微生物のDNAを組み換えてインスリンなどの有用物質を作らせることから始まりましたが、シャルパンティエとダウドナのCRISPR技術によって、人間が進化のプロセスに介入し生命のコードを書き換える時代が到来しました(そこには当然、深遠な哲学的・倫理的問いが付随しますが)。
アレクサンドリアは知識を集約・体系化し、革新的な印刷技術は情報の普及を手伝い、近世合理主義は論理計算で思考を拡張し、産業革命は機械で肉体労働を代行し、複製技術は感性体験を量産・共有し、ゲノム編集は生命そのものを編集可能にしました。
多くの技術が社会を変え、便利さも悲しみも生み出してきました。
そして現代の生成AI。
これはこうした技術変革の延長線上に位置づけられると思っています。
さて、AIが瞬時に膨大な情報を処理し、人間の文体さえ模倣できる今日、編集者の役割とは何でしょうか。
AIは確かに驚異的な速度で文章を生成し、データを分析できます。しかし、その背後にある人間の経験や感情、文化的文脈を真に理解できているでしょうか。
編集者が持つ「人間の物語を見抜く眼差し」や「価値ある情報を嗅ぎ分ける感覚」は、単純にアルゴリズムで再現できるものではありません。
「人間が人間に対し非人間的になる」。スコットランドの農民詩人ロバート・バーンズのこの言葉は、現代の技術状況を予見したかのような響きを帯びています。
それではいけないのです。
AIによる自動生成コンテンツが氾濫する中で、編集者の役割はむしろ重要性を増していくと考えています。
情報の真偽を見極め、深層にある意味を掘り起こし、単なるデータの羅列ではなく人間の経験に根ざした物語として情報を紡ぎ直す役割。これからの編集者に求められるのはまさにこのような役割であり、編集を志す以上はより深く「人」に向き合う必要があると思うのです。
暗黙知と編集の未来
生成AIの性能は確かに驚異的です。そして凄まじく優秀です。既存のパターンから学習し、その範囲内で新たな組み合わせを生み出し、あらゆる情報を再現性をもって抽出してくれます。
デジタル上に存在する情報をただ編集すると言う意味では、もはやAIに人は勝てないかもしれません。
このような時代において特に私が危機感を覚えるのは、生成AIの台頭により「物事を編集的し、情報のつながりを深く見る」という人間特有の視点が希薄になってしまわないだろうかということです。
さて、グラハム・ダンスタン・マーティン著『暗黙知の領域』では、科学者であり思想家でもあるマイケル・ポランニーの「知識には暗黙知と明示知の二種類がある」とする思想が紹介されています。
明示知は「言葉になりうるもの、もしくはある種の象徴で表すことが可能な知識」とされます。一方の暗黙知はその逆。「言葉や象徴によってさえも表現し得ない知識」を指しています。
このような一文があります。
コンピュータ内の諸過程とそれが含む情報はことごとく、完全に明示化されたものであり、コンピュータに入り得る唯一の種類の情報とは明示化された知識である。
今現在AIが抽出できるのはこの明示知のみです。
しかし本当に価値があり、社会を豊かにするのは、人々の内側に潜在的に眠っている独自の情報や文化資源、すなわち「言葉にならない知識」です。
私たちは意外とこのような「言葉にならない知識」を多く知っているものです。
とても不思議ですが、そのような暗黙知を持つ当人は自分自身の知識や経験に独自性や価値があるとは思っていないことが多々あります。
その潜在的な価値を見出し、言語化を手伝い、より良い形で表現する。これは編集者の重要な使命の一つです。
これまでのビジネスでは「再現性」があることが重視されてきましたが、これからはより「独自性」が求められるようになるでしょう。
AIによる模倣コストが大幅に下がるほど「再現できないこと」「AI技術では捉えきれない人間の経験や感覚」に新たな価値が生まれてくると思うのです。
編集者は今後「再現できない独自性ある情報や振る舞い」をいかに魅力的な形で表現し、伝えていくかが強く求められると思っています。
人間の経験や感覚の深みを理解し、それを可視化すること。洪水のような情報の中から真に価値あるものを見極め、人間社会にとって意味のある形に再構成すること。
情報過多の時代だからこそ、編集という営みは新たな意義を帯びていくはずです。
編集者として生きるために重要なのは「編集業務以外の時間をどう生きるか」
書籍の表紙をパッとめくる。記事のリンクをクリックする。
そこに広がるのは文字や図版の世界ですが、本質的にはそこに「人」が宿っていると考えています。
スポーツに詳しい人、花に詳しい人、儒教に詳しい人、新聞に詳しい人、砂に詳しい人。色々な人がいます。そのテーマをずっと追いかけ、真に知り尽くした人の独自の知恵や貴重な経験が凝縮されている、そんな情報たち。
どうしてそんなに詳しくなったのか、その理由を知りたいものです。そしてそれは知ることができるのです。本や記事を読めば。
情報と人を結ぶ扉を作り、魅力的な情報へ誘うための編集
本や記事はその人が人生をかけて向き合ってきた「熱」や「宝物」と読者を出会わせてくれます。その意味では、本や記事は単なる「読み物」を超えた「扉」なのかもしれません。
私たち編集者はその扉を作る職人であり、扉の向こうに広がる世界を設計し、読者をその世界へと誘う案内人でもあります。
その扉を作らなくてはならない。その世界に誘わなくてはならない。このことをまず理解すべきでしょう。
どうすれば作れるか。どうすれば誘えるか。そのためには「人」というものと向き合わなくてはならないと思っています。
あやふやで、面倒で、でも底知れない豊かさを持つ人。その存在をどのように捉えるか、どう知るかは編集者の本質に関わる極めて大きな問いです。人が作り出してきたもの、壊してきたもの、守り継いできたもの、愛したもの、憎んだもの。あらゆる人間の営みに目を向けなければなりません。
日々「人のこと」とどう向き合うか
そんな「人を知る深い編集者」であるためには日々の生き方そのものが問われます。編集業務に従事していない時間に何を思ってどのようなことをしているか。そこが編集者にとって実は最も重要なんじゃないかなと思います。
情報と情報、いわば人と人を繋ぎ合わせる仕事である以上、常にありとあらゆる情報に対して敏感でなければなりません。漫然と日々を過ごす、学びを怠る。こうした態度は編集者としてあってはならないことでしょう。
様々なヒット作品を生み出してきた周囲の編集者たちは、驚くほどアクティブな人生を送っています。なぜそのような場所に足を運ぶのか、どうしてそのような知識を持ち合わせているのか。その行動原理に驚かされることも少なくありません(本人たちはただ楽しいからやっているだけということも多いですが)。
常に編集者としての意識を持ち、世界を眺める。疑問を抱き、調べ、学ぶ。それも徹底的に。
編集の仕事と向き合っていない時間、すなわちオフの時間をいかにインプットに充てられるか。いかに人に会うか。編集的アウトプットの良し悪しは、この見えない時間の使い方によって大きく左右されます。
日々漫然と生きている編集者に、良質な情報は作れません。
常にアンテナを張り、行動していれば企画はおのずと生まれてくるものです。しかし「行動の動機がなくても、行動してさえいればいい」という行動原理主義的な考え方が優位であってはなりません。
真に価値ある編集が生まれるのは、好奇心という内発的な動機と、世界への誠実な眼差しが交差する地点だからです。
一人では何も生み出せない編集者、その中空構造
さて、日々アンテナを張り、さまざまな場所に足を運び、多くの人と出会い、常に自己研鑽を怠らないストイックな編集者ですが、とても残念なお知らせです。
こんなに頑張っても基本的に編集者は自分では何も生み出せません。
色々なプロフェッショナルの方々や、人がこれまで紡いできた文化や歴史に助けられながら、なんとか情報と情報を繋ぎ合わせる仕事です。「このメディアでこんなことを書いたらいいかも」「この人とこの人が並んでいたら面白そう」「このテーマをこの角度から見てみたら新しい価値が生まれそうかも」みたいなことを、常に考え、常に形するのが編集者です。
企画や必要に応じて情報を繋ぎ合わせてなんとかいいものにするために必死で奔走する、そんな泥臭い人たちです。
中空構造という在り方
編集者は何も生み出せないと述べました。しかし何でも受け入れられる「中空構造的編集者」であるべきだと考えています。
日常的にあまり使用しない言葉かもしれませんが「中空」とは、外側だけがあって中が空洞の構造のことです。
この言葉を聞くと私はいつも何も入っていないふわふわとした球体を想像します。
外部のどのような情報もフラットに受容する容量があり、中で様々な情報を組み合わせる実験室のような存在。そんな印象を受けます。
何も固定されたものを持たないからこそ、あらゆる可能性に開かれている。そのある種の空虚さが豊かさの源泉となるという逆説。編集者とはある意味で、そのような中空構造を自らの内側に持ち、情報と情報の出会いによって絶えず新たな意味を生成し続ける存在なのかもしれないと思うのです。
さて、河合隼雄の『中空構造日本の深層』には次のような記述があります。
わが国が常に外来文化を取り入れ、時にはそれを中心においたかのごとく思わせながら、時がうつるにつれそれは日本化され、中央から離れてゆく。しかもそれは消え去るのではなく、他の多くのものと適切にバランスを取りながら、中心の空性を浮かびあがらせるために存在している。このようなパターンは、まさに神話に示された中空均衡形式そのままであると思われる。
何もないからこそ、何かで満たされる可能性が残されている。この言葉に編集者としての希望を見出した気がします。
しかもこれは非常に日本的な思考だと思うのです。
振り返れば、日本はまさにそのような姿勢で進化してきました。
中国から漢字や仏教思想を取り入れ、西洋から科学技術を学び、異なる価値観を融合させ、伝統と革新のバランスを模索し、独自の美学を育み、多様な要素を調和させて今の日本ができました。
日本らしさは本当に様々な編集性の上に成り立っているように感じるのです。
言語も文化も非常に柔軟で、海外の文化への好奇心も旺盛、そして新しいテクノロジーも積極的にどんどん取り込んでいく。この日本文化の特徴は、経済発展の原動力にもなっていたと思います。
日本という中空構造に長い年月をかけて様々な文化がぽんぽんと入っていた結果、様々な情報がぐるぐると混ざり、今の文化が出来上がりました。
中空構造は単に空虚なわけではありません。ただ空っぽなのではなく、常に編集可能な「なにか」が宿る場所なのです。
この中空構造の中にある「なにか」に編集者は向き合います。
固定観念や先入観に囚われず、あらゆる知識を受け入れ、それらを組み合わせて新たな価値を創出するその姿勢こそが良い編集の土台となると思っています。
静かに存在しながらも、内部では絶えず創造的な対話と実験が行われている空間。それは編集という営みの本質を象徴しているように思えます。
中空構造の両義性
しかし前述の『中空構造日本の深層』によれば、この中空構造は「ともすれば中央への理不尽な侵入を許しやすい欠点をもつ」という指摘もあります。
異質なものが入ってきた時、それを正しく検知し、必要に応じて適切に対応できるかどうか。何もかもを無批判に受容してしまうことは、別の問題を生じさせます。情報に濁りが発生してしまう。
中空構造は情報の対立を避け、様々な観点や論点を工夫し、加工するための器としては成立するものの、ゼロからのイノベーションには不向きかもしれませんね。
しかしそれでいいと思うんです。
編集者はゼロからイノベーションを起こす仕事ではなく、情報を適切に取り扱う仕事だと考えているからです。
社会を一変させるようなブレイクスルーを起こすのではなく、情報が正しくより良く扱われる時代を目指し、常に誠実さを保ち続け、時代の情報文化が間違った方向に進まないよう方向修正し続ける。これは編集者に課せられた重要な責務であり、誇らしい仕事です。
好奇心を原動力にできるか
編集という仕事はその舞台となる媒体によって求められる質や色調が変容します。
読者が現在欲している情報を探り出して表現する道もあれば、自らが必要と信じる視点を深く掘り下げる方法もあります。
編集には様々な方向性が存在するのです。
例えば自分の作りたい記事を作る場合は、当然ながら自らの知的好奇心を起点に記事を構築します。自身の好きなものに向き合い、その答えを求めて取材を重ねる、そんな編集のプロセスです。
このような編集企画の着火点には「自身が心底魅了される企画なのだからその感動は必ず読者に届くだろう」「自分と共鳴する感性を持つ人々が他にも存在するはずだ」というある種の直観的確信が原動力となります。
このように情報を編集する場合は、自分の発想や構想に制約をかけないことが大事です。
「これを実現できたら面白いかもしれないぞ」という閃きや事象に対して、どこまで追求できるか。実現不可能な理由を探し始めてしまえば優れた編集には至りません。
それに、自分自身が本当に心惹かれていなければ、一言の表現、一行の見出し、一枚の画像に対しても「より良い表現はないだろうか」「より明確に伝える方法はないだろうか」と徹底的に追求する情熱は湧かないものです。
このような情熱がない場合「最後のもう一踏ん張り」がなかなかできません。
この「最後のもう一踏ん張り」は作品のクオリティに非常に強く影響します。
もちろん、自分が強く関心を抱く分野であっても、知らないことの方が圧倒的に多いのは自明です。だからこそ徹底的な調査と探究が求められますが、これは編集の基本姿勢として当たり前のことでしょう。
常にわからないことの中に立つ
「本当に全く知らないこと」を徹底的に突き詰めなくてはならないタイプの編集も存在します。
いわゆるお客様からのご依頼による編集に特に多く見られるケースです。しかし重要なのは「自分の関心事を深く掘り下げる編集」と同等の情熱をもって、未知の対象と向き合えるかどうかです。
編集は常に「わからないことの中に立つ仕事」です。だからこそ好奇心が必要になります。
しかしそこに「解」はありません。
例えば技術者たちが専門用語で話し合う場面や、現場の細かな判断が交わされる瞬間。目の前で起きていることなのに、その意味をすぐには理解できないことがほとんどです。
そんな情報たちをより良い情報に編集しなくてはならない。
どうしよう、となります。
だからこそ編集者は学び続けます。取材対象と同じ言葉で話せるようになり、その立場から物事を見られるようになるために。
共通の言葉を持ち、お客様側に立ちたいから。
私たちの理解が深まるほど、対話や質問の質も上がり、企画も洗練されていきます。お客様の本当の価値を、より正確に、より魅力的に伝えられるようになります。
「自分が読者だったら、ここが知りたいな」と思えるまでお客様の世界に入り込めるかどうか。これは表面的な知識だけでは生まれない感覚であり、その世界に深く関わってはじめて得られる視点です。
もはやお客様の分身となれるまでお客様の立場に入り込めるか。お客様の役になりきれるか。ここは編集者として意識したいところです。
「お客様の役」になりきるために徹底的に探求する姿勢
少々話は逸れますが、映画俳優であるロバート・デ・ニーロの仕事の向き合い方がまさにこれに近いのではないかと思うのです。
こんなエピソードがあります。
- 「ゴッドファーザー」ではシシリア語を覚えるために撮影前にシチリア島で半年近く生活する。さらにヴィトー・コルレオーネ役のマーロン・ブラントのしゃがれ声を必死に練習して完璧に真似した。
- 「タクシードライバー」では実際に三週間、タクシードライバーとして働いた。主人公であるトラヴィスが不眠症であることを表現するため15kgも減量。役作りのため実際にモヒカンにもした。
- 「レイジング・ブル」ではチャンピオンまで上り詰めたプロボクサーの体を作るために徹底的に鍛え上げた。さらにそこから現役引退後の肥満体型を表現するためにそこから27kgも増量。
- 「レナードの朝」では嗜眠性脳炎の入院患者を演じるために撮影地になった病院で数ヶ月間入院生活を経験した。
などなど、これらはごく一部です。
いわゆる「デニーロ・アプローチ」と呼ばれる狂気的な役作りへの向き合い方には深い敬意を覚えます。この姿勢こそ、編集者が理想とすべき対象への没入の形だと思うのです。
表面的な理解ではなく、本質に触れるための徹底した探求。それが真に価値ある編集を生み出す源泉となると信じています。
お客様の領域の本を最低三冊読む。その上でありとあらゆるインプットをし、行動する
お客様の視点に立つためにありとあらゆることをして情報を集める。
そのためには今の自分の頭を信用しないことは重要なのではないかと思っています。だからこそ積極的に学び、とにかく多くの情報に触れる。
足を身体を動かし、現場で得た実感を伴う情報。これは本当に強い生命力を持ちます。机上で部品を組み替えただけの企画からは、本物の面白さは生まれません。
私たちの場合、お客様からの編集依頼を受けて仕事をします。基本的にはお客様の「黒子」として機能するわけです。
だからこそ、有識者の「目」を意識しなくてはなりません。
「あの人はいま何を見ているのか?」この問いを常に自分に投げかけたいものです。
この「あの人」をクライアントと位置づけるか、インタビュイーと考えるか、読者と捉えるか、あるいは自分自身と見なすか。その視点の選択によって、記事の方向性は大きく変化します。
そして「誰に対して」「なんのために」「どのように情報を集め」「どのように情報を接続させるのか」も考える必要があります。
これが編集および企画の前提です。
例えば弊社では新しい仕事に着手する際、お客様の業務に関連する本を最低3冊読むことを義務づけています。あくまで「最低」3冊であり、時には50冊近くを読破することもあります。
もちろんお客様の領域に関するニュースは欠かさずチェックします。定期的に書店を訪れ、常に最新情報に気を配る。有識者による動画コンテンツがあれば視聴し、セミナーにも積極的に参加します。調査できるものは、時間の許す限りとことん調べ上げるのです。
最低でもこれぐらいはしないと企画の種すら出せません。
私たち編集者はお客様が何を見ているのかをできる限り正しく理解する必要があります。そのためには徹底的にお客様の領域のこと、感度、感性を身につけなくてはならない。
西平直による『修養の思想』には、こんな一節があります。
重要なのは、「聖人の道を学ぶこと」と「聖人を学ぶこと」の区別である。前者は「聖人が学ぼうとしていた理想」であるのに対して、後者は「聖人の姿そのもの」。その具体的な身の振る舞い方である。徂徠によれば、私たちは後者を模倣すればよいのであって、その先の理念を求める必要はない。有名な「先師の求めたるところを求めよ」という言葉の正反対である。氏が求めた理念ではない。むしろ「先師の具体的な身の振る舞い」を真似る。聖人の心を学ぶのではない。聖人の姿をそのまま真似る。徂徠はそう説いた。
江戸の知性・荻生徂徠。
徂徠は学びの本質を「形の模倣」に見出しました。彼は聖人の教えに触れる際、その精神性を抽象的に捉えるのではなく、まず具体的な形式や作法を徹底的に模倣することを説いたのです。
さらにその先に「自得」を置きます。
徂徠は「自らが得ること」を何よりも尊び、そのプロセスにおける「思考」の重要性を強調しました。
あくまで自分の中に受け入れたものを考え直す、掴み直す、咀嚼し直す。これが大事だと。
まず徹底的に染まり、模倣し、そして独自の視点で捉え直す。表層に現れた形だけでなく、その背後に潜む「理」や「事物」の本質を見抜くことで、理解は深まります。この姿勢はまるで求道者のようであり、そして同時に編集という営みの本質とも重なるものがあります。
お客様が世界をどのような眼差しで見つめているのか。その視座に少しでも近づくために学び、その理解を基盤として向き合う。これが私たちが大切にしている編集における所作の一つです。
しかしこのプロセス一つとっても完成された型はありません。常に自己を磨き続け、高め続けること。この修養的な態度こそが、より優れた企画を、編集を、そして記事を生み出す土壌となります。
いかにより良い情報を仕入れるために奔走できるか
編集のため、企画のため、記事を書くため、様々な情報収集を行います。時にはこの情報収集が先行し、そこから企画が生まれることもあります。両者は常に相互作用する関係にあるのです。
情報の編集を行うには膨大な情報を仕入れる必要があります。私たちはお客様の業界に精通しているわけではないからこそ、この過程が不可欠です。
ここでは「勉強する」「行動する」という二つの軸が求められます。
まずその領域の文献をとにかく読む。そして「現場」に行って実際に見聞きする。
机上の学びと現場での体験、この両輪があってはじめて立体的な理解が可能になります。
ただ言葉の上で動いているだけの編集者ではいい言葉は作れません。
造り手と受け手の間に立つ「編集」という仕事だからこそ、人と人との関係値の中でこそ言葉を大切にする編集者でなければならないと思うのです。
前述のように最低3冊の専門書を読み、日々の情報をキャッチアップしていない状態では、そもそも有効な情報収集すら叶わないでしょう。
良質な情報を探り当てられるか。一次情報に辿り着けるか。どこまで行動的になれるか。これは何も特別なことではなく、何かを語るための前提として「真実」を知る必要があるからだけという、至極当然の話です。
「頭を使う」場所と「体を使う」場所を見極める。一度読んだ本をさらに深く読み返す。言葉だけの世界に閉じこもらず、人に聞きに行く。そんな姿勢が大切だと思うのです。
様々な大量の情報を縦横無尽に並べ、それらを意味あるグループに編成し、滑らかな流れへと紡いでいく。さらに、その専門領域だけに目を向けるのではなく、隣接する分野にも視野を広げる。そうすることで、対象世界の理解はより豊かな広がりを持ち始めます。
より価値ある情報を創出するため、既存の情報を有機的に繋ぐために、あらゆる手段を尽くします(もちろん倫理の範囲内で)。
そんな狂気的とも言える姿勢が編集には欠かせません。もはや編集とは単なる技術ではなく、一つの生き方なのではないかと思うほどです。
情報を扱うこと、文化の流れを刻むことへの責任へ自覚的になれるか
さて、多くのメディアには「歴史を記録し、伝える」という重要な使命があると思っています。
だからこそ半端な覚悟で編集という仕事に向き合いたくはありません。
「伝える」という行為は、本来極めて重い責任を伴います。そして「編集」とは単なる情報の整理や編纂を超えて、人や事象の本質的な価値を掘り起こす仕事です。
特定のメディアに言葉を刻むということは、文化や歴史を刻むことであると同時に、人の、そして人の心に向き合うことと同義だからです。
私たちが日々紡ぎ出す言葉は、一見するとデジタルの海に流れていくだけのように思えるかもしれません。しかし、それらは確かに時代の証言として残り続け、いつしか歴史の一部となっていくかもしれない。そのことに自覚的でありたいのです。
一つの記事、一つの企画。その「たった一つの編集」が誰かの人生の転機になることもあれば、社会の小さな変化のきっかけになることもあります。
時には後世の人々が現代を理解するための手がかりとなるかも知れません。こうした認識に立つとき、編集という仕事の重みを痛感します。
真に価値ある情報を伝えるためには、表層に現れた事象だけでなく、その背後にある文脈や、語られていない部分にも目を向ける必要があります。それは時として、社会の隅に追いやられた声に耳を傾け、光の当たらない場所に眠る物語を掘り起こす作業でもあるのです。
優れた編集者は、単に「わかりやすさ」や「読みやすさ」だけを追求するのではなく、時に読者を挑戦的な思考へと誘い、新たな視座を提供することも厭いません。しかし、そこには常に相手を尊重し、誠実に向き合うという倫理が根底に流れています。
かつて、権力や多数派の声だけが記録されてきた時代もありました。しかし現代のメディアには、より多様な視点から世界を描き出し、均衡のとれた記録を未来に残していく責務があると思うのです。
一つの出来事、一人の人生、一つの文化現象。
それらを切り取り伝えることは、単なる事実の羅列ではなく、人間の経験や感情、そして思想の深みまでをも写し取る営みです。
「伝える」という行為の背後にある膨大な責任と可能性を見つめながら、私たちは日々の編集業務に向き合っています。
それは時に重荷のように感じることもありますが、同時に、この上ない特権でもあるとも思うのです。
結びに – 不在の美学を追いかけて
偉そうに筆を進めてきましたが、私自身はまだ編集という営みの深淵には全く辿り着けていません。高き山の麓に立ち、遙か頂を仰ぎ見る旅人のような心持ちです。私は間違いなく編集という山の一合目にすら到達していないでしょう。
もう一度、梅棹忠夫著『知的生産の技術』から。
知的生産の技術には、王道はないだろうとおもう。これさえしっていたら、という安直なものはないだろうとおもう。合理主義に徹すればいい、などと、かんたんにかんがえてもらいたくないものである。 技術という以上は、ある種の合理性はもちろんかんがえなければなるまいが、知的活動のような、人間存在の根底にかかわっているものの場合には、いったいなにが合理的であるのか、きめることがむつかしいだろう。機械や事務組織なら、きわめて目的合理性の高いものをつくることもできるだろうが、人間はそうはゆかない。
知的生産の技術において、いちばんかんじんな点はなにかといえば、おそらくは、それについて、いろいろとかんがえてみること、そして、それを実行してみることだろう。 たえざる自己変革と自己訓練が必要なのである。
編集とは答えがありません。具体的に何をすることが編集だというルールもありません。
まるでバーリトゥードのように、なんでもありなのです。
しかし、こんなに求道的な仕事はそうそうないのではないかと思います。そしてその求道性が私は楽しいのです。
一生かけても到達できないかもしれない高みを目指す旅路。それは時に孤独な戦いを伴うかもしれませんが、その道中で出会う幾多の情報との邂逅はとても豊かなものです。
編集者の歩みは「メディアの特性を深く理解した上で、真に価値あるコンテンツを創造すること」に向けて進みます。そのために「あらゆる知見と技能を総動員し、情報を有機的に再構成し、メディアという媒体を通じて知の新たな連関を生み出し、社会に豊かな価値を提示すること」が求められるのだと考えています。
生半可な覚悟で編集という仕事に向き合うわけにはいきません。
編集は情報を扱う単なる技術的作業ではなく、文化の継承と創造に関わる重大な責任を伴うからです。それは人間の内面や社会の深層と誠実に対話することでもあります。表層的な事象のみを追うのではなく、その奥に広がる人間の心、生き方、営みの本質に迫る。
それは究極的には「人とは何か」を問い続けるような、静謐にして深遠な知の営みでもあるはずです。
時に思うのです。もしかすると編集者は、最終的には「透明」であるべきなのかもしれないと。
卓越した編集ほど自らの手の跡を消し去り、読者は媒介者の存在を意識することなく、伝えられる内容と直接対話できるようになる。その「不在」を目指すべきなのではないかと。
情報の海を静かに形作りながらも、自らは見えない底流のように存在する編集者。声高に主張せず、確かな存在でありながら影のように佇む美学。
そのような「底流の編集者」を目指すべく、編集の世界を漂い、人というものを探求し続けていきたいと思っています。