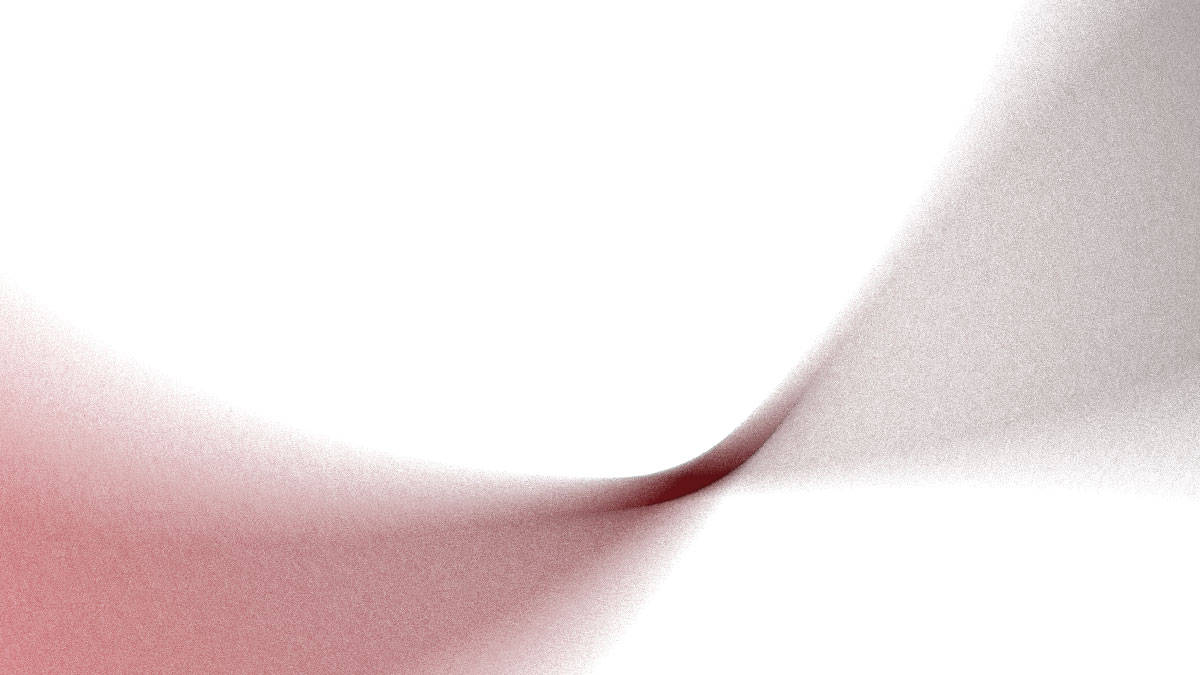「決めすぎても、決めなさすぎても、しんどい。」
ここ数年、仕事をしていて何度そう思ったかわかりません。
私たちの仕事は、設計もデザインも、文章づくりも、最初の段階では形のないものを扱います。だからある程度の“曖昧さ”は必要です。
ただ、その曖昧さをどこまで許容できるか、そしてどの段階で締めるべきか。それを見誤ると、途端にチームも自分も息が詰まってしまいます。
明確な答えを出すために動いているのに、答えを出すことそのものが負担になる。この矛盾をどう折り合いながら働けばいいのか、最近はよく考えるようになりました。
曖昧さが生む「自由」と「不安」
プロジェクトの初期には、何も決まっていない時間が必要です。
いきなり全てを詰めすぎると、いい意味での“遊び”が消えてしまう。発想の余地がなくなり、誰も息ができなくなります。
一方で、決めないまま進めると、いつの間にか「何をつくっているのか」が分からなくなる。会話は続いているのに、前進している感覚がない。
曖昧さは余白を生む反面、地図を失う危険を抱えています。
この“ふわふわ期間”の難しさは、当事者でないと伝わりにくいものです。誰かが「方向性をはっきりさせてください」と言えば、別の誰かが「まだ縛りたくない」と言う。どちらも間違っていないのに、空気がすこしずつ重くなります。
そして私自身も、どちらの側にも立ってきました。
早く決めたくて焦るときもあれば、決めることで可能性を狭めたくなくて逃げ腰になるときもある。
曖昧さとは、「まだいかようにでもなる」という希望と、「どうなるのか分からない」という不安が同居している状態なのだと思います。
決めることのリスク、決めないことのリスク
決めすぎると、あとが苦しくなります。
初期の段階で「これでいこう」と言ってしまうと、後から見直したくなっても変えにくい。「最初にそう言ったじゃないですか」と、言葉が枷になる。
けれど決めなすぎるのも、同じくらいしんどいものです。
判断を先送りしているうちに、みんなの温度が下がり、責任の所在もぼやけていく。「誰が決めるの?」という話ばかりが増える。
私も何度か、そうして自分で蒔いた曖昧さに振り回されたことがあります。
「もう少し考えよう」と言いながら、実際は“決める勇気”を先延ばしにしていただけだった。あとになって振り返ると、その時間がチームにとっていちばんの負担だったと気づきます。
どこまで決めるか、どこで止まるか。その判断の“タイミング”こそが、もっとも難しい設計なのかもしれません。
明確さと曖昧さの間にある「設計」
最近は、「曖昧さを残す勇気」と「締める覚悟」、その両方をどう持ち合わせるかを意識するようになりました。
つまり、どちらかに振り切るのではなく、その間で粘る力です。
「まだ決めない」ことを選ぶのは、何もしないことではありません。考えを寝かせ、材料を集め、判断の精度を上げるための時間です。
逆に、「ここで決めよう」と腹をくくるのも、チームの集中を取り戻すために欠かせないものだと思います。
理想は、曖昧さを段階的に狭めていくこと。最初はふわっとしていていい。でもどこかで輪郭を描き、必要な線を引く。それでも完全に曖昧さを消し去るのではなく、“活かせる余白”として残しておく。
とはいえ、曖昧さを上手く扱えるようになるには、経験と失敗の積み重ねが必要だと痛感しています。
曖昧さとともに働く
仕事をしていると、「決めてほしい」と「もう少し考えたい」の間で揺れ続けます。おそらくこの葛藤は、決してなくなることはないでしょう。
むしろ、それがあるからこそ、私たちは考え続けられるのかもしれません。
曖昧さは、成長の証でもあります。期限から逆算してまだ迷うことができる時間が残されているうちは、グレーの中でうろうろしてみる。
そのうち、どこかで一筋の線が見えてくる瞬間があります。
曖昧さとどう付き合うかを模索し続けることが、結局いちばん人間らしい働き方なのかもしれません。