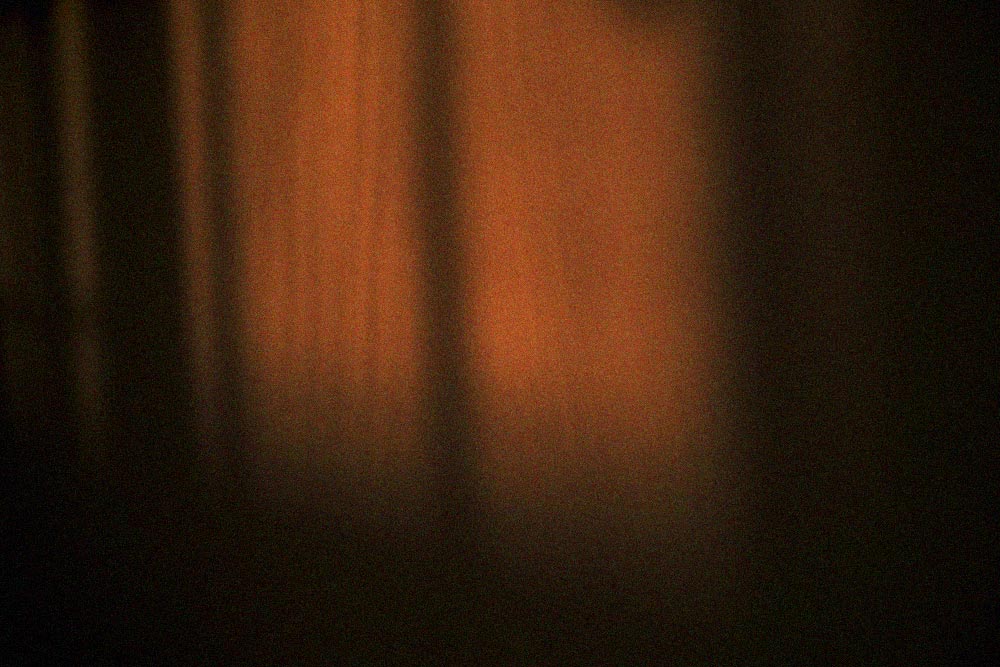ついこの間、ウェブサイトのデザイン時に利用する機会の多いフォント(Noto Sans JP)を見つめながらふと思ったことがあります。
なぜ私はいつもこのフォントを選んでいるのだろう。
可読性の高さや普遍的で匿名性の高い雰囲気は、クライアントの業種問わず使いやすいというのが主な理由かもしれませんが、本当にそれだけなのでしょうか。
考えてみれば、デザインワークやコーディングもなんとなく自分の「型」のようなものがあります。ガイドラインやレギュレーションよりも、もっと曖昧でふわっとしたものです。
手癖とか愛着とか、そんな表現が近いかもしれません。
愛着が生み出す心地よさと安心感
愛着とは不思議なものです。長く使い続けるツールやテクニック、コードの書き方やデザインのアプローチに、私たちは自然と愛着を持ちます。
毎日使うデザインツールの感触、よく書くコードのパターン。そこには確かな心地よさがあります。
例えば私の場合、CSS設計にはBEM(Block Element Modifier)手法を長年使い続けています。
クラス名を「block__element–modifier」という形で構造化する方法は、今では指が自然と動くほど身についています。新しいコンポーネントを設計する時も、まずはBEMの思考法でHTML構造とクラス名を整理することが習慣です。自然と手が動くくらいには使い慣れた設計手法のひとつかもしれません。
デザインとコーディングを行き来する仕事において、このような「無意識の領域」は貴重です。考える余裕が生まれ、より本質的な部分にエネルギーを注ぐことができるからです。
長く付き合ってきたツールやテクニックがもたらす安心感、「これなら失敗しない」という確信が、創作の土台を支えてくれます。その安心感が、時に大きな自信となり、難しいプロジェクトに立ち向かう勇気を与えてくれることもあります。
ツールのことが意識から消える瞬間が訪れる
愛着のあるツールやテクニックに頼ることは、単なる感情的な選択ではありません。
当然ながら、そこには明確な合理性があります。
特定のツールやテクニックに習熟することで作業効率は飛躍的に向上します。そして、習熟が進むと不思議なことが起きます。ツールそのものが意識からすーっと消えていくのです。
画家が筆を持つように、料理人が包丁を握るように、ツールは身体の一部となり、考えていることを直接形にするための「透明な媒体」へと変わります。
「ようやくここまできたな…」夥しい自分の足跡を見つめて思うわけです。しかしながら果たしてそれは、本当に喜ぶべきことなのでしょうか。
愛着の罠は「停滞」
愛着には危うさも潜んでいると思います。
ある晩、新規のお客様のデザインに取り組んでいた時のことです。クライアントから「いわゆる競合にありがちなデザインとは正反対のものを目指したい」と依頼されていました。
しかし気づけば、いつもの定番フォントを選び、お決まりのレイアウトパターンで作業に没頭する自分。
私たちは知らず知らずのうちに、心地よい習慣の檻に自らを閉じ込めてしまうことがあります。いつも同じツールに頼り、同じアプローチを取り続けることで、思考の柔軟性は少しずつ硬直していきます。
「今の方法で十分うまくいっている」と思い込み、学習の機会を逃し、その結果として業界全体の進化から取り残され、そしていつの間にか時代遅れのスキルセットを抱える。
「持っているのがハンマーだけなら、すべての問題が釘に見える」という格言があります。私たちは時に、問題自体よりも、いつもの思考法や使いたいツールに合わせて問題を捉えようとしてしまうのです。
新しい挑戦の価値と成長の機会
実は先日、長年使ってきたwebpackから新しいビルドツールであるViteへの移行しました。
というのも設定ファイルのwebpack.config.jsが「100年以上にわたって継ぎ足してきた老舗鰻屋の秘伝のタレ」のような状態になっていたため、この機会に一新してみようと考えたのです。
初めは設定ファイルの書き方の違いに頭を悩ませ、いつものwebpack環境の半分も効率が出せませんでした。やっぱり元も戻そうかな…と挫けかけたのも正直なところです。
しかし、数日間使い続けるうちに、ビルド速度の劇的な向上や、直感的な開発サーバーの恩恵を実感しました。道具が変わると発想も変わる、という当たり前でありながらつい忘れてしまいがちなことを再確認できた気がします。
特にIT界隈は流行り廃りが激しく、正直ついていくのが大変な時もあります。
昨日まで主流だったCSS設計手法が今日には別のアプローチに人気を奪われ、長年使っていたjQueryが「レガシー」と呼ばれるようになり…。すべての新技術を追いかけるのは現実的ではないですが、たまには勇気を出して「よし、今日からこれに挑戦してみよう」と決めて飛び込んでみることで、思わぬ発見があるかもしれません。
習熟と挑戦のバランスを考える
私が常に心がけているのは、新規案件をこなす際、最低1つは自分が今まで取り組んでこなかった手法を採用する、というものです。
本当はコンフォートゾーンから完全に脱却するくらい、挑戦という海に頭の先までどっぷり浸かるのが成長の近道なのだと思います。しかしながら、人間はそう強くありません。頭ではわかっていても、数十年生きていると人間そう簡単には変われないものです。
なのでまずは自分のできる範囲で精一杯の新しい取り組みを、自分のコンフォートゾーンから一歩踏み出す小さな習慣を取り入れることがとても大切だと思っています。(これは自戒を意味を込めて)
とはいえ実際のクライアントワークでは、納期が厳しく失敗が許されないことも多いと思います。その場合はもちろん習熟したツールや手法を駆使すること自体は否定されません。
でもその中で、ほんの少しで良いので「小さな挑戦」を混ぜ込んでみること、その積み重ねが自信と成長につながるのだと感じました。
結びに
自室の引き出しを開けると、何年も使い続けている無地のノートがあります。
ページをめくれば、私の思考とその変遷が記録されています。同じように好んで使うパターンと、時々現れる実験的な試みが混在しています。この混在こそが、歩みそのものなのだと思います。
デザイナーにとって、愛着と挑戦は決して対立するものではなく、互いを高め合う関係にあります。愛着があるからこそ、安心して挑戦できる。挑戦があるからこそ、愛着は形骸化せず生き続ける。
日々、この繊細なバランスを求めて試行錯誤を続けていますが、正直なところ完璧な答えはないと思います。それでも、時に立ち止まり、自分のデザインワークを見つめ直すことで、いつか自分だけの道を見つけられると信じています。