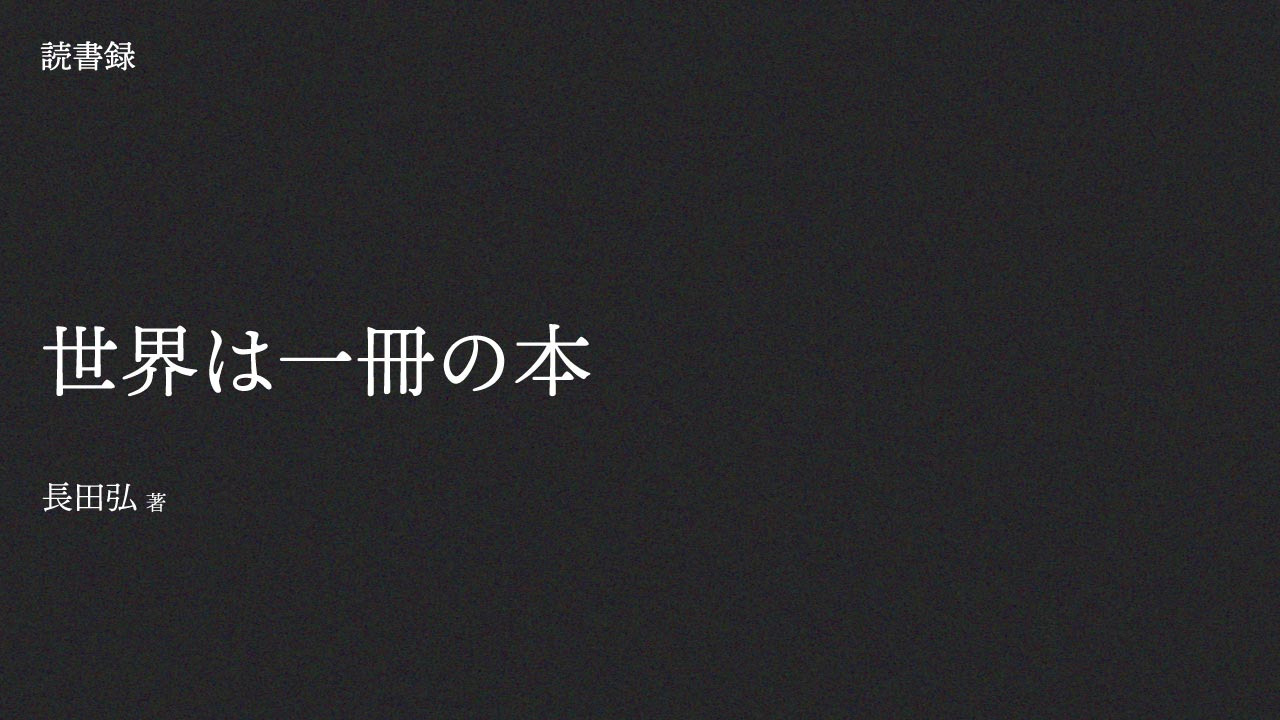今回は、いつもとは少し趣を変えて、とある詩集を手に取りました。長田弘さんの『世界は一冊の本』です。
この詩集は、声高に何かを主張するものではありません。周囲へのまなざし、ことばの手触り、別れをどう受け取るか。そうした日常の作法・眼差しが、17の短い詩の中で少しずつ綴られています。
読み終えて残るのは、結論や答えではなく、「どう立ちどまるか」という姿勢。
少し掴みどころのない部分も多かったですが、ゆえにその部分が一読者としての私に与えられた「余白」なのかもしれないとも感じました。
入口の三篇、寄る・止まる・呼ぶ
冒頭の三篇「誰でもない人」「立ちどまる」「ことば」は、この詩集全体の読み方を示す入り口になっています。
はじめの「誰でもない人」では、世の中の真ん中にいるわけではない人に、あえて目を向けます。華やかさや特別さよりも、「ここに確かに生きている」という存在感を拾い上げる姿勢です。
続いて「立ちどまる」では、急ぎすぎる生活の歩みを一度ゆるめ、目の前の風景をじっと見つめ直すことが描かれます。慌ただしい日常のなかで、忘れがちな「立ち止まる」という行為そのものが大切にされます。
そして「ことば」では、名前を呼ぶことの意味が強調されます。ものや人の名を丁寧に言い直すだけで、その輪郭がくっきりと立ち上がってくる。呼ぶことは、存在を確かめ直すことなのだと気づかされます。
以上3つの詩が示す、寄る・止まる・呼ぶという所作。それぞれはごく当たり前のことですが、冒頭で改めて示されることで、この後の17篇全体を読むときの基本の姿勢になります。どの詩にも、形を変えながらこの三つの動作が響いているように感じました。
別れを日常に馴染ませる
中盤には、友人や役者、詩人、名のない人、家族を見送る詩が続きます。
多くの文学やドラマでは、死別や別れは感情を強く動かす「山場」として描かれますが、この詩集で強調されるのは嘆きの大きさではありません。
火を弱める、窓を少し開ける、机を片づけるといった生活の手順。涙や絶叫の場面ではなく、生活の中の動作を通じて別れが自然と示されるのです。
別れは劇ではなく段取りとして現れ、手を動かすことで不在の重さが現実に馴染んでいく。「こう感じなさい」と指示しないことで、読み手が自分の記憶を自分の速さで開ける余地が保たれています。
悲しみを「山場」にせず「暮らしの続きの中で持てる重さ」にすること。この視線は、読後に長く残りました。
寓話が与えてくれる余白
詩のなかには、ときどき寓話の登場人物が現れます。
イソップの物語のように誰もが知っている話もあれば、歴史の影にそっと息を潜めているような人物もいます。
けれど、それらは「こうすべきだ」と説教するために差し込まれているわけではありません。むしろ、ものごとを少し引いて眺めるためのきっかけとして置かれているように見えます。
寓話は現実から離れているからこそ、読み手は直接の当事者として身構えずにすみます。少し距離をとることで、近すぎて見えなかった輪郭が自然と整うのです。
たとえば、いま目の前で悩んでいることを寓話の枠組みに置き換えてみると、答えは出なくても「どう考えるか」の姿勢が見えてくることもあります。本編において寓話は、読者への啓蒙ではなく「余白」を与えるために差し込まれているのかもしれません。
読み終えて、読みはじめる
世界は広すぎて全体を一度に理解することはできません。
けれど「一冊の本」と呼び直すことで、私たちはページをめくるように、少しずつ読むことができる存在として捉え直せます。
ページは薄く、だから今日もめくることができる。
読み終えて残るのは特別な答えではありません。けれど、湯をわかす、窓を開ける、名前を呼ぶといった何気ない行為に、読んだことばの余韻が重なっていきます。その感覚が次の一冊へと手を伸ばすきっかけになる。
この本を閉じることは、次の本を開く身振りにつながっています。世界は分厚いけれど、読めるのは一頁ずつ。だからこそ、また別の頁を、別の本を、めくってみたくなるのだと思います。