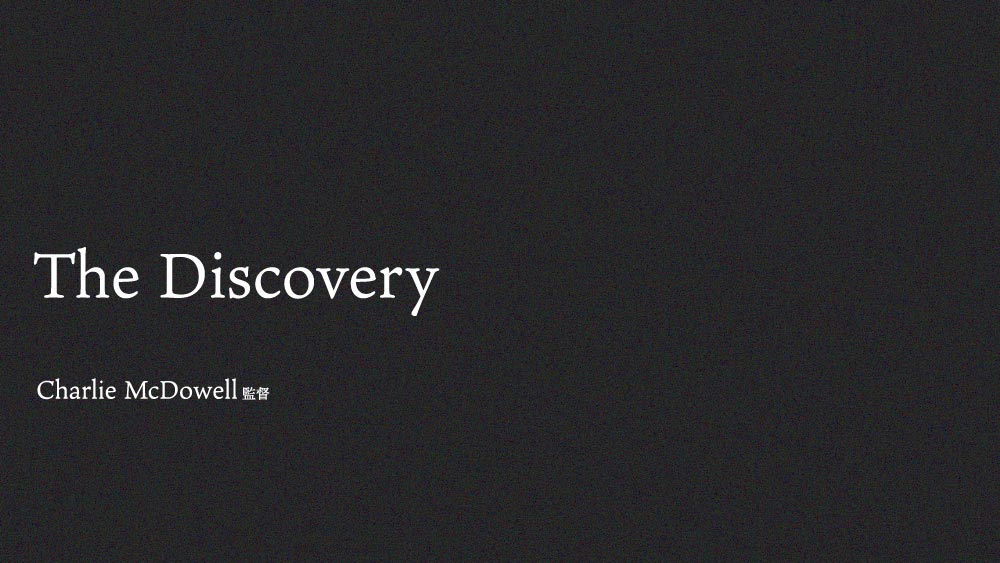先日、Netflixで2017年から公開されている映画「The Discovery(ザ・ディスカバリー)」を見ました。
あらすじ
科学者のトーマス・ハーバー博士は、死後の世界の存在を証明したと世間に公表。
人々は死後の世界に希望を求めるようになり、この世紀の発見によって100万人以上の自殺者が出る。
それでもなお研究を続ける博士に責任を感じる息子のウィルは、疎遠だった父に会うため故郷の島を訪れる。
ウィルは島へ向かうフェリーでアイラという女性と出会い、自殺を図る彼女を止めて博士のもとへ連れて行く。
ストーリー自体は、特別こだわりが感じられる内容ではなかったものの、題材は非常に興味深く、目を見張るものがありました。
特に、死後の世界が判明した後に100万人以上が自殺する、街中のさまざまなところに自殺防止のポスターが貼られているなど、妙にリアリティのある世界観のおかげなのか、映画の題材自体について考えさせられる雰囲気作りが印象的でした。
内容にネタバレを含むので、視聴する予定がある方はその後に読んでいただけると幸いです。
衝撃的な冒頭シーン
映画は開始早々、死後の世界の存在を証明するという、世紀の大発見をしたハーバー博士のインタビュー映像から始まります。
博士は「この発見を発表した後、なぜすぐにインタビューの場を設けなかったのか?」など、インタビュアーの質問を受けます。
発表からインタビューまでの期間に、100万人以上の自殺者が出たことについて、叱責するかのような質問も投げかけられます。
衝撃的だったのが、この発見は「脳の波長を補足した」のみにとどまると言うこと。
つまり、死後に脳波がどこかへ行くことが分かったのみで「どこに行き着くか」はもちろん、良いところに行くのか、悪いところに行くか、なども判明していません。
冒頭の段階では、そんなほとんど何も分かっていないような状況で100万人以上が自ら命を断っている状況です。
死後の世界の有無が判明していない現代社会においても、年々自殺者が増加する傾向にあることを踏まえると、気味が悪いような現実味があります。
そして、インタビューの途中で撮影のアシスタントと思われる人物が、拳銃自殺。参加者が慌てている傍らで、博士が呆然としてそれを見つめる映像でこのシーンが終わります。
後に博士の息子のウィルが故郷に向かうフェリーの中で、この出来事の後、自殺者が400万人以上にまで増えたことが判明します。
死後の世界と宗教を思わせる描写の関係
作中、ハーバー博士は実験を続けているのですが、島内にあるかつての更生施設を買取り、自殺未遂をした人々を集めて共同生活のような環境で暮らしています。
この施設を舞台にしたシーンでは、どこか宗教を感じるような雰囲気が散りばめられているのが印象的でした。
実際に、映画の題材になっている死後の世界は、キリスト教や仏教をはじめとした世の中の多くの宗教で、その本質に近いところで関係しています。
宗教ごとに考え方の違いはあれど、死後の世界に関して共有することで、信者としてあるべき姿を示したり、心の支えになったりするなど、基本的な部分は共通しているような気がします。
その存在自体が実際にあるかどうかが不明だからこそ「死後の世界」が宗教の考え方として成立しているのではないでしょうか。
ですが、本作は死後の世界の存在が判明している世界です。つまり、死後の行き先があることが判明しています。
死後の世界の存在が明らかになっている、さらには行き先まで判明しているような状況では、宗教ごとの考えに差は認められませんし、そもそも決まっている死後に対して考える必要もありません。
私はザ・ディスカバリーには、宗教とそれを否定する科学の、もしくは科学そのものに対する信仰のメタファーとして、宗教的な描写が取り入れられているのではないかなと感じました。
400万人以上にまで増加した自殺者の背景には、死後の世界の証明が世の中に絶望した自殺者予備軍の後押しになっただけではなく、宗教を心の支えとしていた人々の平穏や安心が成立しなくなったことによる影響もあったのではないかな、と想像せずにはいられませんでした。
死後の世界の存在が証明されている世界では、意味をなしていない自殺予防のポスターも皮肉のように映ります。
そして、死後の世界について考えるのは、宗教に限った話ではありません。
特定の信仰を持たなくても、死について正しく理解する前から多くの人が死後の行方について想いを巡らせた経験があるはずです。
本作は「死後の世界の存在が判明したら」と言う「もしも」を題材にしているため、ドキュメンタリーや実話をもとにした作品ではありませんが、誰もが経験しているような身近な考えをピンポイントで取り上げています。
ザ・ディスカバリーに、うまく言えない気持ちが悪いリアリティがあるのは、身近で答えのない題材を、脚色とは思えない現実的に起こってもおかしくないような感性で表現している作品だからなのかな、と思いました。