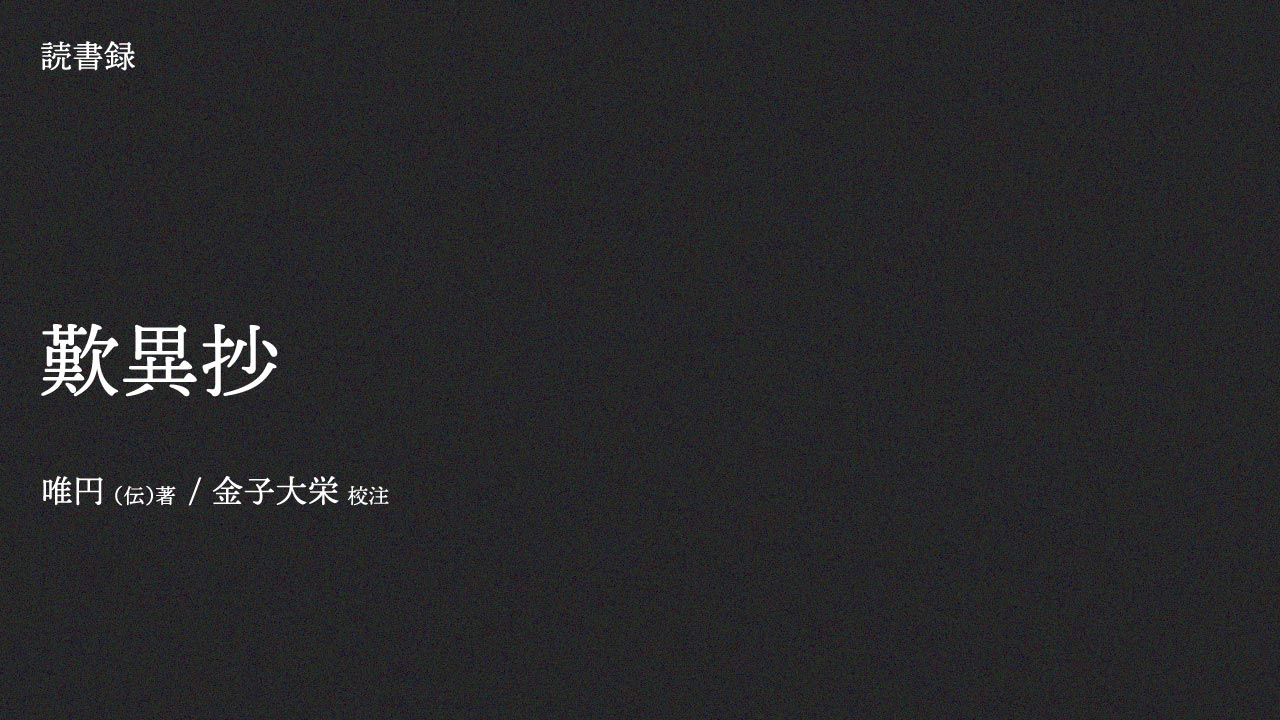『歎異抄』は、正応元年(1288)頃に成立したと伝えられる書物。
今から700年以上も前に書かれたこの書は、浄土真宗の開祖・親鸞聖人を直接知る唯円という人物が、師の語録とその解釈、さらに異端の説への批判をまとめたものとされています。
ただ、当時の原本は現存せず、後世に遺された写本のどれにも「著者名」が記されていないため、正式な著者がはっきりしないという事情もあるようです。
書名の「歎異抄」の由来は、その名の通り「異義を歎く」こと。
親鸞が亡くなった後、師の教えから逸脱する解釈が広まるのを嘆いた唯円が、親鸞の真意を後世に伝えようと筆を執ったとされています。
カミソリ聖教と言われた秘本『歎異抄』
『歎異抄』は現在こそ「日本で最も読まれる仏教書のひとつ」と言われるほど広く知られていますが、江戸時代までは門外不出の秘本とされ、ほとんど世に知られていませんでした。
それは、浄土真宗の八代・蓮如上人が、この書物を「無宿善の機」(仏縁の浅い人)には見せるべきではない、と強く戒めていたためです。
蓮如上人は奥書にこう記しています。
歎異抄の蓮如上人の奥書
右この聖教は、当流大事の聖教たるなり。
無宿善の機に於ては左右無くこれを許すべからざるものなり。
釈蓮如
「無宿善の機」とは仏縁の浅い人、親鸞聖人の教えをよく分かっていない人のことです。そのような相手には、みだりにこの本を読ませてはならない、と上人は言うのです。
これは「仏教を深く理解してから読み進めないと、歎異抄には大変な誤解をする落とし穴があまりに多いので危険だよ」という警告だったのでしょう。
このことからか『歎異抄』には「カミソリ聖教」という異名がつきました。
子どもがカミソリを扱えば命に関わる大事故を起こしかねないように、仏教を深く学んでいない人が読むと誤解を招き、かえって害をなす恐れがあるという意味です。裏を返せば、それほどまでに内容が鋭利で深遠だということの証でもあります。
さて、明治時代になると、清沢満之(きよざわまんし)という学者によって世に紹介され、近代以降は多くの知識人の心を揺さぶることになりました。
京都学派を創始した西田幾多郎は「『臨済録』と『歎異抄』さえあれば生きていける」と語り、西田に学んだ三木清も「万巻の書の中から一冊を選ぶなら『歎異抄』を」と言い切っています。
司馬遼太郎、吉本隆明、遠藤周作、梅原猛など、多様な分野の思想家たちもこぞって『歎異抄』に傾倒したことは、その思想が日本の精神文化にいかに深い影響を与えてきたかを物語っていますね。
真に善と言い切れるもの
『歎異抄』には実に多くの示唆に富んだ言葉が散見されますが、中でもこの箇所が印象的でした。
聖人のつねのおほせには、弥陀の五劫思惟の願をよく案ずれば、ひとへに親鸞一人がためなりけり、さればそくばくの業をもちける身にてありけるを、たすけんとおぼしめしたちける本願のかたじけなさよ
「弥陀仏が五劫もの長きにわたって思惟し立てられた本願を、よくよく考えてみると、それはただひとえにこの親鸞一人のためであったのだ。それほどの深い業を抱えた身でありながらも、なお救おうと思し召された本願の、何とありがたいことか。」こんな意味です。
阿弥陀仏の存在意義とは、まさに「私を救うため」にある、と言う言葉。この「親鸞一人のため」という言葉は、決して親鸞自身だけが特別であるという意味ではなく「阿弥陀仏の救済は万人のためであるが、それを私一人のためと感じることこそが大切である」ということを表しているようです。
ここまで他力の存在を疑いなく信じきる、という感覚は、現代人にとってはむしろ稀有なものかもしれません。
他の章ですが以下も印象的でした。
善悪のふたつ、総じてもて存知せざるなり。
「何が善であり、何が悪であるのか、私にはまったくわからない」と語った親鸞の姿勢は、私たちが日々の暮らしのなかで区別しがちな善悪という評価軸を相対化し、根本から問い直しているようにも思えます。
師と仰いだ聖徳太子の「世間虚仮唯仏是真」(世の事象はすべて仮であり、ただ仏の教えだけが真実である)を継承し、「ただ念仏のみぞまこと」と言い切った背景には、「世間的な善悪の区別」よりも、「仏の教えそれ自体」にこそ不動の価値を見出そうとする徹底した姿勢がうかがえます。
『歎異抄』の根底には狂気的なまでの徹底した他力感覚があります。この他力感覚をもっとも鋭く表現したのが「悪人正機説」でしょう。
歎異抄を象徴する逆説「悪人正機説」
親鸞思想のエッセンスともいえるのが、第三条に記された「悪人正機説」でしょう。
『歎異抄』で最も有名な一文がこれです。
善人なほもつて往生をとぐ。いはんや悪人をや。しかるを世のひとつねにいはく、「悪人なほ往生す。いかにいはんや善人をや」。
善人でさえ浄土に往生することができる。まして悪人はいうまでもない。ところが世間の人は普通、「悪人でさえ往生するのだから、まして善人はいうまでもない」と言う。
あれ?なんだか違和感がありませんか?
一般的には「悪人であっても往生できるのだから、善人ならなおさら往生できるはずだ」という理解に落ち着きそうなところを、親鸞は「善人さえ往生できる。まして私たち悪人ならなおさら往生できるはずだ」と転倒させます。
「悪人」とは単に道徳や法律を破る者ではなく「煩悩まみれで自力の修行に限界を抱える私たち自身」を意味しています。我々が想起する一般的な悪人とは意味が異なるのです。
一方、「善人」は、自分の徳や修行で浄土に往生できる思うあまり、「仏にすべてを任せる」という他力の心が薄い状態だと解釈されます。
つまり、阿弥陀仏の視点から見れば、みな等しく煩悩を抱えた「悪人」で、自分を善人だと思い込む人間の傲慢さこそが、真の救いを阻むのだと。
だからこそ「私こそが煩悩に支配され、救われるべき存在だ」と自覚することが、阿弥陀仏の本願の「正機」になるのだと説いています。
自分の修行や善根によって浄土に往生できると信じ、自力への執着を手放し、阿弥陀仏にすべてを委ねるという「他力」。この悪人正機説には、親鸞独特の逆説的でありながら深淵な洞察が凝縮されています。
あまりに美しい「狂気的な他力」
自らを悪と断じ続け救いを信ず。
『歎異抄』の根底にはまさに「狂気」と形容したくなるほどの徹底した他力感覚が貫かれているように思われてなりません。
日常の常識や倫理観を脱ぎ捨て「自力」への執着を根こそぎ手放す。その極みに至る感覚は、ときに危うさや危険性すら孕んでいるのではないかと感じるほどです。
逆説的に言えば、それほどまでに「自分の力ではどうにもならない」と思い知らされた「切羽詰まった人間の声」こそが、『歎異抄』最大の魅力の一つなのかもしれません。
理屈や道徳の向こう側でただ阿弥陀仏の本願に身を委ねる。自分のすべての思惑や努力が空しいものだと悟る瞬間は、理性の光では照らせないほどの暗がりに身を置くような感覚かもしれません。
もちろん、このような教えが誰にとっても受け入れやすいものではないでしょう。
蓮如上人が「無宿善の機(仏縁の浅い人)に軽々しく見せるべきではない」と戒めたほどの危うさが、まさにこの「狂気的なまでの他力」ゆえなのだと感じます。
しかし、そのような深淵さを持つからこそ、この書は幾多の知性を魅了し、何百年もの時を経てなお私たちの心に鋭く刺さるのかもしれません。『歎異抄』が投げかける問いの前に立つとき、私たちは自らの力の限界と他者への依存について、静かに、しかし避けがたく向き合わされます。
非僧非俗という「中空」の生き方
親鸞の生涯を眺めるうえで欠かせないのが「流罪記録」でしょう。
35歳で僧籍を剝奪され、「藤井善信」と改名させられたのち、親鸞は自らを「僧にあらず俗にあらず(中略)愚禿親鸞」と称しました。
いわゆる「半僧半俗」は日本の仏教史のなかでも数多く見られますが、親鸞は単に僧侶と俗人の中間に位置するだけでなく、二重否定とも言うべき「非僧非俗」を掲げることで既存の枠組みを根底から飛び越えようとしたのかもしれません。
たとえば、聖や沙弥、毛坊主など、僧侶のようでありながら俗人のようでもあるマージナルな存在が歴史上多数登場し、呪術を行ったり芸能民として活動したりと、多彩な役割を担ってきました。
親鸞が自分の生き方のモデルとした教信も、そんな「隙間の人」の一人でした。
今昔物語集や日本往生極楽記にも登場するこの人物は「沙弥」という、本来は「正式の僧侶になる前の見習い」という立場にありながら、日本的なあいまいさの中で、半僧半俗の境界線上を歩む道を選んだのです。
教信は出家修行を中断し、荷物運びなどの労働をしながら家族とともに念仏に生きた人物でした。村人からは「あみだまる」とあだ名されるほど常に念仏を唱え、葬儀も執り行ったといいます。
親鸞はそんな教信の生き方こそ自分の理想だと公言しました。
僧侶でも俗人でもない、宙吊りの「どちらでもない」在り方。
「どちらでもない」。
それはどの場所にも所属せず、どの集団にも帰属しない孤独な立ち位置でありながら、その分だけ厳粛さと覚悟が感じられます。
まるで日本文化の本質とも言える「中空構造」のような在り方です。
しかし親鸞はそこにこそ本当の自由を見出し、念仏を通して自己を貫いていきます。教信の姿を我が手本とし、自らも「愚禿」と名乗ったのです。
既成の立場を捨て去って浮遊するほどの強靭さと自覚は、並大抵の精神では到達し得ないでしょう。
私たちは往々にして安定や所属を求めがちですが親鸞はその安心さえも手放す道を選んだのです。
無常の世を前にして
私たちは日頃、あたかもこの柔らかな日常が永久に続くかのように暮らしています。けれども、災厄や事故、病によって、いつその光が闇に変わるかはわかりません。
どれだけ誠実に生きていても一瞬で暗転するのが人生の脆さです。
『歎異抄』第四条には、こうあります。
いかにいとほし不便と思ふとも、存知のごとくたすけがたければ、この慈悲始終なし。
「どんなに大切な人を想っても、思いどおりには助けられない。人間の慈悲は終始不完全である。だからこそ、念仏という仏の慈悲にのみ真実がある」という意味に受け取れます。
このような無常の世を前にして果たして私たちは何ができるのでしょうか。そこにこそ親鸞の思想が突きつけてくる根源的な問いがあるような気がしてならないのです。
人間の力はあまりに小さく、あまりに孤独です。
何ひとつ思い通りにできない自分に気づくとき、私たちは愕然とするかもしれません。
しかし、そのどうしようもなさを徹底的に自覚したときこそ、「では今、私はどう生きるのか」という真の問いが立ち上がる。そこにこそ、悪人正機であれ、非僧非俗であれ、親鸞が見据えた「本当の生」の在り方が潜んでいるように思われます。
「カミソリ」のごとき鋭い洞察が散りばめられつつも、多くの人を引き寄せてやまない『歎異抄』。
それは、人間の無力と無常を前提にしながらもなお新たな生の次元を切り開こうとする「親鸞の精神」が、いまなお私たちを導いているからかもしれません。
まさしく日本思想史の宝とも言えるその書を、古典としてではなく「今を生きるための書」として味読する意味は、そこに深く根ざしているのかもしれません。
窓の外の景色が変わっても、人間の心の内に潜む問いは700年の時を超えてなお、変わることがないのでしょう。