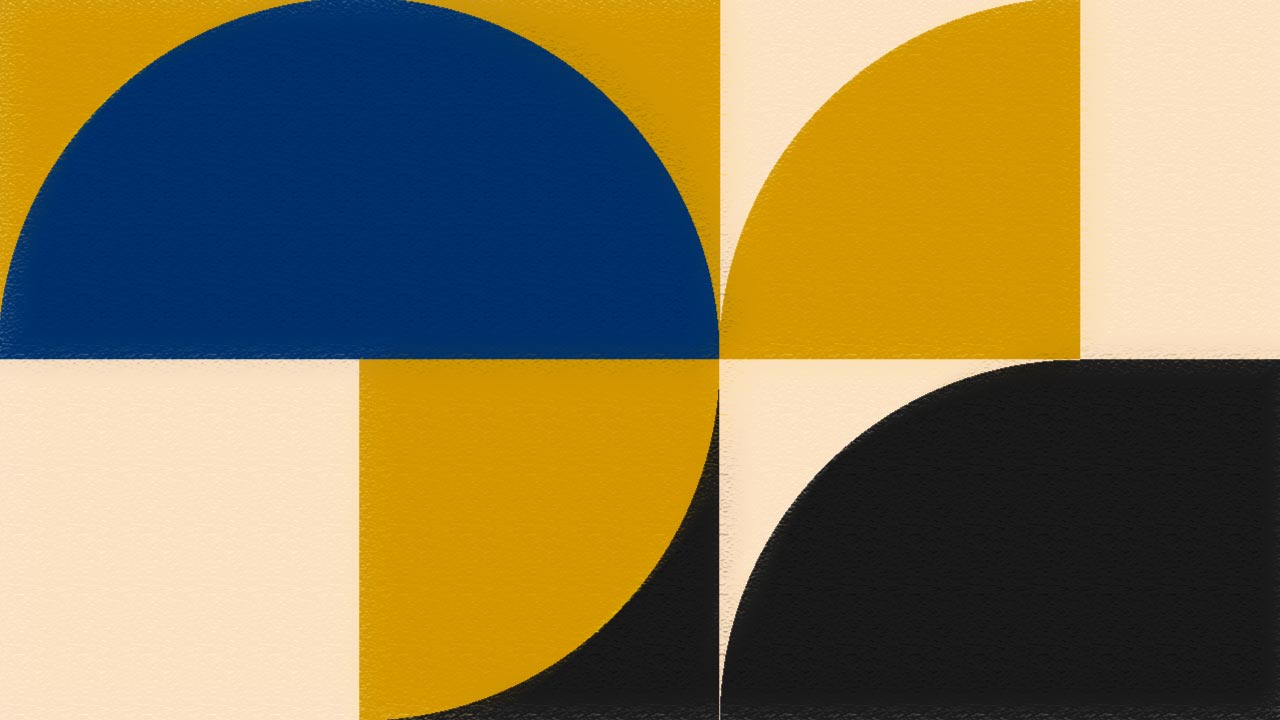デザインでも文章でも企画でも、出来上がった“表面”だけを見てもうまく模倣できないことがあります。
素敵だと思う理由はデザインの要素で説明できますが、その背後には、その人が読み、観て、聴き、経験してきたものが折り重なっているはずです。
最近は、リファレンス収集の手を止めて「その人は何を摂取してきたのか」「どんな問いを持ち続けてきたのか」を想像する時間を意識的に持つようになりました。
上澄みをなぞるだけでは届かない場所がそこには必ず存在していると思います。今回は、その気づきと自戒を込めて。
参照の前に“由来”を考える
デザインをしていると、誰かの手がけた作品に惹かれる瞬間がよくあります。
レイアウト、余白、文字の置き方、どれも整っていて、理屈抜きに「美しい」と感じる。けれどそのあと、ふと考えることがあります。
「なぜ自分はこのデザインに惹かれるのだろう。」
もちろん、色彩や構成といった表面的な要素を分析することはできます。でも本当に惹かれる理由は、もっと奥にある気がしています。その人の中に流れている何か、例えば読んだ本や、見た風景や、育ってきた環境のようなルーツの部分です。
私たちデザイナーの多くは競合のリファレンスを集め、比較し、その中でクライアントにとっての最適な伝え方を模索し続けてきました。
その点はこれから先も変わることはないと思います。でも、時折一度立ち止まって「これはどんな経験から生まれたのだろう」と想像してみる、最近はそんな時間を大切するのも良いかもしれません。
表現の背後にある価値観や思考の流れを読み取ろうとすると、見え方が大きく変わってきます。整っているだけに見えたデザインから、そこにデザイナーの“体温”のようなものを感じ取れるようになるのです。
上澄みを掬うだけでは足りない
良いものをお客様に提供したいと思うとき、まず始めに着手するのはヒアリング、そして調査です。
似たようなトーンのサイトを見たり、配色やフォントの使い方を研究したり。そこには間違いなく大事な意味があります。
けれど、どんなにリファレンスを重ねても、なかなか同じ仕上がりにはなりません。表層をなぞるだけではそのデザインに至った理由、「思考の源泉」に触れられないからです。
その人がどんな本を読んできたのか。どんな音楽を聴き、どんな人と会い、何に心を動かされてきたのか。デザインとは、そうした累積によって生み出されるものだと思います。(デザインだけではないかもしれませんね)
例えば、自分が憧れるデザイナーのアウトプットを模倣しようとするとき、その人の見ている景色まで想像してみる。なぜこの構成なのか、なぜこの行間なのか。
そこに“選ぶ理由”があるはずで、それを考えることが自分の表現を豊かにしてくれることもあります。
上澄みを掬うだけでは足りません。その下に沈んでいる“思考の沈殿”にこそ、ヒントが隠されているのだと思います。
氷山の一角としての成果物
私もかつて、良いデザインを見つけると「これなら自分にもできそうだ」と錯覚していました。
けれど、いざ手を動かすと同じにはなりません。それは単純に技術の差というより、基礎理解の深さの違いでした。
タイポグラフィの扱い、視線誘導の設計、余白の呼吸。それらはすべて、長い時間をかけて培われた基礎の上にあります。
こうして参考デザインサイト等で閲覧できるような完成されたアウトプットは、氷山のほんの一角です。その下には、膨大な試行錯誤と知識、そして失敗の層が沈んでいます。
誰かの表現を真似ることは悪いことではありません。むしろ、模倣からしか学べないこともあります。ただし、それを“自分の前提で再構成する”という過程を抜きにしては、学びになりません。
真似を通じて見えてくるのは、自分がまだ知らない領域。できなかった部分の中にこそ、次の成長の種が眠っているのだと思います。
思考の源泉に触れる習慣を取り入れる
デザインを仕事にしていると、「結果を出す」ことばかりに意識が向きがちです。でも最近は、それ以前の“どう考えるか”の部分を整えたいと思うようになりました。
アウトプットの精度は、結局インプットの質に比例します。とはいえ、やみくもに情報を摂取しても深まらない。だからこそ、「源泉に触れる時間」を意識的に設計することが必要です。
たとえば、週に一度は“遠い参照”を摂る。仕事とは直接関係のない展示や詩集、建築、古い写真集など。それらはすぐに役に立たないかもしれませんが、時間をかけてゆっくり効いてくるものです。
そして、気になった作品や言葉があったら、その“参考文献”を辿ってみる。誰の影響を受けていたのかを知ると、世界が立体的に見えてきます。
アウトプットとは、情報の処理ではなく、思考の発露です。「掘る → 試す → 言語化する」、その小さな反復の積み重ね。
私自身、まだまだその途中です。けれど、誰かが私の仕事を見たときに、「上澄みだけでない由来」を感じてもらえるような表現を目指していきたいと思います。