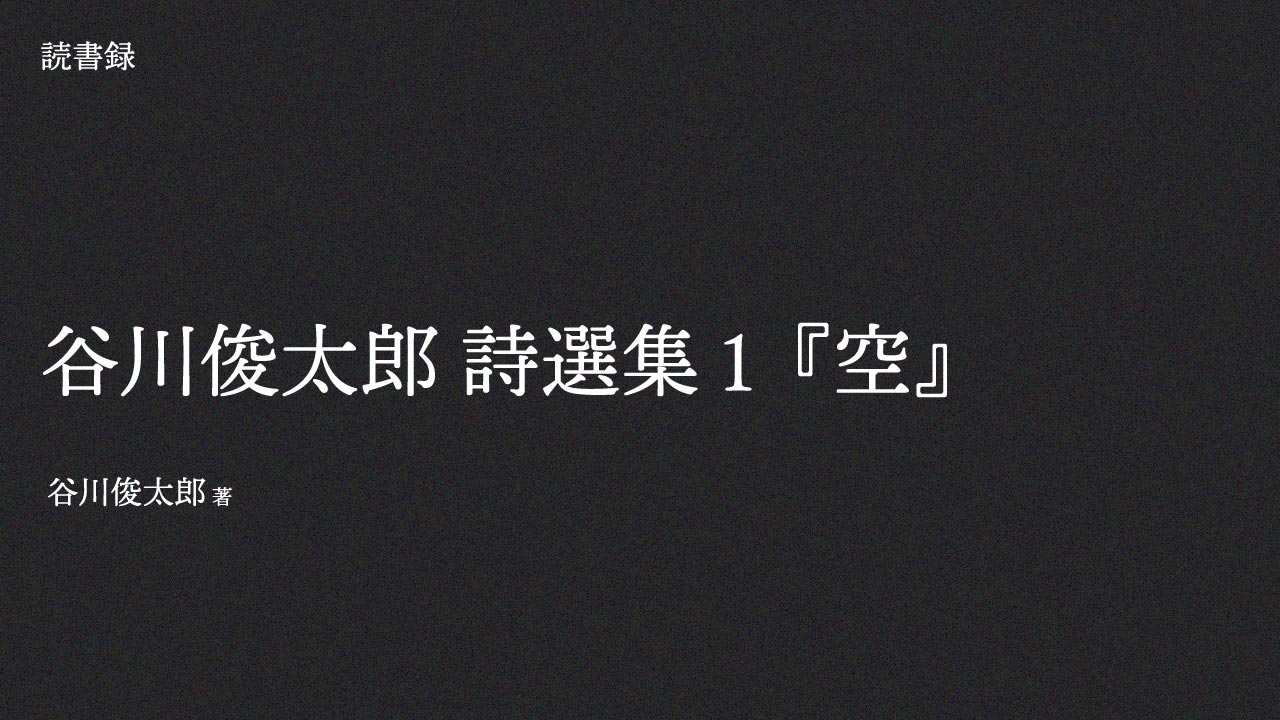幼い頃から大好きな詩があります。谷川俊太郎の詩「空」です。
初読の瞬間からこの詩には言葉では言い尽くせない寂寞の念が漂っているような、そんな衝撃を受けたことを覚えています。
空の無限性を探求すると同時に、対照的な人間の有限性と死の不可避性を浮き彫りにしているかのような、そんな詩。
一見すると素朴な問いの連なりに過ぎないような詩にも思えますが、その表層の下には人間存在の根幹に関わる深遠な思索が潜んでいるようにすら感じられます。
形而上学的な問いに対して決して硬質な哲学用語ではなく、日常の言葉で紡ぎ出しているからこそ、素直な驚きと畏怖を喚起し、読者の思索を深うような気がします。
この詩に内在する時間感覚、生命と死の問題、無垢な日常と永遠性の対比、そして沈黙が孕む意味を通じて、この詩が持つ尊い余韻を改めて味わってみたいと思いました。
今回は『谷川俊太郎 詩選集1』から、「空」を取り上げます。
空
まず詩を。
空はいつまでひろがっているのか
空はどこまでひろがっているのか
ぼくらの生きている間
空はどうして自らの青さに耐えているのか
ぼくらの死のむこうにも
空はひろがっているのか
その下でワルツはひびいているのか
その下で詩人は空の青さを疑っているのか
今日子供たちは遊ぶのに忙しい
幾千ものじゃんけんは空に捨てられ
なわとびの輪はこりずに空を計っている
空は何故それらのすべてを黙っているのか
何故遊ぶなと云わないのか
何故遊べと云わないのか
青空は枯れないのか
ぼくらの死のむこうでも
もし本当に枯れないのなら
枯れないのなら
青空は何故黙っているのか
ぼくらの生きている間
街でまた村で海で
空は何故
ひとりで暮れていってしまうのか
詩の構成、宇宙的問いから日常、そして形而上学的沈黙へ
「空」は複数の連(スタンザ)に分かれ、それぞれ異なる角度から問いを立ち上げているように見えます。
また、語り手が「ぼくら」という一人称複数を用いているのも特徴的で、個人的な問いが人類全体の根源的な疑問として普遍化されている点に、畏怖に近い感覚を覚えました。
さて、それぞれの連を眺めてみます。
まず第1連では「いつまで」「どこまで」という空間的広がりへの問いと、「どうして自らの青さに耐えているのか」という時間的持続の不思議が問われます。この「耐える」という表現には、存在することの重みと美が同居する逆説が込められているのかもしれません。
第2連は「ぼくらの死のむこうにも 空はひろがっているのか」と、人間の有限性と空の永続性を対比させています。ワルツや詩人の思索という人間の営みが死後も続くのかという連想は、文化的記憶の永続性への問いでなのでしょうか。
自身が死んでもこの世界は何も変わらず続いていく。やがて死んでいくその間、いつか消えてしまったその後も、空は変わることなく存在し続ける、そんな空の不変性はある種の神聖性や静寂を伴って迫ってきます。これは限りなく尊いことでありながら、個体としての人間には言い知れぬ孤独をもたらす事実です。
第3連。
子どもの遊びという日常。
「幾千ものじゃんけんは空に捨てられ」「なわとびの輪はこりずに空を計っている」と、無邪気な遊びが無限の空と接する様子、瞬間的で儚い人間の営みが、無限の空間と接する瞬間が描かれます。じゃんけんやなわとびといった儚い遊戯が、実は空の広大さを計ろうとしているかのように映ることに切なさを覚えました。
第4連では空の沈黙への疑問として、「何故それらのすべてを黙っているのか」「何故遊ぶなと言わないのか」と、子どもたちの遊びに対して沈黙を保つ空への問いかけがなされます。空は怒っているのか、喜んでいるのか、それとも無関心なのか。その解釈不可能性が詩に深い余韻をもたらします。
第5連では永遠性と沈黙について。
「もし本当に枯れないのなら、青空は何故黙っているのか」と追及し、空の不変性(永遠性)とそれを語らない沈黙との関係を問いかけています。空が枯れるだなんて、そんな表現があるのかと本当に驚いた記憶があります。永遠と思われるものの中にも終わりの可能性を見出していたのでしょうか。
第6連(最終連)では暮れていく空の孤独を、「街でまた村で海で、空は何故ひとりで暮れていってしまうのか」と締めくくり、空が独り静かに変容していく光景を描きます。
ひとりで暮れる。
あらゆる場所を覆いながらも、本質的に孤独であるという空の逆説。なんと虔恭なのか。ここに描かれる孤独は悲しみではなく、もはや存在の尊厳として捉えていいのかもしれません。
空はどうして自らの青さに耐えているのか
「空はどうして自らの青さに耐えているのか」。
この一文がたまらなく好きでした。
今改めて味わうと、「存在の重み」という普遍的なテーマが浮かび上がってきます。単に存在すること、自分自身であり続けることには「耐える」という行為が内包されているのではないか。
この問いかけはなかなか難題です。
自己を認識すること自体が、時に重荷になり得るものの、空は自らの青さを拒むことなく受け入れ、その本質とともにあることを選び「耐えている」。ここに自己受容の最も深い形を見ることができるようです。
空が青いという本質を保ち続けることで「空」として存在するように、私たち人間も自己同一性を保つことで存在しているのかもしれません。
ここには美しい逆説があるように感じるのです。
空は自らの本質的な姿を「耐える」ことを通して存在している。この表現は、自分自身であり続けることの重み、苦しみ、そして何より美しさを象徴しているかのようです。なんて尊いことか。
美というものは必ずしも軽やかさや華やかさだけを意味するのではなく、時に「耐える」ほどの重みを伴うこともあるのでしょう。
さらに詩は第2連や第5連で「死のむこうにも空は続くのか」「もし枯れないのなら、なぜ黙っているのか」と問いかけています。もし空が老いず、枯れることもなく永遠に青さを保つなら、私たちの死後もそこに在り続けるのか。永遠に存在するものの沈黙とは何を意味するのでしょうか。
空は変わることなく青く、常に頭上に広がっていますが、その不変性には根源的な孤独が付随するように思えます。自分の本質から逃れられないことの孤独が「耐える」という表現に凝縮されているのでしょうか。
この問いは、私たち有限の存在が無限を前にしたときの畏怖と不安を映し出しているのかもしれません。
沈黙する空に耳を澄ます
様々な考察を試みてきましたが、それらが的を射ているかどうかは分かりません。ただ私はこの詩が、敬いたくなるほどに切なく心に染み入るこの詩が好きなだけなのです。
谷川俊太郎本人はもしかすると大した意図はなく、ただ空を見上げた素直な感覚を言葉にしただけかもしれませんね。
さて、最後の連で示されるのは、夕暮れの淋しさと空の孤高さ。
「街でまた村で海で、空は何故ひとりで暮れていってしまうのか」。
昼間の鮮やかな青さから徐々に色を変えながら「ひとりで暮れていく」空の姿には、寂しさと同時に厳粛さが漂っているようです。人々の営みをすべて包み込みながら、静かに変容していく大いなる存在。
そこにはある種の神聖さ、あるいは畏敬の念が自然と湧き上がってきます。ある種の神仏への帰依にも似た感覚のように。
この「空」という詩は、明確な答えを示すことなく静かに問いを投げかけて終わります。しかし、その答えのない問いかけこそが、読者の心に深い余韻と祈りのような感覚を生み出すのではないでしょうか。
私がこの詩に初めて触れたとき、救われたような安堵感と、根源的な恐怖という相反する感情を同時に抱いたことを覚えています。
なんというか、あまりに美しすぎるのです。
空という存在への畏怖、その空が抱える根源的孤独、物言わぬ空の内なる痛みと悲しみ。「人間とは何か」という根源的な問いを突きつけられるような、私にとってはそんな詩でした。
沈黙する空に耳を澄ますという行為は、同時に自分自身の内面を見つめることでもあります。そこには生きていることへの感謝や畏敬が生まれ、言葉を超えた大いなるものとの静かな対峙があります。
「いつかは尽きる身」である私たちは、どこまでも広がる空を見上げることで改めてこの尊い一瞬に気づかされるのではないでしょうか。
そうして生まれる敬虔な感情こそ、谷川俊太郎の「空」が私たちに与えてくれる貴重な贈り物なのだと感じています。