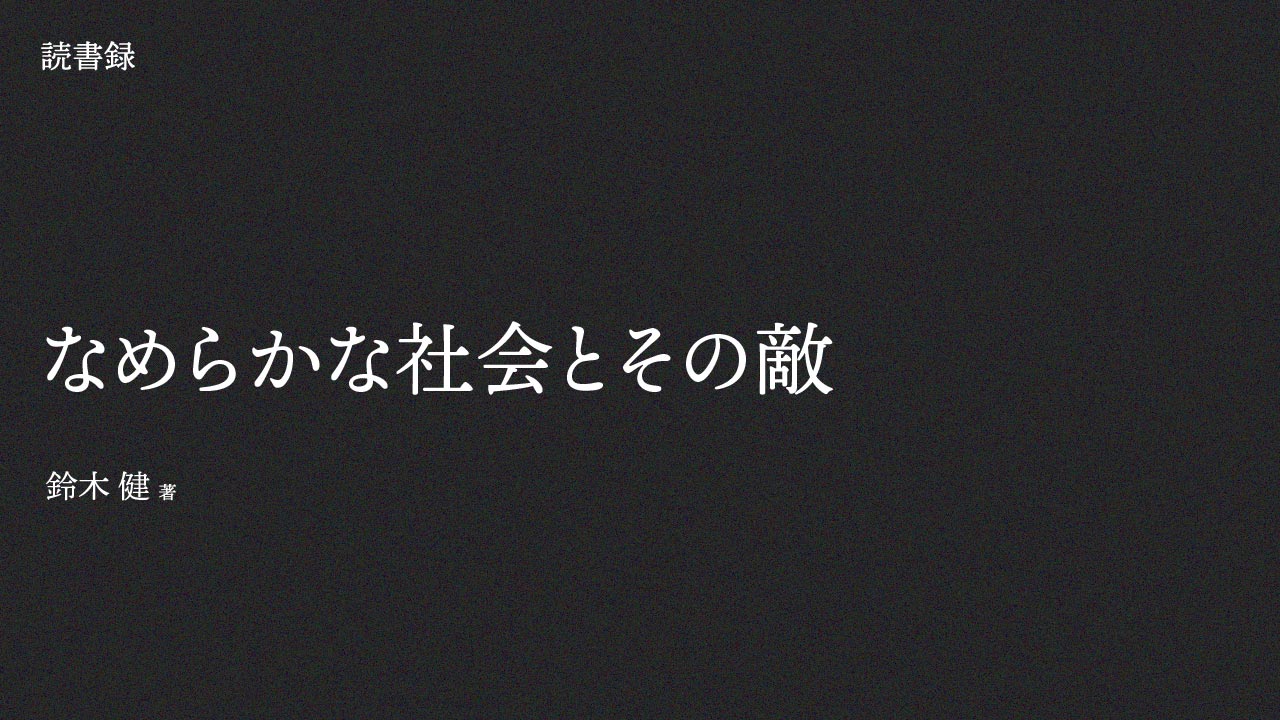テクノロジーの進歩は、私たちの暮らし方や社会の形を大きく変えてきました。
2013年に刊行された『なめらかな社会とその敵』は、その変化を先取りするように「境界が消え、情報や価値が自由に行き交う社会」の可能性を描いた本です。当時は未来の話として受け止められていましたが、2025年の今、生成AIの急速な広がりによって、そのビジョンは現実味を強めています。
一方で、AIは新しい課題も生み出しました。情報が一部に集中したり、制度やルールが追いつかなかったりと、本来「なめらかさ」を実現するはずの技術が、かえって社会を固く縛ってしまう危険もあるのです。
この記事では、『なめらかな社会とその敵』をAI時代の視点から改めて読み直し、「なめらかさ」と「敵」とのせめぎ合いが、これからの私たちの社会にどんな問いを投げかけているのかを考えていきます。
10年前の未来論が現実化する
鈴木氏の著作『なめらかな社会とその敵』が描いたのは、国境や組織、制度といった境界が少しずつ溶けていき、情報や価値が自由に行き交う世界です。彼はその姿を「なめらかな社会」と呼び、逆にそれを妨げる既得権益や中央集権的な仕組みを「その敵」と名付けました。
刊行当時は、ビットコインといった新しい試みを背景に語られた理論にすぎず、現実味を帯びた未来像とまでは受け止められていませんでした。しかし2025年の今、改めて読み返すと、その言葉が現実に近づいていることを強く感じます。生成AIの普及によって、言語の壁や知識の格差といった「境界」が急速に低くなっているからです。
出版から10年以上が経ち、私たちは「なめらかさ」というビジョンが、もはや比喩や理念にとどまらず、テクノロジーの力で一部実現されている光景を目の当たりにしています。鈴木氏の未来論は、もはや「過去の夢」ではなく、「現在の現実」へと姿を変えているのです。
AIが実現した「なめらかさ」
AIは、人類が積み重ねてきた膨大な知識を、誰もがすぐに取得できる環境をつくりあげました。
以前であれば、専門家に相談したり、図書館やデータベースを調べたりしなければ得られなかった情報が、いまでは数秒のやり取りで手に入れることができます。さらに翻訳AIの進化によって言語の壁はほとんどなくなり、専門的な内容も対話形式で理解できるようになりました。
こうした変化は、知識や情報が一部の人に独占される時代から、誰もがアクセスできる時代への転換を意味します。つまり、これまで境界や摩擦によって制限されていた情報の流れが、AIによってスムーズになりました。
鈴木氏が『なめらかな社会とその敵』で描いた、摩擦を取り除く社会の姿はAIの登場によって現実味を帯びています。AIはもはや単なる便利なツールではなく、社会の仕組みそのものを「なめらか」に変えていく存在となりつつあるのです。
AI時代に現れた新しい「敵」
AIの普及は社会をなめらかにし、情報の流れをスムーズにする一方で、新しい「敵」も生み出しました。鈴木氏が本書で指摘していた「敵」は、官僚制や大企業といった、社会の流動性を妨げる既得権益や中央集権的な仕組みでした。
しかしAI時代に入った今、その姿は変わりつつあります。現代の「敵」は、AIを支配する巨大なプラットフォーム企業です。
AIは知識や情報を分散させ、誰もが自由にアクセスできる未来を約束するかのように見えます。しかし実際には、開発や運用が一部の大企業に集中しやすい構造が生まれています。その結果、本来は中央集権を弱めるはずのテクノロジーが、逆に中央集権を強化してしまうという皮肉な現象が起きているのです。
この矛盾は、「なめらかさ」をめざす社会に新たな摩擦をもたらします。私たちはAIの便利さや恩恵を受ける一方で、その裏側で加速する権力の集中や情報の偏りに、どのように向き合うのかを突きつけられているのです。これこそが、AI時代における「敵」の正体だと言えるでしょう。
分散型AIが示す、これからの社会の設計図
鈴木氏が本書で強調した重要なメッセージのひとつは、「制度はデザインできる」という考え方です。社会の仕組みは与えられるものではなく、人間が意識的に作り直すことができるという発想は、AI時代においても欠かせない視点になっています。
AIがもたらすのは技術的な進歩だけではありません。その使い方を決める制度やルール、倫理の枠組みがなければ、社会は簡単に歪んでしまいます。たとえば、誤情報やフェイクニュースをどう扱うのか、AIモデルの仕組みをどこまで公開するのか、利用履歴や生成物の責任を誰が負うのかなどの課題は避けて通れません。
いま注目されている分散型AIやオープンソースAIの動きは、「なめらかさ」を守るための新しい制度設計の試みだと言えます。特定の企業や国家に依存しない仕組みをつくることは、AIを社会の公共財として活用するために欠かせない条件です。制度をどのように整えるかが、これからの社会のかたちを大きく左右していくのです。
集合知とAIの新しいかたち
AIは、人類が積み重ねてきた膨大な知識やデータを学習し、その成果を私たちに返してくれる存在です。言い換えれば、「集合知を圧縮したもの」と捉えることもできます。ただし、それはあくまで過去のデータをもとにした出力であり、自ら新しい未来を切り開く力を持っているわけではありません。
未来を築くために必要なのは、人間がAIをどう使いこなし、新しい問いを立てられるかという点です。AIは膨大な知識を整理し、選択肢や可能性を提示することは得意ですが、それをどの方向に活かすのかは、人間の想像力や判断力にかかっています。
鈴木健氏が語った「集合知」という考え方は、いまや人間同士の知識共有にとどまりません。人間とAIが協働し、ともに考え、学び合うことで、新しい集合知のかたちへと進化しつつあります。AIは人間を超える存在ではなく、人間と結びついてこそ「未来をデザインする知」となるのです。
AI時代のなめらかな社会と新しい敵
『なめらかな社会とその敵』は、単なる未来予測の本ではありません。本書が投げかけているのは、「境界をどう扱うか」という人間社会の根本的な問いです。
国家や組織、制度といった枠組みを越えて、私たちはどう情報を共有し、どう信頼を築き、どう共に生きていくのかなどの課題は、AIが日常に入り込んだ今こそ、より切実なものとなっています。
生成AIの登場によって、社会はかつてないほど「なめらかさ」に近づきました。しかし同時に、その流れを妨げる新しい「敵」も現れています。AIによる情報の偏り、巨大プラットフォームに集中する権力、追いつかない倫理や制度。これらにどう向き合うかを誤れば、「なめらかさ」はあっという間に失われてしまうでしょう。
「なめらかさ」と「敵」とのせめぎ合いをどのようにデザインするのか。それは技術や制度の問題にとどまらず、AI時代を生きる私たち一人ひとりの生き方に直結するテーマです。