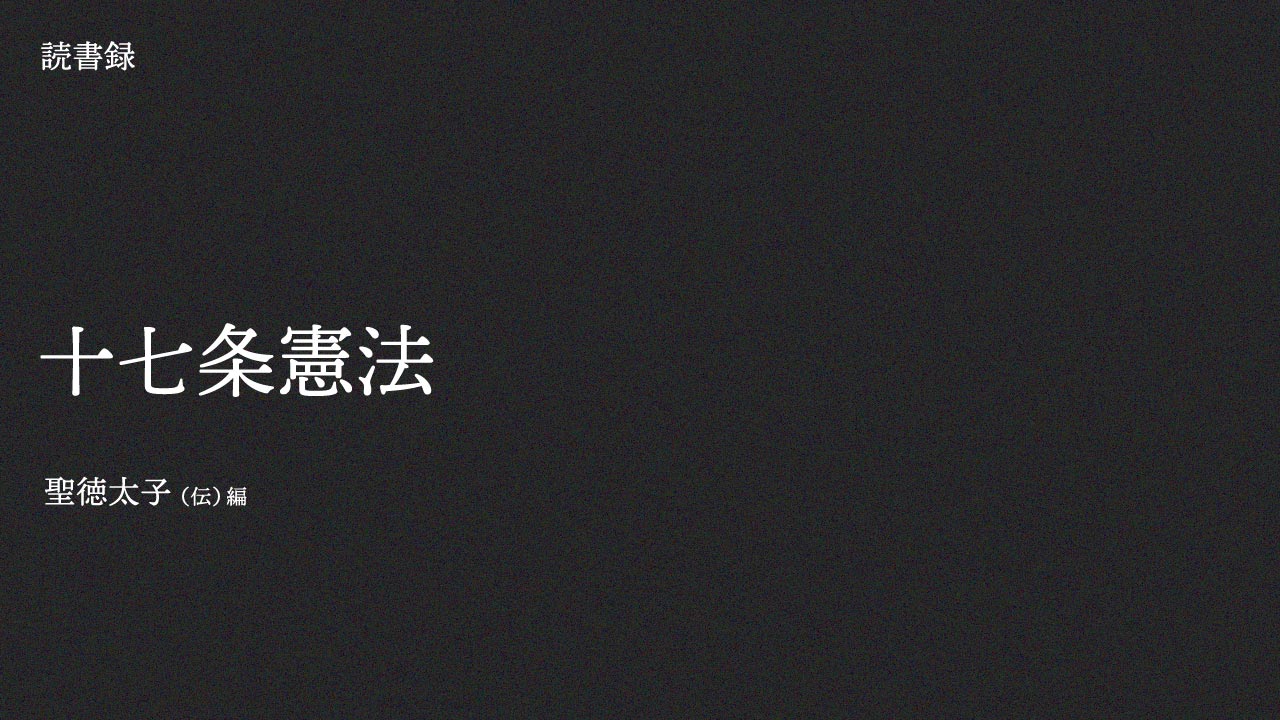先日、奈良県の法隆寺を訪れた時のこと。
法隆寺といえば聖徳太子、聖徳太子といえば十七条憲法……あまりにも単純な教科書的な連想に自分の教養の浅さを思い知らされるようで、軽く眩暈を覚えました。
古都の空気に触れるといつもこんな風に自分の知識の薄さが透けて見えるようですが、それもまた旅の醍醐味ですね。
が、せっかくの機会なのでこれまでまともに読んだことのなかった十七条憲法を手に取ってみることにしました。
今さらながら一度も十七条憲法を読んでこなかった事実にも情けなさを感じます。
ですが、一条、また一条と言葉をたどりながら調べていくうちに、これまで漠然としか認識していなかった十七条憲法が、少しずつ鮮明な姿を見せ始めました。
そこには、驚くほどの示唆が込められていました。
「和」を尊び、「礼」を重んじ、「信」に生きる。組織の病理から、公正な評価のあり方まで現代の組織運営にも通じる視点が随所に散りばめられており、まるで古代から届けられたリーダーシップ論やマネジメントの指南書のようにも思えます。
古代日本の政治理念や道徳観、そして聖徳太子が描いた理想の秩序。
それが十七条の短い条文に凝縮されており、千年以上の時を隔ててなお、その思想は驚くほど現代に通じるものがありました。
人を尊び、組織を生かすための知恵と言葉たち。
今回の読書録はそんな十七条憲法について。
十七条憲法概観
十七条憲法は、推古天皇12年(西暦604年)に聖徳太子が制定したと伝えられる、日本最古の成文法とされる法規範です。
ここでいう「成文法」という言葉は、あくまで後世の史料や伝承に基づいた呼称であり、実際にどの程度「法」として機能したのかには学説上の議論もあります。
いずれにせよ、当時の官僚や豪族に向けた道徳・政治理念を示す内容として、国家のあり方や為政者の倫理を説いた貴重な史料であることは間違いありません。
この法規範は単なる統治のための法律ではなく、当時の官僚や豪族に向けた道徳や政治理念を示したものとされ、国家のあり方や為政者の倫理を説く内容が随所に散りばめられています。
読み進めるうちに、その思想の深さと示唆の豊かさに驚かされました。
古代に生まれたこの条文が組織のあり方や人の生き方について、今なお学ぶべき示唆を極めて多く含んでいると実感しました。
まずは、その十七条憲法をそれぞれ概観しながら、私なりの雑感も綴ってみようと思います。
第一条:調和と合議の要「和(やわらぎ)を以て貴しと為す」
一に曰く、和を以て貴しと為す。忤ふること無きを宗とせよ。人、皆な党あり。亦達れる者は少し。是を以て、或は君父に順はず、乍隣里に違ふ。然れども上和らぎ、下睦びて諧へば、事を論らはむに、則ち理自ら通へり。何事か成らざらむ。
「和をもって尊いものとし、意見の対立が生じないように努めなさい。人にはそれぞれ偏りや主張があり、完全に悟った者は少ない。したがって、君主に反抗したり、隣人と仲違いしたりすることもあるが、上が穏やかであれば下も睦まじくなり、話し合えば道理はおのずと通じるのだから、成し得ないことは何もない」という文章。
「和を以て貴しと為す。」
非常に有名な言葉ですね。
単なる平和や調和を称えるものではなく、むしろ人々が互いの違いを認め合い、協調のなかで真の理を見いだしていくことの重要性を説いた言葉です。
聖徳太子がここで示した「和」は、単なる馴れ合いや対立を避けることではなく、意見を戦わせながらも、最終的には調和と合意を目指すという「建設的な合議」のプロセスを指しているのです。
人はそれぞれ異なる立場や価値観を持ち、決して同じ視点から物事を見ることはできません。
だからこそ、まずは冷静に耳を傾け、他者の考えを尊重する。そして自らの意見と照らし合わせ、より良い結論へと導く姿勢が求められます。
「和」とは、単に争いを避けることではなく、違いを乗り越え、対話を通じて最適解を見出していくための知恵なのかもしれません。
第二条:仏教を柱とする倫理観「篤く三宝を敬へ」
二に曰く、篤く三宝を敬へ。三宝とは仏法僧なり。則ち四生の終りの帰、万国の極宗なり。何れの世の何れの人か、是の法を貴ばざらん。人尤だ悪しきは鮮し。能く教ふれば之に従はむ。其れ三宝に帰らずば何を以てか枉れるを直さむ。
「仏法僧の三宝を深く敬わなければならない。あらゆる生き物は最後にはこの教えに帰依し、世界の根源的な教えでもあるので、どの時代のどんな人もこれを重んじるはずである。悪人はそう多くないので、正しく教えを説けば必ず従うだろう。もし三宝を拠りどころとしなければ、誤りを正す手立てを失ってしまう」という文。
「篤く三宝を敬へ」は、仏・法・僧を国家の精神的支柱として重んじる発想です。
聖徳太子は、当時の先進地域であった中国や朝鮮半島から伝来した仏教思想を積極的に取り入れ、人々の心の安定と道徳の確立を図ろうとしました。社会に「和」を根付かせるためには、人間の持つ欲望や苦悩を制御し、慈しみや仁愛の精神を広めることが不可欠であると考えたのでしょう。
人々が共通の精神的支柱を持つことで、善悪の基準が明確になり、正しき道へと導かれる。これは単なる信仰の問題にとどまらず、社会秩序の維持、さらには国家運営の安定にも深く関わる視点です。
仏教の調和の思想を軸とすることで、個々の利益や欲望に流されることなく、公正な政治と社会を築こうとする意志がうかがえます。
第三条:天と地の秩序「詔を承けては必ず謹め」
三に曰く、詔を承けては必ず謹め。君をば即ち天とし、臣をば則ち地とす。天覆ひ地載す。四時順り行きて、万気通ふことを得ん。地天を覆はむと欲せば、即ち壊るることを致さむのみ。是を以て君言ふときは、臣承り、上行へば下靡く。故に詔を受けては必ず慎め。謹まざれば自らに敗れなむ。
「君主からの詔(みことのり)を受けたならば、必ず慎んで従わなければならない。君主は天であり、臣下は地のようなものなので、もし地が天を覆そうとすれば自ら壊れるしかない。上からの言葉があれば下はそれに従い、もし慎重さを欠けば自らを滅ぼすことになる」という文。
現代の視点から見ると、この上下関係はやや極端に映るかもしれませんね。
しかし、当時の政治の混乱を収めるには、統治の軸を明確に示すことが不可欠でした。大地が天を支え、天が大地を覆うように、それぞれが自らの役割を全うすることで、国家全体の秩序と安定が保たれるという考え方が、この条文には込められています。
この構図は単なる上下関係の強調ではなく、支配と服従の関係を超えた「相互の依存関係」を示しているとも捉えられそうです。
天(君主)が民を慈しみ、地(臣下)がその支えとなることで、政治の安定が実現するという理想を描いているのでしょう。統治の正当性を確立し、秩序を守るためには、それぞれの立場に応じた責務を果たすことが不可欠であるという、当時の政治思想が色濃く反映されています。
第四条:礼儀こそ統治の基盤「群卿百寮礼を以て本とせよ」
四に曰く、群卿百寮礼を以て本とせよ。其れ民を治むる本は要ず礼にあり。上礼なきときは下斉はず。下礼無きときは以て必ず罪有り。是を以て君臣礼有れば、位の次乱れず。百姓礼有れば国家自ら治まる。
「群卿や百寮は礼を基盤としなければならない。民を治める基本は礼にあり、上が礼を失えば下は従わず、下が礼を失えば罪を犯す。君臣が礼をわきまえれば位が乱れず、百姓が礼を守れば国家はおのずと治まる」という文。
礼節こそが国家統治の基盤であるという、揺るぎない信念が込められた言葉、「群卿百寮、礼を以て本とせよ」。
響きます。
礼儀や節度は単なる形式ではなく、社会や組織の秩序を維持し、人々が円滑に共存するための根幹を成すものです。
上に立つ者が礼を失えば、下の者の規範意識は崩れ、やがて組織全体の秩序が乱れる。さらに、下の者が礼を守らなければ、不正や混乱が生じ、最終的には社会そのものが機能不全に陥る。
儒教的思想を色濃く反映させた考え方です。儒教において「礼」とは単なる儀礼ではなく、人々が共に生きるための道徳的規範であるともされています。
礼が機能することで、上は下を慈しみ、下は上を敬う関係が築かれ、社会は安定へと向かう。天皇と臣下、上官と下官が互いに敬意を払い合うことで、ただ上下の序列を守るのではなく、秩序のなかに調和が生まれ、円満な統治が可能になる。聖徳太子の描いた理想の国家像が、この一条に凝縮されているのではないでしょうか。
第五条:公正な裁きと責務「餐を絶ち欲をすてゝ、明かに訴訟を弁へよ」
五に曰く、餐を絶ち欲をすてゝ、明かに訴訟を弁へよ。其れ百姓の訴、一日に千事あり。一日すら尚然り。況んや歳を累てをや。頃、訟を治むべき者、利を得るを常と為し、賄を見ていかりを聴す。便ち財有るものの訟は、石をもて水に投るが如く、乏しき者の訴は、水をもて石に投ぐるに似たり。是を以て貧しき民は、則ち由る所を知らず。臣の道亦た焉に於て闕けぬ。
「私利私欲を捨て、はっきりと訴訟を裁かねばならない。民の訴えは日々膨大であるが、裁判を担う役人が賄賂を受け取り、財産のある者の言い分だけを通せば、貧しい者は正当な道を断たれ、公平を失ってしまう」という文。
「餐を絶ち欲をすてゝ、明かに訴訟を弁へよ」。
公務を担う者としての厳格な倫理観が求められる言葉です。
私利私欲にまみれた者が裁きを行えば、そこに正義はなく、公平さも失われる。聖徳太子は、裁きを司る者に対し、個人的な利益や感情を排し、ひたすら公正を貫くことを求めたのでしょう。
賄賂や権力によって判決が左右されることは、社会の根幹を揺るがしかねません。富める者が常に有利であり、貧しい者の訴えが無視されるような状況が続けば、法の権威は失われ、社会の秩序は崩壊していく。だからこそ、和を守るためには、まず公正であることが絶対条件であり、不正や偏りを断ち切らなければならないのです。
裁きを司る立場にある者がその責務を果たさなければ、社会の混乱は避けられません。
弱い立場の者が救われず、不正がまかり通る世界になれば、いずれは社会全体が機能不全に陥ってしまう。この条文は、そうした危機を未然に防ぐための強い戒めだったのでしょう。
権力や金に左右されることなく、公正な判断を下すことこそが、統治の根本であるという教えだと捉えました。
第六条:正義を貫き不正を許さない政治「悪を懲し善を勧むる」
六に曰く、悪を懲し善を勧むるは、古の良き典なり。是を以て人の善を匿すこと無れ。悪を見ては必ず匡すべし。其れ諂ひ詐く者は、則ち国家を覆すの利器たり。人民を絶つ鋒剣たり。亦た侫しく媚ぶる者は、上に対ひては、則ち好みて下の過を説き、下に逢ては、則ち上の失を誹謗る。其れ此の如き人は、皆君に忠なく、民に仁無し。是れ大なる乱の本なり。
「悪を戒め善を奨励するのは古来からの良き教えである。へつらいや偽りを行う者は国家を覆す武器であり、人々を断ち切る刃でもある。そうした者は上に対しては下の過失を挙げ、下に対しては上の失を誹謗し、忠や仁を持たない。これは大きな乱のもとである」という文。
「悪を懲し善を勧むる」。不正を見逃さず、正しい行いを奨励することが統治の基本であるという強い姿勢を示した言葉です。
社会の秩序を維持するためには、悪を放置せず、善を評価する仕組みが不可欠であり、それなくして公正な政治は成り立たないという考え方です。
特に、この条文では単なる悪事の取り締まりにとどまらず、「へつらい」や「ごまかし」を鋭く批判しています。
上司の前では部下の過ちをあげつらい、部下の前では上司の批判に回るような二枚舌の振る舞いこそが、国家の根幹を揺るがす「大なる乱の本」であると警告しています。
これは、権力を持つ者が真の忠誠を見極める目を持たなければならないという教えでもあり、表面的な調和に流されるのではなく、真の公正を貫けという強いメッセージが込められています。
社会や組織の腐敗はこうした不誠実なふるまいを許すことから始まります。
だからこそ、邪な者を放置せず、正しい行いを評価する仕組みを確立することが不可欠なのです。
第七条:適材適所の人材登用「人各々任し掌ることあり」
七に曰く、人各々任し掌ることあり。宜しく濫れざるべし。其れ賢哲官に任すときは、頌音則ち起る。奸者、官を有つときは、禍乱則ち繁し。世に生れながらに知るもの少し。尅く念へば聖となる事大小となく、人を得れば必ず治る。時に急緩となく賢に遇へば自ら寛なり。此に因りて国家永く久しく、社稷危きこと勿し。故に古への聖王は官のために人を求めて、人のために官を求めず。
「人それぞれに任される職務がある以上、みだりな登用をしてはならない。賢者を官に任じれば誉れが起こり、奸悪な者を官に就ければ乱れが広がる。世に生まれながらに全てを知る人は少ないが、努力すれば聖に近づける。古の聖王は官に適う人を求めこそすれ、人のために官職を作ったのではない」という文。
人材登用において、能力と適性を慎重に見極めること。それは国家や組織を支える最も重要な要素の一つです。
「人各々任し掌ることあり」という言葉には、それぞれの適性に応じた役割を与え、その人物が最大限の力を発揮できる環境を整えることの大切さが示されています。
賢者が要職に就けば政治は円滑に運び、奸者が権力を握れば混乱が生じる。この理屈は極めて単純でありながら、組織運営の本質を突いたものです。
聖徳太子は「聖王と称されるような理想的な支配者であれば、官職にふさわしい人材を慎重に選び、安易に人事を決めることはなかった」と説いています。これは、単なる実力主義にとどまらず、道徳的な価値観とともに政治を運営すべきだという信念を反映しているのでしょう。
聖徳太子が目指したのは、単に有能な者を登用するだけではなく、その人物が精神的にも成熟し、公に尽くす意識を持つことだったのでしょう。
ただ仕事ができるだけではなく、高潔な倫理観を備えた者こそが、国家や組織をより良い方向へ導く存在となる。この条文からは、そうした理想のリーダー像を求める太子の強い意思が伝わってくるようです。
第八条:勤勉と責任感「群卿百寮早く朝り、晏く退りでよ」
八に曰く、群卿百寮早く朝り、晏く退りでよ。公事いとま靡し。終日尽し難し。是を以て遅く朝れば急なるに逮ばず。早く退れば必ず事尽さず。
「群卿や百寮は早く出仕し、遅く退くようにせよ。公務はいとまなく、朝が遅ければ急な事態に間に合わず、早く退けば仕事が終わらない」という文。
一見するとシンプルに勤勉を奨励する教えのように映りますが、当時の役人たちの勤務態度や、公務の遅滞といった実情を踏まえた戒めであったのかもしれません。
聖徳太子は、社会の根幹を担う官人がその責任を十分に自覚し、職務を誠実に果たさなければ、国の統治は決して円滑には進まないと考えたのでしょう。
単に早く出仕し、遅くまで働くことを求めたのではなく、公務に携わる者としての覚悟と勤勉さを持つことが不可欠である、という意識を植え付けようとしたのではないでしょうか。
仕事に対する姿勢ひとつが、組織の安定に直結するという視点は、現代の仕事論やリーダーシップにも通じるものがあります。
この条文には「責任ある仕事を通じ、社会全体の秩序と繁栄を支えるための責務を全うせよ」という強いメッセージが込められているように感じられます。
第九条:信頼こそ組織の根幹「信は是れ義の本なり」
九に曰く、信は是れ義の本なり。事毎に信あれ。其れ善悪成敗、要ず信にあり。君臣ともに信あるときは何事か成らざらむ。君臣信なければ万事悉く敗る。
「信こそが義の土台である。事ごとに信義を守るべきであり、君臣ともに信があれば何事も成し遂げられるが、もし信がなければすべてが失敗に終わる」という文。
組織や社会のあらゆる関係の根本に「信頼」があり、それなくしては何事も成り立たない。この条文が示すのは、まさにその普遍的な原則です。
「信」の持つ尊さ、価値が強調されていますね。
信用や誠実さを欠いたところに、どれほど立派な制度や計画があったとしても、すべては瓦解してしまう。単なる個人の倫理観としての「信」ではなく、国家運営や組織の存続に関わる根本的な基盤として、信頼関係を築くことの重要性が説かれています。
君臣の間に信がなければ、政は乱れ、官僚同士が互いを疑えば、国の統治は行き詰まる。組織がどれほど強固な構造を持っていても、信頼が欠けた途端に綻びが生じ、やがて崩壊へと向かう。
そう考えれば、この条文は単なる道徳の話ではなく、社会の安定を維持し、持続的な繁栄を築くための実践的な哲学でもあるのでしょう。
聖徳太子の時代から千年以上が経った今でも、政治、経済、そして日常のあらゆる関係において、「信」が持つ力は変わりません。信頼の上に築かれた組織こそが真に強く、持続的に発展する。そうした普遍的な原理を、改めて考えさせられる言葉です。
第十条:謙虚な対話と合意形成「忿を絶ち、瞋を棄てて」
十に曰く。忿を絶ち、瞋を棄てて、人の違へるを怒らざれ。人皆心あり。心各々執ること有り。彼れ是なれば、則ち我は非なり。我れ必ずしも聖に非ず。彼れ必ずしも愚に非ず。共に是れ凡夫のみ。是非の理を誰かよく定むべき。相共に賢愚なること、鐶の端なきが如し。是を以て彼の人は瞋ると雖も、還つて我が失を恐れよ。我独り得たりと雖も、衆に従ひて同く挙へ。
「怒りを捨てて他人の違いを許せ。人にはそれぞれ意見があるため、相手が正しいなら自分が誤りの場合もあるし、自分を聖者と思うな。皆凡夫にすぎないのだから、誰が賢く誰が愚かかを簡単に決められない。相手が憤っていても、まず自らの非を恐れよ。自分だけが正しいとしても、多数の意見に従うように心がけよ」という文。
相手の意見や見解に対して、極端に怒らないようにと促すこの条文の背景には、「我れ必ずしも聖に非ず。彼れ必ずしも愚に非ず」という謙虚な人間観が横たわっています。
人は皆、完全ではなく、それぞれに偏りや限界を持つ存在です。だからこそ、自分だけが正しいと決めつけることはできず、一方的な否定や感情的な対立は、かえって物事の本質を見失わせてしまいます。
お互いが凡夫である以上、どちらか一方が絶対に正しいなどということはなく、冷静な合意形成こそが和を保つ道だという洞察。
他者の意見を尊重し、自分の考えもまた絶対ではないことを認識することで、初めて真の調和が実現する。この姿勢こそが、組織や社会において対立を乗り越え、より良い道を探るために不可欠な要素なのでしょう。
第十一条:公正な評価の重要性「功過を明に察て、賞罰必ず当てよ」
十一に曰く、功過を明に察て、賞罰必ず当てよ。日者賞は功に在らず、罰は罪に在らず。事を執れる群卿宜しく賞罰を明かにすべし。
「功過を正しく見極め、賞罰を適切に与えなさい。近頃は功績があっても正しい報いがなく、罪を犯しても罰が与えられないことがある。官を執る者は賞罰を明らかにしなければならない」という文。
成果や過失を正しく見極め、それぞれに応じた賞罰を適切に行うことの重要性が、この条文には明確に示されています。不透明な評価や不公正な懲罰が続けば、人々の信頼は失われ、組織全体の秩序が崩れてしまう。これは古代も現代も変わらぬ組織運営の原則といえるでしょう。
公平な評価がなされなければ、努力が報われず、優秀な人材は失望し、組織に対する忠誠心は薄れていきます。
一方で、過ちを犯した者が正しく処罰されなければ、規律が緩み、不正が蔓延してしまいます。
こうした状況を避けるために、聖徳太子はこの条文を通じて、組織を健全に保つためには「正当な評価の仕組み」を築くことが不可欠であると説いているのです。
現代の企業や行政でも、公正な人事評価や適切なフィードバックの仕組みが求められるのは、この理念と根本的に通じるものがあります。
第十二条:不当な搾取の禁止「国司、国造、百姓に歛めとること勿れ」
十二に曰く、国司、国造、百姓に歛めとること勿れ。国に二君靡し。民に両主無し。率土の兆民は、王を以て主と為す。任せる所の官司は、皆是れ王の臣。何ぞ敢て公と与に百姓に賦め歛らむ。
「国司や国造は民から勝手に取り立てをしてはならない。国に二人の君主はおらず、民にもふたつの支配者はいない。全国の民は王を主として仰ぐのであって、任じられた官司は皆王の家臣であるから、どうして勝手に税を徴収できようか」という文。
この条文は、地方行政の乱れを防ぎ、豪族や地方官が勝手に民を搾取することを制限しようとするものです。地方ごとに異なる権力が勝手に租税を課したり、権威を誇示したりすることが横行すれば、国家全体の秩序は崩れ、民衆の負担は際限なく増してしまいます。
聖徳太子が目指したのは、単に権力を中央に集めることだけではなく、統治の一元化によって民衆を不当な搾取から守ることでもあったのでしょう。地方の豪族や国司が独自に税を取り立てることを禁じることで、天皇を唯一の支配者とし、民の負担を軽減しようとした意図が感じられます。
単なる権力闘争ではなく、「国家としての一体性」を守るための施策だったと考えられます。統治のルールを統一し、無秩序な地方支配を防ぐことによって、国家全体の安定を図ろうとしたのではないでしょうか。
第十三条:連携と情報共有「諸々の任せる官者、同じく職掌を知れ」
十三に曰く、諸々の任せる官者、同じく職掌を知れ。或は病し、或は使して事に闕ぐること有らむ。然れども知ることを得るの日には、和ふこと曾より識れるが如くせよ。其れ与り聞かざるを以て公務を防ぐること勿れ。
「任じられた官職の人々は、互いの職務をきちんと把握しておくべきである。病や用事などで不在になるときも、情報を共有していれば公務は滞らない。自分が聞いていないからといって、仕事を止めてはならない」という文。
属人的な管理を避け、組織としての連携と引き継ぎを徹底する必要性を説いています。個人の能力に依存するのではなく、官人同士がそれぞれの職掌を把握し、不測の事態にも滞りなく対応できる体制を築くことが重要であると。
この条文が示すのは、単なる個々の責任感ではなく、組織全体として機能し続けるための「チームワーク」の重要性でしょう。
特定の人物に業務が集中し、その人が不在になった途端に仕事が停滞するような組織では、安定した統治は成り立ちません。だからこそ、個々の職務を明確にし、互いの業務を補完し合えるような仕組みが必要だということですね。
情報共有やバックアップ体制が整っていれば、担当者が交代してもスムーズに業務が継続され、組織全体の安定性が保たれます。この条文には、組織を長期的に健全に運営するための先見性が表れた一文です。
第十四条:才能を認める度量「嫉み妬むこと勿れ」
十四に曰く、群卿百寮、嫉み妬むこと勿れ。我れ既に人を嫉まば、人亦我を嫉まむ。嫉妬の患其の極りを知らず。故に智己れに勝るれば則ち悦ばず。才己れに優るれば則ち嫉妬む。是を以て五百歳の後乃ち賢に遇はしむるも、千載にして以て一聖を待つこと難し。其れ聖賢を得ざれるときは、何を以てか国を治めむ。
「群卿や百寮は互いに嫉妬を抱いてはならない。自分よりも才能に優れた者がいれば喜ばず、妬むようになるが、それでは賢人を登用できず、国家にとって大きな損失となる」という文。
才能に秀でた者を妬むことの危険性を強く戒めた条文です。有能な人材を排除する嫉妬心こそが、組織や国家の発展を阻む最大の障害になり得るという、極めてシビアな認識が示されています。
もし、人々が優れた者を正当に評価せず、むしろ妬んで遠ざけるようになれば、国を導くべき聖賢の存在すら失われてしまう。結果として、組織は凡庸な人材ばかりが跋扈し、活力を失い、やがて衰退していくことになるでしょう。
他者の優れた点を素直に認め、敬意をもって受け止める姿勢がなければ、短期的には個人の感情が満たされても、長期的には国家全体にとって甚大な損失となるのです。
第十五条:私利私欲を捨て公を重んずる道「私に背きて公に向く」
十五に曰く、私に背きて公に向くは是れ臣の道なり。凡そ人に私あれば必ず恨み有り。憾有るときは必ず同らず。同らざれば則ち私を以て公を妨ぐ。憾起る時は則ち制に違ひ法を害る。故に初の章に云へり、上下和諧れと。其れ亦是の情なる歟。
「私心に背いて公を重んずることこそが臣下の道である。人に私情があれば必ず恨みが生じ、恨みがあれば調和を乱す。初めの条で説かれたように、上下が和合するには私の欲を捨てなければならない」という文。
「私利私欲を捨て、公のために尽くすのが臣下の道である」というこの条文は、個人的な感情や私的な利益を優先すれば、組織の秩序は次第に崩れ、ひいては法そのものが形骸化してしまう危険性を指摘します。
統治に携わる者の基本的な倫理観を示した一文です。
国家や組織という大きな枠組みを維持し、円滑に機能させるためには、それを支える人々が自己の欲を抑え、共通の目的に向かって協力し合う姿勢が不可欠です。個々の利害が対立し、私情が前面に出るようになれば、組織は内部から崩壊し、結果として社会全体の混乱を招くことになるでしょう。この条文が示しているのは、公の利益を第一に考え、全体の調和を重んじることこそが、国家や組織の健全な運営を支える基盤であるという考え方です。
組織や社会を動かす立場にある者が自らの利益を優先し、公の利益を二の次にした結果、数々の問題を引き起こしているのは現代社会においても変わりません。1000年以上経過して「人」というものは変わらないものなのかもしれませんね。
第十六条:庶民の生活と生産への配慮「民を使ふに時を以てする」
十六に曰く、民を使ふに時を以てするは古の良き典なり。故に冬の月には間あり。以て民を使ふ可し。春より秋に至るまでは農桑の節なり。民を使ふ可らず。其れ農せざれば何をか食はむ。桑せざれば何をか服む。
「民を使役するには時期をわきまえよ。冬の月は余裕があるので働かせてもよいが、春から秋は農作や養蚕の時期であるから民を使えば食べ物も衣服も得られなくなる」という文。
民を使役する際のタイミングを慎重に見極めることの重要性を説いています。
人々の生活や生産活動に配慮せず、無計画に徴用を行えば、国家の基盤そのものが揺らいでしまうという考え方ですね。
農業や養蚕が最も重要な時期に農民を動員してしまえば、食糧や衣服の生産が滞り、結果として国全体の経済や民生が悪化することになります。短期的な利益や即時の労働力を優先するのではなく、民の生活を守ることが国家の持続的な繁栄につながるという、極めて合理的な視点が提示されています。
この条文が示すのは、単なる労働管理の話ではありません。
国家運営の根幹に「思いやり」と「長期的な視野」を持つことがいかに大切かを考えるべきでしょう。統治者や指導者は、民を単なる労働力と見るのではなく、彼らの生活と生産のバランスを考慮しながら、社会全体の調和を図るべきなのです。
短期的な生産性や効率だけを追求すれば、持続可能な成長を阻害し、結果として組織や国家の活力を失うことになりかねません。
第十七条:合議制による最良の決定「それ事をば独り断むべからず」
十七に曰く、それ事をば独り断むべからず。必ず衆と与によろしく論ふべし。小事は是れ軽し。必ずしも衆と与にすべからず。唯し大事を論ふに逮びては、若し失あらむことを疑ふ。故に衆と共に相ひ弁ふるときは辞則ち理を得む。
「事を決定するにあたっては、一人で断じてはならない。必ず大勢で議論すべきである。小事ならともかく、大事に関しては誤りも多いので、みなで論じ合えば理にかなった結論が得られる」という文。
「それ事をば独り断むべからず」は、本憲法の締めくくりともいえる重要な理念です。
聖徳太子が描いた理想の国家像とは「権力者が独断で物事を決める統治」ではなく「多くの人々の知恵を集め、最良の結論を見出す統治」だったのでしょう。
重要な事柄は決して独断で決めてはならず、必ず衆と議論し、多くの知恵を結集することで、より正しい道理を導き出すべきである。この条文は、合議制の重要性を強く語ります。
意思決定において多様な視点を取り入れることは、単に慎重さを増すというだけでなく、誤りを減らし、より優れた選択を可能にします。
個人の判断にはどうしても限界があり、偏りや見落としが生じることは避けられません。しかし、複数の視点が交わることで問題の本質がより明確になり、より合理的で公平な結論へと近づくことができるはずです。
この合議制の考え方は、第一条の「和」と密接に結びついています。
単なる意見の一致ではなく、異なる立場や考え方を尊重しそれらを統合することで、最善の答えを導き出すというプロセスこそが「和」の本質でもあるのでしょう。
十七条憲法概要
十七条憲法の条文をざっと眺めてきました。
現代にも通じる普遍的な教えがこんなにも並んでいることに驚きませんか?
およそ1400年も前に考えられたこの文章が時代を超えてなお響くのは、それが人間社会の本質を極めて鋭く捉えたものだからではないでしょうか。
十七条憲法はその名に「憲法」とついているものの、私たちが知る近代的な憲法とは性質が大きく異なります。
まるで儒教の経典を思わせるような「道徳規範」としての側面が強く、統治者や官僚に向けた倫理的指針の集合体である点に特徴があります。
近代的な憲法(constitution)は、国家権力のあり方を規定し、支配する側とされる側の双方が従う法規範であり、政府の権限や国民の権利・義務を明確に定めるものです。
しかし、十七条憲法は、そのような「法の枠組み」とは異なり、当時の官人や豪族に対する道徳・倫理規定としての性格を強く帯びています。
ここで説かれるのは、国家を運営する立場にある者がいかに振る舞うべきかという統治者の心得であり、国民全体の権利や義務を定めたものではありません。
この点において、十七条憲法は、いわば「官僚倫理マニュアル」とも言える性格を持っています。「詔を承けては必ず謹め」「礼を本とせよ」「善を勧め悪を懲らせ」などの条文が示すように、ここで求められているのは政治を司る者の自覚や心構えであり、社会全体の法体系を定める近代憲法とは根本的に異なるものです。
したがって、十七条憲法は現代の立憲主義とは無関係な「行政道徳」の枠組みに位置づけられるべきものです。
「法」というよりは為政者が守るべき「道徳的基準」として機能する(した)ものであり、その思想の根底には、儒教や仏教、法家思想などの影響が強く見られます。
それゆえに、十七条憲法を単なる古代の法令として捉えるのではなく、当時の政治思想や倫理観を知るための貴重な指針として読み解くことが重要なのかもしれません。
十七条憲法発布の背景
聖徳太子が603〜604年頃に制定したとされる冠位十二階は、能力や功績に基づく官僚登用を目指し、日本の政治体制の転換点となりました。
そしてほぼ同時期に発布された十七条憲法。これまで述べてきたように、単なる法令ではなく、官人としての高いモラルを涵養し、統治者のあるべき姿勢を示す「道徳訓戒」としての性格を持っていました。
この背景には、「豪族中心の社会」から「官僚制度」へと移行する過程があります。
それまでの日本は、血縁や家柄を基盤とした豪族の支配が色濃く残っており、権力は有力氏族に分散していました。しかし、聖徳太子はそれを改め、天皇を中心とする中央集権体制を確立するための理念的支柱として十七条憲法を位置づけたのです。
当時の日本は、国内外の大きな変革の波のなかにありました。
7世紀初頭には豪族同士の権力争いや政権内部の対立が深刻化しており、特に仏教の受容をめぐる蘇我氏と物部氏の対立が象徴的でした。推古天皇の即位後も、蘇我馬子が権力を握る一方で、国内には依然として不安定な空気が漂っていました。
こうした混乱を収めるために、聖徳太子は「和(調和・協調)」を最重要視したのだと思うのです。
十七条憲法の第一条において「和を以て貴しと為す」と明確に示されているのは「このような無益な争いを鎮め、合議によって政治を進める必要があるのでは」と考えたからでしょう。
聖徳太子にとって「和の国」を築くことは、単なる理想論ではなく、実際に朝廷を統一し、強固な政治基盤を確立するための戦略だったのでしょう。
また、この時期には日本の対外関係にも大きな動きがありました。
中国大陸では隋が強大な帝国として周辺国に冊封体制を敷いており、日本もその圧力のなかにありました。
推古天皇の時代に日本は遣隋使を正式に派遣し、中国皇帝との交流を開始しますが、その過程で日本の政治制度や文化の遅れを指摘されたとも伝えられています。
この屈辱を糧に、聖徳太子は国内改革を加速させました。
冠位十二階と十七条憲法はいずれも、日本が隋と対等に交際するための最低限の政治制度として位置づけられ、「日出處天子(日の出る処の天子)」として、独立した国家としての威信を示そうとしたものでした。
したがって、十七条憲法は単なる内政改革にとどまらず、日本が冊封体制に組み込まれず、自主独立の立場を維持するための精神的宣言でもあったと見てもいいかもしれません。
即ち、統治のあり方を定めると同時に、国際社会における日本の立場を明確にするための意思表明としても活用したのです。
聖徳太子の目指したものは、単なる国内統治の安定だけではなく、国家としての自立とその基盤となる倫理・道徳の確立だったのかもしれません。
「聖徳太子」呼称をめぐる議論と背景
聖徳太子についても少し触れさせてください。
冠位十二階と十七条憲法を制定した聖徳太子(574〜622)は、日本の歴史教育において長く尊崇されてきた偉人の一人で…などと言われるまでもなく誰もが知っていることだと思いますが、その呼称や歴史的な扱いについては、今日に至るまで議論が続いていることを知りませんでした。
『日本書紀』では、「上宮厩戸豊聡耳太子(うえのみやのうまやどのとよとみみのひつぎのみこ)」と記されており、「聖徳太子」という称号は、死去から129年後の天平勝宝3年(751年)に編纂された『懐風藻』に初めて登場したとされています。
さらに、平安時代に成立した『日本三代実録』『大鏡』『東大寺要録』『水鏡』といった史書には、すでに「聖徳太子」という呼称が定着しており、「厩戸」「豊聡耳」といった本名に近い表記は見られなくなっていたようです。
こうした経緯から、「聖徳太子」という名は、後世になって付与された尊称であり、生前には使われていなかった可能性が高いとされています。
これに関連し、近年、一部の専門家の間で「厩戸王(聖徳太子)」と表記すべきだという議論が持ち上がりました。
2017年2月に公表された中学学習指導要領の改定案では、「厩戸王(聖徳太子)」という表記が提案されました。しかし、この改定案には多くの異論が寄せられ、パブリックコメントでの議論や国会での質疑を経て、最終的に撤回されることとなりました。
この議論の背景には、「聖徳太子」という称号が後世に作られたものであり、生前に使われた本名を重視すべきではないかという考えがあります。
確かに、歴史上の人物の呼称をその時代に即したものへと改める試みは、学術的には妥当な視点と言えるでしょう。
しかし、「聖徳太子」という名称は、長年にわたり広く浸透し、日本の歴史や文化に深く根付いた存在です。そのため、単なる呼称の変更というよりも、日本人の歴史意識そのものに影響を与える問題として扱おうという判断になったのかもしれません。
「和」の思想の再評価と近代以降の聖徳太子像
さて、そんな聖徳太子ですが、その評価やイメージは時代によって大きく変遷してきたようです。
石井公成氏の論文「傳聖徳太子『憲法十七條』の「和」の源流」によれば、聖徳太子が「和の精神」を説いた偉人として広く顕彰されるようになったのは、実は明治時代以降のことだといいます。
もともと民間信仰としての太子崇敬は古くから存在していましたが、近世の儒者たちの間で特に高く評価されていたわけではなく、江戸時代以前の思想界においては、それほど重視されていなかった可能性もあります。
ところが、近代になると聖徳太子は日本の政治や文化の伝統を象徴する存在として急速に注目されるようになりました。
その契機の一つが「憲法」という言葉の登場です。
明治初期には「国憲」という言葉も用いられていたようですが、次第に「憲法」が一般化し、国家の基本法を意味する言葉として定着していきます。
その過程で、「十七条憲法=日本には早くから憲法が存在していた」という図式が形成され、聖徳太子の名声がより強調されるようになりました。しかし、これは近代的な意味での「憲法」とは大きく異なるものであり、「日本には西洋に先駆けた憲法が存在していた」とする論説は、歴史的な脈絡を無視した見解であるとの批判もあります。
さらに、1930年代に入ると、国体明徴声明によって日本の国体(天皇制や家族制度などを中心とした民族精神)を強調する風潮が強まりました。
こうした流れのなかで、文部省が刊行した『國體の本義』(1937年)では、「和の精神」が日本の伝統の根本にあると位置づけられ、その具体例として十七条憲法が取り上げられました。
これによって、聖徳太子は単なる歴史上の人物ではなく、日本の精神文化の礎を築いた象徴的な存在として再評価されることになります。
しかし、戦後。日本社会の価値観の変化に伴い「和」という概念の受け止められ方も変わります。
軍国主義的な色彩を帯びていた「和」は、次第に平和主義の象徴へと移行し、聖徳太子もまた「平和の使徒」のような扱いを受けるようになりました。
戦後教育においても、「和を以て貴しと為す」は、民主主義や平和の精神と結びつけられ、日本人の価値観の一部として広く浸透していきます。
こうして聖徳太子は時代ごとに異なる評価を受けながら、日本の思想や政治的な潮流のなかでその姿を変えてきました。
江戸時代以前にはそれほど重視されていなかった(かもしれない)彼が、明治期以降に日本の精神的支柱として持ち上げられ、さらに戦後になると平和主義のシンボルへと変容していく。その過程は、歴史がいかに時代の要請に応じて「偉人」を再構築していくのかを示す、興味深い事例と言えるでしょう。
古き英知に触れて
もっとも、十七条憲法が制定された当初から社会全体に広く浸透していたわけではありません。
また、時代を経るにつれて「偽作説」が唱えられたり、政治的に利用されたりと、その評価は揺れ動いてきました。
まるで古い着物を染め直すように、時代ごとに異なる色合いを纏わされてきたのです。
しかし、歴史研究の成果や伝承の積み重ねを踏まえればこの憲法に示された理想や教訓は当時として極めて意義深いものであり、現代においてもなお普遍的な価値を持ち続けていることは言うまでもありません。
今日の社会や組織を見渡せば、情報や価値観の多様化、そしてそれに伴う利害の対立は避けがたいものとなっています。こうした環境のなかで、十七条憲法が説く「和」「信」「礼」などといった理念は、迷い歩く私たちの足元を照らす灯火のようにも思えます。
他者の意見を尊重しながらも自らを省み、和をもって議論し、社会や組織をより良い方向へと導いていく。個人の才覚や功績を正当に評価しながらも、公の利益のために私利私欲を慎み、合議を重んじることで社会を安定へと導く。
十七条憲法に記された数々の教えは、1400年以上前の古代日本においても、そして現代の組織論やリーダーシップ論においても、変わることのない本質的な価値を示してくれています。これらの思想は、時代や環境が変わってもあらゆる組織の基盤として不可欠なものでしょう。
組織という概念がかつてないほど複雑化し、多様な価値観が交錯する現代。独断専行ではなく、多様な視点を集約し、誤りを減らすことこそが、時代の荒波を乗り越え、成果を生み出す鍵となるはずです。
聖徳太子の時代から何世紀もの時を隔てながら、なおも現代社会の諸問題と響き合う十七条憲法。その条文に込められた「古き英知」は、私たちが互いを尊重し、組織を活かし、より良い未来へと進んでいくための指針として、今なお強い輝きを放っていました。