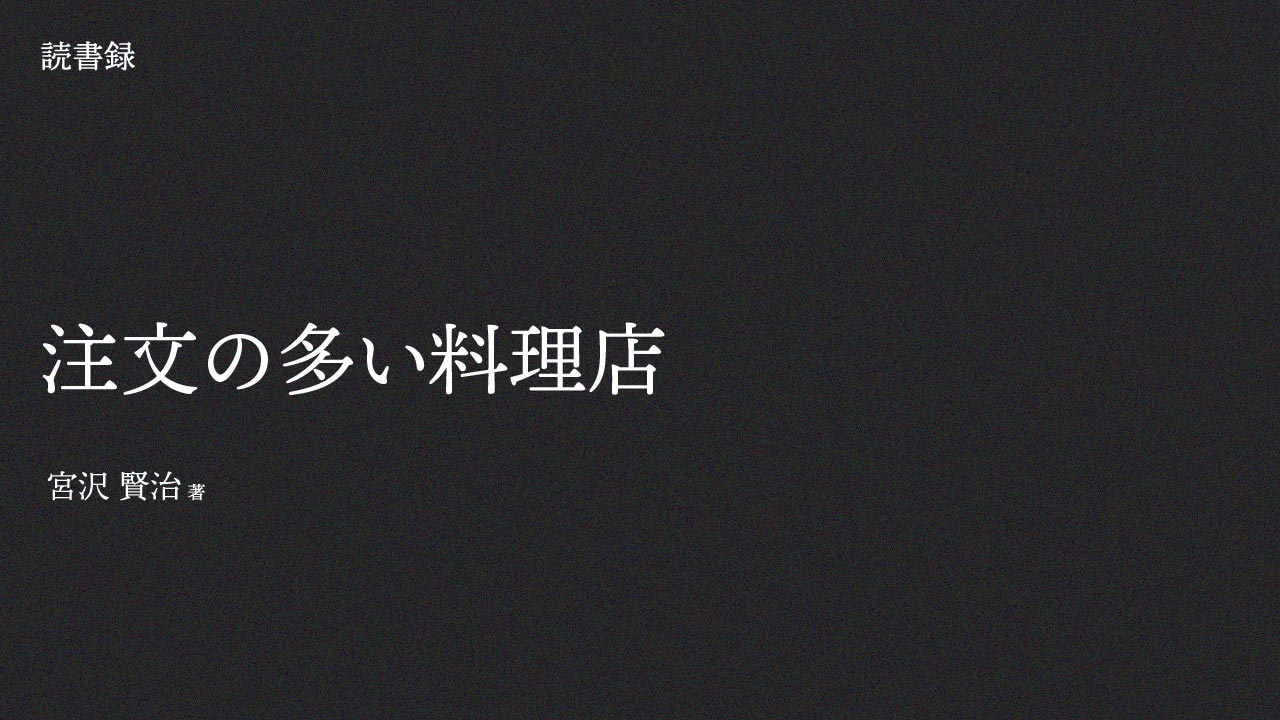そろそろ夏休みの時期ですね。
子どもの頃は、夏休みが非常に楽しみでしたが、同時に悩みの種でもあったのが宿題の存在です。中でも読書感想文は、いつも最後まで手をつけられず、苦手意識ばかりが残っていました。
最近ふと、そんな読書感想文で書いた一冊の本を思い出しました。
それが、宮沢賢治の「注文の多い料理店」です。
当時は不思議でちょっと怖くて、それでもどこか面白い話だなという程度の感想でした。大人になった今、改めて読み返してみると、子どもの頃には気づけなかった深いメッセージが見えてきます。
子どもの頃とは違った視点で、本作品を眺めていきましょう。
森で迷った紳士たちが出会った奇妙なレストラン
まずは簡単なあらすじからお伝えします。
物語の舞台は、深い山の中。
猟に出かけた二人の若い紳士が、道に迷い、空腹と疲れで弱り果てていました。そんなとき、彼らの目の前に現れたのが「西洋料理店 山猫軒(やまねこけん)」という看板。救いを求めて中に入ると、そこには次々と不思議な「注文」が待っていました。
「髪をきちんと整えてください」「クリームを顔に塗ってください」「塩と酢を体にすりこんでください」など、不自然なほど多すぎる注文に戸惑いながらも、紳士たちは指示に従います。
ところが、それらの「注文」の本当の意味は、、、。最後には意外な真相が明らかになり、読者にインパクトを残します。
タイトルの裏に隠された本当の意味
「注文の多い料理店」というタイトルからは、「サービス旺盛なお店」「細やかな気配りのある高級レストラン」を想像するかもしれません。
しかし、この物語に登場する“注文”は、決しておもてなしのためではありません。それらは、客を「料理するための準備命令」だったのです。
表向きは親切で丁寧な態度を装いながら、実は相手を搾取しようとしている。
この物語には、そんな「皮肉」と「構造の逆転」が巧みに織り込まれています。宮沢賢治は、言葉の裏側にある真意を見抜く目を、読者に問いかけているのでしょう。
童話に見えて寓話、物語に込められた3つのテーマ
童話のように読める作品ですが、実は深い教訓や社会風刺を含んだ寓話としての側面を持っています。主に、3つのテーマが読み取れます。
1. 自然への敬意の喪失
物語の舞台は、深い山の中。そこは人間の都合では、動かすことができない自然の世界です。しかし紳士たちは、「自然を狩りの対象」としか見ていません。
その結果、彼らは自らの軽率さと傲慢さによって窮地に陥ります。自然は人間の所有物ではなく、共に生きる存在であるということを訴えています。
2. 客だから偉いという思い込み
紳士たちは料理店からの注文に対して、おもてなしだと勘違いをしています。しかし、その思い込みこそが命取りになるのです。
この構図は、社会の中での上下関係や立場の勘違いを風刺しています。消費者として、立場の強い側に立っているつもりでも、実は仕組まれた構造の中では利用されているだけかもしれないという皮肉としても読み取れます。
3. 表面的なサービスの裏側
物語の舞台である山猫軒は、入り口からして立派に整っており、「どなたもどうかお入りください。決してご遠慮はありません」と丁寧に書かれた札まであります。しかし、その裏には命を奪う罠が仕掛けられていました。
丁寧さや親切さが、必ずしも善意や誠実さとイコールでないこと。この作品は、「見かけだけで安心してはいけない」というメッセージを問いかけています。
宮沢賢治が伝えたかった童話の使命
初版本の巻末に添えられた「広告」(序文)には、賢治の童話に対する真摯な姿勢があらわれています。
イーハトヴは一つの地名である。強て、その地点を求むるならばそれは、大小クラウスたちの耕してゐた、野原や、少女アリスガ辿つた鏡の国と同じ世界の中、テパーンタール砂漠の遥かな北東、イヴン王国の遠い東と考へられる。
実にこれは著者の心象中にこの様な状景をもつて実在した
ドリームランドとしての日本岩手県である。そこでは、あらゆる事が可能である。人は一瞬にして氷雲の上に飛躍し大循環の風を従へて北に旅する事もあれば、赤い花杯の下を行く蟻と語ることもできる。
罪や、かなしみでさへそこでは聖くきれいにかゞやいてゐる。深い掬の森や、風や影、肉之草や、不思議な都会、ベーリング市迄続々電柱の列、それはまことにあやしくも楽しい国土である。
この童話集の一列は実に作者の心象スケツチの一部である。それは少年少女期の終り頃から、アドレツセンス中葉に対する一つの文学としての形式をとつてゐる。
この見地からその特色を数へるならば次の諸点に帰する。
一 これは正しいものゝ種子を有し、その美しい発芽を待つものである。而も決して既成の疲れた宗教や、道徳の残澤を色あせた仮面によつて純真な心意の所有者たちに欺き与へんとするものではない。
二 これらは新しい、よりよい世界の構成材料を提供しやうとはする。けれどもそれは全く、作者に未知な絶えざる警異に値する世界自身の発展であつて決して畸形に涅ねあげられた煤色のユートピアではない。
三 これらは決して偽でも仮空でも窃盗でもない。 多少の再度の内省と分折とはあつても、たしかにこの通りその時心象の中に現はれたものである。故にそれは、どんなに馬鹿げてゐても、難解でも必ず心の深部に於て万人の共通である。卑怯な成人たちに畢竟不可解な丈である。
四 これは田園の新鮮な産物である。われらは田園の風と光の中からつやゝかな果実や、青い蔬菜を一緒にこれらの心象スケツチを世間に提供するものである。
要約すると、宮沢賢治が描いた「イーハトヴ」は、現実の地図には存在しない、心の中にある理想の場所です。岩手県をもとにしながらも、夢や空想が自由に広がるファンタジーの世界で、そこでは風と話したり、蟻と語り合ったり、悲しみさえも美しく輝くような、不思議で魅力的な出来事が起こります。
この童話集は、そんな賢治の心象風景を描いたものであり、子どもから大人になる過程の読者に向けた、文学的な試みでもあります。
作品には4つの特徴があります。
1つ目は、「正しさの種」を内に持ち、それがやがて美しく芽吹くことを願っている点です。古びた道徳や宗教を押しつけるのではなく、純粋な心に語りかけようとしています。
2つ目は、よりよい未来をつくるための材料を提示する点です。ただし、それは完成された理想の世界ではなく、まだ発展途上の未知の世界です。
3つ目は、偽りではなく、賢治自身の心から自然に生まれたものだということです。たとえ難解に見えても、それは人間の心の奥底に共通するものです。
4つ目は、これらの物語が自然とともに育まれた、田園からの新鮮な贈り物であるということです。風や光の中で育った果実や野菜のように、物語もまた誠実なかたちで世の中に届けられています。
要するに、この童話集は、夢と自然、心の真実から生まれた、未来への希望を込めた文学作品なのです。
結びに:読むたびに姿を変える、不思議な物語
「注文の多い料理店」は、決して長い物語ではありません。しかし、その短さの中に、私たちの価値観を揺さぶるような問いが詰まっています。
子どもの頃に読めば、ただ不気味で不思議な出来事として記憶に残るでしょう。大人になって読み返すと、そこに潜む風刺や構造の反転、そして社会への皮肉に気づかされます。
この物語は、読むたびに新しいメッセージを投げかけてくる問いの一冊です。
結末がどうなるかは知っていても、その都度感じることは少しずつ違います。そんな体験を与えてくれるのが、読書の醍醐味であり「注文の多い料理店」という作品が時代を超えて読み継がれている理由なのでしょう。