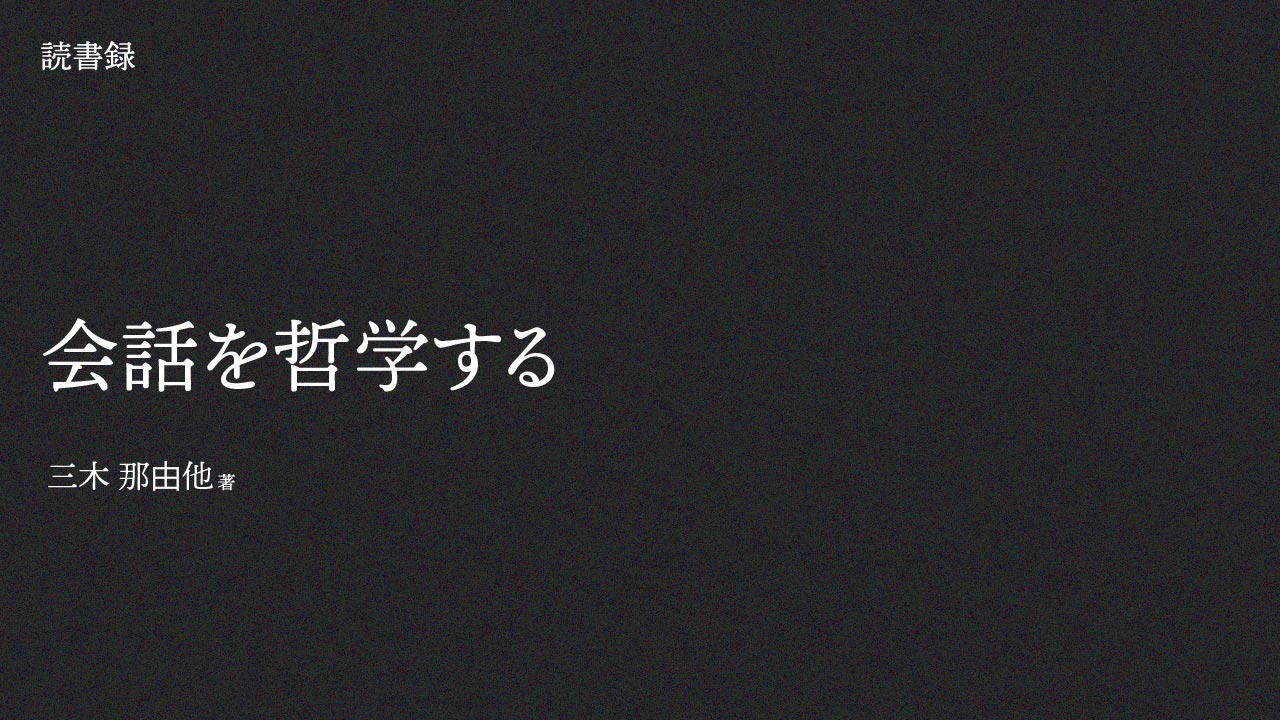三木那由他氏の「会話を哲学する」は、日常的な会話を深く考察し、我々が無意識に行っている言葉のやり取りを哲学的視点から分析した一冊です。
著者は大学の卒業論文から現在に至るまで「会話とはどのような営みなのか」「会話をすることで何をしているのか」といったテーマを探究しています。
三木氏は「会話は一枚岩の営みではなく、いくつもの異なる営みが含まれる集合体である」と主張し、その分析軸として、「コミュニケーション」と「マニピュレーション」という二つの概念を提示しています。
コミュニケーションは「社会的約束事の共有プロセス」であり、相互理解を目的とした情報交換で、マニピュレーションは、会話を通じて相手の心理や行動に影響を及ぼそうとする働きかけです。
会話というありふれた現象をこれまでとは違った仕方で見るためのきっかを与えてくれます。
言葉の深淵を哲学する「会話を哲学する」について
第一章では、コミュニケーションとマニピュレーションという概念について説明。
第二章から第五章では、コミュニケーションを主に扱い、第六章と第七章では、会話においてなされつつあるコミュニケーションとは異なる営みとしてマニピュレーションに目を向けられています。
その中で漫画や小説など様々な作品に登場する会話を吟味し、言葉の裏に隠された「企み」を探ります。
例えば相手の好意が明白な状況でも、あえて「好き」という言葉を言わせようとする行為の心理的メカニズム。純粋なコミュニケーションなら感情の相互理解が達成されれば目的は達せられるはずですが、人間は言葉による「儀式的確認」を求めてしまうものです。
また、死者との会話という特殊なコミュニケーション形態も興味深く分析されています。死者とは約束を交わすことも、その意志を操作することも原理的に不可能であるにもかかわらず、私たちは墓前で語りかけ、返答さえ期待してしまいます。
著者が指摘するように、表向きのコミュニケーションが失敗しながら、知らず知らずのうちにマニピュレーションとして機能しているケースもあれば、逆に作為的なマニピュレーションが、かえって深い相互理解を生む逆説も存在します。
このような会話の曖昧で多層的な性質こそ、人間関係の不思議であり魅力だと気付かせてくれます。
「会話を哲学する」と「三酔人経綸問答」の2つの作品から見る「聴く」という倫理的行為
本書は日常的な会話の中に潜む哲学的意味を掘り下げていますが、日本思想の伝統的な「対話」の系譜に連なるものとも言えます。特に明治期の思想家・中江兆民の「三酔人経綸問答」との思想的共鳴が見えてきます。
両作品は、「酔い」や「日常」という枠組みを用いて、形式張らない対話の可能性を探っている点が特徴的です。
三木氏が現代の日常会話に哲学的意味を見出したように、兆民もまた、酔った三人(紳士君、豪傑君、南海先生)の政治談義という形式を通じて、当時の日本社会が抱えていた根本的な問いを浮き彫りにしています。
また両作品で「聴く」という行為が強調されていることも重要なポイントです。
これは兆民の描く南海先生のスタンスにも通じます。南海先生は対立する二者の意見をじっくりと聴き、調和点を探る姿勢を示しますが、これは三木氏が説く「他者の存在そのものを受け入れる倫理的行為としての聴く姿勢」と重なります。
結びに
日々のコミュニケーションは家族や友人、会社の上司部下、クライアントの方々など多岐に渡ります。またSNSやデジタルコミュニケーションの発達により、現代の会話の形は大きく変容しています。
本書を読み進める中で、日々の会話に対して見つめ直す機会でもありました。
自分の伝えたいことは頭の中にあるけれども、言葉に詰まったり、意味をうまく伝えられなかったりする経験は少なからずあるものです。自分の考えは頭の中にあるのに、それを言葉にすることの難しさを痛感します。
これまでコミュニケーションは、自分の思いを分かりやすく伝えることだと考えていました。しかし本書を通じて、”聴く”ことの重要性を改めて認識しました。
伝えたいことは頭の中にあるけれども、言いよどんだり、止まったりして言葉にするのに時間がかかってしまう方も多いはずです。
そんな時にじっくり待ち、受け止める姿勢こそが大切なのではないでしょうか。
コミュニケーションはお互いに完全に通じ合うことではなく、わかり合おうとすることがとても大切なんだなと改めて感じました。