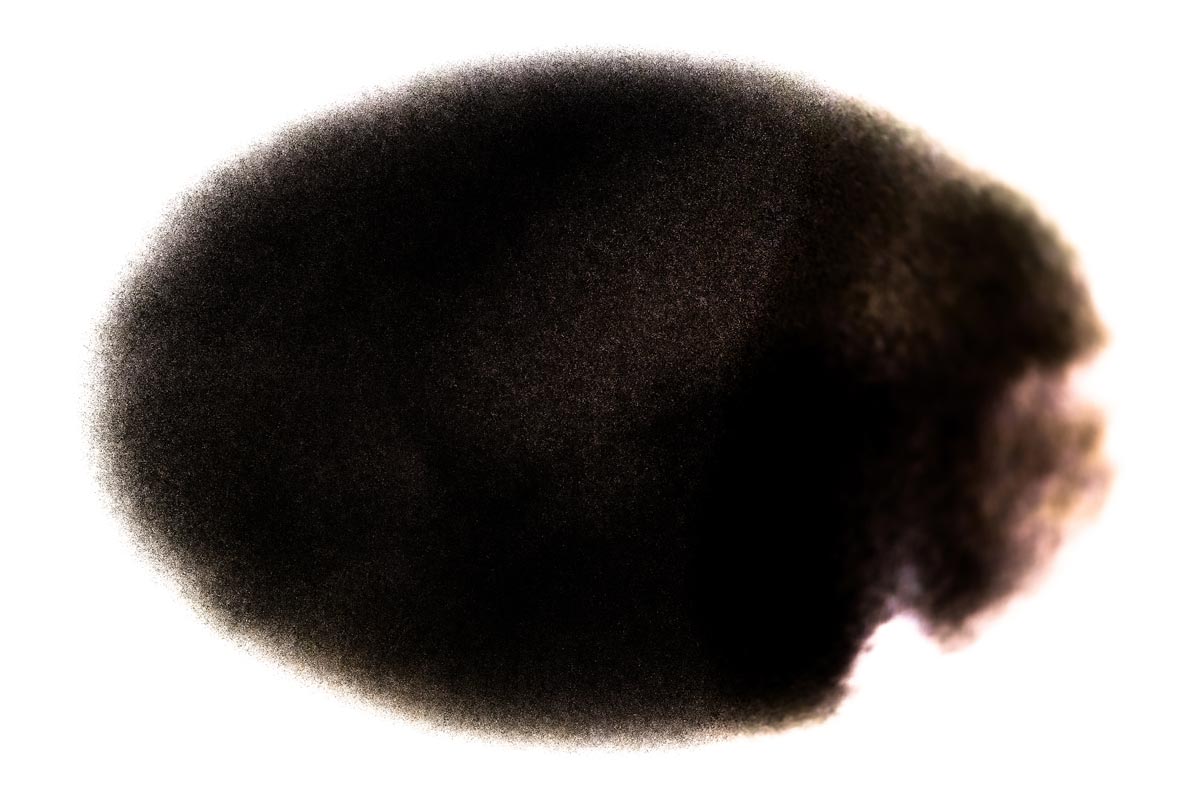最近、この社会でいつから息継ぎがしづらくなったのだろう、とよく考えます。気づけば「息をすること」さえ忘れて生きているような、そんな窮屈さを感じるのです。
なんだかどんどん自分が考えられなくなってきているような、頭が麻痺していっているような感覚なのです。
スマホの通知が鳴り、予定が詰まり、情報が絶えず押し寄せてくる毎日。一息つこうとする間もなく、次の波がもう目の前に迫ってくる状況。
まるで呼吸を許さない社会の中を、ただ懸命に泳いでいるような感覚です。
けれども、人は呼吸なしでは生きていけません。もちろんこれは比喩であり、同時にまぎれもない現実でもあります。
息が浅くなるということは、生きる感覚そのものが浅くなるということだと感じます。呼吸の浅さは、思考の浅さや、心の鈍さに直結しているように思えるのです。
日々の忙しさの中で呼吸を忘れるたび、私たちは少しずつ、自分という存在の輪郭を見失っていくのかもしれません。
呼吸を整えるというのは、単なる深呼吸ではなく「不在を学ぶ」ことかもしれません。
通知の激流の不在を学び、情報の濁流の不在を学び、現代的潮流の不在を学ぶ。
何かをし続けるのではなく、何もしていない「時間」を受け入れること。その静けさの中に、ようやく本当の呼吸が戻ってくると感じます。
呼吸ができるから思考ができる。思考ができるから次の一手を打ち出せるのです。
世界のスピードにただ追いつこうとするより、自分だけの静かな「文化的時間」を取り戻し、豊かな思考に身を預けること。
そのほうが、ずっと人間らしい生き方だと思いませんか?
生活に句読点を打つ
文章には句読点があります。
ざっくりと表現するならば、句読点とは言葉を整理し、思考に呼吸を与えるための仕組みです。
本多勝一の著書『日本語の作文技術』には、
句読点は字と同じか、それ以上に重要
という一節があります。
もちろんこれは文章についての話ですが、私にはいつも、それが人生にも深い示唆を与えているように思えてなりません。
もし句読点がなければどうなるでしょう。
文章や言葉の意味は滲み、読み手はどこで立ち止まり、そしてどこから再び歩き出せばいいのか分からなくなります。
文は方向を失い、やがて論理も構造も崩れてしまうでしょう。
今の社会は、まるで句読点を失った長文のようです。
新しい情報が絶え間なく流れ込み、思考も感情も「次へ、次へ」と追い立てられていく。私たちは、考える前にもう別のことを考えることを要求されています。そんなリズムの中に閉じ込められているように感じます。
呼吸を整えるという行為は、この「無句読点社会」に、自らの手で句読点を打つことに似ています。
一度立ち止まり、「ここで区切る」「ここで息をつく」と決めること。それは、流されることを拒み、自分の時間を自分のものとして取り戻すための意志の表れです。
それは単なる休息ではなく、生きることに「意味」を取り戻すための文化的覚悟です。
呼吸とは、混沌とした生活の中で散らばった意味をもう一度編み直す技法なのだと思います。
どれほど世界が流れても、私たちは本来、自分のペースで句読点を打つことができるはずです。
そして、その自由さこそが、人間が人間であることの証なのかもしれません。
「間」という知性
日本の文化には、「間」という独特の感性があります。
それは単なる空白ではなく、音や言葉、動作のあいだに生まれる「余韻」としての時間です。能や茶道、俳句にいたるまで、「間」は美を生むための前提として、大切に扱われてきました。
この「間」は、まさに呼吸とよく似ています。
息を吸い、吐くあいだに生まれる静けさ。
それは、何もしていないようでいて、実は次の動きを育てている時間でもあります。
間とは、空白ではなく、可能性の空間です。「何かが生まれる前の静かな胎動」とも言えるかもしれません。
現代社会では、この「間」がどんどん削ぎ落とされています。
無音を恐れ、沈黙を避け、あらゆる隙間を埋めることが「効率的」だと信じてしまった現代。しかし、呼吸を止めたままでは、思考は深まらないはずです。
頭に酸素が回らない状態で、本当に新しい発想や感情が生まれるでしょうか。
思考も感情も、呼吸も、本来はこの「間」の中でしか熟成されません。呼吸を整えるとは、この「間」を思い出すことなのだと思います。
沈黙を、空白を、怖れないこと。その静けさに身を委ねること。それは、何かを生み出すための「知的な勇気」です。
私たちは「考える」前に、まず「間を持つ」ことから始めなければならないのかもしれません。
人生を編み直すために呼吸を整える
私たちは、常に外の出来事に反応しながら生きています。
だからこそ、呼吸が乱れると、世界の見え方もまた乱れていきます。
逆に、呼吸を静めれば目の前の風景や、人の声や、心のざわめきが、少しずつ輪郭を取り戻していきます。
呼吸を整えるということは、世界との関わり方を整えるということなのかもしれませんね。
深く息を吸い、ゆっくりと吐く。
その単純なリズムの中に、世界と自分がもう一度つながる瞬間があります。
それは、情報の波から一歩距離を取り「いま、ここ」に意識を戻すための、小さな祈りのようなものです。
文化とは、本来、呼吸のように「間」を前提にしていました。
祭りには静けさがあり、言葉には余白があり、芸術には沈黙が宿っていました。
呼吸のある文化は、世界を急がせず人の時間をゆるやかに包んでいたのです。だからそこに豊かさがあったのでしょう。
しかし、効率やスピードが価値とされる今、その呼吸はいつの間にか浅くなってしまったのかもしれません。
私たちは、次へ、次へと急ぐあまり、「いま」という一呼吸を見失ってしまってしまったようです。
その人生は豊かでしょうか?
私はもっとゆっくりと呼吸をし、この世界に想いを馳せたいのです。
だからこそ意識的に呼吸を取り戻すことが必要だと感じています。ただ自分を癒やすためではなく「生きることのリズム」をもう一度設計し直すために。
呼吸を整えることは、自分と、自分に関わる世界を整えるための、最初の、そして最も静かな一歩なのだと思います。
どうしたら呼吸を取り戻せるか
呼吸を取り戻すというのは、単に深呼吸をすることではありません。
自分の時間を、自分の手に取り戻すことです。
私たちはいつの間にか他者のリズムの中で生きるようになってしまいました。それらは私たちの呼吸を奪っていきます。
だからこそ、呼吸を整えるためには、まず「世界の速度」から少し距離を取ることが必要です。
ほんのわずかな時間でいいのです。
朝の光をぼーっと眺める、湯気の立つコーヒーを黙って見つめる、昼に1時間一人の時間を作る、夜ただ外を見る、深夜に考え事をノートにまとめる。
なんでもいいんです。
そうした小さな「間」を持つことが、呼吸を取り戻す最初のきっかけになるはずです。
呼吸とは、身体の運動であると同時に、思考の運動でもあります。
呼吸が浅くなれば、考えもまた浅くなり、焦りや苛立ちが思考を支配します。
呼吸を深めれば、思考もまた静かに深く沈み、自分の中に眠っていた感情や言葉が浮かび上がってきます。
呼吸を取り戻すとは「すぐに答えを出さない」ことを自分に許すことです。
結論を急がず沈黙の中に身を置く、その「待つ」という姿勢こそ、人間が本来もっていた時間の使い方ではないでしょうか。
忙しさの中で私たちは「息をしているつもりで、呼吸していない」ことがあります。
だからこそ、意識して深く息を吸い、ゆっくりと吐く。そのたびに、世界は少しだけやわらかくなり、自分という存在が思考を取り戻していきます。
そんな時間を自分の人生で多く作っていきたいと、そう思っています。