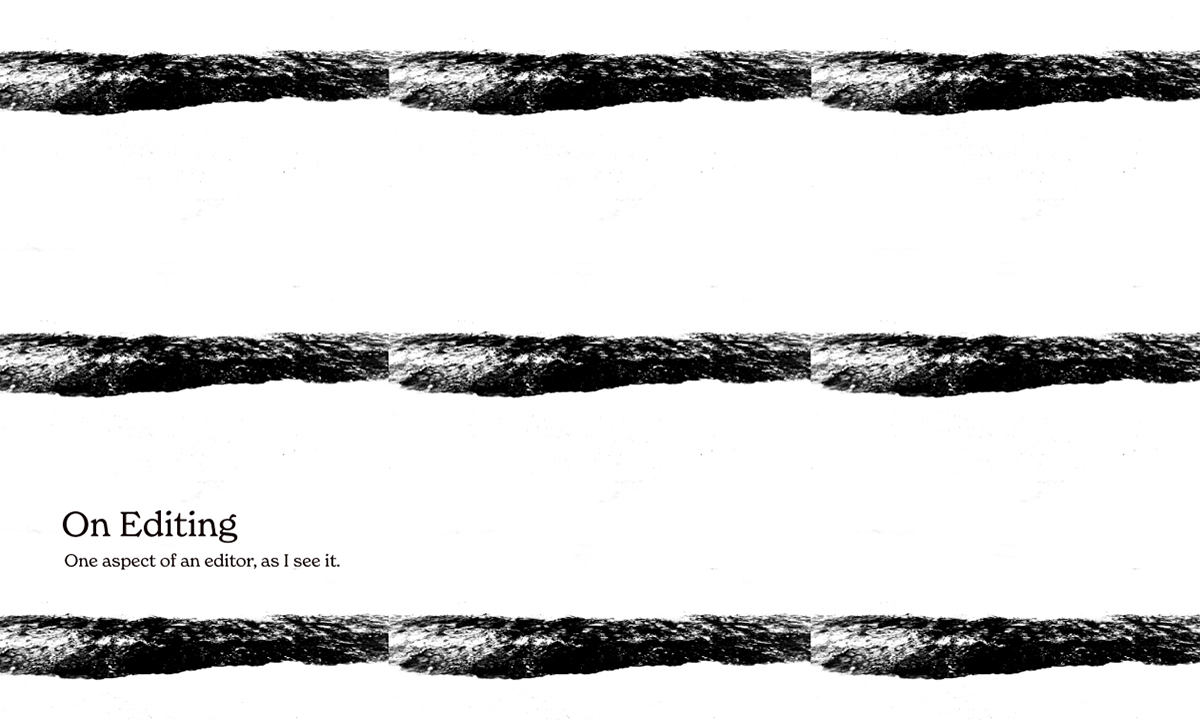最近、決算やらバックオフィスやら何やらで「編集」という言葉からやや遠ざかってしまっていました。
反省です。
情報と情報を繋ぎ新しい情報を創出する「編集」という観点は世界のあらゆる場面に潜んでいるということに対し、やや無自覚な時期が1、2ヶ月続いてしまったように思えます。
大反省です。
ということで、この1、2ヶ月、ぼーっと考えたことなどなどの雑感を綴らせていただきます。
私が久々に編集性に向き合うリハビリの時間としてお付き合いください。
編集って何屋なんだっけ?
「編集をするということは、結局何屋さんなんだろうか?」
最近よく思うことです。
言葉を中心とした仕事かもしれませんし、書籍をまとめることも、映像を構成することも、人と人を結びつけることも、すべては「編集」と呼べるかもしれません。その射程はあまりにも広く、ともすれば「なんでも屋」のように見えてしまうほどです。
人が思考したことをどのようにアウトプットするのか。ここを考えるのが編集者なわけですが、このアウトプットの方向性がなかなか定まらずにいました。
さて、ブライアン・グリーン著、『時間の終わりまで 物質、生命、心と進化する宇宙』に出てくる一文を。
言語の起源は今も謎だが、われわれがここから先に進むためにもっとも重要にして疑問の余地がないのは、言語と思考が合わされば、非常に強力な道具になるということだ。内なる言語に始まって外なる音声化を成し遂げたのかどうかによらず、また、その音声化を促進したのが何だったか──歌だったのか、幼児の世話だったのか、ジェスチャーだったかゴシップだったか、はたまた集団内の交流だったか、大きな脳を持ったことだったのか、あるいはこれらとはまったく違う何かだったのか──によらず、いったん人間の心が言語を手に入れてしまえば、人類という種の実在との関係は、根本的な変化を遂げる。その変化を支えたのが、人間行動の中でもっとも広く行われ、またもっとも影響力の大きなもののひとつ、物語を語ることである。
「物語を語ること」という一言。確かに編集とはある種の物語を作り上げることに似ています。
そのような意味において編集は本来「なんでも屋」的な「すべてに関わる仕事」ではなく「世界をもう一度構造化する仕事」なのだと最近強く思います。
本書からもう一文だけ。
自意識を持つ存在の意志は、物理法則の命じる展開を回避する、従来言われてきたような自由意志ではないが、意志を持つ存在は、高度に組織化された構造のおかげで、内面の感情から外に向けた行動まで、外界の刺激に対して多彩な応答をすることができる。そんな応答は、少なくともこれまでのところは、生命や心を持たない粒子の集まりにはできない。そこに言語が加わると、自意識を持つ種は、そのときどきの必要に対処するだけでなく、過去から未来へとつながる展開の一部として自分を見るようになる。すると、生存競争に勝つことだけが唯一の関心事ではなくなる。もはやわれわれは、ただ生き残るだけでは満足しない。なぜ生きることが大切なのかを知りたいと思う。文脈を探し、関係性を求める。ものごとに価値を与え、行動に対して判断を下し、意味を探し求める。
人は生きる中で、その生命の混沌の中から関係性を見つけ、順序を与え、文脈を編み直す。そこにも編集という行為の本質があるのだと感じます。
デザインもまた似ていますね。
形や色を扱うように見えて、実際には意味を再構成する作業です。編集とデザインは、どちらも世界の断片を扱いながら、その背後にある流れの中から「秩序」や「意味」、「文脈」を探す仕事なのでしょう。
だからこそ、私たちは流れの中のいったい何を編集しようとしているのか。そして、それらをどのように捉え、どのように編集していくのかということを常に考えなくてはならないと思うのです。
この問いを曖昧にしたままでは、編集という営みはどこまでも流動的で、手触りのないものになってしまうなと、改めて自覚しました。
ヒントをくれたブライアン・グリーンに感謝です。
編集者とは何者か
過去の記事でも度々触れていますが、編集者とは情報を並べ替えるだけの仕事ではありません。
むしろ、編集者とは世界や関係性に意味を与える人です。
世間一般で「編集」といえば書籍や映像、あるいは記事などの仕事を想起するでしょう。けれどそれはあくまで「編集という行為の一形態(または一部分)」にすぎません。
本質はもっと根源的なところにあり、散らばった要素の中から「関係性」を見いだし、世界をもう一度編み直す行為だと思っています。
情報をただ整理するのではなく、そこに「新しい構造」を見つけ出す。言葉を選び、順序を定め、余白を生むことで、読者や受け手が「考えるための空間」をつくる。その一連のプロセスを通じて、世界の見え方を少しだけ変える。
それが、編集という仕事の本質だと思います。
だから、編集者は「なんでもできる人」ではなく、「何をすべきかを決める人」でなければならないのです。情報の海にただふわふわと漂うのではなく、目的を持って航路を描ける人間であり、そして、自らの手で「この世界をどう見せたいか」という責任を引き受けられる人間であるべきだと。
それが私が思う編集者の一側面です。
もしこの思想を持たずに編集を行えば、仕事はすぐに「御用聞き」に堕してしまうでしょう。クライアントの要望を形にするだけの請負に終わってしまうかもしれません。
それが悪いことだとは言いません。しかし本来、編集とは他者の言葉を「ただ整える」ことではなく、そこに「新しい問い」を投げ込むことなのです。
つまり編集者とは「現実に対して問いを立て続ける存在」でなければならないと改めて感じたのです。その問いの強度こそが編集の価値を決めるのだと、やはり思います。
編集に必要な「略す」という態度
編集という仕事はその特性上、世界のあらゆる断片を扱うことができてしまいます。文化も、ビジネスも、人間関係も、時に悪意すらも「編集」という言葉のもとに語ることができる仕事です。
だからこそ危険なのです。
編集の範囲を無限に広げてしまうと、やがて自分たちが何をしているのか分からなくなってしまいます。私自身、その感覚に陥りそうになったことが何度もありました。
「自分ってなんの情報をどのような形でアウトプットする人なんだっけ…?」そんなふうに、自分の役割や存在の輪郭がぼやけていくような、ちょっとした「アイデンティティの揺らぎ」のような瞬間が、これまでに何度もありました。
さて、「戦略とは戦いを略すこと」「経営とはしないことを決めること」などの言葉もありますね。
編集も同じだと思っていて、「略す」という観点が必要です。
何を扱うかを決める前に、まず何を扱わないかを決めること。この「略す勇気」が、編集という行為を正しく輪郭づけると感じています。
「略す」と言っても、ただ単に削除するということではありません。
それはむしろ「核心に届くための構造化」という意味に近いと思っています(私は勝手に日本酒の大吟醸のようなイメージでいます)。
伝えたいことを研ぎ澄ませば、余計な枝葉は自然と落ちる。略すことで、残されたものがかえって強く響くようになる。
例えば文章の編集もそうです。
言葉を足して整えるよりも、削って余白をつくる方が、読む人の想像力を引き出せることがあります。
デザインもまたそうですね。情報を盛るより、制約を設けることで、ようやく「意味」が立ち上がったりするものです。
つまり編集とは、「加える」ことよりも「引く」ことにこそ技術があると。略すことは、無関心ではなく、世界との距離の取り方の表明です。
HUNTER×HUNTERのメルエムとコムギの最期のシーンなんてまさにその極地だと思います。読んでない人はごめんなさい。
自分たちがどの領域で語り、どの領域では黙るのか。その線引きの美学が、編集者の思想を決めるのかもしれません。
この視点で見るならば私はできないことだらけです。都市開発を編集することはできませんし、科学や医療技術を扱うこともできません。けれど「人が何を感じ、何を伝えようとするのか」を編集することは、ほんの少しだけできるかもしれません。
この「できるorできない」を明確に意識することが、編集の第一歩だと、最近強く感じています。
略すことは、限界を知ること。
限界を知ることは、焦点を得ること。
そして焦点を得たとき、はじめて「自分たちが何を編集すべきか」が見えてくるのだと思うのです。
関係性のデザインとしての編集性
さて、もしこの編集という仕事を突き詰めていけたならば、最終的に行き着くのは「関係性」というキーワードなのではないのかと思います。
情報と情報をつなぐだけではなく、人と人、組織と社会、過去と未来といった、あらゆる「間」を扱うこと。
それこそが、編集の核心にあるのではないでしょうか。
私たちはしばしば「コンテンツをつくること」を編集だと考えます。
けれど本当に編集者が行っているのは「世界のつながり方を再構成すること」だと思うんです。
何をどう見せ、どんな関係を成立させるのかを設計する。その結果として、記事や映像やデザインといった形が生まれます。
つまり、コンテンツとは「関係性を可視化した副産物」なのです。
優れた編集には、見えない関係性を見抜く力があります。
異なる分野の言葉同士を響かせ、バラバラだった文脈をひとつの構造に編み直し、ときには、まだ存在していない関係を「仮に結ぶ」こともあります。
編集とは、世界をどうつなぎ直すかという試みであり、社会の関係構造をデザインする行為でもあるのです。
たとえばメディアの編集は、情報と読者の関係性を設計しまし、企業ブランディングの編集は、組織と社会の関係性を編み直します。
コミュニティ形成やアートキュレーションも、異なる領域の関係をデザインするという点では本質的には「編集的」だと言えると思っています。
そしてそこにこそ、考えるべき編集性の倫理があります。
どの関係を強調し、どの関係を断ち切るのか。何を見せ、何を隠すのか。その選択の積み重ねが、世界の見え方そのものを変えていきます。
だからこそ、編集者は常に「自分はいま、どんな関係性をつくろうとしているのか」とに自問自答し続けなければなりません。
この問いを忘れたとき、編集は単なる情報操作になり、思想を失ってしまうのでしょう。
編集とは、関係性のデザインであり、関係性とは世界をどう生きるかという態度そのものなのかもしれません。
見る力
編集という行為の出発点は、いつだって「見ること」にあります。見る力のない編集者は、どれほど技術を磨いても、本質的な編集はできないと私は思っています。
「見る」とは、単に目に映るものを確認することではありません。
人の感情、対象の奥にある構造、背景に潜む意図を読み取ることが「見る」ことだと思っています。人によっては「聴く」の方がしっくりくるかもしれませんね。
「なぜそれが存在しているのか」「なぜ人はそれに反応するのか」。その理由を見抜く力こそが、編集を支える基礎能力になります。
そういった意味だと、編集者はいつも世界をスケッチしながら歩いているようなものかもしれませんね。街を歩けば看板の配置を、会話を聞けば言葉のリズムを、資料を読めば構成の呼吸を観察します。
その無数の観察があるからこそ、自分の中の「構造の辞書」が育っていくのだと思うのです。
だから私は散歩が好きなのかもしれません。
その一方、見る力とは「判断を保留する力」でもあると思うんです。
すぐに善悪や好悪で切り分けず問いを立てたり、一度立ち止まって世界をそのまま観察したり、色々な観点から情報を咀嚼したり。
編集者は、断定よりも「保留の中に意味を見つけることができる人」であるべきだと思うのです。なぜなら、保留の中にこそ「変化の兆し」が現れるからです。
さらに言えば、見る力とは「他者の目で見る力」でもあります。
自分の視点だけでなく、読者の視点、依頼者の視点、さらには時代の視点を重ねて世界を観察することに自覚的であるべきでしょう。複数の視点を行き来する中で、編集者はようやく「全体を見通す」ことができるようになります。
だから私は「常に読書をしようね」「色々なプロフェッショナルとお話しして観点を学ぼうね」と社員に伝えたりしています。
もしかすると編集者にとって最大の武器は、目の前の情報を整理することではなく、膨大な知識でも、特定の技術でもなく「どれだけ世界をよく見ようとしているかという態度」なのかもしれないなと感じます。
この武器を扱う力とその重要性に比べれば、文章力や表現力のレベル感などは些細な問題なんじゃないかなーとすら思っています。
自分の世界を信じることができるか
編集という仕事は、なんだか孤独です。
世界の断片を拾い集め、意味のかけらをつなぎ合わせて、誰かに届くかどうかもわからない「ひとつの形」を信じ、つくり続けるような、そんな仕事です。
まるで答えのない旅のようなものです。答えがないので大変です。
そのためなかなかにきつい編集ですが、世界を信じる仕事という意味において、非常に希望に満ち溢れた仕事でもあると感じるのです。
この文脈におけるこの世界を信じることとは、バラバラに見える情報や出来事の中にも、どこかに「つながるはずの構造」があると信じることや、すれ違う人々の思いや感情の中にもいつか交わる瞬間があると信じることです。
その「まだ見ぬつながり」を信じ続けることが、編集者のもっとも根源的なエネルギーなのかもしれないなと思うのです。
編集とは、世界をより良くするための即効性のある魔法ではありません。世界をもう一度見つめ直すための「ただの眼差し」です。もしかすると商業主義的に即座に役に立つものではないかもしれませんね。その眼差しが人の流れに寄り添い、成熟し、現実の中で意味を持つようになるまでにはきっと少し時間がかかるのでしょう。
ただ、秩序を見つけようとすることや声にならない思いを拾い上げようとすることや、違う価値観のあいだに橋をかけようとすることなど、その小さな手作業の積み重ねが、世界の見え方を少しずつ変えていきます。
本記事の冒頭で引用した一文をもう一度。
もはやわれわれは、ただ生き残るだけでは満足しない。なぜ生きることが大切なのかを知りたいと思う。文脈を探し、関係性を求める。ものごとに価値を与え、行動に対して判断を下し、意味を探し求める。
私たちは無秩序の中に意味を見いだそうとし、絶望の中にもまだ関係を編めると信じる姿勢を持たなくてはなりません。
だからこそ、編集は大変でもあると思うのです。
きっと私は死ぬまでこの世界を完全に理解することはできないでしょうね。けれど、それでも自分が関わる本の小さな世界をより良く編集したいという気持ちはあります。
自分がいるそんな世界を信じられるかどうか。そんな気持ちで編集に向き合いたいと思います。
さてさて、今日の私のリハビリは一旦ここまで。
色々書いてみましたが自分は編集者として全然まだまだです。これからもしっかり頑張ります。