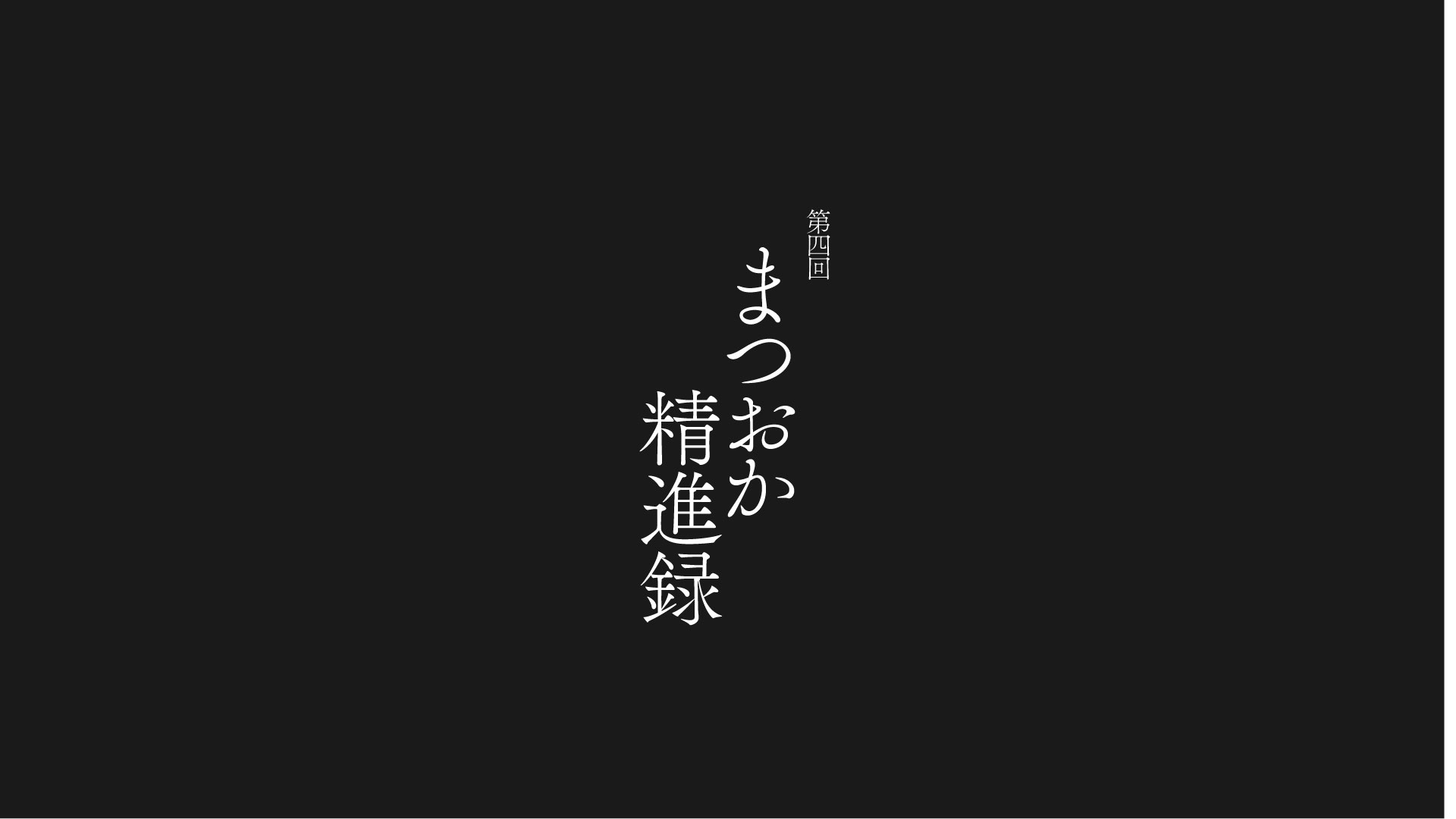「傷口を直視できる兵士は死なない」。
MBAの授業で先生が口にした言葉が強烈に響きました。有名な人物の言葉なのか、その先生自身の言葉なのかは分かりません。
比喩的な表現にすぎませんが、自分自身が「傷口を直視できていない」と自覚していたからこそ、深く突き刺さったのだと思います。
戦場で出血しながら無闇に前進すれば、いずれ命を落とします。逆に、傷が浅いからといってその場に座り込み、ただ留まっていても状況は悪化していきます。大切なのは、自分の傷を直視し、応急処置を施し、それでもなお歩みを止めないことなのかもしれません。
この比喩は、事業の営みにそのまま重なります。経営もまた、常に見えない戦場を進んでいるようなものだからです。
傷を直視しないことの危うさ
事業を進めていると、どうしても思い通りにいかない局面に直面します。
例えば収益の低迷、キャッシュフローの悪化、事業計画の未達…。このような「傷」と常に向き合わなくてはいけません(ものすごく業績のいい会社は別として)。
私自身も、こうした数字から目を逸らしてしまったことがあります。「今はまだ大丈夫だろう」とごまかし、小さな亀裂を見て見ぬふりをしてしまっていました。
それは血を流しながら戦場を走り続ける兵士と同じことだと、今では思います。
特に事業において最も直視しづらいのは、数字の現実です。
キャッシュフローや収支、停滞するKPI。これらは単なる記号ではなく、経営者や責任者にとって「自らの意思決定が可視化された成績表」です。
だからこそ、目を向けることは精神的に重く、時には強い痛みを伴います。しかし目を背け続ければ、やがて取り返しのつかない出血となってしまいます。
数字を確認していなかった時のこと
特に会社の3期目を振り返ると、私は「傷口を直視する」という基本を怠っていたと痛感します。
日々の業務に追われる中で、キャッシュフローや収支の確認を後回しにしてしまう。決して軽んじていたわけではありません。しかし最優先にすべきことの優先度を少し下げてしまっていたように思います。
KPIが未達だったとしても「次の四半期で巻き返せるだろう」のような楽観的な意思決定をしていた記憶があります。情けない限りです。
結局のところ、私は数字を正確に見ることから逃げていたにすぎません。
現状の解像度がぼやければ、当然アクションもぼやけます。「やっているつもり」だけの施策が増え、努力と成果が結びつかなくなってしまいます。結果、改善すべき課題からどんどん遠ざかっていきました。
そして何より恐ろしかったのは、数字から目を逸らしているときほど「事業が順調に回っている」という錯覚に陥ってしまっていたことでした。
実際には水面下で出血が続いているのに、自分だけが楽観的なストーリーに浸っているような感覚。これは、経営者にとって最も危うい状態だったと今では思います。
3期目に経験したこの失敗は、自分にとってそれこそ痛みを伴う記憶ですが、その後「現実を直視する」という姿勢を身につける大きなきっかけになりました。
傷口を直視するために
ただ闇雲に傷口を直視しても、有意義な改善にはつながりません。
重要なのは、直視を習慣化し、そこから次の一手へとつなげる仕組みを持つことです。
まず行ったのは定点観測の仕組みをつくることでした。
人は痛みを避けたい生き物です。
だからこそ、数字を見るタイミングを「気分」や「都合」に任せていると、どうしても先延ばししてしまうのかもしれません。もしかすると私だけかもしれませんが。
私はそれを防ぐために「毎週土曜の午前9時は必ず事業収支を確認し、アクションプランを考える」と決め、ルールとして日常に組み込むことにしました。
「いつまでにどの数字を満たさなければどうなるか」を改めて明文化しようと思います。特定の事業の撤退ラインや資金ショートのシナリオを具体的に描いておくことで、現実の数字を目にしても「ここまでは耐えられるが、その後はどうする?」「ここまでに新しい動きをしなくてはならないが、そのために今すべきことは?」という「問い」を得られます。
直視する勇気とは、突発的に湧くものではありません。むしろ、ルールと仕組みで支えることで初めて持続するものだと実感しています。
結びに:見ることを恐れずに
「傷口を直視できるかどうか」。
それは経営者や事業責任者にとって、単なる比喩ではなく、生死を分ける問いそのものだと思います。
現実から目を逸らすことは、一時的には心を守ってくれるかもしれません。しかし、その代償は大きいのです。血を流しながら走り続ける兵士のように、気づいたときには取り返しのつかない地点に立たされてしまいます。
一方で、直視することは痛み、苦しみを伴います。数字は残酷に「現状」を突きつけ、過去の判断を否定するかもしれません。しかし、その痛みこそが回復への第一歩であり、未来への新しい選択肢を切り拓く契機になります。
私が学んだのは、直視する勇気とは特別な才能ではなく、仕組みと習慣によって支えられる技術だということでした。
事業は戦場のように過酷ですが、だからこそ「見る」ことを恐れない者だけが次の一手を打てるのだと思います。