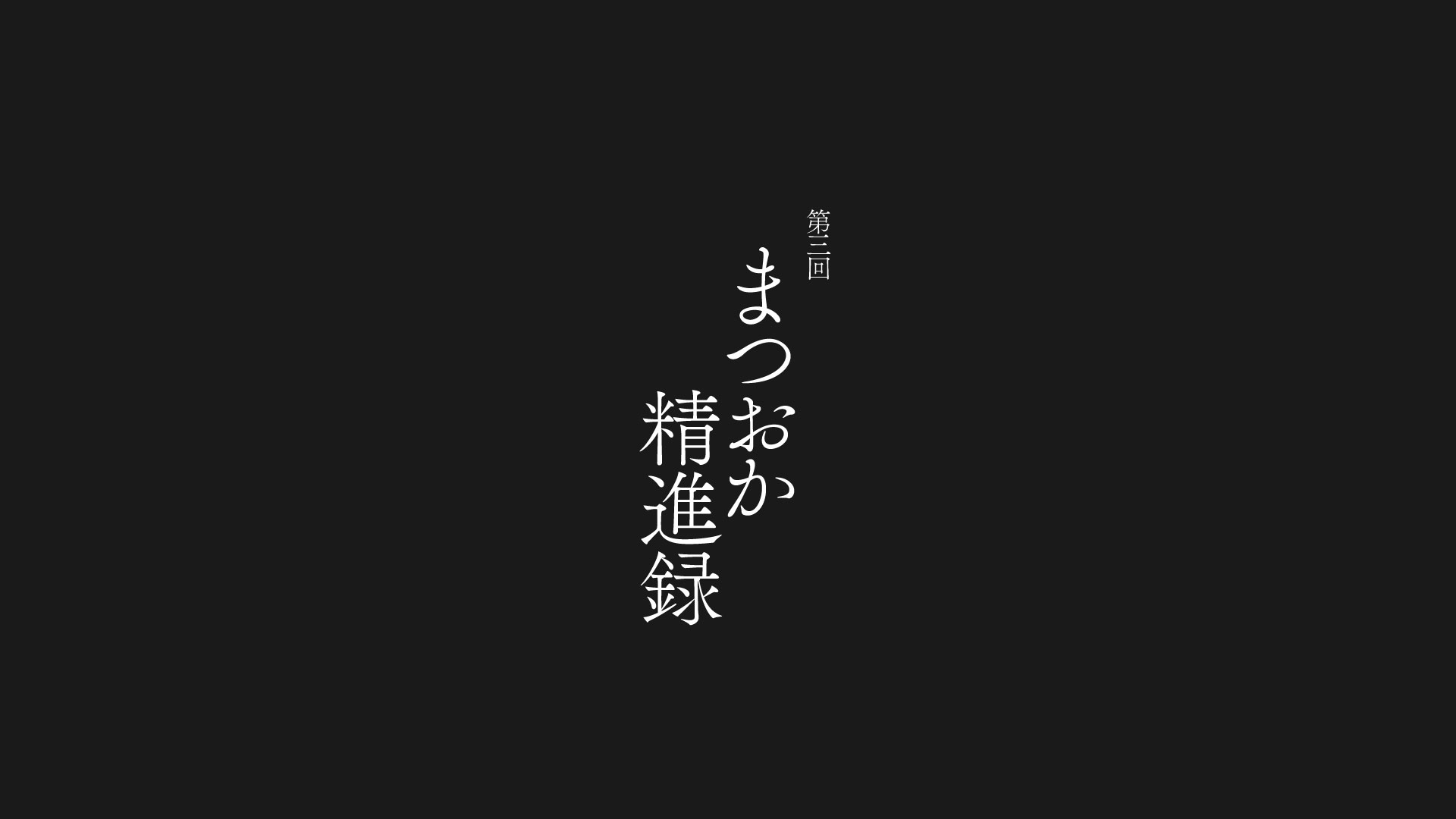どれだけ多くの情報を集めても、正しい問いを立てられなければ、答えにはたどり着けません。
当たり前のことですが、これがまた難しいのです。
そして問いを立てることは考えることよりもずっと難しかったりします。
ここ数年、その事実を嫌というほど痛感しています。
会議では「話したいこと」から始まり、調査では「調べやすいこと」に時間を割き、資料づくりでは「並べやすい情報」だけを必死に集める。
しかし本当に考えるべき問いがどこにあるのかを見極めない限り、努力はただ空回りするだけです。
「何を問うか」で、思考の質も、成果も、少し大袈裟かもしれませんが人生すら変わってしまう。
このシンプルで残酷な原則を受け入れてから、私の意思決定は少しずつ変わり始めました。
今回は「イシュー」と、それを構成する「枠組み」というものについて考えてみます。
イシューがすべてを決めてしまう
気づけば、考えること自体が目的になってしまっていた時期がありました。
資料をつくること、調べること、議論すること。どれも精一杯やっているつもりなのに、なぜか手応えが薄いような、そんなこともたくさんありました。
今改めて振り返ってみると、その理由はとても単純でした。
「そもそも、何を考えるべきか」という問いを正しく立てられていなかったのです。
つまり、イシューを正しく設定できていなかったんですね。
最近つくづく思うのは、ビジネスにおける思考の質は「どの問いを立てるかで決まる」ということです。
どれだけ論理的に考えるかよりも、そもそも「どの問いを考えるか」を見極めることのほうがはるかに大事なようです。
イシューを正しく設定できるかどうかが、成果を左右する最大の要因なのだと思います。
たとえば、過去に社内で「サービスの認知をどう拡大するか」という議題がありました。私はSNS広告やSEO施策など、具体策ばかりを必死に調べていましたが、後になって振り返ると、本当に問うべきはそこではなかったのです。
「このサービスはそもそも認知拡大に投資する価値があるのか」「市場で勝ち筋はどこにあるのか」などなど、本来はこうした問いを立てるべきでした。
問いを間違えれば、どんなに綿密に分析しても結論はずれてしまいます。逆に、問いさえ正しければ、必要な情報はおのずと絞られ、意思決定は驚くほどシンプルになると思っています。
では、イシューを設定するとき、何を意識すればよいのでしょうか。私なりに整理すると、視点は大きく三つありました。
- 上位目的との接続:その問いに答えた先に、何が決まるのか。意思決定のゴールと直結しているか。
- 影響範囲の大きさ:答えが変わることで、プロジェクト全体の方向性にどれだけ影響を与えるか。
- 代替問いとの比較:他に優先すべき問いはないか。より上位の視点から見たとき、別の問いを立てるべきではないか。
この三つを意識して問いを磨き込むことで、情報の渦に飲み込まれることなく、本当に考えるべき場所に立てるようになるはずです。
どうして問いは設定しにくいのだろう?
これまでの社会人人生を振り返ると、「考えるべき問い」を正しく設定できていなかった場面が、驚くほど多かったと感じます。
会議では「話したいこと」から入り、調査では「調べやすいこと」に時間を割き、資料づくりでは「とりあえず情報を並べる」ことに必死になっていた時期がありました。
結果として、そもそも何を明らかにすべきなのか。イシューの核を見失ったまま進めてしまうことが少なくなかったのです。
何年も昔の話ですが新規プロジェクトの戦略資料を作った時、私は「市場の最新トレンド」や「競合分析の深掘り」ばかりに集中していました。しかし本当に会社が求めていたのは「このプロジェクトはやるべきなのか、それとも撤退すべきなのか」という意思決定だけでした。
「情報はいろいろ揃っているのに、意思決定には使えないんだなあ…」。そんな虚しさが、資料を閉じた後に残りました。
「考えたいこと」と「考えるべきこと」は似ているようで、まったく違うということを痛感しました。
考えるべきことを考えていない。だから問いが設定できない。
すごくシンプルです。
そして私ができていなかったのは、まさにこの部分でした。
イシューを考えるうえで重要なのは、「解決したいこと」ではなく、「解決すべきこと」を見つけられるかどうか。それができなければ、努力の方向を誤り、どれだけ走っても成果にはたどり着けないようです。
「解決したいことではなく」「解決すべきこと」を考える
前述の例と重複するようですが、私たちは考えるとき、しばしば「解決したいこと」から入ってしまうようです。
けれど、本当に成果を生むのは「解決すべきこと」を見極めることです。
この違いを見失うと、努力の方向は簡単にずれてしまいます。
たとえば、新規事業の会議で「売上を伸ばすにはどうすべきか?」という議題が掲げられたとします。ここで多くの人は、SNS広告、キャンペーン、営業体制の強化など施策のアイデアに飛びついてしまいます。
私もそうでした(今もそうかもしれません)。
しかし立ち止まってデータを見れば、そもそも市場自体の成長率が鈍化しているかもしれないし、既存顧客のLTVが低く、売上よりもリテンション施策が本質的な課題かもしれません。
つまり、「どう売るか」ではなく、「そもそも何を売るべきかが本当のイシューだったよね」というケースは少なくありません。
ここで鍵になるのが、「ファクトを起点に問いを立てる」という姿勢だと感じています。先に仮説を立てることは重要ですが、それを事実で裏付けなければ、結論は主観の延長にすぎないためです。
具体的には、次の3つを意識するようにしました。
- 事実を最初にそろえる:数字・データ・事例など、検証可能なファクトを出発点にする。
- 仮説を構造で捉える:「売上低迷=広告不足」という短絡ではなく、「市場・顧客・競合・提供価値」の四つの軸で全体像を構造化する。
- 「ファクト → 仮説 → 検証 → 結論」のように論理を積み上げる順序を守る:順番を逆にすると、思い込みを補強するだけの“調査”になってしまうため。
ファクトを見ずに「解決したいこと」だけを追うと気持ちは楽です。考えた感も出ますし、やるべきことが明快に見えた気になるからです。
けれど、そのまま進めば正しくない問いに答えるために、もしくは間違った道から正しい道へ戻るために膨大な時間とリソースを浪費します。
だからこそ、問いを立てるときは一度立ち止まる必要があると思うのです。
「それは本当に、解決すべきことなのか?」と、この自問を習慣にするだけで、意思決定の精度は劇的に上がると感じています。
問いを握り続けることの難しさ
しつこいようですがイシューを定めることは大切です。
しかしもっと難しいのは「その問いを最後まで握り続けること」だと思っています。人はすぐイシューを忘れてしまうのです。私だけだったらすいません。
あくまで私の例ですが、会議や調査、資料作成の過程で、別の興味深い情報や新しい論点に出会うたび、そちらに引き寄せられてしまうことが多かったのです。気がつけば、本来のイシューとは別の場所に立っているような、そんな経験を何度も繰り返してきました。
イシューを理解したとしても手放してしまっては意味がありません。「イシューを一貫して抑える仕組み」がなかったことが要因でした。
たとえば、ホワイトボードの冒頭、ToDoリストの見えやすい場所に「今解決すべきイシュー」を書いておく、あるいは議論の途中で「この話はイシューに答えているか?」と自問するなど、ほんのそれだけで、議論の迷走は防げたりします。
問いを立てることは、まだ比較的簡単かもしれません。し歌詞その問いを握り続けることは想像以上に難しいようです。
そして、ここができていなかったことこそ、私の意思決定の精度を何度も下げてきた要因でした。
なぜ?繰り返し論点の枠組みを作る
イシューを握りしめることができても、もう一つ欠かせないものがあります。
それは「枠組み」です。つまり、問いに答えるための地図のようなものですね。
私はこれまで、「まず考え始める」「とにかく調べてみる」という姿勢で仕事に臨むことが多くありました。けれど、枠組みを持たずに情報を集めると、思考はあやふやになり、使いものにならない結論を出してしまうような経験を何度もしてきました。
そこで意識するようになったのが、イシューに対して最低二つの論点を疑問形で立てることです。
たとえば、「売上が上がらない」というイシューがあるとしましょう。
このとき、まずは大きな論点を設定します。
- 「営業不足なのではないか?」
- 「顧客単価が低いのではないか?」
このように、イシューを構成する要素を「問い」の形で分解していきます。これが枠組みの第一歩です。
さらにここから「営業不足なのではないか?」という論点の方を掘り下げてみます。
- 「そもそも人手が足りていないのではないか?」
- 「接触数が十分ではないのではないか?」
こうして論点を段階的に、繰り返し分解していくと、問題の核心が少しずつ見えてきます。
「なるほど、ここに原因があったのか!」と、点と点がつながる感覚になるはずです。
やはり重要なのは、常にイシューを見失わないこと。掘り下げる過程で興味深い情報はいくらでも出てきますが、最後に出した結論が、最初に立てたイシューをきちんと解決するものでなければ意味がありません。
だからこそ、課題と出会ったときは必ず「論点の枠組み」を用意し、疑問形で掘り下げていくことが大事なのです。この習慣があるだけで、思考はぶれず、結論は自然とイシューに収束していくと思っています。
まだまだ私にはこの思考法は使いこなせていませんが。
結びに:正しい「問い」と生きるために
イシューを立てること。それを最後まで握りしめること。そして、答えへとたどり着くための枠組みを描くこと。
どれも一朝一夕には身につきませんし、私自身、何度も迷い、立てた問いを手放し、情報に溺れてはやり直してきました。偉そうに書いてきましたがまだまだイシューを捉えることに難しさを感じます。
それでも、問いを見失ったまま努力を重ねるよりは、何倍もましだと思うのです。
結局のところ、思考の質を決めるのは「どの問いを選ぶか」なのでしょう。問いが定まれば、情報は自然に整理され、議論は澄み、意思決定は迷いなく進んでいく。逆に問いを誤れば、どれほどの時間と労力をかけても、結論は現実からずれてしまう。
だから私はこれからも繰り返し「それは本当に、解決すべきことなのか?」と自分に問うつもりです。
このような問いと向き合うたび、私たち自身の仕事や思考もまた、少しずつ確かなものに変わっていくのだと思います。