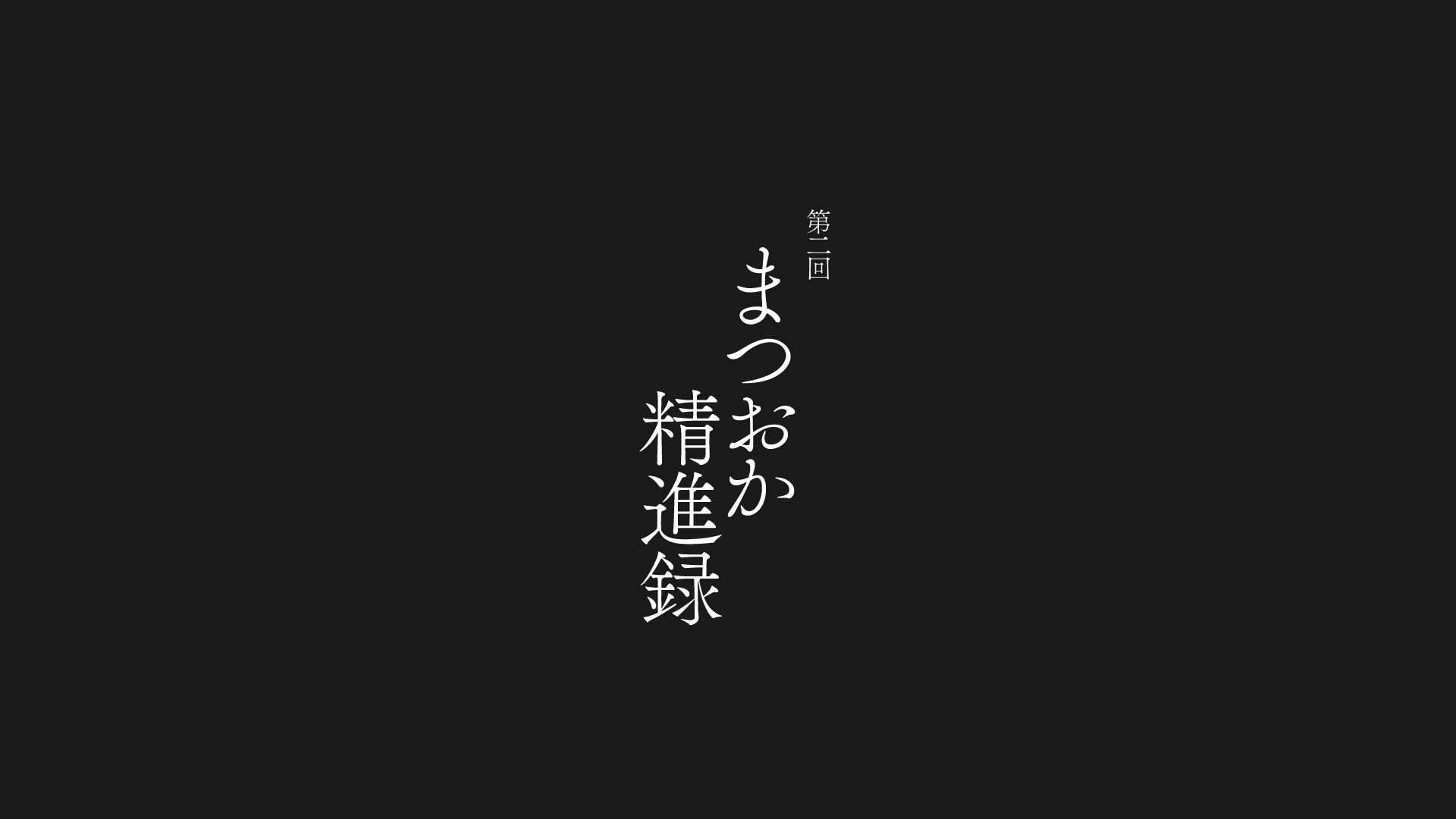ご相談をいただく際、できることなら、相談してくださった方にとって少しでも良い時間になるような返答をしたいと思っています。
こちらからお返しする言葉や提案に、何らかの「価値」がなければ、せっかく時間を割いて話してくれた相手をがっかりさせてしまうかもしれない。そう考えるからです。
しかし「自分の出す主張にはっきりと価値があると言い切れるか?」と自問したとき、私は言葉が詰まってしまうことがあります。
どうすれば、お客様に対してより良い時間を提供できるのか。どうすれば、メンバーに対してより良いフィードバックができるのか。
そうした問いを立てていくなかで、私自身の足りなさや思考の弱さが、次々と浮かび上がってきました。悲しいものです。
今回もまた、自分自身への振り返りの時間にお付き合いください。
そもそも、なんでそんなことになってしまうのか
もし自分の主張に価値を感じられないとき、そこには何かしらの原因があるはずです。
が、それは単純に「勉強不足」や「準備不足」といった言葉で済む話ではないような気もしています。
そもそも、なぜそんな状態になってしまうのだろう。なぜ自分の言葉が、どこか弱く、浅く、拡がりに欠けてしまうのだろう。
思い返してみると、それは「相手に言うべきこと」がないわけではなく「自分の中で言える理由」が足りていないときに起きていることが多いと感じました。
言葉が不安定になるときは、支える思考が浅い時でしたし、提案が心もとないときは問いが足りない時だした。そして話が伝わらないときは、前提がすれ違っている時だったように思えます。
そう考えてみると、主張の価値とは、単なる情報や知識ではなく、それをどう構造化してどう相手に合わせて組み立てるかという、思考の総合力そのものなのだと思えてきます。
私の主張が弱いことがあるとすれば、たぶん、考え方そのものが足りていないからです。
結論が出てしまったような気がしますが、もっと考えてみます。
意識したいこと:主張を支える「根拠の束」をつくる
自分の主張に価値を持たせるために意識したいのが「根拠の密度」でした。
主張は根拠によってしっかり支えられていなければなりません。
細くて頼りない1本の根拠では、すぐに主張はグラグラしてしまいます。もちろん、一本でも揺るがないほど太く強い論拠があればそれに越したことはありません。しかし、私にはまだそんな強靭な一本の柱を立てられるだけの力はありません。
だからこそ、複数の根拠を束ねて支えることを意識したいと思っています。
事実にもとづいた定量的なデータ、観察や経験にもとづいた定性的な視点、外部の事例や比較対象、相手の前提や文脈に寄り添った理解など、こうした複数の支柱を交差させながら、揺れの少ない構造をつくることを意識しようと思います。それによって、主張はようやく「安心して乗せられる土台」になっていくと思うのです。
価値のある主張は、たいてい根拠がビシッとしています。
感覚ではなく構造で語る。印象ではなく支点で語る。これから先の提案にもフィードバックにも常にそんな意識を持って臨みたいと思います。
意識したいこと:全体を分けて、ズレをなくす
主張に価値を持たせられていないと感じるとき、その原因は根拠の不足だけではありません。
むしろもっと手前に「そもそも何について話しているのか?」という前提のズレがあることも多い気がします。
こちらは「この話だ」と思って主張しているのに、相手は「その話じゃない」と感じているような場面がそれです。最近はそんな場面はそう多くないと思ってはいるのですが、駆け出しの頃はしょっちゅうやってしまっていた気がします。
こうしたすれ違いがあると、いくら論理を積み上げても噛み合いません。どれだけ良いことを言っていたとしても、それは独り言になってしまいます。
だからまず「事象を分解する」という工程を意識したいと思っています。
たとえば「ウェブサイトの集客力が下がっていて困っている」というご相談を受けたとします。この一文だけを読んでも、そこには無数の切り口が含まれています。
- 特定チャネルからの流入が減っているのか
- 特定コンテンツのパフォーマンスが落ちているのか
- 競合の動きに押されているのか
- そもそも市場のニーズが変化しているのか
- それらが複合的に絡み合っているのか
など、挙げ始めたらキリがありません。もし「ではSEOを強化しましょう!」というような反応をしてしまうと、それは価値のある主張にはなりません。
「ハンマーしか持っていない人には、すべての問題が釘に見える」状態ですね。
そうならないように、私はなるべく「手癖」から離れたいと思っています。
すぐに答えを出そうとせず、まずは問いを立て、対象を観察し、構成する要素を見極める。そうして初めて、主張に厚みが出るのではないかと思うのです。
意識したいこと:問いの数を適切に増やす
私は時々、自分のアウトプットがどこか一面的になっているのではないかと感じることがあります。
一つの事象に対して、すぐにひとつの主張だけを出してしまうことも、正直あります。
その主張が正しいかどうか以前に「君、本当にそれしか考えられなかったんですかね?」と、自分自身に対して疑問を感じることがあるのです。
ある事象について考えるとき、本来なら無数の切り口や仮説があるはずです。
しかし私は「他の可能性」まで思考を伸ばせていないことがあります。伸ばし過ぎも考えものですが、まずここはしっかり向き合わなくてはいけません。
私自身、自分の考えが浅いと感じる時、必要なのはたいてい「答え」ではなく「問い」だったりします。
だからこそ意識的に問いを増やしたいと思っています(ただやたらと増やすことはしませんが)。
「なぜその数字が落ちたのか?」「それは他の要因と関係していないか?」「過去にも似たようなケースはなかったか?」「その変化は一時的なものか、そもそもの構造的なものか?」など、このような問いをたくさん立てることで、ひとつの事象を多面的に見ることができるようになると考えています。
意識したいこと:仮説の組み合わせ
「仮説を一つ立てて、それで終わってしまっていないだろうか?」という観点、これは最近の自分にとって大きな課題になっています。
「これが原因かもしれないぞ」と思いつくことはあっても、その先が続かない場合があります。
Aルートが行き止まりになってしまっているような、そんな感覚です。そこからより良い仮説に進化させるためにはBルート、Cルートにある仮説が必要だったりすることもありますが、Aルートで進んだ場所にあった仮説のみで戦おうとしてしまう、そんな状態です。
これは実に良くありません。
複数の仮説を並べて、さらにその間に関係性を見出すというような、複層的な思考が足りていないのではないかと感じることが多いのです。
Aの仮説、Bの仮説、Cの仮説など、それぞれをバラバラに考えて終わるのではなく、これらがどう関係し合い、組み合わさると何が見えてくるのかまでしっかり考える。
仮説同士を掛け合わせることで、見えてくる全体像や新たな仮説があります。これは編集と同じかもしれません。
たとえば、ユーザーの離脱率が高いという事象について考えるとき、
- Aルート:導線設計の問題かもしれない
- Bルート:コンテンツの内容が期待に届いていないのかもしれない
- Cルート:そもそも流入チャネルのユーザー属性と合っていないのかもしれない
といった仮説を立てることはできても、そこで止まってはいけません。
じゃあ何が考えられるか。
- A×B:導線が悪く、さらに内容も薄い→訪問しても迷ってしまい、そもそも読む前に離脱
- A×C:導線が悪く、来ているユーザーも適合していない→入口から出口までミスマッチ
- B×C:内容が期待に沿わず、そもそも来訪者がターゲット外→内容刷新、集客経路見直しが必要
- A×B×C:導線・内容・集客すべてに課題→全面的な設計の再構築
すごく雑な仮説で恐縮ですが、ここからさらにたくさん考えられそうです。
仮説単体で勝負するのではなく仮説同士がどう繋がっているのか、仮説の構造を組み立てていくことで、初めて「解像度の高い、価値のある主張」になるのだと思います。
そして、そのためには当然、素材としての情報も必要です。
仮説の組み合わせを成立させるには、まず多様な仮説を用意しなくてはならず、そのためには多くの事例や観察、情報に触れておくことが欠かせません。
結局のところ、主張の重みは素材を集め、組み合わせ、構造をつくるという「構築力」から生まれるのだと思うのです。
意識したいこと:耳馴染みのいい言葉を使わず、具体化する
「最適化」「最大化」「効率的に」「ユーザー目線で」など、それっぽく聞こえる言葉たちはたくさんあります。しかしこれらの言葉にちゃんと意味を込められているだろうか…?という不安が昔からずっとあります。
耳馴染みがよく、誰もが一度は使ったことのある言葉ですが、それがどんな意味を持つのかを文脈に即して説明できなければ、思考は表面をなぞるだけになってしまいます。
それを簡単に言えば「意味のない言葉」になってしまいます。
私自身レポートで何度「最適化」を使用したことか…。
この「最適化しましょう」という言葉ですが、本来は「一体何をどうしたら最適なの?」「誰にとって、どの時間軸で、どの目的において最適なの?」などを考えた上で使用するべきでしょう。「最適化」を言葉として掘り下げられなければ「最適化」はできません。
言葉にできないということは、思考が浅いということ。思考が浅いということは、相手に伝わらないということ。伝わらないということは、主張の価値が届かないということです。
耳触りのいい言葉を選ぶ前に、まず自分の中で「具体にまで分解できているか?」を問う癖をつけたいと思います。
抽象的な言葉を使ってしまうこと自体が悪いわけではありません。しかしその言葉を正しく使うのであれば、どこまでも説明できる準備があるかどうかどうか、その言葉の中に自分なりの実感や経験や観察が詰まっているかどうかなどの「手触り」が求められるはずです。
言葉をぼんやりさせてままにせず、構成要素がしっかり見えるまで具体化する。
それを怠った瞬間、私の主張は「思考したようで、していない言葉」になってしまい、価値のある主張からまた遠ざかってしまいます。
言葉は、ただ表面的に何かを伝えるための道具ではなく、思考の帰結であるべきだと思うのです。
結びに:価値のある主張のため、常に考え続ける
うまく提案ができなかったり、本当に言いたかったことが言えなかったり、準備が足りなかったり。そういう日は、きっとこれからも何度も訪れると思うんです。
しかし、価値のある主張を届けたいと思うのなら考え続けるしかないのだと思います。それも受け手目線で。
もし、自分の言葉に手応えがなかったときは、それをそのままにせず、自分の思考のどこが至らなかったのかを分解し、仮説を立て、構造を見直してみる。そこから、次に活かすための教訓をすくい上げなくてはなりません。
まずは、自分自身にとって価値のある主張や仮説をつくる練習から始めてみるのもいいかもしれませんね。
他人に届ける前に、自分の中に届いているかどうかを確認するのも練習になりそうです。その繰り返しの中で、思考は少しずつ鍛えられていくかもしれません。
もしかしたらいつか、アドリブでも価値のある主張を連発できるようになるかもしれません。たまにいますよね。そういうすごい人。
私はまだまだそのレベルには至れていません。まずは丁寧に、ちゃんと考えるところから始めようと思います。