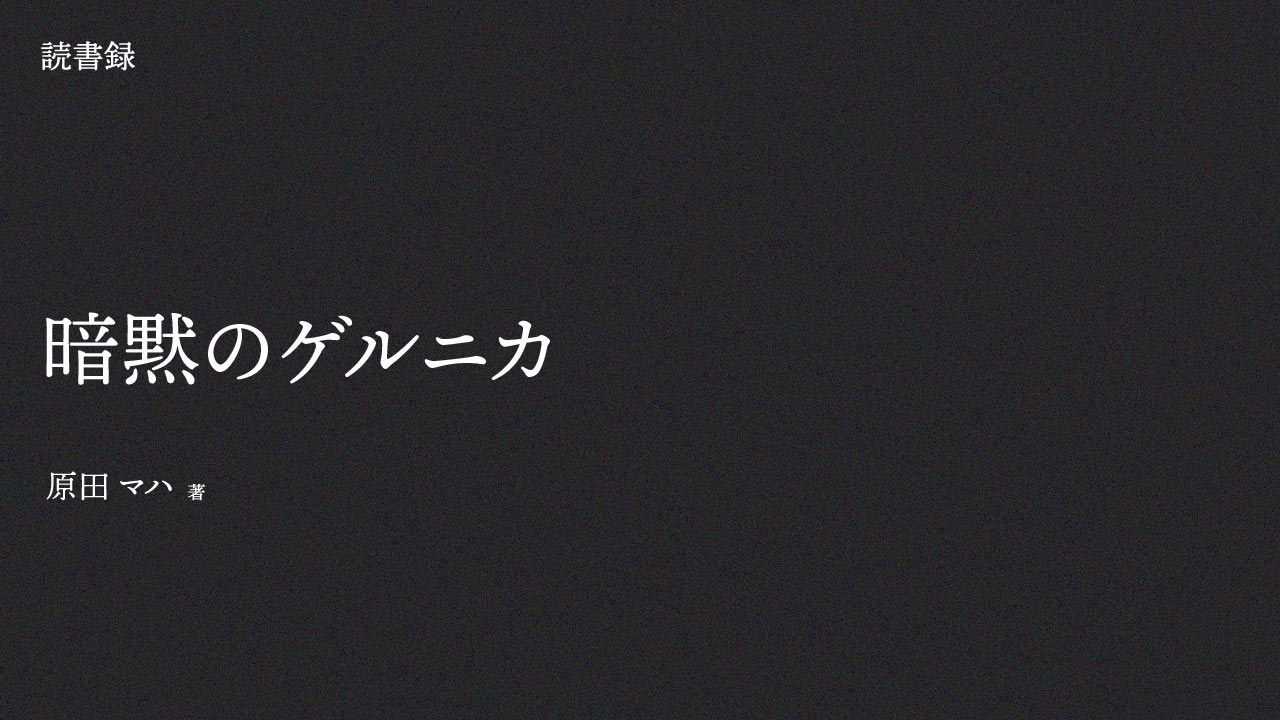美術と歴史が織りなす物語の魅力を独自の視点で描き続ける原田マハ氏。
2016年に発表された「暗幕のゲルニカ」は、パブロ・ピカソの代表作「ゲルニカ」と、ニューヨーク近代美術館(MoMA)を舞台に、芸術作品が持つ力と人間の葛藤を鮮やかに描き出した作品です。
本作のテーマでもるピカソが描いた「ゲルニカ」について触れつつ、書籍に関するあらすじをお伝えします。
アートの歴史を創り上げた偉大なアーティスト、パブロ・ピカソ
本作のテーマでもあるゲルニカを描いたパブロ・ピカソ。
彼は1881年10月25日、スペイン南部の地中海に面した港町マラガに誕生しました。わずか10歳で美術学校に入学したのち、14歳で画家デビューを果たし生涯を通じてアートに捧げた画家です。
91歳でこの世を去るまでに、ピカソがこの世に生み出した生涯作品は14万7800点に及びます。現代でも多くの方を魅了する画家の一人で、世界で最も作品数が多いことでも知られています。
キュビスムの創始者として知られるだけでなく、絵画、彫刻、陶芸、版画など多岐にわたるメディアで革新的な表現を追求し続けた彼は、まさにアートの歴史そのものを塗り替えた存在と言えるでしょう。
本作の中心となるゲルニカは、ピカソが56歳で描いた作品で高さ3.5m、幅7.8mいう圧倒的なスケールを持つ巨大な絵画でした。この作品が誕生した背景には、1937年のスペイン内戦における悲劇的な事件がありました。
スペイン・バスク地方の小さな町ゲルニカが4月26日、爆撃機によって民間人を対象とした史上初の本格的な空爆を受けたのです。当作品は史上初の無差別爆撃を描いた作品であり、爆撃を受けた「ゲルニカ」という地名からタイトルが決定。
当初、ピカソはパリ万国博覧会のスペイン館に展示する壁画として、芸術の自由をテーマにした作品を依頼されていました。しかし、なかなか構想が定まらず筆が進まない中、祖国の悲劇的なニュースを知ります。
市民の日常を無差別に破壊する残虐なニュースを知り、ピカソは深い衝撃を受け即座にテーマを変更しました。
それまで停滞していた創作が一転、爆発的なエネルギーとなって解き放たれます。通常、重要な作品を制作する際には多くの習作(練習のための作品)を経て完成に至りますが、ピカソはわずか2週間で45枚もの習作を描き上げ、最終的な「ゲルニカ」を驚異的なスピードでたった1ヶ月で完成させました。
この異例の集中と速度からも、ゲルニカの惨劇がピカソの心に与えた衝撃の大きさを伺うことができます。
ゲルニカ爆撃が起こった歴史的背景
ゲルニカ爆撃の発端はスペインの内戦でした。
民主的なスペイン共和国政府と、軍人フランコが率いる専制国家を目指す反乱軍との戦いです。両者がスペイン内部で争っており、内部の戦いではあったものの他の国も参戦していました。
スペイン政府には旧ソ連が。反乱軍にはナチスドイツやイタリアなどが支援につきます。
ピカソは、民主的なスペイン共和国政府を強く支持していました。ゲルニカ爆撃以前にも、彼は「フランコの夢と嘘」という作品を制作しており、ピカソにとって初めて政治的メッセージを込めた作品でもあったのです。
長らく政治と芸術を分離してきたピカソにとって、この転換は、祖国の危機という状況に対する強い使命感の表れだったのではないでしょうか。
ゲルニカ爆撃の一報を受けた時のピカソの心境は、想像を絶するものだったに違いありません。美しい故郷の街が、無辜の市民もろとも無差別爆撃によって破壊されるという現実。
その怒りと悲しみのエネルギーが、「ゲルニカ」制作における驚異的な集中力と創造性へと昇華されたのでしょう。わずか1ヶ月という短期間で完成させたこの大作には、ピカソの魂の叫びが込められているように感じます。
「ゲルニカ」に描かれた馬や牛といったモチーフについては、様々な解釈が存在します。馬がフランコ将軍を、牛が民衆を表しているという説や、ピカソ自身が作品の中に描き込まれているという見方もあります。
こうした多様な解釈の可能性こそが、この作品の奥深さを示しています。
ピカソの友人で闘牛マニアでもあった民俗学者ミシェル・レリスは、「牡牛がフランコや暴虐を意味するなどありえない。牡牛もまた必ず虐殺されるのだ」と述べ、この作品には政治的対立を超えた普遍的な「哀れみ、苦しみの世界」が描かれていると解釈しています。
しかしピカソ自身は「牡牛は牡牛、馬は馬だ」と述べ、特定の象徴的意味を意図的に込めていないことを強調しています。彼にとっては、戦争の悲惨さをありのままに描いただけであり、そこに特別な意味を持たせようとはしていなかったのです。
描かれているモチーフには、その国の文化や歴史、環境で少なからずあると思うので本人は意図せずとも無意識に描いたものなのかもしれません。
そして観る側の解釈で意味が追加されていったのでしょう。
名画として再評価された「ゲルニカ」は時代を超える反戦のシンボルへ
ピカソの「ゲルニカ」は、現代では芸術史上の偉大な傑作として広く知られていますが、発表当初はむしろ批判的な評価が目立ちました。
1937年のパリ万博でお披露目された際、多くの批評家や観客からは「ゲルニカ爆撃をリアルに描けていない」「抽象的すぎる」などの声が上がり、必ずしも好意的に受け入れられなかったのです。
この評価が大きく転換したのは、第二次世界大戦後のことでした。世界が未曾有の戦争の惨禍を経験した後、「ゲルニカ」に描かれた恐怖や苦しみ、悲しみといった感情表現が、特定の事件を超えた普遍的な戦争の悲劇として再評価されるようになりました。
ピカソが具体的な歴史的事実よりも、戦争がもたらす人間の感情や精神的苦痛を抽象的に表現したからこそ、時代や国境を超えた反戦のモニュメントとしての力を獲得したのです。
「ゲルニカ」の強さは、特定の事件に縛られることなく、あらゆる戦争の悲劇を象徴する作品へと昇華した点にあります。具体的な政治的シンボルや明確な敵を描かなかったことにより、見る者それぞれの解釈を許容しながらも、戦争の残酷さと平和の尊さを訴える普遍的なメッセージを発し続けています。
その影響力は現代にも強く残っており、2003年のイラク戦争の際には反戦運動のシンボルとして使用されるなど作品が持つ影響力はいまでも衰えていません。
ピカソが描いた悲劇の記録は戦争と暴力に対する永遠の警鐘として、今日もなお私たちの心に強く訴えかけてくるのです。
芸術と政治の緊張関係を描く物語
「暗幕のゲルニカ」は、ピカソが描いた「ゲルニカ」をめぐり、1940年代と2003年の二つの時間軸が交錯する小説です。
物語は実在の写真家ドラ・マールと、架空のMoMA学芸員・八神瑤子の二人の女性を軸に展開します。
ドラ・マールは、ゲルニカ制作当時にピカソの愛人だったと言われる才気あふれる写真家。彼女はピカソのゲルニカ制作過程を記録した貴重な写真家で知られていますが、「泣く女」のモデルとしても有名です。
戦時下のパリを背景に、彼女の複雑な内面と緊張感ある日々が繊細に描かれています。
現代の視点からは、9.11テロで夫を失った八神瑤子が物語を牽引します。MoMAで開催予定の「ピカソの戦争」展に、彼女はスペインのレイナ・ソフィア美術館が所蔵する「ゲルニカ」を展示したいと願います。
反戦の象徴であるこの作品を通じて平和のメッセージを伝えたい。そして亡き夫への思いを形にしたいという強い願望がありました。
しかし展示交渉が難航する中、イラク戦争が勃発。国連本部での会見で、いつもなら「ゲルニカ」のタペストリーが掛けられている場所に暗幕が下ろされていることに衝撃を受けた瑤子は、「本物のゲルニカをMoMAに」と決意を新たにします。
両時代に共通して登場するのが、スペインの富豪パルド・イグナシオ。若き亡命青年から世界的大富豪へと変貌を遂げた彼は、物語の展開を左右する鍵を握っています。
原田マハは史実と創作を巧みに織り交ぜることで、芸術作品が持つ政治的意味と平和への祈りを、二つの時代を通して浮き彫りにしました。
緊張感ある展開で引き込みながら、最後には「霧が晴れる」ような感動的な結末へと導いていきます。
結びに
「暗幕のゲルニカ」は芸術と歴史、政治と人間の普遍的なテーマが融合した作品です。
原田マハ氏は一枚の絵画が持つ力とその背景にある物語を通して、平和の尊さと戦争の残酷さを語りかけます。
現代社会においても紛争や暴力が絶えない世界で、ピカソの「ゲルニカ」が放つメッセージは決して色あせることがありません。本作は芸術の持つ社会的意義とそれを守り伝える人々の情熱を称えると同時に、深い平和への祈りを込めた物語となっています。
原田マハ氏の作品は史実と創作の絶妙なバランスで紡がれており、芸術の持つ普遍的な力を改めて教えてくれました。
故郷を守りたい気持ち、戦争を失くしたいという思いに胸が打たれる一冊です。