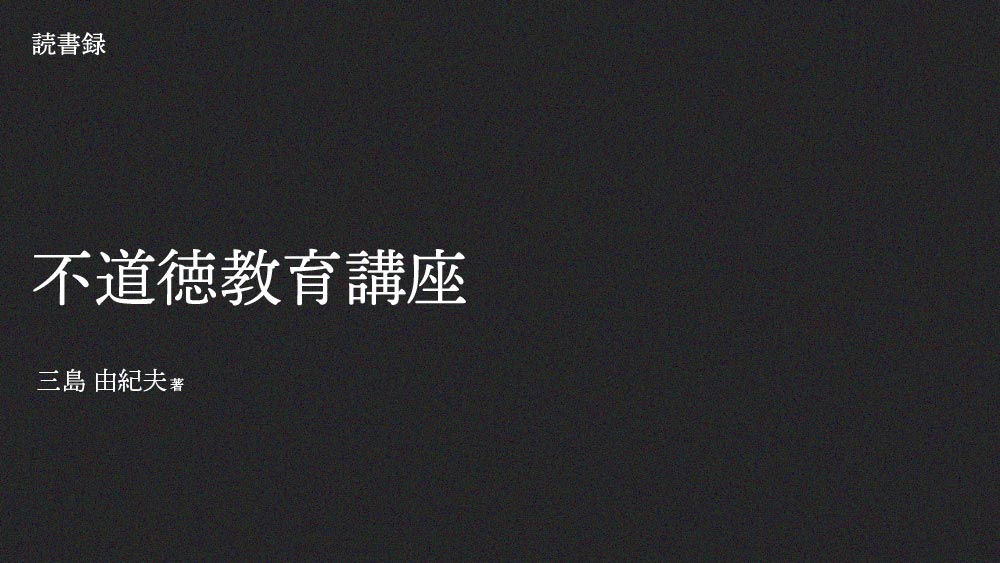今回は三島由紀夫が発表した「不道徳教育講座」。
内容はタイトルに“不道徳”とついているだけあって、世間の常識や正論の逆をいくものばかりです。
例えば、「大いに嘘をつくべし」や「約束は守るなかれ」、「教師を内心バカにすべし」などなど、見出しを読むだけでぎょっとするような常識に反する三島由紀夫ならではなのタイトルが並びます。
しかし、この一冊は不道徳を薦めているわけではなく、常識や道徳に縛られない自由な思考を促すエッセイ集です。
挑戦的なタイトルから、過激な内容を想像してしまいますが、実際に読み進めていくとその鋭い洞察とユーモアに富んだ語り口に引き込まれます。
三島が「不道徳」を通じて問いかけるのは、私たちが無意識に従っている社会規範や価値観のあり方です。読後、既存の道徳観を見直すきっかけとなったと同時に、自由に思考することの重要性を強く感じさせられます。
三島由紀夫という人物
三島由紀夫は、1925年1月14日に東京で生まれました。幼少期から文学に親しみ、16歳で初めての小説「花ざかりの森」を発表します。東京大学法学部を卒業後、大蔵省に勤務しますが、かねてからの夢だった作家としての道を選び、1949年に「仮面の告白」でデビューを果たしました。
こちらの作品は自伝的要素が強く、同性愛や自己認識の問題を扱い、当時の社会に大きな衝撃を与えました。
その後、「金閣寺」「潮騒」「豊饒の海」など、数多くの名作を生み出します。しかし、1970年11月25日、自衛隊市ヶ谷駐屯地でクーデターを呼びかけ、割腹自殺という衝撃的な最期を遂げました。この事件は、三島の文学と思想を象徴するものとして語り継がれています。
三島由紀夫は、その特異な生涯と文学を通じて、日本文学に大きな足跡を残しました。三島作品は美と死、伝統と近代、肉体と精神といった普遍的なテーマを追求し、読者に深い思索を促します。
またどの作品も共通しているのは、人間の持つ感情の表現力が魅力です。文字から景色が見えてくるような力を感じられ、引き込まれる文体で展開されていきます。
作品によっては、難解で硬い印象を受けることもありますが、数ある作品の内容には幅があり、親しみやすい作品も発表されています。今回紹介している「不道徳教育講座」もそのうちの一冊で、口語に近い表現で書かれており、三島らしいユーモアを交え展開されているため、時にクスッと笑える内容になっています。
人間の本質や自由の意味を浮き彫りにする一冊
不道徳教育講座は約70のタイトルで構成され、人間の本質や自由の意味を浮き彫りにします。
その中でも印象に残っているのは「人の恩は忘れるべし」というタイトル。
三島は恩の受け手が恩人に「貸し」を作ってしまったことを「負債」と捉え、その恩の返済に苦しむと述べています。また恩人も恩を返そうとしない相手に苛立ちを募らせ、結果としてお互いが不幸になってしまうと主張しています。
生きていれば必ず友人や家族、時には見ず知らずの他人に助けられることがあります。その恩に持ちつ持たれつ生きていくのが人間です。
しかし、恩人に会うたびに助けてもらった恩を返さないといけないと考えながら生きていくのは大変です。また、恩を施した側も、相手から何もお返しがないから情けない人だと、恩に執着してしまうのも不幸と言えるでしょう。
いっそのこと恩という概念を忘れることで、生きることが楽になるのではないかという内容です。このような考えを持つことで、恩を仇で返すという概念は生まれないわけです。
義理や恩情は美しいものと捉えられることが多いですが、本当の愛情や友情、感謝というのはお互いに存在し続けることができるのか、また人の裏切りや恩を数えて一生を送ることが果たして幸せなのかといった部分に焦点を当てています。
また恩を受けたとか与えたなど、恩の貸し借りで相手との立場や関係を判断する人に対しての、皮肉な感じも含まれていると感じました。
現代社会に響く、言葉と向き合う姿勢が生む三島独自の世界観
三島由紀夫には、辞書を引くのではなく、読んで言葉を学んだという逸話が語り継がれています。このエピソードからも分かる通り、それほどに深く真摯に言葉と向き合っていたからこそ、独自の言葉、表現の世界を築き上げていくことができたのでしょう。
言葉の使い方には、日常的な表現と文学的な表現の二つの側面があります。日常的な表現では、シンプルで分かりやすいことが好まれます。これは、コミュニケーションの効率を重視するためですが、文学的な表現では緻密な構成のもとに言葉を精選し、豊かな表現によって作品固有の美しい世界が生み出されます。
三島の言葉への真摯な姿勢は、自身の文学に深みと独自性を与えました。言葉は、単なるコミュニケーションの手段ではなく、芸術を創り出すための重要な要素です。
私は本書を通して、既存の価値観を疑うことの重要性を強く感じました。
三島は「不道徳」というテーマを用いて、物事を違う視点から見ることの重要性を訴えています。既存の道徳観に疑問を投げかけ、「不道徳」な視点を取り入れることで、固定観念を打破し、新たな発想を生み出すことができます。
現代社会では、「正しさ」や「道徳」が過剰に強調され、時に息苦しさを感じることも少なくありません。三島のメッセージは、そんな現代社会に一石を投じるものであり、自由な思考がもたらす可能性と危うさを同時に考えさせられます。
SNS上では多様な意見が交錯しており、異なる視点を受け入れることで、より深い理解と寛容さが生まれます。ビジネスの世界では、違う視点から物事を見ることがイノベーションを生み出す鍵となります。個人レベルでも、新しい視点を取り入れることで、自己の思考や価値観を広げ、自己成長を促進することができるでしょう。
三島が提唱する「不道徳」は、単なる反逆ではなく、むしろ多様性を受け入れるための一つの方法として読み解くことができます。これは、現代社会においても重要な示唆を与えてくれるものです。
文学の対極、三島由紀夫と太宰治
日本文学を代表する三島由紀夫と太宰治は、しばしば比較される存在です。お互いの作風や思想は対照的であり、それぞれが独自の文学的アプローチを追求しました。
太宰治は私小説的な作風で知られ、自己の内面や弱さを赤裸々に描きました。代表作「人間失格」や「斜陽」では、社会からの疎外感や自己嫌悪がテーマとなっています。
太宰の文学は、戦後の混乱期に生きる人々の心に深く響き、多くの読者を惹きつけました。
そんな太宰の文学を三島由紀夫は、「弱さの文学」と批判。太宰の作品が自己憐憫に満ちており、読者に無力感を与えると指摘したのです。特に太宰の自殺への傾倒や、その作風が持つ「退廃的」な要素を強く否定しました。
三島は自身の文学において「強さ」や「美」を追求し、太宰の「弱さ」とは対極を目指しました。三島にとって文学は自己を高め、理想を追求する手段であり、太宰のような自己破壊的な傾向は受け入れられないものだったのでしょう。
そんな三島ですが若い頃に太宰の作品を読み、その文学的才能を認めていたと言われています。特に太宰の文体や表現力には一定の評価をしており、その影響は三島の初期作品にも垣間見えます。
また、三島は太宰の死に強い関心を抱いていました。太宰の自殺は、三島にとって一種の「文学的象徴」として捉えられ、彼自身の死生観にも影響を与えたと言われています。
三島の最期が自決であったことは、太宰との暗黙の対話を感じさせます。両者は、文学を通じて互いに影響を与え合い、戦後文学に大きな足跡を残しました。