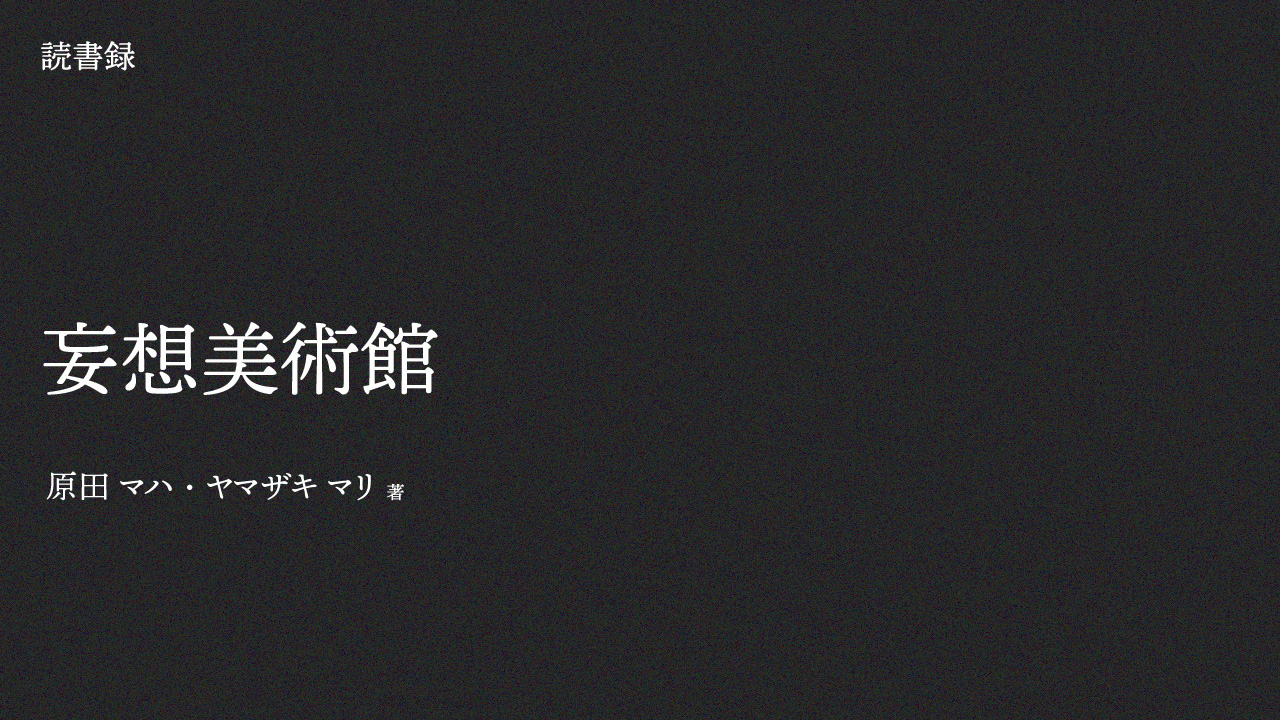元キュレーターの経験を持ち、アートを題材とした数々の小説を手がけてきた原田マハさん。「テルマエ・ロマエ」の作者であり、美術史に深い知見をもつヤマザキマリさん。
アートを愛してきた、おふたりの表現者が紡いだのが「妄想美術館」です。
おふたりの対話は、アートを教えるのではなく、近づけてくれるものでした。作品の意味や文脈を知らなくてもかまわない。「きれい」「変」「引っかかる」といった気持ちを大切にしていい。
「妄想美術館」は、アートの世界の敷居を取り払ってくれる一冊です。
美術館は“幸せになりに行く”場所
「妄想美術館」は、アートへの情熱を語り合う、おふたりの対話形式で進んでいきます。
子どもの頃に初めて訪れた美術館の記憶。心を奪われた一枚の絵。語り出すと止まらない偏愛の画家たち。そのどれもが、知識よりも感情を起点とした、非常に印象的なエピソードばかりです。
なかでも心に残ったのは、原田さんの「美術館は、幸せになりに行く場所」という一文でした。
美術館は鑑賞の場であると同時に、癒しの場であり、感性を取り戻す場でもあります。だからこそ、年齢も関係ないし「うまく見よう」と身構える必要もないのです。
絵画の奥にある「生き様」にふれる
「妄想美術館」には、おふたりが好きな作家について語る場面があります。
たとえば、フィンセント・ファン・ゴッホ、アメデオ・モディリアーニ、パブロ・ピカソ、ジョヴァンニ・ベッリーニといった世界的に有名な画家たちの名前が登場します。
そこで語られるのは決して「技法のすごさ」や「美術史における評価」だけではありません。むしろ彼らが、貧困や病気に苦しみながらも筆を取り続けたことなどについても記載されています。
アートとは、技巧を競うものではなく、「どう生きたか」がにじみ出るものです。一枚の絵の前に立ったとき、心の奥に残る余韻こそが、作家との対話なのではないかと気づかされます。
空想が広げる“妄想美術館”という舞台
本書のタイトルでもある「妄想美術館」は、原田マハさんとヤマザキマリさん、おふたりの自由な想像力から生まれた、架空の美術館です。
ここでは、実在の美術館のように所蔵品や展示方法が厳格に定められているわけではありません。むしろ、「こんな美術館があったら楽しいよね」という遊び心と情熱があふれた、まさに空想の舞台が広がります。
たとえば、未完成や傷のある作品ばかりを展示する「不完全美術館」や地球最後の日に人類が残したい芸術を集めた「国連美術館」といったユニークなアイデアが語られます。
わからないから始まるアート体験
美術館でアートを前にすると、ふと湧き上がる「この作品、どういう意味なんだろう?」という問い。
アートに対するこの意味探しは、私たちが知らず知らずのうちに刷り込まれてきた正しい見方の呪縛かもしれません。
けれどアートに正解はありません。「わからない」という感覚さえも、立派な出発点なのです。
美術史や作者の背景を学ぶことも確かに豊かさをもたらしますが、まずは「なんだか惹かれる」「嫌いじゃない」という自分の感覚を信じてみることが大切であり、アートとの距離を縮める第一歩です。
アートは「特別な人だけのもの」ではありません。
美術館に行ったことがなくてもいい。画集を読んだことがなくてもかまわない。“好き”という感情さえあれば、それだけで十分です。
本書には、美術評論や難解な専門用語はほとんど登場しません。その代わりに、「ある絵を見て強い印象を受けた」「この色、気持ちいいよね」といった対話が繰り広げられます。
知識よりも感覚を。正解よりも自由を。
アートとの関係性に不安を感じている人ほど、すっと内容が入ってくるのではないでしょうか。
アートは意味を与えるものではなく、問いを投げかけてくるもの。その問いに、どう感じ、どう応えるかは人それぞれです。
大切なのは、自分がどう感じたか。その一点に尽きます。
音楽を聴くときを例にすると「正しい聴き方」を気にする方はいません。心が動いたら泣くし、嬉しくなったら踊る。それと同じように、アートも“感じたまま”でいいのです。
「この色が好き」「この形が不思議で面白い」「この絵を部屋に飾ってみたいと思った」。そんな気持ちのひとつひとつが、アート体験の始まりなのです。