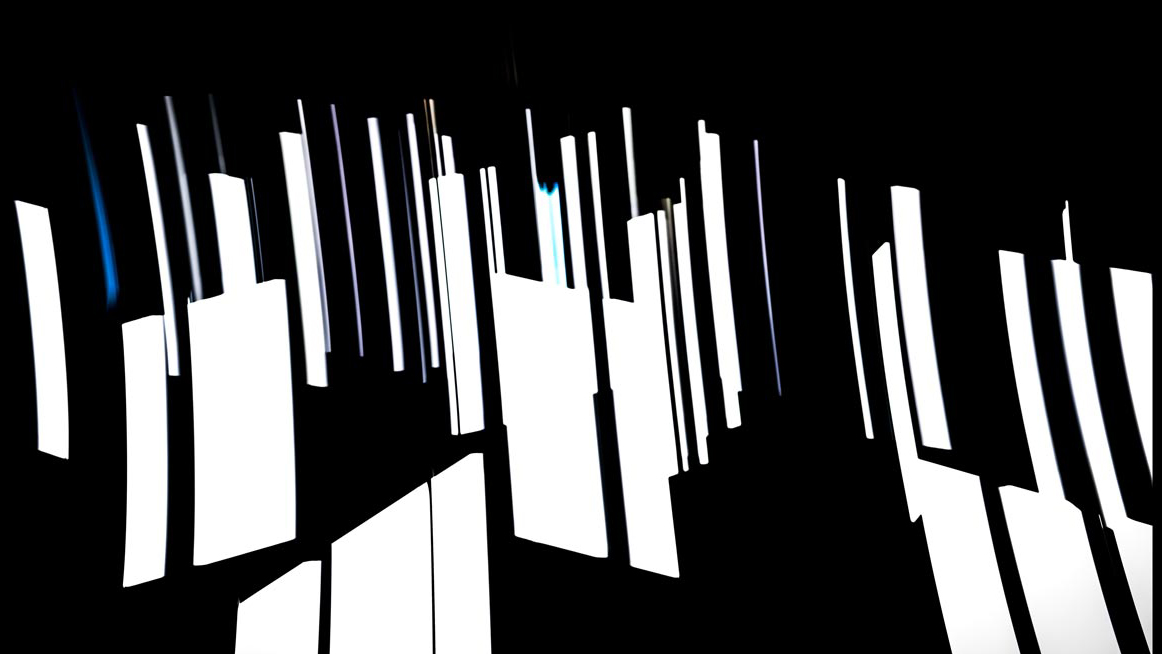記事を書くうえで、「調べること」は避けて通れません。
ライターや編集者、コンテンツに関わるすべての人にとって、リサーチの質はそのままアウトプットの質に直結します。
浅いリサーチのまま書かれた記事は、どうしても他の記事のなぞり書きになったり、根拠の弱い主張にとどまってしまいがちです。読者に新たな発見をもたらすことができず、似たような記事のなかに埋もれてしまうことも珍しくありません。
実際、上位表示された他の記事を表面的に参考にして書くと、内容の誤りに気づけなかったり、自分の言葉として語れなかったりするリスクがあります。
一方で、深いリサーチに裏打ちされた記事は、読み手にとっても書き手にとっても、明らかに手応えが違います。独自の視点、精度の高い根拠、行間から滲む信頼感。それらはすべて「調べる」という地味で愚直な仕事から生まれてくるのです。
私自身、満足にリサーチできなかった経験もあれば、何十時間もかけて調べたのにピントがずれていたこともあります。でも、だからこそ「どう調べればよかったのか」を自分なりに考え続けてきました。
もちろん、そこまで調べなくても成立する記事は世の中にたくさんあります。
しかし、しっかり書こうとすると、いずれ「自分ひとりではどうしようもできない情報群」を扱わなければならない場面に必ず出会います。
この記事では、私が日々の実務のなかで磨いてきたリサーチの心構えや技術をまとめてみました。とはいえ、方法論は人によって異なるものです。
あくまで一人の書き手のやり方ではありますが、大手出版系の編集長から「リサーチ番長」と呼ばれた松岡(私のことです)なりの方法論として、わずかでも参考になれば嬉しいです。
本記事では、「調べるとはどういう行為か」から始まり、リサーチの設計、どのような点に気をつけてリサーチをしているのか、どんな場所から調べているのかなどなど、非常に泥くさい内容を共有していきます。
2万字を超える長文ですが、その中のほんの一節だけでも、誰か記事づくりの支えになれば幸いです。
では、いきます。
そもそも「調べる」とは何か?

我が家の猫。次女。
まず、「調べる」とはどういう行為でしょうか。
その意義を考えてみます。
手元の大辞林アプリには以下のように定義されていました。
しらべる【調べる】(動バ下一)[文]バ下二 しらぶ
[一]
①物事を明らかにするために、観察したり、尋ねたり、本を読んだりする。調査する。「井戸の水温を—べる」「郷土の歴史を—べる」「辞書で—べる」
②求めているものがあるかどうかさがしてみる。検査する。「乗客の荷物を一つ一つ—べる」
③不都合な点がないかどうか見てまわる。点検する。「帳簿のあやまりを—べる」「病院で—べてもらったがどこも悪くないといわれた」
④理非曲直を明らかにするために、あれこれと問いただす。尋問する。取り調べる。「容疑者を—べる」「罪ヲ—ベル/和英語林集成」
[二]
①楽器を演奏する。かなでる。「琴を—べる」
②楽器の音律を合わせる。「琵琶を黄鐘調に—べて…をかしく弾き給ふ/堤中納言物語花桜」
③調子にのって言う。図に乗る。「我もとより知りたることのやうに、こと人にもかたり—ぶるもいとにくし/枕草子28」
今回の対象は[一]ですね。
簡単にまとめると、「わからないことを色々な方法で確かめること」のように見えます。
記事執筆におけるリサーチは単に情報を集める以上の意味を持つと思っています。
私にとって「調べる」を定義するならば、「自身の知識の拡張と視野の拡大」です。
調べることは自分の中に新しい知識を取り入れ、視野を広げる行為です。新しい知識は視点を拡張するレンズやパーツのようなもので、知識が増えると世界の見え方が大きく変わります。
例えば、ある歴史的事件について調べれば、現在の社会問題を別の角度から理解できるかもしれません。リサーチを通じて「今まで見えなかったものが見える」ようになることこそ、知的成長の醍醐味です。
また、自分一人では思いつかない観点に触れられるのもリサーチの意義です。
専門家の論考や多様な立場の人の意見を調べることで、それまで自分になかった物の見方や価値観に出会えます。
結果として、当初漠然としていたテーマに対して新たな切り口や問いを発見することができ、そうした思考の深まりが記事や企画に厚みを与えてくれます。
単に情報を得るために情報を集めるのではなく、自分を広げ、問いを育てるために情報と向き合う。
それが、私にとっての「調べる」ということです。
誰のために調べるのか

三男。最初は白猫だったのにどんどん茶色くなっていく。
前述のように「調べる」という行為は、自分自身のために行うこともあります。
しかし今回は「記事執筆のために調べる」という前提に立った話をしたいと思います。
つまり「お客様の代わりに書く。そのためにリサーチをする」ということです。
お客様の代わりに書くということは、当然ながらお客様の視点を持っていなければなりません。
この視点を持てるかどうかが、リサーチというか記事執筆の第一歩です。
たとえば、エネルギー関連のクライアントから「水素エネルギーの動向を調べてほしい」と依頼されたとしましょう。
その際に、エネルギー業界の人たちが普段どのような情報に触れているのか、どんな観点を大切にしているのかがわからなければ、的外れなリサーチになってしまいます。
だからそこから調べる。
リサーチの前に大切なのは、「お客様の目を持つこと」です。
ただ情報を集めるのではなく「お客様の立場だったら、何を知りたいか」を自分の中に落とし込むこと。
そのため、リサーチとは「お客様の目を獲得するために、自分を変えていくプロセスでもある」と私は考えています。
その視点を持つために自分自身の視野や理解を広げていく。
これこそが「書くために調べる」ことの本質的な意義だと思っています。
リサーチは嘘がつけるし、成長せずとも記事は書ける。そうならないため徹底的に向き合う

次女。運動神経が良い。
私がまだ駆け出しだった頃、ある記事のために約1ヶ月かけてリサーチをしたことがありました。
現場の声を集め、論文を読み、統計資料を追い、専門家に話を聞いてまわりました。
ところが、いざ原稿を書き上げてみると、それは驚くほど「簡単なデスクトップリサーチ」でも似たようなものが書けてしまう内容でした。
あのときは正直、少し打ちのめされましたね。
努力が報われなかったような気がして、書くことの無力ささえ感じました。
けれどそれでも、「手は抜きたくない」と思ったのです。
なぜか。
「軽い態度で作られた薄い記事」にはどうしても負けたくなかったのです。
リサーチという行為は、ときに「正しそうな嘘」を生み出すからです。
都合のよい情報だけを集め、ある結論に向けて巧妙に編集された「リサーチ結果」。
それがまるで真実であるかのように、堂々と流通している現実を私たちは日々目にしています。
リサーチは、ある種の権威をまとうことができます。
引用元を明記し、数値を並べれば、それはたとえ意図的な切り取りであっても「根拠ある言説」に見える。
だからこそ、リサーチには倫理が要るのです。
書き手には、「なぜこれを調べるのか」「誰の目線に立って調べるのか」という問いを、自分自身に投げかけ続ける姿勢が求められるのです。
そして恐ろしいことに、リサーチは必ずしも書き手自身の成長を伴わなくても成立してしまいます。
AIや検索エンジンに入力すれば、無数の情報が目の前に現れ、整った文章を組み合わせるだけで「それっぽい記事」がすぐに書けてしまう。
けれど、そこで得られた知識は、果たして自分の中に根を下ろしているでしょうか?それは思考の糧になっているでしょうか?
その記事で社会は、企業は成長するでしょうか?
そこに書き手としての成長はあるでしょうか?
「書けてしまう」ことと、「本質的に理解している」ことは、まったく別物です。
だからこそ私は時間がかかっても、自分の体を通して調べたいのです。
表面的な「知っている」ではなく、咀嚼し、血肉となった知識で言葉を紡ぎたいと思っています。
私たちがリサーチするのは、お客様や読者の目線に立ち、彼らの問いを代わりに引き受けるためです。
そのときに必要なのは、自分の言葉で考えるという覚悟です。
そして、自分の中に「まだ見えていないものがある」という前提に、謙虚であり続けることです。
リサーチは、情報を集めるための手段ではなく、自分を更新し続ける姿勢でもあります。
それを怠らずにいることが、書き手としての誠実さをかろうじて保つ方法なのだと、今は思っています。
ちょっと熱くなってしまいました。次に進みます。
リサーチ時に意識している10のステップ

長女モノクロ版。最ももふもふしている。
リサーチとは、情報を探す行為であると同時に、問いを深めるプロセスでもあります。
記事を書くという営みは、単なる知識の整理ではなく、「何を伝えるか」と「どう伝えるか」を磨き続ける思考の連続です。
私は編集者・ライターとして、リサーチを「素材集め」に終わらせないように心がけています。
目的があやふやなリサーチは、どれだけ情報を積み上げても、伝わる記事にはなりません。逆に、問いの輪郭さえ明確なら情報が活き、読者の心に届く記事になると考えています。
ここでは、私自身が記事制作において意識しているリサーチの10ステップを簡単にまとめてみました。
ステップ1:なんのためのリサーチかをまず明確にする
リサーチとは、ただ情報をかき集める作業ではありません。
それは「何かを明らかにしたい」「誰かに何かを伝えたい」という衝動に対する、一種の誠実な対話です。だからこそ、その行為の出発点にあるべきなのは、自分自身への問いです。
「私はなぜ、これを調べるのか?」
この問いに対して右往左往しているとリサーチは散漫になります。
記事を書き進めるにつれて主題がぶれ、説得力のないものになってしまうでしょう。逆に目的が明確であれば、リサーチはその目的に向けて有機的に編まれていきます。
仮にテーマが与えられた仕事であっても、そのテーマのどこに自分がひっかかりを感じているのかを言語化することで、リサーチは「作業」から「探求」へと変わります。
- 「このテーマで、私は読者に何を届けたいのか」
- 「この問いをめぐって、何が明らかになれば、自分は納得できるのか」
調べる前に立ち止まって、この問いと向き合う時間を持つこと。リサーチの成否は、実はこの最初のステップでほとんど決まっているような気がします。
ステップ2:「知りたいこと」は「何で構成されているのか」を考える
リサーチの目的を定めたら、次に必要なのは「そのために、どんな情報が必要なのか」を丁寧にほぐしていく作業です。
目的が山の頂だとすれば、情報とはそこに至る登山道のようなものです。どのルートを選ぶかによって、見える景色も、記事が立ち上がる角度も変わってきます。
たとえば「企業の環境対策」について調べたいとします。
そのとき、必要な情報は「制度面」かもしれないし、「技術革新」かもしれないし、「現場の声」かもしれません。
それらはすべて「環境対策」という言葉の内側に潜む要素であり、それぞれに異なる情報源が必要になります。
つまり、リサーチとは「言葉を解体する作業」でもあるのです。
よくあるのが、「一言でテーマを掴んだつもりになって、実は何も調べていない」という状態(私自身よくやってしまいます)。
この言葉の中には、どんなレイヤーの要素が含まれているのか。自分が知りたいのは、そのうちのどこに当たるのか。
このステップは、調べる対象に「輪郭と奥行きを与える」ための下ごしらえのようなものです。ここが甘いと、リサーチは的を外し、記事は表層的なものになってしまいます。
ステップ3:情報がありそうな場所に目星をつける
まだリサーチは始まりません。
本格的に調べ始める前にまず考えるべきなのは「その情報は、どこに眠っているのか?」ということです。
必要な情報をただネット上に漠然と求めるのではなく、誰がその情報を持っていそうか? どんな場所に書かれていそうか?を想像することが、リサーチの効率と精度を大きく左右します。
たとえば、ある社会課題について調べたいとき。
その「事実」は行政の統計かもしれないし、研究者の論文かもしれない。
「背景」は学術書や専門誌の中にありそうで、「現場の声」はnoteやインタビュー記事に出てくるかもしれない。
逆に、「検索上位に出てきたから」という理由だけで情報を使ってしまうと、発信者の立場やバイアスを見落としがちです。
だからこそ、リサーチには情報の居場所を想像する力が必要です。
- この情報、自治体の白書に載っていないか?
- このテーマ、○○大学の先生が研究していそうだな
- あのジャンルの雑誌、こういう視点で特集してたかも
そんなふうに、情報が生きていそうな「土地勘」を持つことが重要です。
完璧じゃなくていいのです。
だいたいこのあたりにありそうだ、と目星をつけることが、深いリサーチへの道しるべになります。
検索する前に地図を描く。それが、リサーチの本当のスタートラインです。
ステップ4:情報を取りに行くための「土台」を自身に作る
リサーチを始めるとき、すぐに情報に飛びついてしまいそうになりますが、実はその前にやるべきことがあります。
それは、自分がその情報を理解するための「下地があるか」を確かめることです。
たとえば、経済白書を読んでもそこに出てくる「実質GDP」や「乗数効果」の意味がわからなければ、数値や図表は単なる装飾になってしまいます。
あるいは、海外論文を読みたいと思っても、基礎的な専門用語やリサーチモデルの概念がわかっていなければ、読み進めることは難しいでしょう。
つまり「あの情報を取りに行くには、どんな知識が必要か?」という視点を持つことが、この段階では欠かせません。
「Aという知識が欲しければBという知識がいる、Bの知識が欲しいならCという知識を身につけなくてはいけない」みたいなイメージですね。
情報には、それを受け取るための前提知識という「鍵」が要るのです。
例えば、
- 統計にあたるなら、統計用語の基本を軽く押さえておく
- ある技術の歴史を追いたいなら、業界の年表や沿革に目を通しておく
- 専門家の議論に触れたいなら、最低限の関連概念は把握しておく
など。
そうすることで、その後に出会う情報の「意味」が違って見えてくるはずです。
ただ読むだけでなく、背景を理解し、構造の中に位置づけられるようになるのです。
急がば回れ。
すぐに情報に飛び込むのではなく、自分の立ち位置を整えることで、リサーチの深さと精度は確実に変わっていきます。
ステップ5:まず何からインプットすれば欲しい情報に近づけるかを考える
必要な前提知識群が見えてきたら、いよいよインプットの第一歩です。
ようやくここからインプットです。
とはいえ、すべてを網羅しようとするのは難しいでしょう。
むしろ重要なのは、「どこから手をつければ、その後の情報の見え方が変わるか」を考えることです。
リサーチにおいて最初に読む一冊、最初に開く一本の記事は、地味にその後の展開を大きく左右します。
なぜなら最初のインプットは、そのテーマを見るための「眼鏡」をつくる行為だからです。
どんな知識から入ったかによって、同じ出来事をどう解釈するかが変わってしまう。だからこそ「とりあえずネットで見つかった順に読む」ではなく、最初に何を読むかに慎重さを持ちたいところです。
ここで意識したいのは、「全体の地形がざっくり見えるもの」を優先するということ。
- 業界の入門書
- 最新の解説記事
- 総論的な白書や概説レポート
などが分かりやすいかもしれません。
「◯◯業界の課題って何だろう?」という漠然とした問いも、関連資料やデータを調べていくうちに「なぜ◯◯業界では△△が慢性的な課題となっているのか?」というようにより焦点の定まった問いへと発展するでしょう。
さまざまな情報に触れ、自分の疑問を洗練させていくことで、記事全体の論点も明確になっていきます。
今回も完璧な情報でなくてもかまいません。
それよりも、これから出会う情報をどう整理していくか、その「フレーム」を手に入れることのほうが大事です。
ステップ6:目星をつけた情報源に、実際にあたってみる
リサーチの目的が定まり、必要な知識も下地として入ったら、いよいよ本格的なリサーチの入り口に立ちます。
このステップではこれまでに目星をつけておいた情報源に実際にアクセスし、情報を読み取り始める段階です。
ここで意識したいのは情報に「触れる」ことと「使える形で読み取る」ことはまったく別だという点です。
検索結果をざっと見るだけ、記事をスクロールするだけでは、本当の意味で情報を「読んだ」ことにはなりません。
大切なのはその情報が自分の問いに対して何を語っているか、どの部分が使えそうかを、意識的に選びながら読み取っていくことです。
- この論文は、どの文脈でこのデータを提示しているのか?
- この記事は、どんな立場から書かれているのか?
- この本の著者は、何を問題にしようとしているのか?
そうした問いかけをしながら読むことで、情報の背後にある意図や構造が見えてきます。
ただ情報を「摂取」するのではもったいない。
その情報がどこから来て、どこへ向かおうとしているのかを追う姿勢が読み手の側にも求められます。
この時点では、まだ深堀りには入らなくて構いません。
まずはリストアップした情報源に実際にあたり、どのような質感の情報がそこにあるのかを掴むことが先です。
その中には「思っていたより浅いかも」「逆に思っていた以上に深かったな」という発見もあるでしょう。
その感覚が、次のリサーチの方向性を教えてくれます。
ステップ7:当たった先を、さらに深掘りしていく
リサーチとは、一度見つけた情報を「消費」して終わりにする行為では当然ありません。
本当に意味のあるリサーチは、出会った情報を起点にして、さらに掘っていくところから始まります。
たとえば、ひとつの有益な記事や論文に出会ったなら「その出典や引用元はどうなっているのか?」「その著者は他に何を書いているのか?」「この情報に反論や補足をしている人はいないか?」などを追ってみましょう。
そうやって、「情報の背後に広がっている構造」へと潜っていく姿勢が、リサーチの密度を変えていきます。
ここで頼りになるのは、好奇心の精度です。
- なぜこのデータが使われているのか?
- なぜこの視点が選ばれたのか?
- この議論に欠けているのは何か?
などなどの問いを自分の中に持ちながら読み進めると、情報がただの素材ではなく「関係性を持ったネットワーク」として立ち上がってきます。
そしてそのネットワークの中で、自分なりの立ち位置が少しずつ見えてくるのです。
ここで大事なのは「情報量の多さ=良いリサーチではない」ということです。
「無闇にたくさん集める」だけでは、むしろリサーチの意図がぼやけてしまうこともあります。必要なのは、出会った情報を「入り口」として捉えること。
それが表している構造や対話の文脈まで踏み込み、理解を深めることです。
つまりこのステップは、「表層をなぞる」から、「構造を知ること」へと進むフェーズです。
ステップ8:集まった情報を整理し、構造化
いよいよリサーチの後半戦。膨大な情報を取捨選択し、論理的な筋道を立てて配置するプロセスです。
この段階では手元にはさまざまな情報が集まってきているはずです。
統計データ、専門家の意見、現場の声、歴史的な背景、そして一次資料。
けれど、それらはまだ「バラバラの素材」にすぎません。
この段階でやるべきことは、バラバラな情報たちを一度テーブルの上に並べて「そこにどんなつながりがあるか」を見極めることです。
検証を経て有用だと判断した情報を、記事の論旨に沿って整理・構造化していきましょう。
具体的には、共通するトピックごとに情報をグルーピングしたり、因果関係や対比関係を軸に並べ替えたりして、記事のアウトラインを作成します。
この構造化プロセスによって各情報が持つ意味合いがはっきりし、記事全体の流れが見えくるはずです。
もちろん情報整理とは、単なる分類作業ではありません。
- この情報同士は、どんな関係にあるか?
- 主張を支える根拠として、どれが効いてくるか?
- 背景情報としてどこまでが必要か?
- そもそも、何を削るべきか?
そういった問いを繰り返しながら、情報の位置づけを決めていきます。
この段階で「このデータは背景説明に使おう」「このエピソードは主張の具体例として入れよう」「すごくいい情報だけどこの記事の文脈では浮いてしまうから使用しないでおこう」といった配置を決め、無駄な情報は省きます。
もうひとつ意識しておきたいのは、「情報には重みがある」ということです。どんなに正確な情報でも、それが主張に対して効いていなければ残す意味はありません。
逆に、データとしての重要度は低くても記事全体の構造を語る「エピソードの力」がある情報も存在します。
情報の価値は「正確さ」と「役割」で決まると思っています。この視点で整理を進めていきましょう。
ステップ9:情報の正しさと筋を再確認する
リサーチを重ね、構造も見えてきたとなれば、いよいよ執筆へ。
と急ぎたくなるかもしれません。
けれどその前に、必ず立ち止まってほしいプロセスがあります。
それが「本当にこの情報は正しいか?」を再点検するステップです。
ここでの確認は、「正確さ」と「文脈の妥当性」の両面を見ます。
まずは出典の確認。
そのデータや言説は、どこから来たものか?引用した数字の年次や対象範囲は合っているか?情報源の信頼性は十分か(専門性・中立性・更新日など)?など。
次に、文脈の精査。
その言葉は、著者のどんな立場から語られたものか?元の資料ではどう使われていたか?都合よく切り取ってしまっていないか?などにも目を光らせたいものです。
特に注意したいのは、「誰かの主張を使うときの扱い方」です。
たとえば、ある学者の一文を引用するなら、その論文全体の論旨と照らして妥当な引用になっているかを確認する必要があります。
たった一文が、自分の主張を支える都合の良いピースになってしまっていないか。リサーチする者としての倫理が問われるポイントでもあります。
また、ファクトチェックの過程では「調べたつもり」の落とし穴にも気づきやすくなります。
- 複数のソースを照らし合わせたか?
- 過去と現在の情報が混在していないか?
- 自分の解釈に引っ張られすぎていないか?
このステップは、言うなればリサーチの「目視確認と安全点検」。
せっかく集めた情報も、根っこがぐらついていれば説得力を失います。信頼できる記事には、見えないところに慎重な裏取りがある。
最後に、声に出して記事の冒頭から目を通してみるのもおすすめです。
読者として自分が読んだとき、その主張やデータは自然に受け取れるだろうか?
情報の通り道に不自然な段差はないか?そんなことを意識しながら情報を取りまとめていきます。
ステップ10:全体の一貫性を見渡す
リサーチを終え、記事を書き上げたあとに立つべき最後の地点。
それが「この文章は、最初に立てた目的と整合しているか?」を見直すステップです。
これは文章の整える作業というよりも、文章全体の「魂」がどこに宿っているかを確かめるようなプロセスです。
リサーチを重ねていくうちに、当初の関心や仮説が変化することはよくあります。
むしろ変わるのは健全なことです。
けれど、リサーチの過程で拡張された知識や視点が、ちゃんと「ひとつの線」として記事に流れているかどうかを、ここで確かめておく必要があります。
たとえばこんな問いを立てながら読み返してみてください。
- 導入で提示した問いに、本文は応えているか?
- 集めた情報が、主張の展開に自然に接続しているか?
- 引用したデータや事例は、話の芯を支えているか、それともノイズになっていないか?
- 結論は、最初の問いから自然に導かれているか?
この確認を怠るといくら情報が正確で構成が丁寧でも「なんとなく散らかった記事」になってしまいます。
逆に言えば、文章に一本筋が通っているとき、それは読者にも「読後感」として確実に伝わるのです。
ここでおすすめしたいのは、書き手としてではなく「編集者として」自分の文章を読むことです。
つまり、自分がリサーチし、考え、書いたすべてをいったん脇に置き、まっさらな目で「この構成で本当に伝わるか?」を問う視点を持つ。
主張の順番、情報の流れ、視点の置き方、全体が呼吸しているかを確かめる。
この段階でイマイチな出来だった場合は最初からやり直すことも珍しくありません(すごく辛いですが)。
リサーチと執筆に向き合う際に大切にしている10のこと

次女。寝ています。
記事制作におけるリサーチに関して、これまで私が基本的に意識しているステップを記載してきました。
しかしただ型をなぞるだけでは良い記事につながる良いリサーチができません。
この章ではリサーチし、記事を制作する際に気をつけている点を記載していきます。
1. とにかく幅広く色々な情報を仕入れる
私は基本的に、まずはとにかく幅広く情報を集め、一度「カオス状態」をつくることが多いです。
書籍、新聞、学術論文、SNS、専門家の話、業界誌、note記事などなど、とにかく手当たり次第に目を通し自分の中に素材を片っ端から溜め込みます。
そこから、主題に合う情報をひとつひとつ選び取り、徐々に記事として構築していきます。
正直、効率の良いやり方とは言えないかもしれません。
実際、納期との兼ね合いもあるため、毎回このやり方ができるわけではありません。
企画がある程度定まっている場合には、一点集中で必要な情報だけを調べることもあります。
ただ、その場合、どうしても記事の内容が「無難な一般論」に寄ってしまう感覚があります。
簡単に言えば読み応えがない気がするのです。
独自の視点を記事に宿らせたいのであれば、やはり情報収集の時点で視野を広く持つことが不可欠だと感じています。
異なる業界、異なる論点、まったく異なる文脈に見えるもの同士が、ある一点でつながる瞬間があるためです。
「このテーマとこのテーマって、つながるのか?」という、ギリギリの距離まで目線を広げておく。
そして最後に、ぎゅっと一気にまとめる。
そのプロセスこそが、自分にとっての「書くためのリサーチ」の基本的な型になっています。
2. 「問い」を記録する、更新する
調査中に生まれた問いを、書き留めておく。これは単純なようでいて、実践している人は意外と少ないかもしれません。
リサーチを進めていると、「あれ?これって本当かな」「この現象とあれって関係ある?」といった小さな疑問が連続して生まれてきます。けれど、その問いをそのまま流してしまうと、本来深掘るべきテーマの芽を、自分で見逃してしまうことになります。
そんなふうに湧き上がった違和感は、記事に厚みを与える可能性のある伏線です。けれどそれを記録せずに進んでしまうと、後から思い出せず、結果的に文章の深掘りチャンスを逃してしまう。
記事にとって「問い」は設計図でもあり、読者との接点でもあります。
調査中に出てきた違和感や未解決の疑問を都度メモしておくと、後から構成を練るときに非常に役立ちますし、自分の視点がどこにあるのかが明確になります。
私は普段、企画ごとにNotionでボードを作り、リサーチの途中で生まれた問いを可能な限り残すようにしています。小さな気づきや違和感でも、あとで見返すと企画の方向性を決定づけるヒントになっていたりします。これは感覚的には「問いのログを残す」というより「問いを育てていく」という感覚に近いかもしれません。
また、リサーチを続けていくうちに、「最初に立てた問い」と「途中で見えてきた本当の論点」がズレてくることもあります。そうしたとき、問いの変化を追えていれば、構成そのものを見直す判断もスムーズにできる。記事の筋を立てるために、問いの変遷を追える状態にしておくことはとても重要です。
さらに、「最初に立てた問いが、最後まで同じである必要はない」という柔軟性も大切です。リサーチの過程で問いが更新されていくことは、むしろ良い兆候だったりします。
3. 困ったら小さなクラスターから始めてみる
リサーチというと、つい最初から大きな全体像を掴もうとしてしまいがちです。
しかし、全体を俯瞰しようとするあまり、どこか抽象的で大味な理解にとどまってしまうことがあります。
そんなときこそ有効なのが、「小さなクラスターから始めてみる」ことです。
たとえば、「日本のウェルビーイング政策」という広いテーマを調べようとしても、あまりに対象が大きすぎて何から手をつければよいか、混乱してしまうはずです。
しかしそこで、「○○県の自治体で行われている高齢者の対話活動」や「とある公立小学校での朝の会の取り組み」といった、具体的で局所的な事例から調べてみると、そこに施策の実装現場や生活者のリアルが見えてきたりします。
小さな情報の密度は、大きな概念よりもずっと高いのです。
文章もまた、ミクロな具体の集合体です。
どれだけその「ひとつ」を深く掘り下げられるかが、最終的に全体の厚みを決めます。
大きな話を語るには、小さな現象の観察から始めること。これはリサーチにも執筆にも共通する姿勢と言えるでしょう。
4. 読み手に何の情報を持ち帰ってもらうべきかを考える
少し抽象的な話かもしれませんが、記事を書くときには常に「この文章を読んでくれた人に、何を持ち帰ってもらいたいか?」を意識するようにしています。
たとえば、サブスクリプション型のメディアや雑誌など、ユーザーが「お金を払って読む」タイプの媒体では、読者というより「情報を得るために投資しているユーザー」という存在になります。
そうした読者にとって価値のある情報とは何か。
専門誌であれば、業界の定量的なデータ、特定企業の戦略、キーパーソンの発言といった情報が大きな意味を持つでしょう。
一方で「なんとなく業界の現状がまとまっているだけ」の記事は、情報としての解像度がやや弱く感じられるかもしれません。
この考え方は無料のメディアにおいても同様だと思っています。
どんな媒体であれ、読者は何らかの「時間」を使ってその情報に触れてくれています。
であれば、その時間に対して、何かしらの価値を、例えば気づき、納得、視点、行動のヒントなどを返す必要があると私は思っています。
「この文章を読んだ人は、何を持って帰れるだろうか?」「この情報は、本当に誰かの役に立つだろうか?」そんなことを考えたいのです。
リサーチや執筆の過程で、たびたびこの問いに立ち戻るようにしています。
それは、記事の「出口」を意識するということでもあり、自分の書く言葉に責任を持つための姿勢でもあります。
5. 必ずオピニオンを用意する
リサーチはもちろん大切です。
ただ、調べた情報をそのまま整理して書いただけでは、それは単なるレポートになってしまいます。
それだけでは記事としての力が弱くなってしまうことがあります。
だからこそ、必ず「オピニオン」を入れるように意識しています。
意見や見解、視点といった要素が加わることで、記事は単なる事実の羅列から、意味のある言葉に変わります。
ここで注意したいのが、「誰のオピニオンを入れるのか?」という点です。
執筆者自身の見解が求められる場合もあれば、クライアント企業のブランドとしての立場や思想を代弁する必要があるケースもあります。
どちらであっても言えるのは、「その分野について、相応の理解と納得をもって書けているかどうか」が問われるということです。
浅い理解のまま意見らしきものを差し込むと、読者にもすぐ見抜かれてしまいます。
だからこそ、オピニオンを書くためには、それを語るだけの土台となる知識が欠かせません。
また、クライアントや掲載媒体がある場合には、意見を盛り込むことがブランド方針やメディアの論調と矛盾しないかどうか、事前にしっかり確認しておく必要があります。
記事にとっての「芯」となるのは、たいていこのオピニオンです。
事実と意見が乖離していないか、無理に主張していないかも含めて、慎重に向き合っていきたいポイントです。
6. その記事はここでしか読めない情報になっているか?を考える
専門誌やメディアにブランドとしての価値が生まれるのは、そこに「その媒体でしか読めないコンテンツ」があるからだと思います。
他の媒体から引用してきただけの記事には、少し厳しい言い方をすれば、あまり価値がありません。
なぜなら、その情報はすでに別の場所で読めるからです。
読者が「このメディアだから読みたい」と思うのは、他にはない視点、他では語られていない文脈、そして他では手に入らない情報に触れられるからです。
つまり、そのメディアにしか出せない記事になっているかどうか。この視点を持つことは、記事制作において非常に重要です。
しかし、リサーチという行為は、どうしても「他のメディアに載っている情報の集合体」になりがちです。ここがリサーチ記事の難しいところです。
だからこそ、切り口が大事になり、先ほどのオピニオンが重要になるのです。
情報の集め方以上に、「どう語るか」「どこから語るか」が、記事の価値を決定づけます。
そして何より、「このコンテンツにはレアリティがあるか?」という問いを、常に自分に投げかけること。
その問いが、リサーチを単なる調査で終わらせず、記事を「その媒体らしい言葉」へと昇華させる鍵になるのだと思います。
7. 同じ声ばかりを拾わないよう、「確証バイアス」や「エコーチェンバー」に注意する
情報を調べる過程で、無意識のうちに自分と似た意見や価値観ばかりを集めてしまうことがあります。
それは一見効率的で、仮説を裏付けてくれるようにも見えるかもしれません。
しかしそれは、思考の幅を狭め、記事の視野を閉ざしてしまう「エコーチェンバー現象」の罠でもあります。
エコーチェンバーとは、自分と似た意見ばかりが反響し合う閉じた情報空間のこと。
SNSや検索エンジンのパーソナライズ機能によって、私たちは気づかないうちに「見たいものしか見ていない」状態になりがちです。
都合の良い情報だけを集めて都合の良い結論に導いてしまう「確証バイアス」にも注意が必要です。
自分の立てた仮説を裏付けるものばかり集め、反するデータを無視しては公平な記事とは言えません。
リサーチにおいてこれらを続けると、都合の良い情報だけで構成された、バイアスに満ちた記事が出来上がってしまいます。
だからこそ「反対意見にも一度は目を通す」「異なる立場からも同じ事象を調べてみる」姿勢が大切です。
違和感こそが、視野の拡張装置なのです。
リサーチの段階でわずかでも不安を覚えたとき、それは「まだ見ていない場所があるぞ」というサインかもしれません。
リサーチを進めるほどに、世界は広がっていくはずです。閉じない、偏らない、問い続ける。その姿勢が、質の高い文章を、リサーチを支えるのです。
8. 時に一次情報正確説を疑う
「一次情報に当たれ」というのは、リサーチや記事制作の鉄則としてよく言われることです。
確かに、できる限り原典にさかのぼる姿勢は大切です。
けれど実際に一次情報を読むと、その内容が驚くほどわかりにくいこともあります。専門的すぎたり、前提知識が求められたり、解釈の余地が広すぎたりして「当たったはいいが、どう読めばいいのかわからないぞ」ということは少なくありません。
さらに言えば、一次情報そのものが間違っているというケースも実は意外と多いのです。
統計の出典に誤記があったり、公式資料の中で過去の事実が矛盾していたり。つまり、「一次情報だから正しい」という思い込み自体が、危うい前提になっていることがあるということです。
だからこそ私たちは、出典の「権威性」だけに頼るのではなく、「なぜそのデータが出されたのか」「その記述の背景にはどんな構造があるのか」といった視点で読み取る必要があります。
案外、二次情報のほうが正確で、わかりやすかったなんてことも実際には少なくありません。一次情報はもちろん大切です。希少性という意味でも、情報の質という意味でも、信頼に足るケースが多いのは事実でしょう。けれどそれは「一次情報=常に正しく、常に上位である」という意味ではありません。
むしろ、丁寧に咀嚼された二次情報のほうが、全体像が整理されていたり、誤解の余地が少なかったりすることさえあるのです。
だからこそ、一次情報を「絶対視」しすぎる必要はないと感じています。
もちろん、できるだけ一次情報にあたることは基本姿勢として持ちたい。ただ、それだけに固執して他の視点を捨ててしまうと、かえって全体のバランスを欠く恐れもある。
情報のレイヤーに優劣をつけすぎず、その文脈と構造を見極めること。それがリサーチの深さを支える感覚のひとつだと思っています。
9. AIは優秀、ただし鵜呑みにはしない
AIによるリサーチは、たしかに非常に優秀です。
とくにウェブ上に公開されている情報を横断的に整理する力は、人間の手作業では到底かなわないスピードと広さを持っています。
ただし、その力が発揮されるのはあくまで「デジタルに存在している情報」に限られるという前提は忘れてはいけません。
たとえば有料記事、限定配布の資料、現場の感覚、あるいは未発表の研究。そういった「データベースに乗っていない情報」には、今のAIはアクセスできません。
また、AIは公的な統計と個人ブログの主観的見解を、同じ階層で並べてしまうこともあります。
情報の信頼性や文脈、温度感を自動で判断するには、まだまだ改善点があるように思えます。情報の粒度が揃っていないまま提示されるため、使い手がそれを精査しないと誤った理解やミスリードを生むおそれもあるのです。
とはいえ、AIを使って「アタリをつける」ことには大きな価値があります。
関連トピックの洗い出し、検索キーワードの発想、論点の棚卸しなど、リサーチの出発点を設計する段階では非常に心強い味方になります。
つまり、AIは頼れるパートナーではあるけれど、すべてを預けてしまってはいけない存在です。
テーマの重さや扱う情報の種類によっては、AIリサーチだけで完結させるとどうしても記事が浅くなってしまうこともあります。
だからこそ、AIの出してきた情報を「どう読むか」「どう深めるか」は、やはり人間の仕事であると、その意識を忘れないことを心がけています。
10. とにかく一気に調べる
複数の企画を同時に抱えていると、つい日替わりで少しずつ手をつけたくなってしまいます。
「今日はA企画を少し、明日はB企画、その次はC企画…」と順番に進めていくようなスタイルです。
けれど私自身の経験として、それはあまりうまくいきませんでした。
頭の中にそれぞれのテーマが並列処理されてしまい、情報が深く定着せず、リサーチの地盤がふわふわしたままになる感覚がありました。
それよりも「ひとつの企画にまとまった時間と集中を投下し、一気に調べ切り、そして次の企画に移る」という「バッチ処理的」な進め方のほうが、ずっと手応えがありました。
これは、情報の量や質というより、調査を通じて頭の中にテーマの地形を作れるかどうかの問題です。
Aを調べている間は、自分の関心や疑問がそのテーマに最適化されていて連想や疑問が連鎖的に立ち上がってくる物です。それが一番リサーチの密度を上げてくれるのです。
もちろん、日々並行して動かさなければならない業務もあるでしょう。
でも、「リサーチする日」は可能な限りひとつのテーマに専念することをおすすめします。
深く潜るなら、ひとつずつ。
そんな進め方が、自分のなかでは最も成果につながる感覚があります。
どこから情報を調べるのか。主に利用する7つの情報源

三男。とても良い表情。
私がいつもリサーチの際に検討する「当たる場所」をいくつか挙げてみます。
とは言っても特に奇をてらったものはなく、あくまで一般的な内容ですのでご容赦を。
1. 書籍から調べる
リサーチというと、ついWeb検索に頼りがちです。
けれど私はむしろ、情報の起点は本に置くべきだと考えています。
とくに専門書や新書、業界の解説本などは、ネット記事にはない背景・歴史・構造といった「文脈」を豊かに与えてくれるからです。
インターネットの良さは、必要な情報にすばやくアクセスできることですが、ただその反面「それがどうしてそうなったのか」という背景や前後の流れが切り取られやすいのも事実です。一方で本は、情報そのものだけでなくその情報の位置づけを教えてくれるメディアです。
たとえば、歴史的な出来事についてWebでは年号や概要を即座に知ることができますが、一冊の本を通して読めば、その事件の社会的背景や関係者の立場、事件後の余波に至るまで、多層的な理解が可能になります。本は、情報を立体的に見るための装置としても機能してくれます。
私は、未知の分野に挑むときには必ず最低3冊の本を読むようにしています。
これは個人的な習慣であると同時に、弊社でもルールとして推奨している姿勢です。
複数の本を読むことで、それぞれの著者の観点の違いが浮かび上がり、逆に共通して何が重要視されているのかが見えてきます。それが、その分野の地盤をつくる作業です。
書籍から調べるというのは単なる下調べではありません。
情報を「骨組み」として組み立てるためのリサーチの起点です。
時間はかかりますが、その時間は記事の説得力として確実に回収されるという実感があります。
2. 専門誌を読む
情報のリサーチにおいて、業界ごとの専門誌をチェックすることは非常に実用的で効果の高い手段です。
専門誌とは、一般メディアでは拾いきれない業界内部の動きや、最新トレンド、実務的な視点を伝えるメディアのこと。ニュース性や速報性はそこまでなくても現場の「リアルな関心」が反映された貴重な情報源です。
特定の分野においては、実はWebよりも専門誌のほうが情報が早かったり、精度が高かったりすることもあります。
医療、農業、製造、建築、教育、エネルギー、福祉などなど、あらゆる業界には「業界人しか読まない雑誌」が存在しています。そして、そういう雑誌にこそ、その分野の専門家が何を問題にしているのか、どんな言葉で語っているのかが載っているのです。
もちろん専門誌、そして専門誌の独自調査情報の多くは有料です(驚くほど高額なものもあります)。
手に入れるには図書館や購読、あるいはバックナンバーの購入が必要になることもあります。けれど、その一記事が一次情報としての価値を持ち、構成の軸になることも少なくありません。
特に、業界外の読者向けに記事を書くときは、専門誌で得た知見を「翻訳」するように用いることで、記事に深みとオリジナリティが生まれます。
Web検索だけでは出会えない、業界内部の空気感。それを感じたいとき、専門誌は「情報」以上に「温度」を伝えてくれるメディアとして頼りにしています。
3. 人に会う、取材する
実際に人と会って話を聞くことも非常に重要なリサーチ手段です。
そしてそれは単なる情報収集ではなく、数字では見えない温度や文脈を拾いにいく行為だと私は考えています。
デジタル業界の人は意外なほどこの「人に会って聞く」ということをしない印象です。
「なぜそのサービスを使うのか?」「なぜその選択をしたのか?」「この商品の魅力は何か」などという問いに対して、統計や調査データでは語りきれない背景が必要になることがあります。そのとき、実際にその人の声を聞いてみることが、何よりも確かな素材になるのです。
たとえば、あるヨーロッパの法規制について調べていたとき、複数の資料には「環境に配慮した対応」と書かれていました。しかし実際に有識者に話を聞くと、運用上の課題や「数字に出ない現実」が次々と出てきました。その瞬間、データの背景が立ち上がり、文章に「血の通った理解」が生まれる感覚がありました。
もちろん、毎回インタビューができるわけではありません。
しかし身近なユーザーの声、知人へのヒアリング、店頭での会話、講演会での質疑応答など、「人の声を拾う場」は思っているより多く存在しています。
そして、人の声を扱う以上、誤解なく、丁寧に取り扱うことも欠かせません。
話をメモや録音で記録し、事実確認を本人にとる、文脈を曲げないように編集するなど、これらはすべて、リサーチにおける信頼の設計でもあります。
数字は傾向を語り、人の声は理由を語る。
その両方が揃ってこそ読者に伝わる記事になると、私はそう信じています。
4. 論文を読む
あるテーマについて深く理解したいとき、そして記事に強度のある裏付けを与えたいとき、欠かせないのが論文の存在です。
私はGoogle ScholarやConsensusといった論文検索ツールをよく使います。
とくに、誰がどういう立場で何を研究しているかを把握するうえで論文は非常に有効な情報源です。
Google Scholarは、学術論文を横断的に検索できる無料ツールですが、検索キーワードに関連する研究を一覧で表示してくれます。また、最近の研究に絞って調べたい場合は、検索期間を限定することも可能です。
さらに、ConsensusのようなAI型の論文検索ツールを使えば、複数の論文から共通見解やトピックごとの要旨を短時間で把握することができます。英語論文が中心とはいえ、リサーチの入口として非常に便利です。
論文は単なる情報ではなく、その分野の思考の流れや議論の蓄積がそこにあることにも価値があります。
著者の立場、用いられている手法、分析の前提などを丁寧に読み取ることで、記事に厚みのある観点や信頼できるデータを加えることができます。
もちろん、海外の論文を読み解くには一定の読解力も必要ですが、近年はDeepLなどの高精度の翻訳ツールもあり、以前よりずっと理解しやすくなっています。特に一次データに近い統計や実験結果は、他のメディアよりも正確かつ中立であることが多く、信頼できる材料になります。
迷ったときこそ一度論文に立ち返ってみると、言葉の揺れや根拠の弱さに自分で気づくことができるはずです。
5. 学術データベースを使う
学術的な信頼に基づいた知識が体系的に整理されたデータベースも記事によっては役立ちます。
JSTORやCiNiiのようなサービスがそれです。
たとえばJSTORは、歴史・文学・哲学・経済など、人文社会系を中心に幅広い学術誌・論文を収録しています。過去に蓄積された学問的知見に触れることができ、一時的なブームや話題性に流されない観点を得ることができます。
一方、CiNiiは日本語の学術論文に特化した国立情報学研究所の論文検索サービス。
日本の大学や研究機関で発表された論文を探すのに非常に有用で、特定の業界や制度、歴史的トピックなどを深掘りしたいときには欠かせない情報源となります。
情報源が明確であり、査読を経た論文が多く掲載されているため、曖昧なWeb情報よりも遥かに確かな裏付けとなります。また、過去の類似研究や反対意見にもあたることができるので、記事の中で複数の視点を構成する際にも役立ちます。
もちろん、専門用語や文体に慣れが必要な部分はありますが、概要だけでも読んでおくと、情報の厚みや社会的背景の理解度がまるで変わってきます。
ウェブ検索では辿り着けない知識に触れたいとき、学術データベースは遠回りのようで近道な選択肢です。
6. 報道と白書を読む
世の中の動きに対して記事としてどうアプローチするかを考えるとき、最初にあたるべき情報源のひとつが信頼できる報道機関による取材記事や、官公庁・企業による調査レポート、そして各種白書です。
報道記事には、記者が現場で得た情報が詰まっています。とりわけ全国紙や専門性の高いメディアは、裏付けのとれた証言やデータ、関係者の生の声を慎重に構成しているためリサーチの基礎として非常に有用です。
一方、白書や調査レポートは、より体系的かつ客観的に情報をまとめた資料です。
経済産業省や内閣府、企業の調査部門などが発行する白書・年次報告・調査報告書などは、あるトピックについて網羅的な現状分析や傾向を提示しており、構成の「骨組み」にもなりうる情報源です。
こうした文書の強みは、まさに今の社会的現実がどのように捉えられているかが見えてくること。
数字や発言だけでなく、それをどう解釈しているのかまで踏み込んで読むと、社会の問題構造や論点のズレも見えてきます。
そして、報道と白書は併用することで補完的に機能してくれます。
たとえば白書が示すマクロの傾向を踏まえつつ、報道記事からミクロの現場の声を拾えば、記事の中で動きが出ます。「誰が、いつ、何を、どの立場で語ったか」を読み取る訓練としても、これらの情報源はとても優れています。
データと人の声、制度と感情。その交差点を探るために、報道と白書は欠かせない素材です。
7. 公的統計を使う
情報の説得力は、言葉の力だけでは生まれないこともあります。
時に、確かな「数字」が支えとなることで、主張は初めて地に足のついたものになります。
その意味で、官公庁や信頼性の高い機関が発表している統計データはリサーチにおいてきわめて重要な情報源です。
数字の推移を追うことで時系列の変化に気づいたり、属性別に分解してみることで、見えなかった傾向が立ち現れたりするためです。
たとえば総務省統計局の国勢調査、経済産業省の産業構造白書、内閣府の世論調査、厚労省の雇用統計など。これらの公的な統計は、データの信頼性が高く、更新頻度も明確で、出典としての強度があります。
たとえば、「20代の◯◯に関する意識変化」や「高齢者の単身世帯比率」など、構造的な主張を立てたいときに、一次統計の存在は欠かせません。「ネットで見つけた誰かの声」ではなく、「〇〇白書(20XX年版)によれば…」という一文を加えるだけで、記事の重心はぐっと安定します。
また、統計を見ることで、思い込みを手放す契機にもなるのです。
自分の肌感覚とは違う数字に出会った時、なぜそうなるのかを考えることで記事に複眼的な視点が生まれます。それは「一見当たり前と思われていることを、数字で検証する」視点でもあり、構成のなかで深みをつくるために非常に有効です。
加えて、統計の読み方にも工夫が必要だと考えています。
「統計を読む」というより、「統計と対話する」感覚を持つと、記事の奥行きが一段変わってくるのです。
信頼できる数字があると、文章は強くなります。
数字に依存するのではなく数字を自分の視点で読み解く力を持ってこそ、それは本当に意味のあるデータになるのだと思います。
結びに:千の情報にあたり、百の仮説を当て、十の草案を練り、「一つの記事」を作る
長々と書いてきました。これで最後です。
千の情報にあたり、百の仮説を当て、十の草案を練り、「一つの記事」を作る。これは私がリサーチをするとき、記事を書くときに心のなかでそっと唱えている言葉です。
自分のために私が勝手につくった、いわば「誇張気味の標語」です。サボりたくなる自分への抑止でもあり、誠実な書き手でありたいという願いでもあります。
実際、千の情報にあたることも、百の仮説を立てることも、十の草案を練ることも、なかなかできることではありません。私自身、それが本当にできた経験はまだありません(すいません)。
けれど、それでもこの言葉を意識していたいのです。
たったひとつの小さな記事の背後に、狂気にも似たリサーチがあることが大事だと思うのです。
書きすぎて削ぎ落とし、集めすぎて一点に絞り込むような、過剰な誠実さが裏にあるからこそ、文章には「重みのある静けさ」が宿ると信じています。
結局のところ、リサーチとは、正解に近づく行為というよりも、ぼんやりしたものにひとつの形を与える仕事なのだと感じます。
大量の情報に触れ、迷い、問いを持ち続け、構造を組み立て、言葉にしていく。それは書き手にとっても思考を形にする行為であり、時に自分自身を見つめ直し成長させる行為でもあるのです。
だから私は、調べることをやめたくないし、書くことからも逃げたくありません。
「千の情報にあたり、百の仮説を当て、十の草案を練り、一つの記事を作る」。
これは、派手な成果ではなく、極めて地味な手つきで丁寧に世界を見つめ直す、その態度を忘れないための結びの言葉でもあります。
さて、ずいぶん長々と書いてきましたが、これで終わりにします。
書きすぎて、正直、腱鞘炎になるかと思いました。
けれど、たとえほんの一文でも、一言でも、誰かのリサーチや執筆の助けになれば。
そう願いながら、そっと筆を置こうと思います。