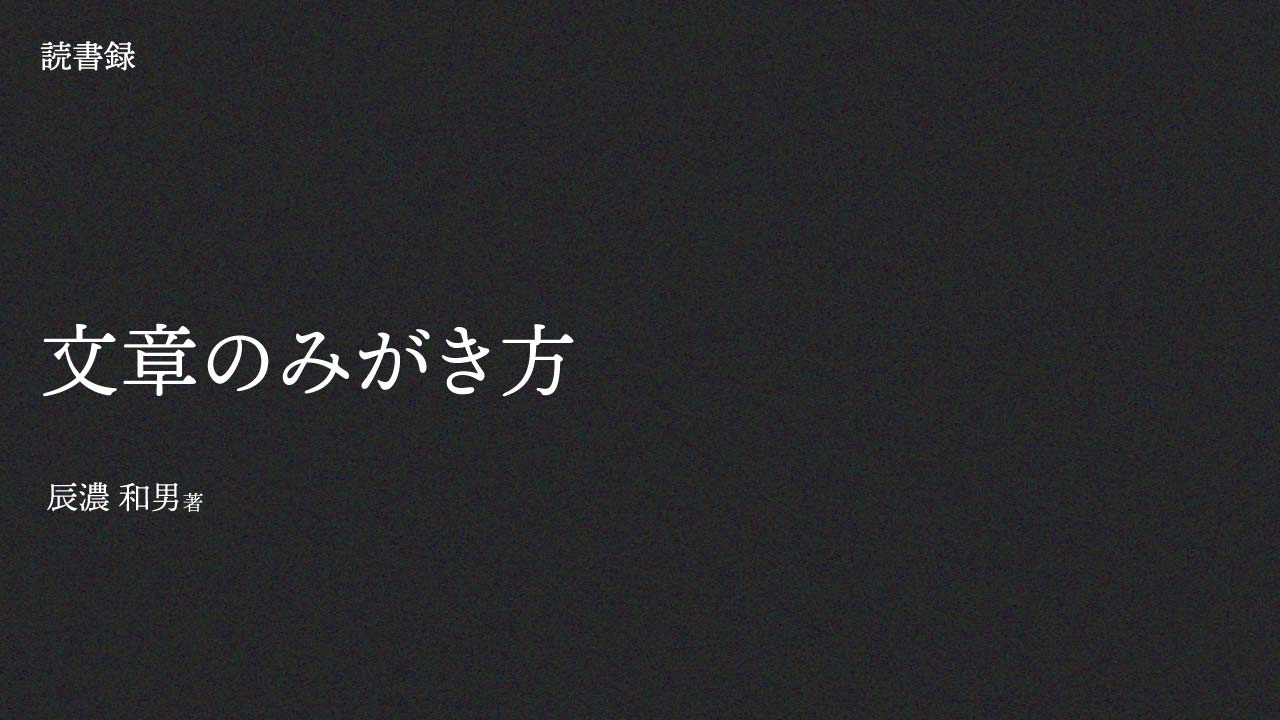弊社では半年ほど前から各人が週に1〜2回を目安に、自分の学んだことや感じたこと、伝えたいことをリトルプレスと称して発信しています。
文章を書くという行為は、机上で筆を取り、文字をしたためる以上に、そのもっと前の段階が非常に大切であることをとにかく痛感するばかりです。
とにかく読むこと、毎日書くこと、そして学ぶこと。
クライアントワークとしての記事執筆以外でも、文字を綴るという行為が日常の一部になりつつある今、改めて「書く」という行為を見直すきっかけを与えてくれた一冊でした。
毎日書く
毎日続けることは本当に大切です。
サッカー、野球、ピアノ、バレー、そろばん…何でもそうですが、意図しない空白期間ができると、その空白期間で失った感覚を取り戻すための時間がかかります。
何の領域においても同じことが言えるかもしれません。書くという行為も然りです。
その失った時間を取り戻す気力が出ないからと、そこで継続を諦めてしまうこともあると思います。恥ずかしながら、私自身もその手の挫折は数知れません。
目標を立て、期限を切ることは重要ですが、殊「書く」という行為については、初めからあまりに過大な目標設定をする必要はないと思います。
いきなり富士山の剣ヶ峰登頂を目指すのではなく、まずは小さく刻んでいくこと。
目を見張るような素晴らしい文章である必要はなく、気負わず、まずは身の回りの出来事を綴るだけでも十分なのかもしれません。日記や雑記でも良いと思います。
大切なのは行住坐臥のように「書く」を「日常」にすること。それでも毎日息をするように続けるのは苦痛を伴うものです。その苦痛を取り去るのもまた、「書く」ことだけなのが、難しいところですが。
乱読し、その中から精読する
書き手としての自分を鍛える上で、文字を書く行為と同じくらい大切なのは「読む」ことです。本書に記載されている内容をそのまま借りるならば「乱読」でしょうか。
言葉の持つそこ知れぬ力を体験するには、とにかく色々な本を手に取って読むしかありません。その力がそのまま文章力、表現力につながることもあるからです。
実は、私は昔から一冊読み終えるまでの時間がとても長く、一般的な読書好きの方と比べると、表現に触れる面積が圧倒的に少ないのが欠点でした。
「精読」の名の下に正当化してきた節があるのですが、やはり読書量の多い弊社スタッフのしたためた文章と自分の文章を見比べるとよく分かります。パターン化した表現の頻出、推敲の甘さなど書き手としての能力の差が顕著に現れています。
乱読と精読は本来、二律背反ではありません。乱読したものの中から、精読したい本が見つかることもあります。
まずは少しでも興味を持った書籍を手当たり次第読み下し、書籍自体が提供するあたらしい世界、そして文章表現に触れる機会を増やすこと。
あまり考えすぎずこの書籍を読み通すことを持って、私の「乱読」の第一歩にできればと思っています。
書き下し、直し、削り、整える
一度書いた文章を「直す」ことには、どこか自分自身を否定するような感覚がつきまといます。けれど、本来「直す」ことは、「よりよく伝える」ための営みであり、自分の内側と向き合いなおす内省的な作業でもあります。
最初の書き下しでは、勢いに任せて言葉が溢れ出すこともある。それをひとたび寝かせて、翌朝の目で読み直してみると、思いのほか饒舌だったり、逆に伝えたいことの核が埋もれていたりすることに気づきます。
私はよく、原稿の末尾に「この部分、言いたいことはここじゃない」と自分に向けた注釈を残すようにしています。そうすると、一度は通り過ぎてしまった論点や感情を、もう一度拾い上げることができるからです。
文章を「削る」ことは、勇気の要る行為です。しかし、不要なものを削り取ったあとの文章には、書き手が本当に伝えたかった「核」の部分が残ります。
この「削り整える」過程こそが、文章に輪郭を与え、余白にまで思いを託せるようになる瞬間だと感じています。
「抑える」こと
頭からこぼれ落ちてきた文章をそのまま出力すると、パワーや鮮烈さを感じるありのままの文章が生まれることがあります。これ自体は決して悪いことではないのですが、呼吸を整え、一拍置いてから眺めてみることもとても大切です。
感情に任せて綴られた文章が、過大な表現だったり、独り善がりになってしまっていることもあります。
私も、特に自分の体験を言葉にする時、デスクトップリサーチや伝聞よりも強い言葉を使ってしまう傾向にありました。つい先走ってしまうのが悪い癖です。
俳句の世界でも「情」を敢えて作品の背後に隠すことの奥ゆかしさが説かれてきました。剥き出しの感情的な表現よりも、感情の昂りを抑えた方がむしろ物事の本質が滲んでくることもあるでしょう。
力任せに書いた後、一拍置いてみること。
時に「低い視線」で
時に「書く」という行為には、自分を高い位置から語るような視点が混じってしまうことがあります。
とりわけ、何かを伝えよう、良いことを言おうという気持ちが強いときほど、自分でも気づかないうちに、読み手より少し上の立ち位置から書いてしまう。
けれど、辰濃さんはその姿勢に対して、時には「低い視線」で書くことの大切さを説きます。
それは、謙遜というよりも、むしろ等身大でいること、物事を見上げる角度で見つめ直してみること。自分の未熟さを認めることでもあり、世界の広さを改めて受け入れることでもあります。
私は書くとき、つい「うまく伝えなければ」という意識が先行して、言葉に無意識の鎧をまとってしまうことがあります。でも、そんなときこそ、少し腰を落として、自分の中にある実感や疑問、迷いに目を向けるべきなのかもしれません。
「低い視線」で書かれた文章には、肩の力が抜けた誠実さと、少し泥臭い「想い」のようなものが宿る気がします。
借り物でない、自分のことば
AIの発達により、それらしい文章は誰にでも生成できるようになりました。
けれど、そこに「その人らしさ」があるかと言えば、そうではありません。
辰濃さんの言う「自分のことば」とは、誰かの言葉をなぞっただけではたどり着けない、経験や感情と地続きの言葉です。それは決して技巧的なものではなく、自分の目で見たこと、耳で聞いたこと、心が動いた瞬間にだけ生まれるものだと思います。
たとえば、自分の暮らしや仕事の中でふと気づいたことを、自分の体温のままの言葉で書き留めてみる。
その時の戸惑いや躊躇いも含めて、無理に整えずに残しておく。そうした「未完成さ」こそが、自分の文章のかけがえのなさにつながるのかもしれません。
読み手としての自分を鍛える
書く人である前に、よい読み手でありたいと思います。
文章に限らず、映画でも写真でも、誰かの表現に対して丁寧に向き合うことは、自分の中の感受性を呼び覚ます行為です。
特に、辰濃さんが説くように「読み手としての自分を育てること」は、書き手としての厚みを増すためにも欠かせません。
読んで、感じて、問い返す。その繰り返しの中で、言葉はより立体的になっていくと信じて。