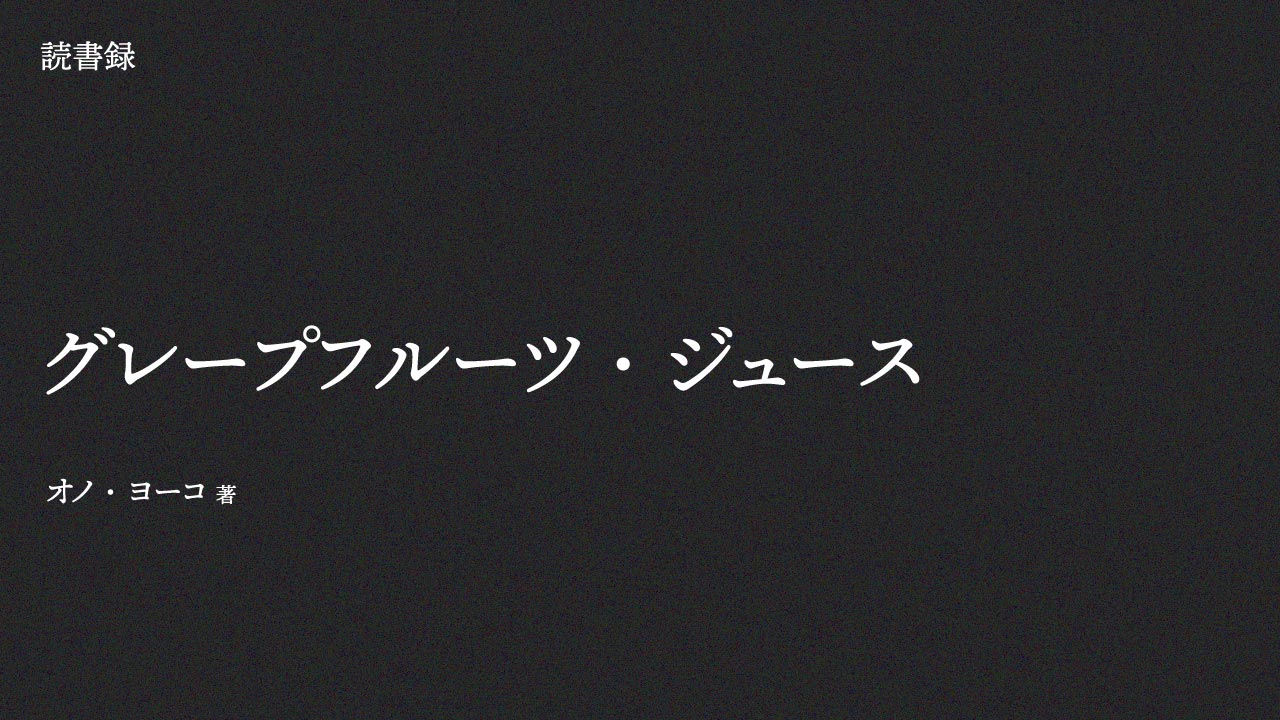オノ・ヨーコによる一冊、『グレープフルーツ・ジュース』。
最初にこの本を手に取ったとき、戸惑いがありました。ページをめくっても、「物語」が立ち上がってこないのです。
そこに並んでいるのは、文章というより指示。
やってもいいし、やらなくてもいい。短くて、謎めいた行。
読書というより、こちらが読書の外へ呼び出されているような、そんな、どこか落ち着かない感覚を覚えました。
しかしページをめくるうちに、その一行一行に惹かれていきます。
どこか祈りに似た指示が並ぶ、そんな本を読んで。
イマジンの前夜、繰り返される祈りのような言葉
『Grapefruit』は、1964年にオノ・ヨーコが東京で自費出版した小さなアーティスト・ブックです。正方形の白い冊子、初版はわずか500部。のちに1970年、サイモン&シュスターより英語版が刊行され、ジョン・レノンによる序文が添えられたようです。
私が手に取ったのは『Grapefruit』の中から代表的な「指示詩(instruction pieces)」を選りすぐって翻訳した日本語訳版、1988年初版の『グレープフルーツ・ジュース』です。
本書は、いわゆるインストラクション(指示)の連なりで構成されています。
読むことで完結するのではなく、読む人の想像や行為によって完成していく、一風変わったテキスト集です。
たとえば、こんなふうに。
太陽を見つめなさい。それが四角くなるまで。
あるいは、
隠れていなさい。
みんなが家に帰ってしまうまで。
隠れていなさい。
みんながあなたを忘れてしまうまで。
隠れていなさい。
みんなが死んでしまうまで。
また、こんな一節もあります。
想像しなさい。
千の太陽がいっぺんに空にあるところを。
一時間かがやかせなさい。
それから少しずつ太陽たちを空に溶けこませなさい。
ツナ・サンドウィッチをひとつ作り食べなさい。
その指示は命令ではなく、どこか「許可」に近い手触りを持っています。
行間に広がる白さはふとした寂しさを呼び込みますが、読み進めるうちにその寂しさはやわらぎ、やさしさへと縁取られていくように感じられます。
繰り返される「想像しなさい」という呼びかけは、ジョン・レノンの名曲《Imagine》の着想のひとつとも言われています。
世界をすぐに変えようとするのではなく、見え方の角度をほんの少しだけずらすこと。
その静かな一行が、読者の内側で音楽のように鳴りはじめ、現実の手触りをわずかに変えていくような、そんな本です。
優しさ、過激さ、ユーモア、反転、祈り
インストラクションは、命令ではありません。むしろ、それは「許可」に近い言葉のように思えます。
日常の文法を少しだけずらし、世界の見え方をわずかにやわらげるような、そんな許可。
『グレープフルーツ・ジュース』に並ぶ一行一行は、そのための小さな合図です。
この本は「必ず実行せよ」とは言いません。「やっても、やらなくてもいい」のです。
その緩さの中に、逆説的な強さが宿っています。概念を押しつけず、感受性の余白をそっと差し出す本だからこそ、読む人の数だけ異なる世界が立ち上がるのだと思います。
そしてこの本に登場するインストラクションの多くは、ある種のシュールさとでも言うのか、可笑しみを帯びています。
それはときに拍子抜けするような短さで、ふいに現実を手放させるような表現です。しかしそれらは、現実を軽んじるための「装飾的なユーモア」ではありません。
むしろ、都市の騒音や、戦争の気配、メディアの喧騒といった現代の厚みを、声高に否定することなく、そのまま反転させていくような静かな回路のように映ります。
そこには、シュールな視点もあり、祈りのような静けさもあり。読むたびに角度を変えながらも、あとに残るのは優しさに似た温度です。
あえて命じないからこそ届く。従わせるのではなく、預けてくる。その手つきのなかに、私は、この本のいちばん静かな過激さを見ています。
フルクサスの中で生まれた祈りたち。オノ・ヨーコという生き方について
この作品が生まれた背景には1960年代という特異な時代状況があります。
当時のアメリカでは、伝統的な美術の枠を壊そうとする前衛的な運動が盛んでした。
彼女がニューヨークの前衛芸術シーンに登場したのは1950年代末から60年代初頭。
この時代、アートは「もの」から「こと」へと変化していました。ものを作るのではなく、観念を提示する。完成品ではなく、関係性をデザインする。
そんな時代の空気のなかで、オノ・ヨーコは「インストラクション・アート(指示芸術)」というスタイルにたどり着きます。
中でも「フルクサス(Fluxus)」と呼ばれる芸術運動は、作品という「完成されたモノ」ではなく、行為やアイデアそのものをアートとして捉えようとするもの。オノ・ヨーコはこのフルクサス運動の中心人物のひとりとして活動していました。
オノ・ヨーコは、日本とアメリカという異なる文化の狭間に身を置いてきた人物です。
安田財閥の家に生まれ、戦時中は疎開を経験し、戦後はアメリカへと渡ります。その境遇は、華やかでありながらも、どこか常に疎外感や孤独を抱えるものだったと言われています。
後年、ジョン・レノンと出会い、パートナーとなった彼女は、「ミューズ」ではなく「共作者」としての立場を貫きます。ジョン・レノンとの共作やパフォーマンスにおいても、この『グレープフルーツ・ジュース』の思想、すなわち「行為する前に、まず想像せよ」という態度は一貫して流れています。
たとえば“ベッド・イン”や“ウォー・イズ・オーバー”といった平和運動も、根底には「イメージすることが現実を変える」という思想が横たわっていました。
彼女はこの本に“Grapefruit”というタイトルを付けましたが、オレンジとレモンの交配種であるグレープフルーツが、「東洋」と「西洋」、「男性」と「女性」、「論理」と「直感」など、さまざまな二項のあいだに立つハイブリッドな存在であることにかけた象徴とも解釈されています。すなわち、それはオノ・ヨーコ自身を象徴する言葉でもあったのでしょう。
この本に見られる簡素で静かな言葉の数々は、まさにそうした彼女自身の内面と、外の世界との繋がりを試みたものだと言っていいかもしれません。
さて、この作品の特徴は、「命令文」であるはずの指示が読者に強制をまったく与えない点にあります。
むしろその逆で、読む人の想像や感性に委ねることで、自由に解釈され、自由に受け取られていくのです。
「転居通知を出しなさい。あなたが死ぬたびに。」という言葉が、ある人にはユーモラスに映り、またある人には祈りのように響くかもしれません。
正解も不正解もなく、それぞれの心の動きがアートそのものになる。それが『グレープフルーツ・ジュース』の本質です。
一冊の本であると同時に、オノ・ヨーコの思想と生き方のマニフェストのような存在のように思えます。ページをめくるたび、そこにある言葉の奥から、ひとりの女性が自分の輪郭を確かめながら世界に働きかけていく、静かな決意が感じられます。
結びに:燃やせない一冊について
『グレープフルーツ・ジュース』は、読む人を信頼している本だとも思います。
すべてを説明せず、押しつけず、完成させようともしません。余白のまま、そっとこちらに視点を差し出してきます。
読む側に解釈も、実行も、委ねられている不思議な本です。その結果がどうであっても、決して咎めることはありません。
できなくても、忘れてしまっても、たぶんそれでいいのでしょう。
世界は今日も、何事もなかったように続いていきます。
でも私はほんの少しだけ、見る角度を変えてみようと思います。それだけで、世界の輪郭が少しやわらかくなる気がするからです。
最後のページには、たった一行の指示が記されています。
この本を燃やしなさい。読み終えたら。
私はまだこの一冊をそっと抱えたままにしています。
燃やさずにいることもまた、この本がくれた「自由」のひとつだと信じて。