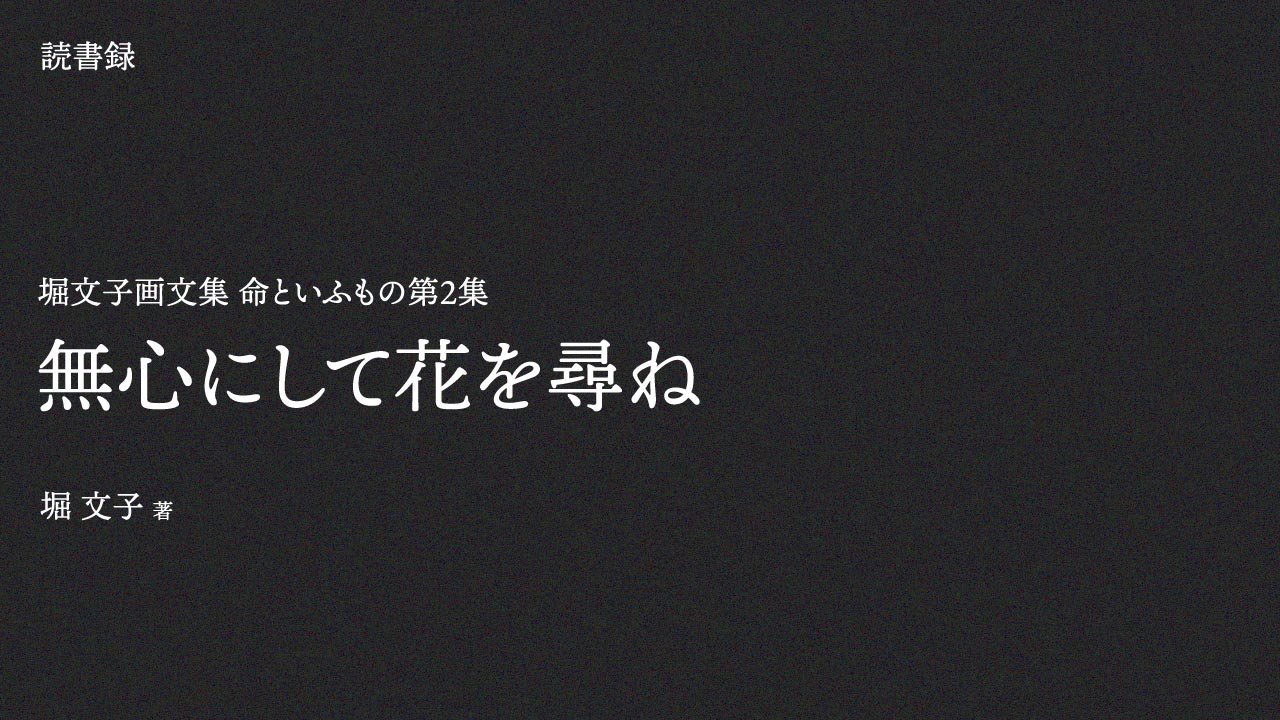私の手元に、一冊の画集があります。
『堀文子画文集 命といふもの第2集 無心にして花を尋ね 』。
いつだったでしょうか。古本屋で偶然出会った、日本画家である堀文子さんの作品集です。
一目見た瞬間、言葉にしがたい吸引力を感じ、特に迷うこともなく手に取りました。その時はただ「なんだか美しい本だな」という感想だけで、深く考えるには至りませんでした。
ある日、ふと気まぐれに本棚からこの画集を取り出し、改めてページを繰ってみたのです。
驚きました。
日本画の線と色彩が醸し出す静謐な空気。そこに添えられた言葉の奥に広がる深い余韻。
絵そのものの美しさはもちろんのこと、堀文子さんの人生観から紡がれる言葉のひとつひとつに、思いがけないほど強く胸を打たれました。
これほどまでに人生を味わい、このような高みにまで辿り着くことは果たして自分にも可能なのだろうか、と。
一枚一枚の絵と、一行一行の言葉。そのすべてに、憧れにも似た想いを抱きながら私はゆっくりとページをめくっていきました。
堀文子という「生き方」に触れて
と、語っておいて大変お恥ずかしい話ですが、無教養な私は堀文子さんのことを存じ上げませんでした。
この作品集を通して初めて彼女の人生の一端に触れたわけですが、そこに描かれていた生き方の美しさに私は大きく心を揺さぶられました。そして、あれこれと調べを進めていくうちに、深い哲学を土台とした人生を歩まれた方なのだと次第に分かってきました。
例えば、
争いに関わりたくないがために美へと近づいていったという彼女の言葉。「美は何の役にも立たない」という、現代の功利主義とは真っ向から対立するような視点。
バブルの只中「恥知らずの国に成り下がり、品位を失ったこの国で死ぬのは嫌だ」と、69歳にしてイタリアへ移住するという気骨。
一つの場所に安住することなく、絶えず新しい感動を求めて旅をしながら居を変える「一所不住」という信条。
庭の片隅に咲く名もない雑草たちを「名もなきもの」というテーマにし、主役にはならないけれど逞しく生きる小さな生命を讃え、その姿を表舞台に残そうとする創作への眼差し。
晩年まで創作活動に情熱を注ぎ続ける生き方。
都会的な賑やかさよりも、自然の中にある暖かな静謐さを求めるような、そんな歩み方。
「誰もがひとりが寂しいと言うが、人といれば本当に寂しくないのか?人はそもそも孤独なのだ」という在り方。
なんと粋で、なんと見事な生き方なのでしょうか。私自身、こんな生き方をしたいものだと心底思います。
静謐な言葉が綴られたページを一枚ずつめくるたびに、堀文子さんの生き方が、私の胸の内でいつしか憧れへと変わっていくのを感じました。
彼女の人生の足跡を辿りながら、自らの歩みをそっと振り返る。そんな時を過ごすほどに、一枚一枚の絵と言葉が、私の心をさらに深い静けさへと誘ってくれるようでした。
生きることとは何なのだろうか
『花木と共に』『旅へ』『「老い」と生きる』。
この三つの章から成る一冊には、それぞれに短い作品が収められています。どの作品も驚くほど美しく、どの作品にもしんとした静寂の気配が漂っているように感じられます。
穏やかに流れてゆく日々の欠片をすくい取ったページ、異国の文化を鮮やかに描き出すページ、生と死の狭間に思いを寄せるページ。一枚一枚をめくるたび、穏やかながらも奥深い光景や言葉が、そっと心の奥底へと滲み込んでくるようです。
なかでも心を打たれたのは、『「老い」と生きる』の章にある「老い」という作品。その中で触れられているのは、江戸時代の禅僧・良寛の姿でした。
山中の小庵にとじこもり、孤独と寂寥の中で己れを磨いた良寛。経典を説かず、己れの思想を押し付けぬその生き方そのものが美であり、温かく澄み切った脱俗の芸術だった。
この孤高の禅僧をこうまで美しく描き出す筆致に、思わず息を呑みました。
日々の暮らしの中で、私たちは誰かに何かを期待し、あるいは押し付けながら生きています。それゆえに、良寛のような生き方は自分にはとても真似できないのではないか。この一文からそんな畏れにも似た衝撃を感じたのです。
そして堀文子さん自身の生き方にも、良寛を想わせる気高さがあるように思えてなりません。
もう一つ、忘れがたい作品があります。同じく『「老い」と生きる』の章にある「過ぎ去った時」。
「人生の大半は、もはや思い出すことさえできない。自分の中に鮮明に残っている出来事など、今まで生きてきた中のほんの一握りにすぎない」。
そんな主旨の文に続き、次のように綴られます。
日毎に起きる事件を無我夢中で片付け、茫然と佇み、怒り、悲しみながら何万という日を迎えては送ったわけだ。どんな時にも諦めず、大まじめに考え込んで生きて来た事は確かだ。記録もせずに送った膨大な時間。取り返しのつかないその無駄な日々は堆肥となって、私を育ててくれたのかも知れない。
しくじった時、無念の時、誰にも助けて貰えぬ苦痛の中で、大切な思い出は生まれる。
それが重要な節々となって私の生涯を紡いでくれたが、忘れ去った名もない日々が、私という一本の老木を養ってくれた大地だったように思う。
このあまりにも非凡な一文のあとに、私のあまりに凡庸な感想を添えるのは気後れするほどですが、ここまで「日々を大切に生きねば」と強く感じさせられた文章は、そう多くはありませんでした。
生きるとは何なのか。美しく生きるとは、いかなることなのか。
窓の外の景色をぼんやりと見つめながら、そんな問いが心に浮かびました。
今目の前にある景色すら、いつかは記憶の彼方へこぼれ落ちてしまうのだろうか。そう思うと、なんともいえない切なさとともに、より一層しっかりと景色に目を凝らさずにはいられませんでした。
その高貴な生き方に触れて
晩年まで旅を続け、創作を続けた堀文子さんの凛々しい人生。それは私にとってとても眩しく映りました。
「群れない」「慣れない」「頼らない」。
堀文子さんの信条なのだそうです。
人と群れると、いつのまにか周囲に合わせることに気を取られ、自分らしさが失われてしまう。結果、群れに迷惑をかけることにもなりかねないので、できるだけ一人でいることを選ぶ。誰かに頼ってしまうと、その人の肩車に乗るような形で、自分の器以上のことをしてしまう。そして、そうするうちに本来の自分を失ってしまう。
なんと高貴な生き方だろうと思います。
彼女にとって、孤独は決して後ろ向きの孤立ではなく、自分を研ぎ澄まして自由を得るための積極的な選択だったのでしょう。
それはまるで禅の「無心」に通じる境地のようにも思えます。余分なものを削ぎ落としたとき、初めて内なる好奇心と向き合うことができる。そんな深い哲学を、彼女はその生き方で示しているかのようです。
最後に、本書からの一文を引かせてください。
今の私は、何事も珍しく、驚くことが増えている。
やがて死ぬ気色も見せず鳴く蝉のように、生きている限り私たちの眼は美しい物に感じ、脳は不思議を見付け、考え、好奇心を燃やす。筋肉が衰え目もかすみ、耳も遠くなるが心は衰えず、死を迎えるまで私たちは考え続ける筈だ。若い頃、観念で想像した底知れぬ死の恐怖がいつしか消え、老いを生きる私の体の中で生と死が穏やかに共存しているのを感じる。
始まりの生と終わりの死が一つの輪になっていて、永劫に続く命の輪廻が吾が身の中にあり、それを静かに見詰めている自分に驚いている。
九十の齢を迎えた今、逆らう事を忘れ、成り行きのまゝに生きる安らぎの時が、いつの間にか来たようだ。
なんと見事な在り方なのでしょうか。かくも素晴らしい生き様に、ただただ感嘆の念を禁じ得ません。
死は例外なく全ての人に訪れます。もちろん、私にも。
願わくば、自分もまた、このような静かな視点をもって生の終わりを見据えていきたいものです。
その時まで、穏やかな時の流れに寄り添いながら、どれだけ自分自身と深く向き合い、かけがえのない一日一日を味わうことができるでしょうか。
いま私に残された時間がどれほどなのかは分かりません。
美しく豊かなものを探しながら、ほんの少しでも生きた証を遺せるように。そう願いつつ、ひとつひとつの瞬間をしっかりと噛み締めながら歩んでいきたいと思います。