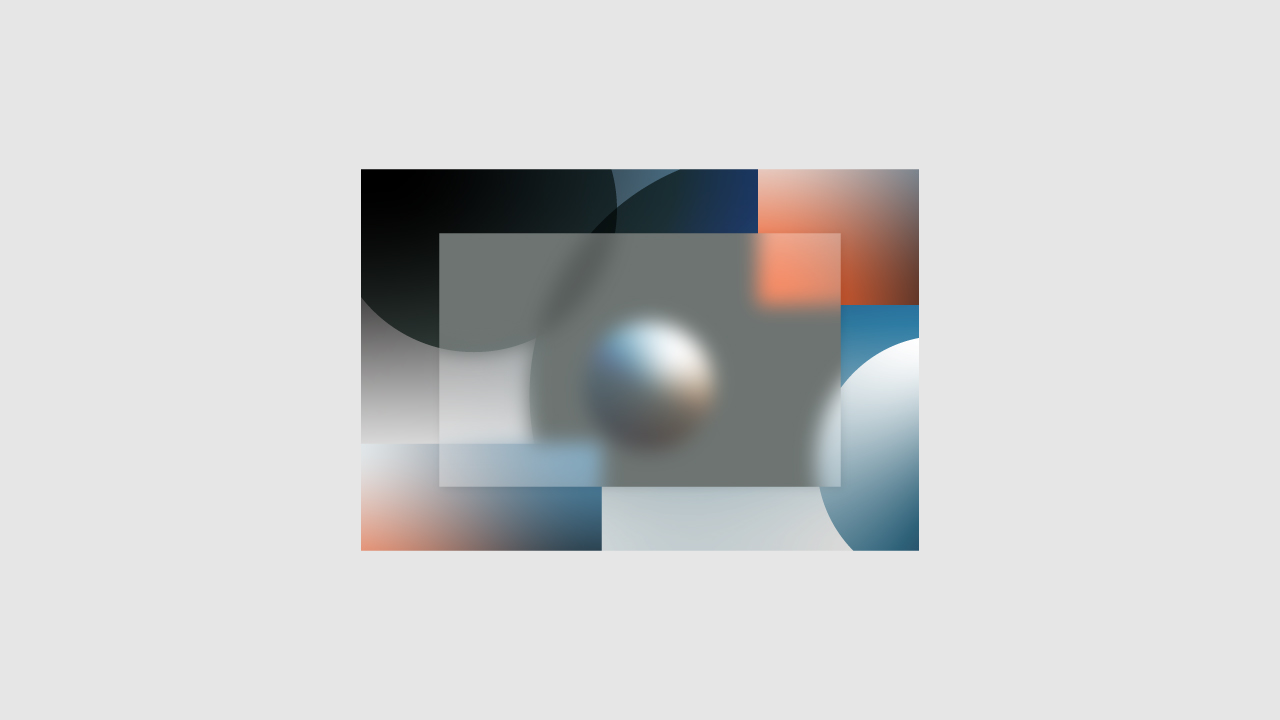実務を続けていると、「すぐに使える学び」と「すぐには役立たないけれど、思考を豊かにする学び」のどちらを優先すべきか、迷うことがあります。
前者は日々の判断を支え、後者は視野を広げてくれる。
どちらも大切だとわかっていても、バランスを取るのは簡単ではありません。
デザイナーという職種の関係上、どうしても実務に偏りがちな自分の経験を振り返りながら、二つの距離を行き来する学びのあり方について自分なりに改めて考えてみました。
行動のための学びと、思考のための学び
仕事をしていると、学びにも二つの方向があると感じます。
一つは、明日からの行動に直結する「近くの学習」。もう一つは、すぐには役に立たないけれど、思考の土壌を耕してくれる「遠い参照」。
前者は効率的で、成果につながりやすいですが、後者は非効率で、すぐには意味が見えません。けれども、どちらが欠けても仕事はどこかで行き詰まります。
私はどちらかといえば、後者を後回しにしてきた方です。新しいツールや制作フロー、技術への理解など、目の前の課題を解くための知識ばかりを追いかけてきました。
それ自体は悪くありませんが、ある時ふと「なぜそれをやるのか」という根っこが痩せていく感覚に気づいたのです。
近くの学習は、生きるための筋肉
とはいえ実務の知識は、やはり欠かすことはできません。
現場では、理想よりも先に「いかに具体的に動けるか」が問われます。納期や仕様があり、迷っている余裕はありません。
なので私は、まず“筋肉”をつけることが大事だと思っています。細かな仕様理解、データの見方、ユーザーの動線。そうした地道な積み重ねが、判断の支えになります。
泥臭くても、動けることはやはり強いです。それは私が何度も実感してきたことでもあります。けれど、筋肉だけでは長く走れません。
判断が「正解を当てるための作業」になってしまい、柔軟さを失っていく。それが“近くの学習”の限界でもあります。
遠い参照が与えてくれる余白
先行きがなんとなくぼんやりして見えてしまう。行き詰まっている感覚がある、そんな時だからこそ、もう一方の“遠い参照”を意識的に取り戻したいと思うようになりました。
- 業務とは直接は関係のない分野の本を読む
- 展示に足を運ぶ
- 興味のなかったジャンルの音楽を聴く
それらは仕事とは関係ないようでいて、後からじわじわ効いてきます。
たとえば哲学や文学の言葉に出会うと、普段の「なぜ」を別の角度から見直すことができます。思考の呼吸が深くなり、作業の中での“選び方”が変わることもあります。
遠い参照は、成果を急がない時間です。でもその“無駄”のような時間のなかで、感覚の精度が少しずつ上がっていく。結果として、日々の判断や言葉の選び方に余白が生まれます。
即効性はないけれど、確実に土を肥やしてくれるものだと思います。
二つの距離を行き来する
結局のところ、どちらかに偏るとどこかで息苦しくなります。近くの学習だけでは、世界が狭くなる一方で、遠い参照ばかりでは、現実から浮いてしまう。
卵が先か、鶏が先か。
賛否両論あるかもしれませんが、私にとっては、まず実務の知識を磨くことが出発点だと考えています。実際に手を動かし、試行錯誤の中で「何がわからないのか」を知ること。
目の前のお客さんの困りごとを解決するには、どうしても手札の数と深さが必要です。
手持ちの手札が少なかったり、その領域に対する知見が浅い場合、人はどうしても自分の理解できる範囲で世界を処理しようとします。「ハンマーを持つ人には、すべてが釘に見える。」とはよく言ったものです。
もちろん実務だけを追求していては結局先細りであることに変わりはありません。
実務に対する理解を深め、その上で、現状を少し引きで見て、自分の枠を問い直す。そして、問いただす際に必要になるのが、遠い参照なのではないか、と。
引きで物事を見るとき、たとえ直接関係のない分野の知識であっても、思いがけずアナロジーが効くことがあります。建築の話から情報設計を、哲学の一節からチームの在り方を考えることだってある。遠い参照とは、別の角度から自分の思考を照らし返すための灯のようなものなのだと思います。
結局のところ、近くの学習が足場を固め、遠い参照が視野を広げてくれる。どちらか一方ではバランスを失ってしまいます。
現状、私はどちらも足りていない状態であることを自覚しつつ、やや「遠い参照」が不足気味であることは否めません。地に足をつけたまま、少し遠くを見る癖をつけていければ、もう少し視界が変わってくるのではないかと思います。
仕事に追われる日々のなかでは、どうしても近くの学習に意識が向きがちです。けれど、その一歩先にある“遠くの視点”を思い出せるだけで、手を動かす理由や意味が少し変わる。そうした小さな変化を積み重ねながら、行き来する感覚を育てていけたらと思います。