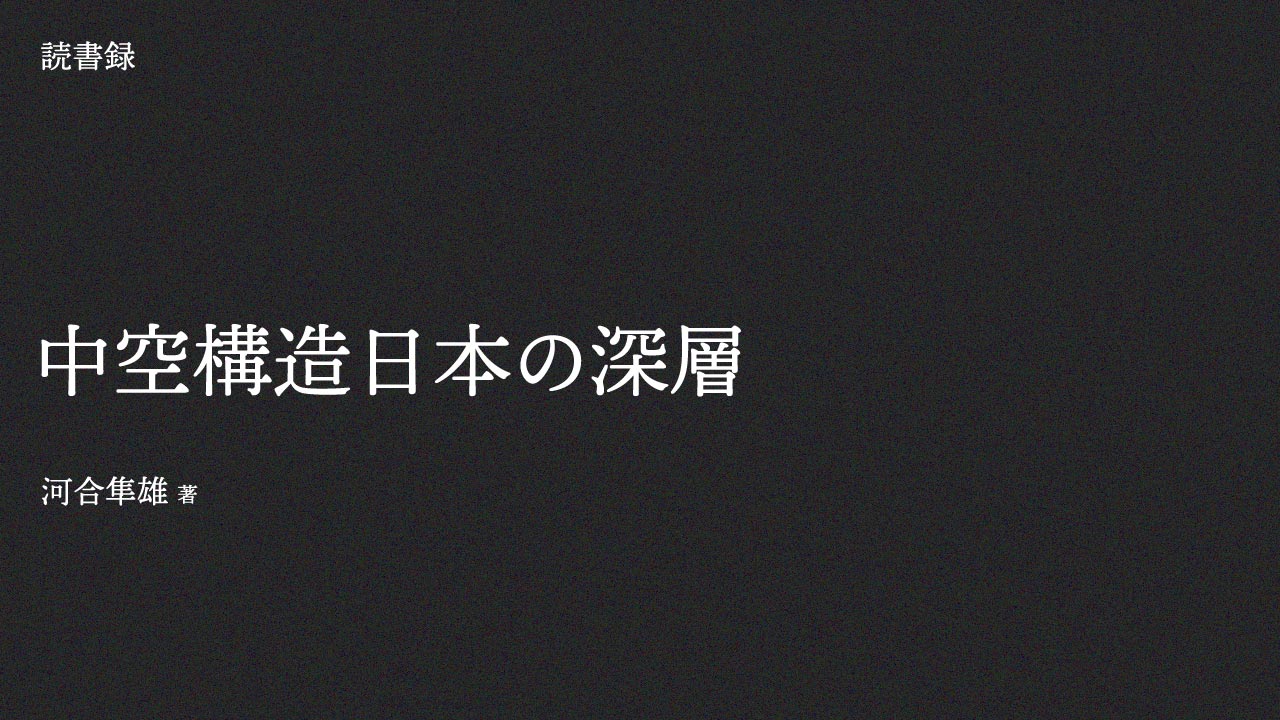「中空構造」。
これはごく簡単に言えば中心に何もない状態を指す言葉、概念です。しかしこれは単なる「空洞」や「空白」というわけではなく「中心が固定化されず、様々な要素がバランスを取り合う構造(場)」という表現が適切かもしれません。
中空構造、特に日本における中空構造は「不確かさ」によるネガティブな側面と、「多中心性」によるポジティブな柔軟性の両側面を併せ持つように思います。
西洋の中心統合型構造と対照的な日本の中空・均衡構造は、相反する要素が精妙なバランスを保つ特異な構造を有しており、真ん中が「空」であるという特別な社会システムを形成しています。この空の中心こそが、日本文化の適応力と柔軟性の源泉となっている、そんな考え方です。
私は編集という職業に携わる上で、この中空構造という思想を日々強く意識しています。自分は何者でもない、そのような「空性」を深く認識しているからこそ、多様な視点や感性を柔軟に受け入れ、創造的な編集作業が可能になると思っています。空であることは単なる不在を意味するのではなく、無限の可能性を秘めた豊かな「場」的なものだと思うのです。
今回は河合隼雄の論考が収録されてる『中空構造 日本の深層』から、「空」であることの奥深い尊さと創造的可能性について考察してみたいと思います。
「中空構造」と「空」
河合隼雄は、ユング派の臨床心理学者として、神話や昔話の分析を通じて日本人の深層心理に鋭く迫った思想家です。
1970年代から80年代にかけて、日本社会では家族形態に関する社会問題など様々な問題が顕在化していきました。
あくまでも一例ですが、高度経済成長のピークを過ぎた1970年代半ば以降、いわゆる過疎化・核家族化・父親の不在感が家庭問題として注目され始め、その背景として工業化社会からポスト工業化社会への移行があったようです。
このような例に限らず実に様々な社会問題があったようですが、多くの社会課題の根底に対して「科学の知」だけでは十分に捉えきれない何かがあるのではないかと、河合はそう洞察するようになります。
この時期は高度経済成長を経た日本が自らのアイデンティティを根本から問い直す時期でもあり、欧米との文化比較を軸とした「日本人論」が知的世界で活発に展開されていました。河合もまた、心理学的アプローチから日本人の精神構造を綿密に分析し、日本固有の特質を明らかにしようとしたのかもしれません。
その過程で、彼は日本人の心の原型風景を古代神話、すなわち『古事記』に探り、他文化とは一線を画する独自の構造を見出します。
この「中空構造」という創造的発想の背後には、日本思想における「空(くう)」の本質的重要性があります。仏教思想や禅の伝統においては、「空なるもの」そのものに創造の契機を見出す考えが根付いており、たとえば西田幾多郎が提唱した「絶対無の場所」などもその哲学的表現だと思うのです。この中空構造論も、こうした日本の豊かな思想的土壌の上に展開された、知的創造の結晶であると感じます。
中空とは「無」か、「有」か
中空構造は、一見すると内部が空っぽであることから「無」を象徴しているかのように思われます。
しかし、その内側に本当に何も存在していないのか、あるいはむしろ特定の価値や機能を秘めているのではないかという問いは、決して単純ではありません。この問題は、仏教における「空」の思想や、西洋哲学の「虚無」に関する議論にも通じるテーマのように感じます。
仏教哲学で語られる「空」は単なる虚無や否定を意味するものではなく、固定された実体がないことを示す概念です。それは決して否定的なものはなく、例えるなら「無自性的」とでもいうのでしょうか。
この「空」であるがゆえに、そこにはあらゆる可能性が内包され、移ろいゆく現象や関係性が絶えず生起し得る。この視点を中空構造に当てはめるなら、外見的には「無」のように映るその空隙が、実は多様な機能や価値を生み出す創造的な基盤になり得るということになります。
例えば楽器の胴が空洞であることは音の共鳴に深く関わり、豊かな響きをもたらします。さらに、パイプやチューブの中を流れる空気や液体が、さまざまな機能を担うことを思い起こせば、「空いている」こと自体が一種のエネルギーや可能性を宿しているといえるでしょう。
中空構造は「何もない」ようでいて、実際には何らかの「働き」や「意味」を担っていることが多々あります。その意味では、外形としては「無」を想起させながらも、内実としては「有」の力を発揮する存在なのかもしれません。あるいは、中空構造そのものが「無」と「有」の境界を揺るがし、両者を包括するような次元を開示しているとも捉えられそうです。
西洋哲学に目を向けてみます。「虚無」はしばしば絶望や不在を連想させる概念として扱われてきました。しかし、その「無」が却って人間の自由や創造の源泉となると考えられる場合もあります。何もないように思える部分こそ、あらゆる新しい価値の萌芽を育む場である、という洞察です。
私たちの日常においても、頭の中が情報や思考で埋め尽くされていると、新しい発想を得る余白がなくなりがちです。しかし意図的に「空白」を作り出すと、そこに新たなインスピレーションが差し込んでくることがあります。中空構造が無意識のうちに担っている働きも、これと似ているように感じられます。何かが充満しているわけではないからこそ、あらゆる可能性を開く余地が生まれる、そんな場所として。
このように中空構造を眺めると、内部に空間があることは決して「空疎な無」で終わるのではなく、潜在的な力を宿す「豊かな余白」になり得るという視点が得られます。
しかし結局のところ、中空構造を「無」と断じるのは早計ですし、「有」と位置づけるには安易かもしれません。むしろ、中空構造は「無」と「有」のあわいにあり、両者の密やかな交差によって新たな価値を創出する「場」を生み出しているように思われます。その「輪郭を定めず、柔軟に揺れ動く線」こそが、中空性にとって重要なのかもしれません。
日本の様々な中空性
河合は日本神話、特に『古事記』に分け入り、神話の構造から日本社会の深層構造を読み解こうと試みました。
「中空構造」という概念は、神話にとどまらず、日本文化のさまざまな領域にも見られると指摘されています。河合自身は主に日本神話を中心に論じましたが、広範な文化的事例にもこの中空性は見て取れます。
例えば日本の神社建築。
拝殿から奥へと進むほど空間は簡素になり、最奥部にある本殿にはしばしば御神体として「鏡」が祀られています。しかしこの鏡は、何か特定の神像を映し出すためのものではなく、「何も映し出さない空(うつろ)を象徴するもの」という見方もあるようです。つまり、中心にあるはずのものが、むしろ”空である”ことによって最高の神聖さを帯びるという逆説的な構造がそこに存在するということですね。
とはいえ鏡にはさまざまな解釈があるため一般化することはできませんが、“何も映さない空”としての象徴性は、神社の中空性を際立たせる議論として興味深いのではないかと感じます。
さらに、日本の神々自体も、特定の場所に常駐する存在ではなく、折口信夫が洞察した「まれびと(客人)神」のように、必要なときに現れては去っていく流動的な存在として捉えられてきました。これもまた「固定的な中心」ではなく、一時的な顕現としての中心=中空性の美学を象徴する例かもしれません。
日本の美意識にも「中空構造」は深く根づきます。
例えば、茶室では何も置かれていない”余白”の美が重要視されます。そして禅の精神に基づく枯山水庭園では、石の間に広がる砂の空間が、見る者に多様な解釈を促す”空の領域”として存在します。
さらに、祭礼において担がれる神輿の中身は基本的に見ることができず、中が見えないこと自体が神聖性を際立たせている場合も少なくありません。連歌や歌会といった伝統的な詩歌の場においても、明確な主役を立てることなく、即興の応酬によって全体の調和を生み出すという繊細な構造が重んじられています。
これらの文化的実践はすべて、「絶対的な中心」がなくても秩序と意味が成立するという、日本文化に固有の”中空のバランス感覚”を体現しているようです。この独自の美学こそが、日本文化が持つ柔軟性と創造力の源泉となり、今日の日本らしさにつながっているのかもしれません。
日本の政治構造においても、「中空性」が見られるようです。
例えば天皇は、日本国家の象徴として中心に位置づけられてきましたが、実際には歴史上しばしば政治的実権を持たない存在として機能してきました。古代から中世にかけては摂政や関白、あるいは将軍が実際の権力を掌握し、戦後は「象徴天皇制」として制度的に非政治的な存在となっています。
フランスの思想家ロラン・バルトが『表徴の帝国』の中で端的に表現したように、日本における権力には一定の”中空性”が見られるようです。
日本の歴史を振り返ると、前近代や幕藩体制では多中心的な権力分散が見られたものの、明治以降には中央集権化が進んでいます。とはいえ、象徴天皇制や地方自治制度などに“中空的”な特色が残存していると考えることはできるかもしれません。
言語と文化の中空性、日本的特質
次に日本語という言語自体に目を向けてみます。
主語不在であいまいな主体性。事象を直接的に言い切らない婉曲表現の多さ。カタカナ表記で「外来語」を切り分けることによる境界の不確かさ。
奥深い言語だなと感じます。
日本語は非常に特殊な構造を持っている複雑な言語で、三種の文字体系を併用していることもあり、外来語を比較的取り込みやすい表記文化があります。
日本語は外来語を次々と取り込み、自分たちの言葉として吸収していく驚くべき柔軟性を持っており、この融通無碍な性質は、日本語の最も際立った特徴の一つと言えるでしょう。
「カタカナ」などはなかなか独特だなと思います。多くの外来語は「カタカナ」という特別な表記体系によって区分され、それ以上は日本語の核心には浸透しないよう、巧妙な境界線が設けられているようにも思われます。「柔軟かつ選択的な受容性」として言語が使われている、そんな印象です。
また、主語と述語の関係が意図的にあやふやに保たれ、主語がなくても文が成立してしまうという独特の文法構造は非常に特殊です。このため、話者が実際にはその出来事の当事者でない場合でも、あたかもその場に立ち会っているかのように感じさせる文体を形作ることもできてしまう。
そうした特性からか、日本語で何かを記述する場合、現実をそのまま客観的に描写するというよりも、一段階フィクション化されたような独特の感覚が生じることが少なくありません。言い換えるなら、日本語という言語には、どこか「空虚さ」や「虚構性」が本質的に内包されているように感じられるのです(そこがまた儚く、脆く、美しいところでもあるのですが)。
こうした言語の特性と深く呼応するように、日本文化そのものにも共通する性質が見られるように思えます。日本文化は、非常に柔軟で、外来の文化に対して旺盛な好奇心を示し、さらに新技術にも積極的に適応してきました。この特性こそが、戦後の目覚ましい経済発展を支えた創造的な原動力になったことは間違いないでしょう。
他のアジア諸国と比較しても、日本は外来文化をそのまま受け入れるのではなく、「和風」にアレンジし、独自の美意識でモディファイして取り込んできました。これはもはや「創造的変容の文化」と言ってもいいと思います。
中空構造の両義性
「中空構造」は長所と短所の両面を併せ持つ構造として捉えられています。「中心が空である」ことは、柔軟さと多様性をもたらす一方で、場合によっては無責任や統制の欠如を招く危険もあるという点には注意が必要なようです。
中空構造の最大の利点は、絶対的な価値や単一の原理に支配されることなく、対立するもの同士を共存させる包容力と柔軟性を持つ点です。非常に編集的ですね。
「絶対化された中心」は相容れぬものを周辺に追いやってしまいますが「中心が空」であれば、善悪や正邪といった判断を相対化することができます。言い換えれば、正面からの対立を避け、調整的に事を進める余地があるのが中空構造だということでしょう。このような構造があるからこそ、日本社会は外来の宗教、思想、技術を柔軟に受け入れながらも、独自のバランスを保ってきたのだと考えられます。
一方で、中心が空であることがマイナスに働く局面も存在します。中心に明確な実体や権威が存在しないことで、外部からの介入や内部からの逸脱が起きやすくなるという点です。
中心に強い求心力がないとき、周辺は徒党化し、依存的になりやすくなります。その結果、全体の方向性が不明瞭になり、問題が起きても責任の所在が不透明なまま放置されるような、いわゆる「無責任体制」が生じやすくなります。なんだかよく耳にする状態だと思いませんか?結果、誰が意思決定するのかが不明確になり、対応が後手に回ることが少なくありません。このような状況が他文化圏の人々の目には「日本人特有の優柔不断さ」と映ってしまうのかもしれません。
実際、国際社会においても、日本がグローバルな課題に対して明確な意思表示を避け続けることに対する批判は根強く存在しています。
例えば安全保障や国際的な交渉の場面では、中途半端な態度よりも明確な価値観の表明や立場の主張が重視される傾向にあります。対立を避けることを優先しすぎるあまり、自国の立場が不明確になってしまうことは、国際社会においてリスクとなりうるでしょう。中空構造に基づく態度が、時に「事なかれ主義」や「責任回避」として機能してしまうという指摘も、今日の日本に対する厳しい視線として存在しています。
こうした状況においては日本が持つ「中空構造」の負の側面が顕著になっているように思えます。
「空」の力を活かすための多中心構造という観点
こうした批判に対して、中空構造論を補完・発展させる試みもいくつか見られます。
たとえば松岡正剛は、日本文化を語る際には「中空構造」に加えて「多中心構造」にも目を向けるべきだと述べています。これは、日本が一つの固定的な中心を持つのではなく、文脈や時代に応じて中心が流動的に移り変わる文化的特性に注目した視点だと思われます。
「中空構造は時として負の側面が顕在化することもあれど、別の文脈では柔軟性や包容力として機能する」そんな余白を持っていることに自覚的でありたいものです。
こうした視点を取り入れれば、日本文化を「空なる中心」と「複数の動的な周縁」との関係性の中で捉えることが可能になり、より現代的で柔軟な理解につながるでしょう。
中空構造が内包する「複数の声が積み重なる」性質は、編集行為が持つ「調整者」としての側面と深い親和性を持っているように思えます。私たちのような編集者はしばしば、著者が伝えたいことと読者が求めていること、さらには出版社の方針やマーケットの動向など、複数の利害や文脈を調整しながら最終的な形を生み出します。
中心を一つに決めきれない状況であっても、多元的なバランスを繊細に整えながら価値ある成果物を作り上げる営為こそ、編集なのです。この「空洞」を余白として活かす創造性こそが求められます。
日本社会の中空構造はしばしば「不明瞭」「責任の所在がぼやけている」など否定的な文脈で語られることもあります。しかし一方で、それがもたらす柔軟性や、他者を自然に巻き込む開かれた場の創出は、創造的環境の基盤ともなります。編集の視点から見るならば、「空洞」を余白として積極的に活用することで、多様な要素を有機的に結びつけ、新たな価値を生み出しやすくなるという捉え方も可能だと思うのです。
明確な中心を固定せず複数の視点を流動的に掛け合わせられる自由度が、新たな発想や表現を模索する源泉となると感じています。
いずれにせよ、中空構造論は万能の理論ではありませんが、日本人の行動や思考の深層に迫るための重要な手がかりを提示したことは確かです。その意味で『中空構造 日本の深層』は、文化心理学・民俗学のみならず、現代社会を考察するうえでも多くの示唆を与えてくれました。
日本的基層文化の深層を見つめ直すための中空構造
日本が持つ中空構造の本質である「創造的に変容させる力」は、一見すると、完全なるゼロから何かを創造するというラディカルなイノベーションの領域では制約となる可能性も否めません。すごく簡単に言ってしまえば時代を変革するような革新的なアイデアが創出しにくいと思うのです。
だからこそ、急速に時代を進めることにのみフォーカスせず、これまで十分な光が当てられてこなかった文化資源に対して「中空的」に関わることの必要性を感じています。
幸か不幸か、私はスタートアップ的なマインドとでも言うのでしょうか、急激なイノベーションやスピードを重んじる文化や思考に傾倒していない人間です。どちらかといえば、目まぐるしい速度で前進することよりも、ゆっくりと過去の英知を丁寧に集め、味わい、咀嚼していきたいと考える方が性に合っているのです。
多種多様な要素を精妙に折衷し繊細なバランスで統合するという日本的な知性は、表層的な速さと新奇性に目が奪われがちな現代において、これまで以上に必要になる考え方なはずです。
急速な変化の波に乗ることよりも、時間をかけて醸成される深層的価値を探求すること。これが文化創造の本質を紡ぎだす源泉になるはずだと、私は信じています。