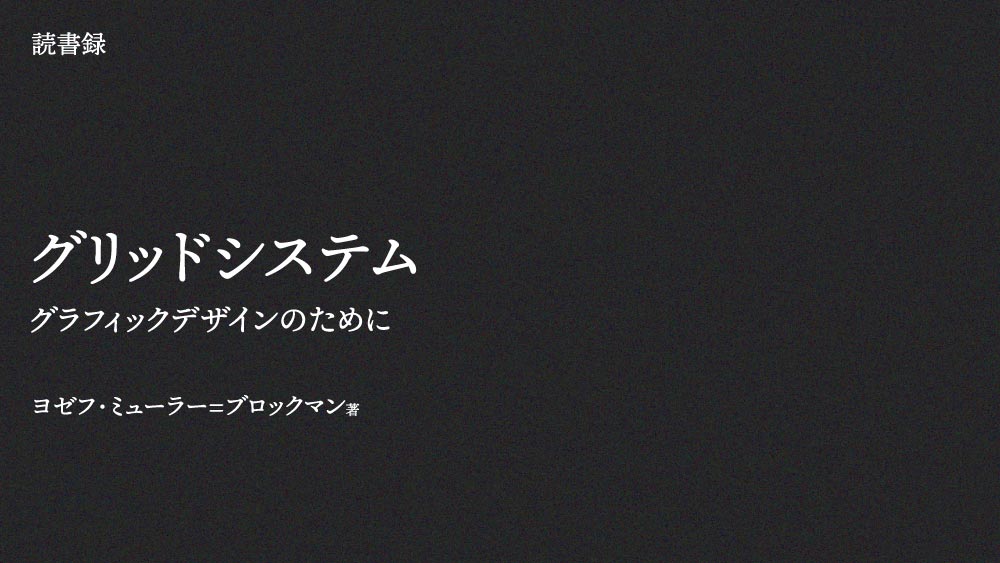グリッドシステムは、古くから紙面を中心に活用されてきた最も古典的かつ代表的なレイアウト手法です。
対象となる平面(または三次元)を格子状の行と列で構成し、その格子に沿ってオブジェクトを配置することで、規則的かつ整然としたレイアウトを実現できます。私たちのコーポレートサイトもまた、規則的なグリッドシステムに従って構築されたものです。
ヨゼフ・ミューラー=ブロックマンによって考案された当システムは、近年では伝統的な活版印刷の枠組みを超えて、ウェブサイト等のデジタル上においても活用されています。
グリッドシステムは、例えば、何も描かれていない真っ白なキャンバスにも、数学的比率に基づく秩序を与えてくれます。
設計の原則をある程度理解していれば比較的容易に美しいレイアウトを実現できてしまうほど、グリッドシステムは優れたレイアウト手法です。ゆえに、単なる「数理的基盤」として深い思考もなく利用してきた自分がいたことも否定できません。
より深い思考に根差した成果物を創出するために、グリッドシステムの源泉となる思想的背景に触れなくておく必要がある、そんな気持ちに駆られて手に取ったのが、氏の遺した名著『グリッドシステム』でした。
恥ずかしながら実践的な示唆は少ないかもしれませんが、私が本書を読んで思ったこと、感じたことを素直にしたためていこうと思います。
「秩序」による自由
デザイナーであれば、真っ白なアートボードを目の前にすると、さてここから一体どんなデザインを生み出そうか、何から着手するのが先決だろうか、そんなふうに考え倦むことも多いと思います。
手を動かすうちに自分なりの規則性を見出したり、或いはあえて無秩序なデザインを志向する場合もあるかもしれません。いずれにせよ、規律なき状態では、デザイナーは荒野を彷徨っているようなもの。もちろんこれもデザイナーの醍醐味かもしれませんが…。
一方グリッドシステムは、こうしたデザイナーの主観や属人性を可能な限り排して、客観的かつ数理的基盤に支えられた堅牢なレイアウトを与えてくれます。
精緻な計算の上に引かれたグリッドは、伽藍堂のアートボードに心地よい「秩序」と「律動」をもたらします。デザイナーはこの秩序の上で、本文や画像といったオブジェクトを論理的に配置していくことになるでしょう。
時に大胆に区画を組み合わせたり、反対に分割することも許されています。一見、厳しい制約を自ら課しているように映りますが、デザイナーにはその中で自由が与えられているのです。
根底にある「モダニズム」の思想
ブロックマンの生きた20世紀中期は、いわゆる「モダニズム」の思想が台頭していた時代でした。
モダニズムという言葉は、芸術、建築、哲学、思想など様々な分野で用いられています。特に、建築やデザインの文脈におけるモダニズムとは、「合理性」「機能性」「普遍性」を重視し、装飾を排除して普遍的な表現を追求した諸運動・様式全般を指すことが一般的です。
例えば、1919年、ドイツのワイマールに設立された国立造形学校「バウハウス(Bauhaus)」では、装飾を可能な限り排除し、機能性を重視する合理主義的なアプローチに基づいたカリキュラムが展開されていました。
ナチスの弾圧により、わずか14年で閉校を余儀なくされましたが、バウハウスの合理的かつシステマティックな思想は、後のグリッドシステムの理念と呼応する部分も多く、ブロックマンの思想形成に影響を与えた要因の一つと考えられています。
グラフィックデザインの文脈からは少し逸れますが、かの有名なミース・ファン・デル・ローエやル・コルビュジエに代表される、インターナショナル・スタイルもまた、モダニズムを源泉とする建築様式の一つです。鉄とガラスとコンクリートを駆使した合理的かつ機能的な設計は、グリッドシステムの思想と通底する部分が多いように思えます。
グリッドシステムは「民主的」なデザイン手法
デザインの技術は、一朝一夕で手に入れられるものではありません。多くの人にとって、デザインという行為自体が、近寄りがたく、自分とは無縁の分野のように感じられることもきっとあるでしょう。
一方で、グリッドシステムはどうでしょうか。
センス、才能といった属人的な要素に依存せず、(もちろん技術と経験は要求されますが)誰に対しても開かれた客観的な方法論を提供してくれます。
特権的でなく、誰もが理解し、誰もが使用できること。文化や言語の違いを超えて理解される「普遍的な視覚言語」であること。こうした点において、グリッドシステムは、極めて民主的なデザイン手法なのです。
ブロックマンは、チューリッヒ応用美術学校やウルム造形大学での教育活動、そして精力的な講演や出版活動を通じて、この考えを広く伝えようと努めました。それは単なる当時のインターナショナルスタイルという潮流への迎合ではなく、デザイナーとしての社会的責任を果たそうとする強い意志の表れだったように思えます。
このグリッドシステムという方法論は、今日でも変わらず、デザインの敷居を下げ、より多くの人々にデザインの可能性を開く役割を果たし続けています。それは、まさにブロックマンが目指した「民主的なデザイン」の理想が、現代に受け継がれている証といえるでしょう。
デジタルデザインの文脈において、ブロックマンのグリッドシステムはどこまで活用されるべきか
デジタル上のデザインは書籍やポスターのような印刷物とは異なり、さまざまな端末・ブラウザで閲覧されることを考慮した柔軟性と可変性が要求されます。
画面サイズやウィンドウサイズの変更に応じて、文字サイズやレイアウトが動的に変化するデジタル上のコンテンツに、ブロックマンの厳格なグリットシステムを、そのまま適用することは現実的とは言えません。
細かなカーニングや約物の処理などを行えるCSSプロパティが登場してはいるものの、各種ブラウザの対応状況も今一歩。総合的に紙面の再現度にはまだまだ及ばない点が多いのは、仕方のないことです。
デジタルデザインの文脈においては、グリットシステムの本質を理解した上で、その特性に応じた拡張や解釈を加えていくことが大切なのだと思います。
例えば、情報の重要度や関連性を空間的な配置によって表現することは、ユーザーに対して情報のまとまりを正しく伝える上で非常に重要です。見出し、画像、本文からなるブロックを、適切なスペーシングを用いて配置することで、ユーザーが意味のまとまりを理解しやすくなります。
さらに、この配置や余白自体に、黄金比などの数学的原理を用いることで、より拡張性・再利用可能性の高いデザインを実現できるはずです。もちろん、お行儀よく配置していくだけではなく、グリッドを基準としつつも、時に意図的なコントラストや変化を加えることで、単調さを避けつつ秩序ある視覚的リズムを生み出せます。
ルールに従いつつ、その中で最大限の創意工夫に苦心すること。「心地よい律動を生み出す」技術を磨いていくことがデジタルデザインという文脈でグリッドシステムを活かす上で、デザイナーに求められるスキルなのかもしれません。
精神的な態度を模倣してみる
デザイナーは時として、グリッドシステムを単なる実践的な手法として捉えてしまうことも多いように思えます。
もちろん、本書が実践書であることに間違いはありません。しかし、その本質により深く目を向けると、そこには物事を整理し、理解し、表現するための普遍的な思考法が内包されていることに気づきます。
つまり、グリッドシステムが示す「秩序ある構造」「無駄の削除」「明快な意図」といった要素は、デザインの領域を超えて、私たちの思考や行動の指針となり得るのです。
例えば、お客様への資料作成について考えてみます。
私たちは混沌とした情報をまずは階層化し、関連する要素をグループ化し、視覚的な秩序が保たれるよう注意深く配置します。これは、グリッドシステムの目指す『構造化された明快さ』と共通点があります。また、本質的でないものを取り除き、必要な要素だけを残す判断も、グリッドシステムの思想と重なる点が多いように思えます。
その意味で、(少しアナロジーが過ぎるかもしれませんが)本書は単なる実践書を超えて、仕事における精神的態度を示す指針としても読むことができます。即物的で明快な方法論は、より良い社会の構築にも通じる視座を私たちに与えてくれるのです。
結びに
本書は、デザイナーであれば一度は手に取る名著である一方、「名著だから」という理由でただ手元に置いておくだけになってしまうことも多いのではないでしょうか。実は、私自身もその1人でした。
「グリッドに沿ってオブジェクトを配置するとなんとなく気分が良い。」
この「なんとなく」の理由をしっかりと理解しておくこと。それは、グリッドに対する向き合い方、そしてデザインそのものに対する姿勢にも大きな影響を与えるはずです。
余談ではありますが、本書は重厚な内容だけでなく、そのレイアウト自体がブロックマンの考えるグリッドシステムを体現しています。(失礼を承知で申し上げれば、この視覚的な実践は、時として本文以上に雄弁かもしれません。)
余白、行間、フォントサイズ、カラム数、オブジェクトの配置。ミニマルでありながら、視覚的なグルーピングがなされており、間隙なき完成度です。ページをめくるたびに、グリッドシステムの持つ深い思想と、その実践的な美しさを教えてくれる一冊でした。