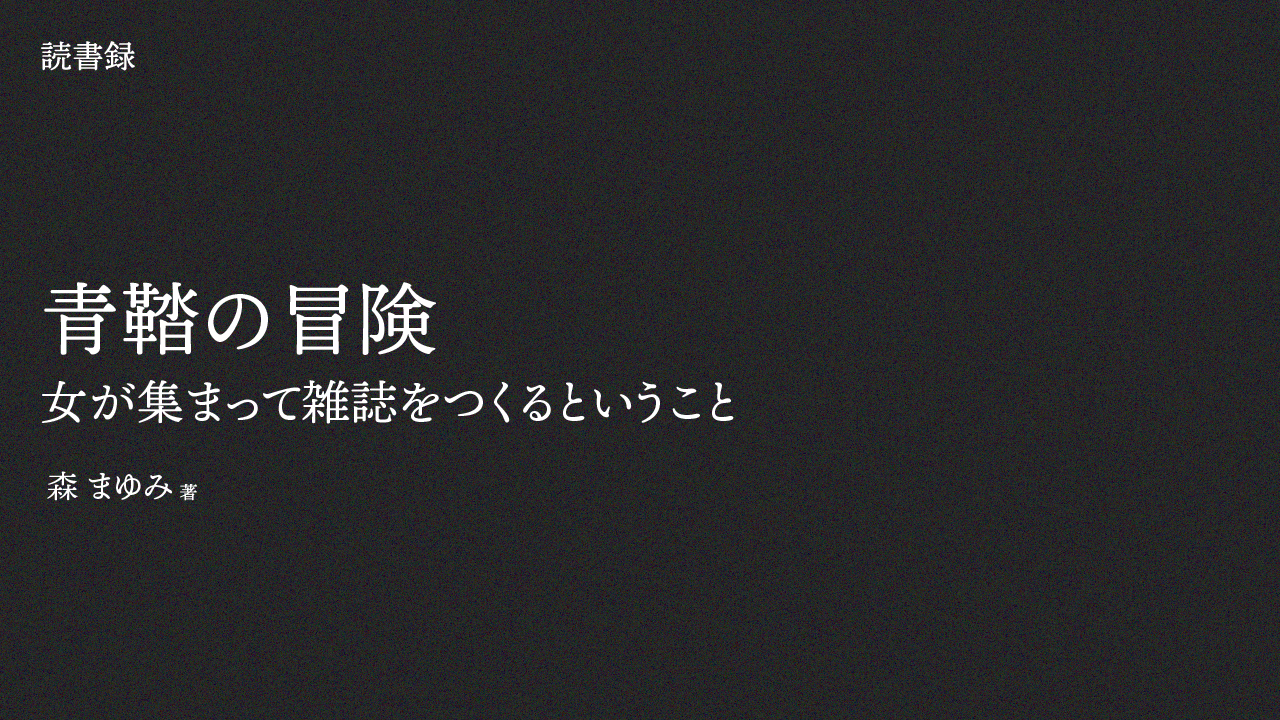「元始、女性は太陽であった」。
この有名な言葉で知られる平塚らいてうを中心に、明治末期の日本で創刊された雑誌「青鞜(せいとう)」。
1911年、女性たちだけの手によって創刊されたこの雑誌は当時の社会に強烈な衝撃を与え、約5年間の活動で実に52号を刊行し、後の日本におけるフェミニズム運動の源流となりました。
それから73年後の1984年、森まゆみ氏らが地域雑誌「谷中・根津・千駄木(通称:谷根千)を創刊。
そして森氏は著書「青鞜の冒険 女が集まって雑誌をつくるということ」において、雑誌「青鞜」とその創刊に関わった女性たちの姿、彼女たちの闘いについて描き出しました。
彼女たちは何と闘い、どのような言葉を世に送り出したのか。
本書を読み解きながら、そのドラマを探っていきます。
女性が自ら書き、女性のために発信する「青鞜」のはじまり
明治から大正にかけての日本では、女性には「良妻賢母」であることが求められ、社会での発言権や参政権は与えられていませんでした。政治集会への参加すら、治安警察法によって禁じられていた時代です。
そんな時代に、女性たちだけの手によって雑誌「青鞜」が創刊されました。
雑誌名につけられた「青鞜」は、18世紀のイギリスで女性知識人を指したBluestockings(ブルーストッキング)に由来します。
「青鞜」は、日本で初めて「女性が自ら書き、女性のために発信する」文芸雑誌であり、既存の価値観に揺さぶりをかける存在となります。誌面では、女性の自己表現や自立、そして男女平等の考えを発信しました。
この雑誌の中心人物が、思想家であり作家でもあった平塚らいてうです。
創刊号の冒頭で掲げられた「元始、女性は太陽であった」という有名な言葉。
この一文には、「かつて女性は自由で主体的に輝いていたが、いまや社会の中で受け身の存在にされてしまっている」という平塚の強い問題意識が込められていました。
彼女は創刊の辞で、「日本が生まれたとき、女性は太陽であった。今では女性は月である…」と語り、男性の光を反射するだけの存在に甘んじている現状を嘆いています。
「青鞜」の創刊は、日本で初めて、女性が自分たちの言葉で、自分たちの力だけで社会に声を届けようとした試みでした。それは単なる雑誌づくりではなく、女性たち自身が自己表現し、社会に問いかけるための運動でもあったのです。
青鞜は政治的な雑誌ではありませんでしたが、「女性が言葉をもつ」という行為そのものが、時代にとっては挑戦であり、変革の始まりでもありました。
雑誌「青鞜」の創刊メンバーと彼女たちの思想
創刊メンバーには、平塚らいてうのほか、物集和子、保持研子ら女性5人。他にも伊藤野枝や与謝野晶子といった、のちに日本の女性史に名を刻む人物たちが名を連ねていました。
思想や立場には違いがあったものの、彼女たちに共通していたのは、「女性が自らの言葉で語ること」への希望が込められてた点です。
彼女たちが青鞜を通して発信した主なテーマは、以下の4つ。
-
自由恋愛:恋愛結婚の肯定
-
家制度批判:家父長的な戸主制度への異議
-
性の自立:女性が自身の性を主体的に捉えること
-
女性教育の必要性:女性にも十分な教育を受ける権利があるという主張
こうしたメッセージは、当時の保守的な社会においては、たびたび激しい批判を受けました。
「青鞜」は風紀を乱す雑誌だと非難され、内容はたびたび検閲にかかりました。政府はその論調を「社会を混乱させる」と判断し、発行禁止処分を下したこともあるほどです。
さらに、メディアは青鞜社の女性たちの私生活を面白おかしく暴き立て、スキャンダラスな存在として彼女たちを批判しました。
それでも彼女たちは筆を置くことなく、「語らなければ、生きていけない」という切実な思いを胸に、書き続けたのです。
創刊から終刊までの5年間のあゆみ
1911年に創刊された青鞜は、1916年に終刊となるまで約5年間にわたり刊行されました。その短くも濃密な活動の中で、どのような出来事があったのかを振り返ります。
1911年:創刊と予想外の反響
1911年9月に創刊号を発行。平塚らいてうを編集長として創刊されました。
創刊号は文芸色の濃い内容で、詩やエッセイを通じて女性の内面世界を掘り下げた内容でした。創刊号は発売初月に1,000部を売り上げ、編集部には3,000通を超える購読申し込みや女性たちからの相談の手紙が押し寄せるなど大反響を呼んだそうです。
それは当時の女性たちが自らの声を発する場をどれほど求めていたかを示す出来事でした。
1912年:スキャンダルと相次ぐ発売禁止処分
創刊から一年後、雑誌は早くも社会の逆風にさらされます。
創刊号に掲載された短編小説が「縁談の破棄(婚約破棄)」を描いていたことで発売禁止に。さらに4月号では、荒木郁子の短編「手紙」が女性の性的体験を赤裸々に描いたとして再び発売禁止処分を受けました。
同年夏には、寄稿者・尾竹紅吉が酒や恋愛体験を自由に綴ったこと、吉原の遊廓を訪れたエピソードなどが新聞で報じられ、「男の世界に踏み込むふしだらな女たち」とメディアから激しいバッシングを受けます。
女性の品行に厳しい時代背景も手伝い、私生活まで好奇の目に晒された結果、将来の結婚や家族への影響を懸念して離脱するメンバーも現れました。
1913年:思想の深化と同人の脱落
社会的批判や警察の監視が強まる中、「青鞜」は次第に文芸から社会批評へと舵を切っていきます。
女性解放や労働問題を取り上げ、「女性は恋愛結婚すべき」といった主張を展開。1913年4月号ではその内容が当局の検閲に触れ、またも発売禁止処分を受けました。
同時に、創刊時の中心メンバーの多くがプレッシャーや方向性の違いから退社が相次ぎます。運動の先鋭化とともに、内部でも温度差が顕在化していったのです。
1914年:価値観の違いと編集内部の対立
雑誌を取り巻く状況はさらに緊迫します。
1924年2月号では、家制度から逃れた女性が恋人と駆け落ちするも裏切られるという短編が掲載され、「不道徳」として発売禁止処分に。
この頃には、誌面の内容をめぐって編集部内の対立も深まり、思想や活動の方向性をめぐる意見の衝突が続出したようです。対立の末に仲間の離反も相次ぎ、雑誌は少しずつ足場を失いはじめます。
1915年:伊藤野枝の編集長就任と激化する論調
雑誌「青鞜」は、一つの転機を迎えます。
それまで編集長を務めていた平塚らいてうが退任。後任には伊藤野枝が就任を果たします。
創刊以来、社会批評的な色彩を強めていましたが、無政府主義者でもあった彼女の下で、「青鞜」は急進的な女性解放論や社会批判へと大きく舵を切ります。発行部数は一時3,000部に達し、雑誌としての影響力は最盛期を迎えました。
しかし同年6月号で堕胎(人工中絶)の合法化を訴える論文を掲載したことで、当局に没収され、発売禁止処分を受けます。それ以降、地方書店には警察からの圧力がかかり、流通の妨害も始まります。
当局は発行号丸ごとの発売禁止を連発して「青鞜」を有害な雑誌と断じ、発売元や書店に罰則をちらつかせて販売網を締め上げていくのです。
1916年:終刊と、静かな幕引き
社会からの圧力に加え、編集部内部の混乱も次第に深刻化していきます。
平塚らいてうは、内縁の夫・奥村博との生活を優先し、編集の現場を離脱することを決断。一方、伊藤野枝も無政府主義運動に傾倒し、大杉栄との激しい恋愛にのめり込む中で、次第に雑誌編集から手を引いていきました。
こうして内部の混乱や資金難も極限に達し、遂に1916年2月号(第52号)をもって「青鞜」は静かに幕を下ろしました。
わずか5年間という短い活動期間ながら、「青鞜」は女性たちが自らの言葉で社会と向き合い、声を上げた先駆的な雑誌でした。
時代背景も相まって、終焉はある意味で必然だったのかもしれません。しかし、彼女たちが放った言葉の数々は、日本のフェミニズムと女性表現の土壌を耕し、後の時代に受け継がれていきます。
伊藤野枝・平塚らいてう・与謝野晶子らの思想と対立
「青鞜」を語るうえで欠かせないのが、内部における思想の違いと対立です。誌面に関わった女性たちは、しばしば「新しい女性像」として注目されましたが、決して一枚岩の集団ではありませんでした。
平塚らいてうは、女性の内面的自由を重んじる文芸思想家でした。
彼女は「精神的自立こそが女性解放の出発点である」と考え、創刊当初の「青鞜」を文学を通じた内面的覚醒の場にしようと構想していました。
一方、のちに編集長を引き継ぐ伊藤野枝は社会主義・無政府主義を目指し、より直接的で急進的な社会変革を志向する思想の持ち主でした。
彼女のもとで「青鞜」は、女性の権利拡張や家制度批判など、社会制度に対する攻撃的な論調を強めていきます。その姿勢は、大逆事件以降の社会主義運動とも連動し、より実践的な女性解放を目指すものでもありました。
与謝野晶子は芸術家肌で、女性の表現の自由を何より尊重しました。
家父長制や戦争に対して鋭い批判を続けながらも、家庭では多くの子どもを育てた母親としての顔も持ち、現実主義的な立場から語る場面もありました。創刊号に詩を寄せるなど「青鞜」への協力もしましたが、運動に深く加わることはなかったようです。
このように、女性であるという共通点はあっても、思想や目指す方向性はそれぞれ異なっていました。当然ながら、時には激しい議論がぶつかり合うこともあったようです。
しかし皮肉にも、そうした多様な思想の交錯こそが「青鞜」を単なる同人誌ではなく、思想的運動体として機能させる原動力となったことも事実です。
異なる視点や意見を内包しながら発信を続けたことで、「青鞜」はより多くの女性たちを巻き込み、社会に対して強い問いかけを行う存在となっていきます。
異なる意見を内包しつつ発信を続けたことで、「青鞜」はより多くの女性たちを巻き込み、社会に問いかける力を強めていきました。
編集という闘い、雑誌作りの現場で起きたこと
「青鞜」の編集部では、発行を続けるためにさまざまな困難が立ちはだかっていました。
最も深刻だったのは、常に資金不足に悩まされていたことです。広告収入も乏しく、有力者からの援助を仰ぎながら資金繰りに奔走していたものの、雑誌の発行スケジュールはたびたび遅れがちでした。財政の逼迫は慢性的で、毎号の刊行が綱渡りのような状態だったようです。
また、誌面の内容が過激と見なされることが多かったため、印刷を引き受けてくれる業者を探すのにも苦労を強いられました。政府の監視の目が光る中で、印刷所や製本所との関係を築くことは容易ではなく、協力してくれる業者は限られていたのです。
内部でも順風満帆とはいきませんでした。編集方針や思想の違いから、メンバー同士の対立が絶えず、険悪な空気になることもしばしば。意見の食い違いから仲間が次々と離脱し、人手不足に陥ることも少なくありませんでした。
さらに、雑誌を読者に届けるための流通面でも問題を抱えていました。そもそも書店に置いてもらえなかったり、発送のミスや配送体制の未整備によって、読者の手元に届かないことがあったようです。編集部の女性たちは、自ら書店を一軒ずつ訪ねては販路を開拓し、地道に読者を増やしていきました。
限られた人員で作業をこなしていたため、校正作業にも十分な時間が割けず、誤植や誤記がたびたび発生してしまいます。時にはそのミスが世間から批判され、編集部が謝罪に追われることもあったようです。
このように、女性である以前に、「何かを自分たちの手で世に出すこと」がいかに困難だったかがわかります。編集者たちが東京の町を駆け回る姿が目に浮かぶようであり、その生々しい苦闘の記録は想像を絶するものだったでしょう。
森まゆみ氏による「青鞜の冒険」が示す女性メディアの原点
本書の著書でもある森まゆみ氏は、地域雑誌「谷根千」を創刊し40年以上にわたり編集・発行してきた経験を持つ編集者です。
自身も地元の主婦仲間の山崎範子氏と実妹である仰木ひろみ氏という、三人の女性によって立ち上げられました。
だからこそ「女性だけで雑誌を持続して発行すること」の困難さや限界、掲げた理想と現実とのギャップ、言葉が時に独り歩きして暴走する危うさ、そして権力や世間から理解されないもどかしさなどを経験してきたのではないでしょうか。
本書は「女性解放の成功物語」として美化するのではなく、泥臭い現実に直面した彼女たちの姿を描いています。
また「メディアを持つとはどういうことか」を問いかけてきます。
誰が語り、誰が発信するのか。言葉を発するとはどういう責任を伴う行為なのか。仲間とともに何かを創り上げることの難しさと、その中にある尊さ。
雑誌という手段を通じて「青鞜」の女性たちは社会と闘い、同時に自分自身とも闘っていました。その姿は、メディアにおける「声」のあり方を問うものでもあります。
現代と比べれば、「青鞜」は決して大部数が刷られた商業誌ではなく、女性たちが自前で細々と作り上げた小さな雑誌でした。しかし彼女たちはそれを通じて、「誰にも従属しない自分たちの言葉」を世に示しました。
このことは、女性が自らメディアを持つ意義の原点を示していると言えるでしょう。そして彼女たちの試みは、雑誌刊行が単なる営利事業ではなく一種の社会運動でありうることを証明しました。
青鞜から考える現代のメディア発信
現代では、SNSやブログなど個人が容易に発信手段を持てる時代に生きています。しかし「青鞜」の時代、女性たちにとって「語ること」「印刷すること」「発信すること」のすべてが闘いでした。
その歴史を知ることで、現代の私たちが持つ言論の自由や選択肢が、どれほど多くの先人たちの努力と犠牲によって支えられているかに気付かされます。
同時に、現代の女性運動やメディア発信においても、「連帯の難しさ」「多様性の受け入れ方」「活動を継続する困難さ」といった課題は決して過去のものではありません。
フェミニズムをめぐる現代の議論でも、意見の対立や方向性の違いにより分断が生じたり、運動の長続きが難しかったりする場面は少なくありません。「青鞜」の物語は、私たちに歴史的な教訓を与えるだけでなく、今なお続くこれら共通の課題について考えるヒントを与えてくれます。
「青鞜」は1916年に終刊しました。しかし、その理念と情熱は形を変えて今も生き続けています。
当時の女性たちが示した「書くこと」「発信すること」への情熱と覚悟は、私たちに自己表現の原点と責任を改めて考えさせてくれます。