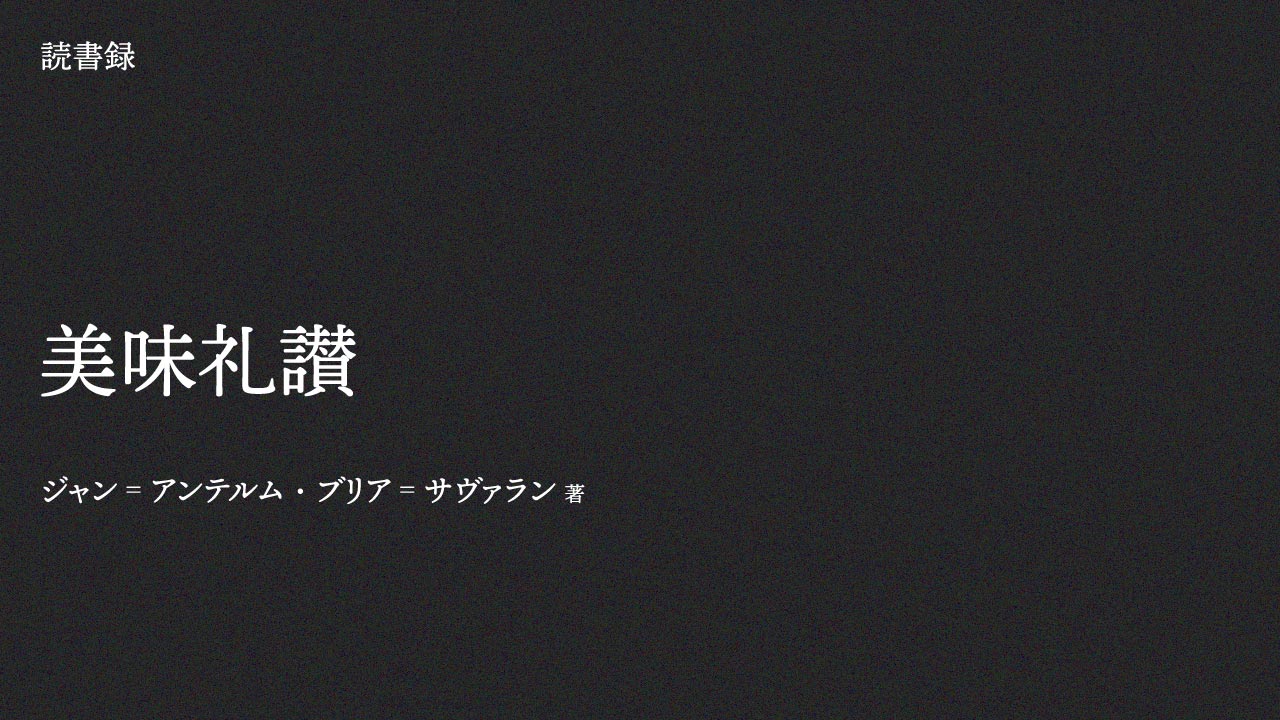人間を養う学問は少なくとも人間を殺すことを教える学問よりも価値がある。
私が本書の中で最も好きな一文です。
哲学的には食を通じて人間存在を問い、美学的には味覚の世界を文学的に謳歌し、歴史的には自らの時代の食文化を記録した一冊。文化的には後世の美食思想に計り知れない影響を及ぼした不朽の名作『美味礼讃』。
著者ジャン゠アンテルム・ブリア゠サヴァラン(1755〜1826)は、法律家として公的な職務に就く一方で、諸学に通じた教養人でもありました。晩年に執筆されたこの著作には、美食家としての情熱と豊かな知見が凝縮されています。サヴァランは、食べるという行為が人間と社会にとってどれほど根源的な意味を持つのかを、多角的な視点から掘り下げています。
1825年に出版された本書は料理の技法を紹介する実用書でも、栄養学の教本でもありません。むしろ「食べること」がもたらす快楽と精神の充実を、科学的・哲学的に解明しようとする試みとして執筆された本です。刊行当時から高い評価を受け、美食(ガストロノミー)を理論的・歴史的・文化的に論じた初期の書物として、しばしば「美食学の聖書」とも称されてきました。
サヴァラン本人は刊行の翌年、生涯独身のまま七十歳でその生涯を閉じていますが、後世に与えた影響は計り知れません。
食べることは、生きることであり、よく生きるためには、よく食べなければなりません。そして、よりよく食べるということは、生の時間を愛おしみ、人間であることの歓びを静かに肯定する営みだということを教えてくれるかのような、そんな強い語り口。
では食べるとは何か。
この一見素朴な問いは、ふとした味わいの余韻の中に、あるいは食卓を囲む静かな会話のなかに、そっと姿を現します。
人間はどのように「食」と向き合い、それを文化として育ててきたのか。
『美味礼讃』は、その長い問いかけに寄りそうように多くの言葉を残してくれます。
今回はそんな200年前の名著を。
フランス美食文化への静かな貢献
グリモ・ド・ラ・レニエールと並んで「グルメエッセイ」という文芸ジャンルを創始した本書は、以降の食文化論や料理エッセイの範となりました。
『美味礼讃』が後世に及ぼした影響は測り知れないものがあります。
19世紀フランスにおいては、サヴァランの先駆的業績を継ぎ、バルザックが食の随筆を著し、デュマが料理事典を編纂するなど、美食文学は一つの顕著な潮流となりましたが、その源流に『美味礼讃』が位置することは論を俟たないでしょう。
また、1980年代には記号学者ロラン・バルトによる本書についての評論『〈味覚の生理学〉を読む』(1985年)が出版されており、学術的な分析対象としての価値も認められています。
これらは本書が単なる古典に留まらず、「生きた文化的遺産」として認識されている好例と言えるでしょう。
では『美味礼讃』の文化的価値の「要」はどこか。
それは「食文化を尊重する精神」を社会に広めたことにあると感じました。
サヴァランは美食を国家や社会の命運にも関わる重要事と捉え、食べることの意味を本質的に格上げしました。この思想がフランスにおける食文化のアイデンティティ形成に多大な貢献を成したことで、フランス料理が「世界無形文化遺産」(2010年ユネスコ認定)として国際的評価を受ける一つの遠因ともなったと考えられます。
言い換えるならば、本書はフランスの美食文化に誇りと理論的支柱を提供し、フランス人が自国の食を文化的遺産として自覚する精神的土壌を培ったと言えるかもしれませんね。
18世紀フランス、激動の中で生まれた食への眼差し
この『美味礼讃』が著された18世紀末〜19世紀初頭のフランスは、食文化にとって重大な転換期でした。フランス革命(1789年)前夜からナポレオン時代にかけて、美食は王侯貴族の独占的享楽から市民社会の文化的営みへと変容しつつありました。
サヴァラン自身はこの激動の時代を生き抜き、第三身分の代議士としてヴェルサイユに赴いた経験を持ちます。革命後には政治的混乱を回避すべく一時的に国外(スイスやアメリカ)へ身を退いたものの、帰国後には裁判官として再び公職に就き、社交界やサロンにおいて美食家としても多彩に活躍していたようです。
こうした激動の時代背景が彼に「食」という行為に対し新たな視座を与えたのかもしれません。
政治や社会構造が大きく揺らぐ中にあっても、食卓における喜びは人々を結びつけ、文化を支える普遍的な力として機能する。その深い洞察があったからこそ、この不朽の書が生まれたのかもしれません。
19世紀初頭のパリでは、すでに料理人グリモ・ド・ラ・レニエールによる美食評論(現代のレストランガイド的活動)が萌芽しており、料理を批評的に評価する文化も揺れ動いていたようです。
サヴァランはそうした先行者と並び立ち、あるいはそれ以上に、食文化を学問的に体系化しようと試みたのです。
彼が美食を「すべての食物に関する知識を体系化した学問」と捉え、化学・生理学・経済・芸術といった多角的視点から食を考察したことは全くもって驚くばかりです。
当時ナポレオンの侍医であったコルヴィサールや外科医デュピュイトランなど科学者との交流を通じて、食物の化学的性質や消化の生理学的機序にも深い理解を示していたことが著作から窺えます。啓蒙時代の科学的精神と結びついたこの美食論は、一種の「食の形而上学」と評しても過言ではないでしょう。
また、革命後に台頭したブルジョワ階級の食文化も本書を理解する上で欠かせない背景です。
王侯貴族の贅を尽くした饗宴文化は革命によって一時的に途絶えましたが、かつて宮廷に仕えた料理人たちが市中でレストランを開業したことにより、公共の美食文化が花開きました。
サヴァランは貴族的美食の真髄を熟知する一方で、市民社会へと広がりゆく新たな食文化にも鋭い洞察を向けたことは、本書を「パリの美食家たちへ捧ぐ」と謳っていたことからも見てとれます。
彼の美食論が出版当時に歓迎されたのは、まさに時代が求めたものだったからでしょう。
旧体制の宮廷料理の洗練された伝統と、新たな市民社会の科学的・合理的精神。これらを見事に融合させ、「よりよく生きる術」としての食文化を提示した点には時代適合性を超えた圧倒的編集性を感じます。
「食」とはなんだろう
「食」とは一体何なのでしょうか。
率直に申し上げれば、これまでその本質を真正面から考察することなどほとんど(というか全く)ありませんでした。
私は昔から食に対する関心が殊更に高いわけではなく、正直に言ってこの書物との邂逅によって俄かに興味が深まったわけでもありません。
私が興味を持ったのはむしろ「食」というある種のメディア、あるいはコンテンツを媒介として人間をいかに観察し、いかに理解しようとするかという「態度」のほうです。
単なる生存のための行為を芸術的・哲学的次元にまで高め、文明の発展を支える重要な要素となっている食。
そもそも、食とは人にとって何であるのか。
私たちは食材を育んだり狩りをしたりしながら収穫し、時に裁断し、時に洗い、時に加熱し、さまざまなプロセスを経て摂取します。生命機能を維持するだけならそれだけで良かったのです。
ただそれのみで完結し得たはずの営みが、なぜフランス料理のような複雑かつ多彩な装飾的様相へと発展していったのか、かねてより非常に不思議でした。
こんな一文があります。
「食欲、飢え、渇きなどの刺戟によって生じる味覚は、人間にとって必要なさまざまな作用の基盤となり、それによって人は成長して大きくなり、各部を発達させ、身体を維持し、生命の発散によって生じる消耗を補うのである。この世に存在する有機体は、かならずしも同じ方法で自らを養っているわけではない。造物主は、きわめて多様な方法によって、それぞれに確実な効果が得られるよう、さまざまの有機体に互いに異なる自己保存の方法を割り当てたのである。」
〜
「人間は、特殊な本能が食を摂る必要があることを彼に告げると、ただちに探索行動に入り、その必要を満たすものがありそうだと直感するとすぐにそれを捕まえて、食べる。そうやって人間は英気を養いながら、彼に与えられた人生の役割を果たすべく生きていくのである。」
原始的に、人はただ食べるだけで良かったのです。
しかし、人には対話を重んじる精神性があったからこそ進化したのではないかと思うのです。
フランス料理の伝統や『美味礼讃』に象徴される食文化の発展を振り返ると、単なる栄養摂取や個人的満足を超えた、対話という社会的営みを尊重する精神性がその根底にあったように感じてなりません。食卓を囲んで思想を交換し、感性を共有する場としての「食」の位置づけこそが、洗練された美食文化を生み出す原動力となったと思うのです。
サヴァランが生きた時代の社交界やサロン文化、そして革命後の市民社会における食文化の変容は、いずれも人々の対話を促進する媒体としての「食」の重要性を示しています。人類が築き上げてきた食文化の真髄には、常に他者との関係性を豊かにし、共感の場を創出しようとする深い願いが横たわっているのかもしれません。
食を通じた対話の重視。
その時間をより特別で豊穣なものとする媒体として、華麗な料理や格式ある調理法が受容されるようになっていったのではないかと感じました。
家族や友人、親しい人々、身分を異にする人々と食卓を共にし、言葉を交わし、時には饗宴を設けて交流を深める。そうした文化が私たちの社会には根付いています。
フランス料理のコースが前菜からメイン、デザートへと展開する「物語性」と「歓待の精神」を重んじてきたのも、まさに食卓での対話をより深淵なものへと誘う工夫なのでしょう。
フランス料理は長い時を経て「高度に体系化された技術」と「素材の旨みを繊細に引き出す調理法」、さらには「美的に洗練されたプレゼンテーション」が融合し、いつしか料理は芸術と評される境地にまで到達しました。シェフは職人であると同時に創造者でもあり、独創的な着想と繊細な技巧を駆使して、新たな味覚の芸術を創出していくのです。
このように思索を巡らせると、食とは単なる栄養摂取の行為を超えて、他者への敬意や配慮を形態化するデザイン的思考の結晶であり、人類が幾星霜を経て培ってきた対話の叡智そのものだと言えるのではないか、そう感じました。
何を自らの内に取り込むかに自覚的になること
サヴァランは、人間にとって食べることが単なる生存行為以上の意味を持つことを哲学的に論じました。
有名な箴言はこれですね。
「Dis-moi ce que tu manges : je te dirai ce que tu es.(君が何を食べているか言ってみたまえ。君が何者であるか言い当ててみせよう。)」 。
この洞察は、単に栄養素の摂取という次元を超え、より広範かつ奥行きある意味を内包しています。
しかし、この思想の射程は「食べる」という物理的行為の範疇に留まるものではないと思うのです。
例えば、何を学び、誰と交わり、何を見つめ、何に触れるか。このような動作もまた私たちが「摂取」し、自己の一部として同化していくものと捉えることができるでしょう。
ここに浮かび上がるのは、人間存在とは外部からの取り込みと内部での変容の連続的過程であるということです。
我々は「閉じた体系」ではなく、常に外界と相互作用しながら自己を形成する「開かれた存在」だということを改めて認識させられます。この視点から見れば、食事という日常的行為は、人間が世界と交わる最も根源的な様式の一つと言えるのかもしれません。
知識体系、人間関係の網目、蓄積された経験、感覚的情報、そして食物。これらが有機的に結合し、私たちの生の質と方向性を決定づけていきます。我々が何を選び取り、何を排除するかというこの絶え間ない選択の連鎖が、やがて人格、人生という複雑な物語を織りなしていくのです。
サヴァランが残した多くの箴言は、単なる食に関する指摘、助言、警句ではなく、人間存在の本質に迫る哲学的命題を含んでいます。
何を自らの内に取り込むかによって存在そのものが変容していくという真理は、現代の消費社会においてなお、いやむしろ今日においてこそ、深く考察されるべきなのかもしれません。