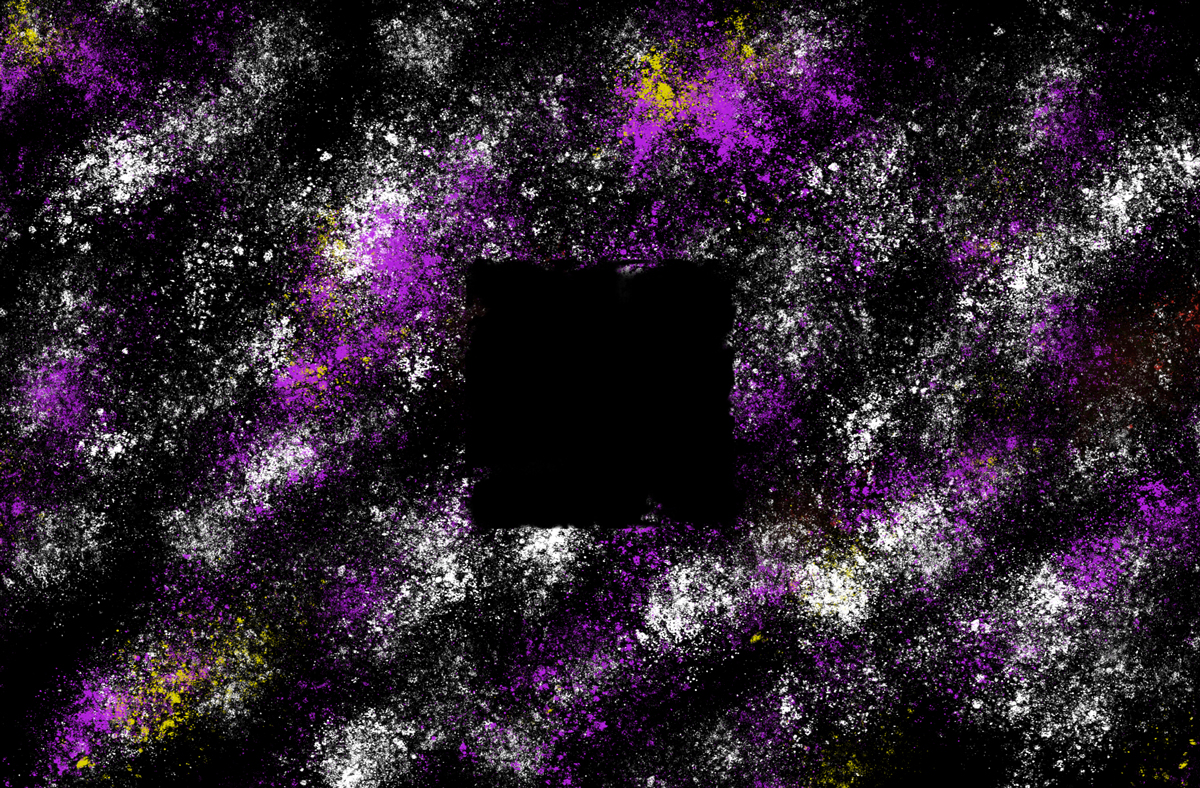2025年も気づけば11月も半ばですね。
つい先日まで「暑い暑い」と言っていたような気がするのに、季節はあっという間に秋を越え、冬の気配すら感じる頃になりました。
年々、時間の流れが加速しているように感じます。
さてさて、そんな中、先月10月の会社の動きを振り返ってみました。
これまでの振り返りでは「組織としての成長」を感じることが多かったのですが、今回は「私自身が経営者としてどう向き合うか」に焦点が当たった1ヶ月だったように思えます。
今回は会社全体というよりも、私個人がどのように考え、どのように動いたのかという点を残しておこうと思います。
実感できた成長
10月を振り返ると「会社が成長する前に、まず自分が変わらなければダメだぞ」という当たり前すぎる気づきに、ようやく腹の底から向き合えた月だったように思います。
「お前は何年経営をしているんだ」というご指摘は本当にごもっともです。すごく反省しておりますのでどうかご容赦ください。
さて、まず伝えておきたいのは弊社の社員である中川と小林の存在です。
彼らは本当に優秀で、二人がいなければ会社の運営は成立しません。長年一緒に仕事をしていますが、ここまで信頼できる仲間はそうそういないだろうなと思っています。
成果物の質、仕事の進め方、向学心、視座などなど、尊敬すべき点がたくさんあります。もっとすごくなるんだろうなと日々楽しみな二人です。
が、直近で締まった第3期は、私が予想した以上の何倍も苦しい状況が続いてしまいました。
理由は明確で、彼らの強みを相殺するような「組織的な弱さ」が数多く存在していたからです。
10月は、その弱さと正面から向き合うために使用しました。
優先的に向き合ったのは個別具体的な実務やスキルの話ではなく、「組織構造」「仕組み」「役割」「体制」といった、すごく根本的な部分です。
「実感できた成長」という章タイトルではありますが、正直なところ成長というよりも、まずはマイナスをゼロに戻すために何ができるのかを考えた時間だった気がします。放置してきた課題をひとつずつ拾い、考えていくような、そんな地道な月でした。
その中で私が強く感じたことがありまして。
会社を前に進めるためには私自身が現場に居続けるのではなく、「経営」に徐々に軸を移す必要があるということです。これは到底1、2ヶ月でできることではなく、10年20年とかかる話かもしれませんね。
現場は好きですし、実務のスキルもしっかり磨きたいと思っています。それが故に気づけば自分で手を動かしてしまうこともありました。でも、それでは会社が大きくならないんです。
メンバーは十分に力を持っており、伸び代もあります。私が実務を抱え込むのはむしろ会社の成長を遅らせてしまうリスクがあると感じました(もちろんただ単に私の業務を減らし、彼らの業務量を増やしたいという話ではありません)。
彼らが成長しなければ会社の成長もありません。会社の成長がなければお客様の成長もご支援できず、結果として社員の物心両面の幸せも叶えられない。
もしそうなったとしたら、その原因は何か。
私なんですね。
だから10月は「自分が変わるための準備期間」としての意味合いが強くなりました。
財務状況の棚卸し、事業計画の作り直し、経費の見直し、バックオフィスの再構築、そして会社の方針づくり。このあたりはほとんど私の仕事で、実務面では中川と小林に負担をかけてしまった部分もあったと思います。ごめんねという気持ちもありながら、経営に向き合わせてくれた二人には本当に感謝しています。
3期目は、組織として未熟な点がたくさん露出した時期でした。
その弱点をひとつずつ潰し、会社をもう一度健全な状態に戻す。そのための大切な一歩が、10月だったように思います。
次の一歩に向けて
10月で明らかになった弱点は数えきれないほどあります。
ただ、そのすべてを一度に改善しようとしても前に進めません。だからこそ、「今取り組むべき点」を3つに絞りました。
この3つは、会社の未来に直結する“骨格づくり”として捉えています。
1 会社の方針の明確化
これはですね、ずっと向き合い続けながら結論が出せずにいたテーマなんです。10年近くずっと葛藤してきました。
方向性をAに寄せればBが消える。しかしBを立てればHとLが喧嘩してしまい、Aが成り立たなくなる。そんな感じ。
真っ白なピースのパズルを完成形の絵がわからないまま延々と組んでいるような感覚でした。
何を選んでも何かがこぼれる。何かを決断した瞬間、大切にしていたものが霧散してしまう。そんな不安がずっと判断をぼやけさせていたのだと思います。
そして、その原因もまた明確でした。
私自身の力不足。それだけです。
本当にありがたいことに、色々な相談をいただけるという何とも恵まれた状況に甘えてしまい、範囲を広げすぎていました。
「ある程度何でもできる会社」に見えてしまっていたんですね。結果として、自分たちが何者なのかが曖昧になってしまった。
多芸は無芸。
“何でもできる”は、“何も極めていない”と同義でもあります。
私はその危うさに薄々気づきながら、会社存続のためにずっと目をそらしていたのだと思います。
逆説的ではありますが、私の仕事は会社を存続させること。そういった意味では正しい意思決定だったのかもしれません。しかしこの判断を続けてしまうと会社存続の毒となる。
だからこそ「自分たちは社会に対して、どんな価値を提供する会社なのか」を11月で形にすると決めました。
何年も考え続けてきたためピースはたくさんあります。それを編集し、まず形にするのが最も優先されることだと思っています。
2 やらないことを決める
戦略とは “戦うことを略すこと”。
いい言葉ですね。本当にその通りだと思います。しかし実践するとなるとなかなか大変でした。
前述の通り、これまでは「とりあえず相談に乗る」ことが多かったのですが、ご相談に対する課題解決手法が会社の方向性とずれてしまうと「ただの消耗」になってしまいます。
これからはそれをやめようと思っています。
例えば今の会社の強みと一致しない仕事。成長方向と真逆の領域。期待値に応えられない可能性が高い依頼。
こういったものは、しっかり線を引いていきます。
しかし時代や社会の変化に対応していくことは大切です。
何でもかんでも頑なにルールに嵌めるようなことはしません。水のように柔軟に形を変えながらも、踏み込まない“境界線”を持つという意識です。
この「やらないこと」は明文化されていませんでした。だからこそ今、それを丁寧に決めている真っ最中です。
少し余談になりますが、最近、正確な金額は伏せますが数千万円クラスのご相談をいただきました。弊社の規模からすれば、喉から手が出るほどほしい売上です。この売上があればどれだけ助かることか…。
本当に、本当にありがたいお話でした。
結論から申し上げると、このお話は辞退させていただきました。
理由はひとつです。
「やらないことを決める」という方針に反していたから。
いただいた案件は、私たちがまだ十分に専門性を発揮できる領域ではありませんでした。お受けしたとしても、お客様にとって最高のアウトプットを約束できませんでした。
「お客様が感動するものを作れるの?」という問いに、自信を持って「はい」と言えなかったのです。
この判断は経営者失格なのかもしれませんね。“目の前に売上があるのだから何が何でも食らいつくべきだ”という考え方もあるでしょう。
でも弊社はこれでいいんです。
目先の売上のために、自分たちの価値基準を曲げる会社にはなりたくありません。もし私が「やろう」と言えば、社員たちはきっと全力で取り組んでくれるでしょう。でもそれでは彼らを疲弊させてしまいます。
必要以上の負荷を強いることになるし、未来に必要な学びとは異なる方向に時間を使わせてしまう。
そして何より怖いのは「売上のためなら無理な仕事も受ける会社」という癖がついてしまうことです。
これは、私が絶対に避けたいことでした。
だから今回の判断は、会社の未来のためでもあり、メンバーの未来のためでもあり、そして何より、自分たちの信じる仕事の仕方を守るための選択にもなりました。
3 月次決算をもっと深く読み解く
これは11月だけでなく「これからずっと続けること」ですが、念の為綴ります。
月次決算はやっているものの、それを“ただ眺めているだけ”になっていたことは否めません。
例えば、
- どの数字がどれだけ何に効いているのか
- どの指標を改善すれば、どんな結果が生まれるのか
- いつまでに何をどう変えなくてはいけないのか
- 減らすべきコストはどれで、増やすべき投資は何か
- 計画との差異がどこから生じているのか
などなど、数字に向き合わなくては経営ができません。適当に眺めるだけであれば数字は情報ではなく「ただの数字」です。
私自身の数字意識が低ければ、会社全体の数字意識向上など期待すべくもありません。
だから、まずは私が変わる必要がありました。
もちろん財務状況の全てを社員に共有する必要はないと考えていますが、決算書の読み方、財務諸表の見方など、他社事例などを参考にさせていただきつつもっと積極的に共有していくつもりです。
数字に強い組織は、絶対に強い。逆は言うまでもなく。
その土台の土台をまさに今作ろうとしています。
2025年11月の動き
11月は、これまで書いてきた内容を「実際の計画」に落とし込んでいく月になります。
やるべきことは既に明確で、あとはどれだけ具体的に、どれだけ深くできるか。その勝負です。
まずは会社の方針づくり。
数年単位で霧が晴れなかったテーマにようやく向き合い、今まさに形にしようとしています。これは会社の背骨になる部分で、ここが定まらない限り、採用も、サービスの磨き込みも、投資判断も、全部が揺らいでしまう。だからこそ、11月はここにかなりの時間を使うつもりです。
そんな中、新しいご相談も増えています。
チャレンジングな案件もありますが、だからこそ慎重に見極めて進めていかなくてはなりません。単純に「売上としてやる/やらない」ではなく、会社の方向性と整合しているか、メンバーの成長につながるか、会社としての価値を高められるか。そうした視点をより強く意識することになります。
今は「個々のスキルアップ」と「組織としての骨格づくり」の、ちょうど境界線に立っているような時期です。
個人としての力を高めることにも意識を向けなくてはいけませんが、会社としての仕組み・役割・判断基準・方針を整えなければ、チームの力は最大化しません。
11月はまさにその“骨子づくり”を重点的に進めるタイミングです。
言い換えると、「これからの数年を決めるための準備をする月」と言えるかもしれません。
この準備が整えば2026年、そしてその先のフェーズに向けてより強く加速できるはずです。
なかなかヘビーな課題ですが、がっつり思考して行こうと思います。