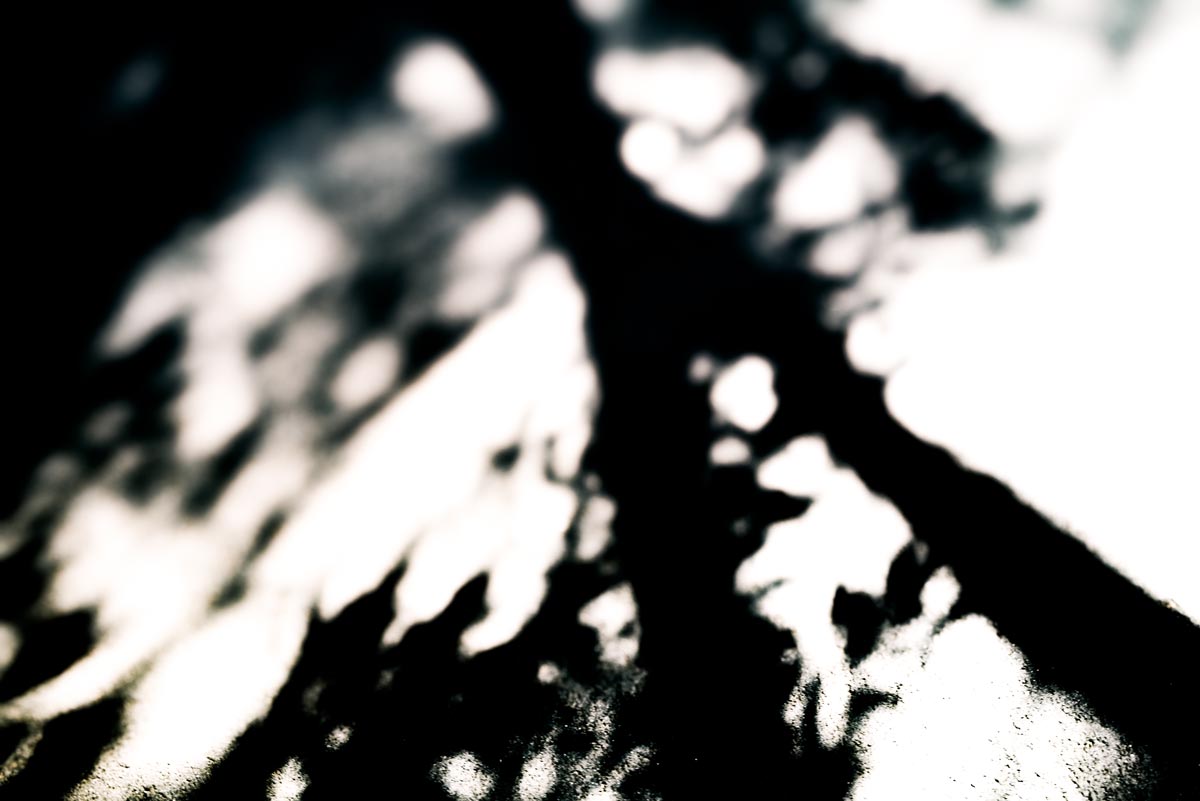「間欠」という言葉には、「一定の間隔で止まったり始まったりする」という意味があります。
それは単なる中断ではなく、揺らぎを含んだ流れなのだと思います。
ひとつの方向に一直線ではなく、時に沈み、また浮かび、折り返し、離れ、戻ってくる。その柔らかなリズムの中に、人の営みの自然さが宿っているのかもしれません。
間欠性、「間」の美
世界は、間欠的に現れます。
風は吹いたり止んだりし、木々は芽吹いたかと思えばいつしか静かに眠ります。虫は年に数日だけ姿を見せ、花は僅かな時間だけ咲きます。
それらは、続いているというより、「現れては消える」というリズムの中にあるようです。
私たちの営みもまた、そのような断続の中にあります。
あるとき言葉が浮かび、あるとき手が止まり、何もしないまま一日が過ぎていく。でも、それは途切れではありません。
沈黙の中にも、流れはあります。
間欠的であることこそが、世界の呼吸であり、私たちの自然な姿なのです。
日本の文化には「間」という美意識があります。
音と音のあいだ、語と語のあいだ、人と人のあいだにある、名づけがたい空白。それは、単なる「何もない状態」ではなく、意味を孕む余白です。
休符があるからこそ音楽が生まれ、沈黙があるからこそ言葉が届きます。
空いていること、それ自体が深さを生み出しているのです。
間欠性は、調和の感覚でもあります。
何かをしていない時間にも、私たちは世界と関わっています。外に向かって動いていないときでも、内に向かって深く沈み、まだ言葉にならない感覚を耕しているのかもしれません。
連続することや、成果として積み上げることだけが生ではありません。
現れては消えること、途切れながらも確かに続いているような、そうした非連続の時間の中にむしろ深く根を張る何かがあるように感じます。
私たちは、何者かになるために動くだけでなく、ただ「そこに在る」ことで世界とつながる瞬間もあります。
続いているようでいて実は一つひとつが関係している。そんな「点の時間」のつながりが、私たちの生を静かに形づくっているのかもしれません。
2025年7月のプレイリストを作りました
私は間欠的にしか現れないものに惹かれてしまいます。
沈黙と声、書く日と書けない日。それらを切り離さずに抱えていくことで、かたちにならない何かが立ち上がる気がします。
すぐに全てがつながらなくてもいいのです。
つながらない断片が、なぜか心を打つことがある。途切れながら、揺れながら続いていくような、そんな静かな拍動に今月は耳をすませてみたいと思います。
このプレイリストの収録曲
- Intermittent – Iwamura Ryuta
- Donna Lee – Joseph Shabason
- Berlin – アルヴァ・ノト & 坂本龍一
- april ~ from sea shell – Sawako
- A Message to Women – Reyna Biddy
- 新しい靴を買わなくちゃ – 坂本龍一
- Chōchin – 冥丁
- I Miss You – 巨勢典子
- 空色 – いろのみ
- Above Chiangmai – Harold Budd & Brian Eno
1. Intermittent – Iwamura Ryuta
タイトルの通り「間欠」を意味する曲です。
ミニマルな構成のなかに微細な音の揺らぎや間が差し込まれ、聴く者の時間感覚をやさしくずらしていきます。
派手な展開もなく、ただ浮かんでは沈むような音の粒たち。
その間欠的な構造は、何かを語るというよりも「語らないこと」を通して、沈黙や余白の豊かさを伝えてくるようです。
耳を澄ませば澄ますほど、そこにある「何もないもの」の深さが立ち上がってきます。
聴くこと自体が、ひとつの瞑想行為になっていくような、静かで孤独な美しさをもった一曲です。
2. Donna Lee – Joseph Shabason
旋律の断片が残響とともに間欠的に立ち上がる、アンビエント・ジャズ。
ジャズ特有の即興性はここでは霧散し、輪郭を失ったフレーズが空間に浮かんでは消えていきます。
サックスの音はときに遠く、ときに近く、フィルターを通したような質感で語りかけ、まるで古いカセットテープを再生するかのよう。
整ってはいない、しかし美しい。「再解釈されたジャズ」というよりも「記憶の隙間に現れるジャズの幽霊」のような一曲です。
3. Berlin – アルヴァ・ノト & 坂本龍一
アルヴァ・ノトと坂本龍一という異なるフィールドの音楽家が融合した名作。
ノトの緻密なグリッチ音と坂本のピアノが互いに距離を保ちながら交わるその構造は、音と音のあいだに「間」が確かに存在することを感じさせます。
規則性と不規則性のあいだを揺れ動くリズムは、まさに間欠的。整然としているようで、どこか不安定で、呼吸を合わせることすらためらうような、静かな緊張感を伝える一曲です。
4. april ~ from sea shell – Sawako
環境音と、ほのかにかすれる電子の響きがレイヤーとして重なり合い、まるで貝殻の内側で響いている音に耳を澄ますような没入感を与えてくれる、そんな曲。
断続的に現れるさざ波のようなパルスと、静寂の気配が交錯する音の構造は、「聴こえるもの」と「聴こえないもの」の境界線をぼんやりとさせ、時間の感覚さえも間引いていきます。
5. A Message to Women – Reyna Biddy
ロサンゼルス出身の詩人・作家・スピーカーであり、自己愛、癒し、そして黒人女性としてのアイデンティティをテーマに詩的表現を続ける現代アメリカ文学の新しい声のひとり、Reyna Biddy(レイナ・ビディ)。
「A Message to Women」は、彼女の代表作『I Love My Love』(2017年)に収録された詩の音源化であり、音楽というよりも“祈り”や“呼びかけ”のような作品です。
6. 新しい靴を買わなくちゃ – 坂本龍一
北川史悦吏子監督の映画『新しい靴を買わなくちゃ』のサウンドトラック・アルバムから。
軽やかな旋律とシンプルな構成は、表面上は明るく穏やかに流れていきますが、その裏側には「理由のない寂しさ」や「何かを失った後の空白」が潜んでいるような一曲です。
7. Chōchin – 冥丁
広島を拠点に活動する日本の音楽家、冥丁。
「Chōchin」はまるで夜道にぽつんと灯る小さな明かりのように、控えめで、しかし深い余韻を残します。光そのものよりも「闇の中にぽつんとある光」としての在り方が、この曲全体の構成と深く響き合っています。
8. I Miss You – 巨勢典子
ローズピアノソロアルバムから。
Nujabesの「reflection eternal」に「I Miss You」がサンプリングされた、一曲。
音楽というより「内面の独白」のような佇まいがあり、言葉にならない想いが音と音のあいだに浮かび上がってきます。
9. 空色 – いろのみ
柳平淳哉と磯部優による日本のアンビエント・デュオ。
「空色」とは単に色彩を表す言葉ではなく、空が刻一刻と移ろうように「ずっとそこにあるのに、同じではいられないもの」の象徴でもあるように思えます。
澄んだ空気にそっと添えられるようなピアノの旋律は、明確な始まりも終わりも持たず、音が生まれ、揺れ、消えていくような、どこか切ない響きを孕んでいます。
10. Above Chiangmai – Harold Budd & Brian Eno
単音がゆっくりと空間に置かれるように鳴るハロルド・バッドのピアノ、イーノのアンビエント的感覚がその余韻を拡張していきます。
音は決して押し寄せてこず、むしろ「鳴らない時間」を積み重ねることで、聴く者を内面へと沈めていきます。ピアノの一音一音が、時間の中にぽつんと佇むように響く、静かな浮遊感に満ちた楽曲です。