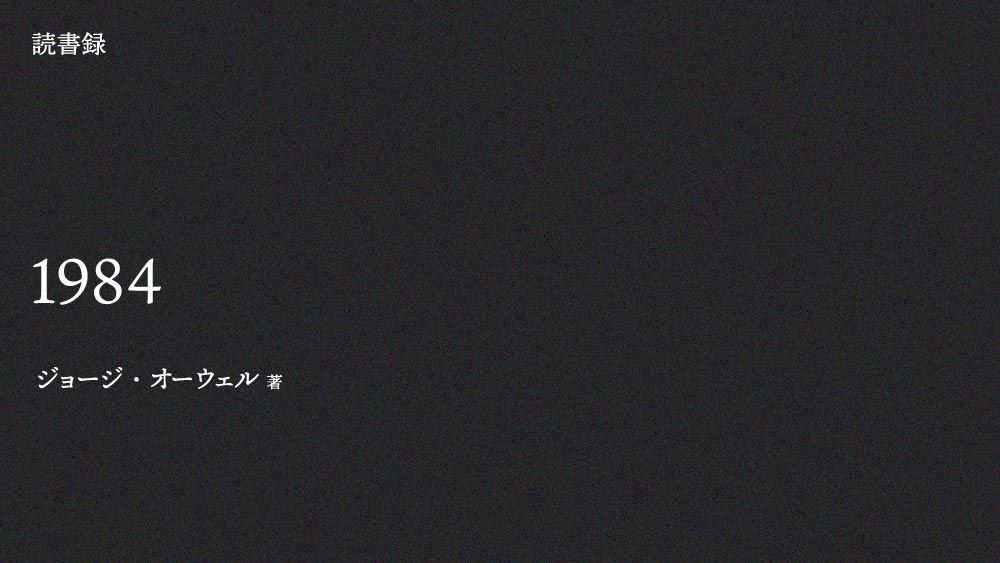ディストピア文学の金字塔「1984」。
本当に恐ろしい作品でした。
1949年にジョージ・オーウェルが著したこの作品は、70年以上の時を経てなお衝撃的です。
ディストピアとはユートピアの対義語。社会全体が統制され、人間性が否定され、個人の自由や人間の尊厳が脅かされるような、そんな絶望的な社会状態を指す概念です。
数あるディストピア作品の中で、1984ほど本質的な恐怖を描き出した作品はないのではないかとすら思います。
それは、社会における人間性の抑圧と管理というテーマを驚くほど本質的に描き出しているからでしょう。
70年前に書かれたこの作品には現代社会を予言するかのような描写が数多く登場します。今私たちが生きているこの世界こそディストピアなのかもしれない、そう思うほどに。
今私たちが生きている社会を理解するために、人間らしさとは何かを考えるために、この作品との出会いを通じて感じた雑感を記していきたいと思います。
あらすじ
まず簡単なあらすじを(ネタバレを含みます)。
「1984」の世界は、核戦争以来終わることのない争いに支配された社会です。人々は完全な監視下に置かれ、「テレスクリーン」と呼ばれるモニターが各家庭やあらゆる場所に設置され、政府のプロパガンダを流すと同時に、人々の一挙手一投足を監視しています。
さらに街中には無数のマイクが仕掛けられ、誰もが常に監視の目にさらされている、そんな社会が舞台です。
街には「ビッグ・ブラザーがあなたを見ている」と書かれたポスターが貼り巡らされています。このビッグ・ブラザーは党のリーダーであり最高権力者とされている人物です。
この世界の主人公であるウィンストンが働く「真理省」。
その壁面には「戦争は平和なり」「自由は隷属なり」「無知は力なり」という党のスローガンが掲げられています。この省の役目は、歴史や情報の改ざん。ありとあらゆる記録や情報が党の主張に沿うように書き換えられ、真実は闇の中に葬られてしまいます。
そんな世界に疑問を抱いたウィンストンは、ある日テレスクリーンの死角で日記をつけ始めます。しかしこの行為は最悪の場合死刑にも値する重罪とされていました。個人の思考をアウトプットする行為そのものが、この社会では許されない行為だったのです。
「未来へ、或いは過去へ、思考が自由な時代、人が個人個人異なりながら孤独ではない時代へ― 真実が存在し、なされたことがなされなかったことに改変できない時代へ向けて」と日記を綴ります。
自由、真実なき時代、ウィンストンはビッグ・ブラザーを打倒するための歩みを進めます。
ある日、ウィンストンは真理省の同僚ジュリアから突然愛の告白を受け、戸惑います。この社会で愛は不要なものとされ、党によって否定されていたからです。
しかし二人は会う場所を探すことすら困難な中、監視の目をかいくぐり、徐々に親密さを深めていきます。
人目を忍んで出会う場所を探す中で、二人は下町の古道具屋に辿り着きます。古い時代への郷愁を抱く老人チャリントンが営むその店の2階は古い版画が壁にかかり、マホガニーの大きなベッドがありました。その部屋を借り、密会を繰り返します。
チャリントンによればこの場所にはテレスクリーンがないとのことだったため、密会には最適だったのです。
その後二人は、真理省の高級官僚オブライエンとの接触を試みます。
ウィンストンは、彼もまたこの世界に疑問を持つ者ではないかと直感していました。
オブライエンの自宅に招かれた二人に対し、彼は自身も党への反抗者であることを告白し、共に行動することを提案します。禁じられた愛から始まった二人の物語は、やがて体制への抵抗という新たな段階へと踏み出していきます。
二人はオブライエンの手引きにより、体制の敵として徹底的に排除された人物、エマニュエル・ゴールドスタインの禁書を手にします。
この世界の真実が記されているとされる本。二人はようやく世界の核心に迫りつつありました。
チャリントンの古道具屋の2階で禁本を読み、世界の真実について語り合っていた二人。その背後から声が響きます。
「諸君は死んだも同然だ」。
この部屋にかかっていた版画が落下し、突如テレスクリーンが現れます。そして黒い制服の男たちが現れ、二人を囲み、抵抗の余地もないまま思想警察に逮捕されてしまいます。
密告したのは古道具屋の主人チャリントン。チャリントンは実は思想警察でした。
二人は「愛情省」へと連行され、離れ離れになります。
そこで待っていたのは凄絶な拷問の日々でした。あまりに苛烈な拷問を繰り返されたウィンストンは、拷問による苦痛を避けるために身に覚えのない罪さえも自白するようになります。精神を破壊されたウィンストンの前に現れたのは、かつて同志だと信じたオブライエンでした。
彼は二人を罠にかけるために以前から監視していたことを明かします。
全てが欺瞞であり、信頼できるものは何一つなかった。この残酷な真実が、ウィンストンの精神を更なる深淵へと追い込んでいきます。
ここからさらにウィンストンへの拷問は加速します。党の思想、真実を捻じ曲げることの正当性など、歪んだ思想を叩き込まれ、数々の暴力に見舞われます。骨は砕け、毛髪は抜け落ち、痩せこけてしまいます。
拷問はまだまだ続きます。
オブライエンから党の歪んだ思想を徹底的に叩き込まれ、肉体は限界まで追い込まれていきます。かつての面影は完全に失われていきました。
そして最後の場所、「101号室」。
それは、人間が最も恐れるものと対峙させるための拷問室でした。ウィンストンを待ち受けていたのは、彼が最も恐怖する存在であるネズミが入ったケージ。ケージの片側に顔をはめ込むマスクがついており、そこに顔を入れるとネズミが襲いかかってくる仕掛けが施されています。
ケージに顔を入れられ、眼前に迫ったネズミにより限界を迎えたウィンストンは絶叫します。ジュリアを身代わりにしろ、ジュリアなんてどうなってもいいと。
この言葉と共に、彼の中で最後まで残っていた人間性、愛する者を守るという最後の尊厳までもが、完全に崩壊していきました。
オブライエンはこの言葉を聞くと同時にケージを閉じます。
党による拷問は肉体の破壊を超えた、人間の魂の根幹を破壊する残虐な行為でした。愛する者を裏切ることで、ようやく救われる。この究極の選択を強いられることで、ウィンストンの人間性は完全に打ち砕かれてしまったのです。
釈放されたウィンストンの姿は、もはや人間というより空っぽの容器でした。そこに流し込まれていくのは、巨大な党の思想。自我を完全に失った彼の精神は、党の教えに従順な存在へと変貌を遂げていきました。
党の真の目的は、単なる拷問による屈服ではありませんでした。
彼らが求めたのは、ウィンストンの精神を根本から作り替え、ビッグブラザーへの純粋な愛を植え付けること。そして、その上で彼を抹殺することだったのです。
そんなウィンストンは同じく釈放されたジュリアと偶然の再会を果たします。しかしそこにはもはや、かつての愛の痕跡すら残っていません。互いが互いに違和感を感じます。拷問により変わってしまったのは一体どっちだったのか。
ウィンストンの心に残されたのは、ビッグ・ブラザーへの深い、歪んだ愛情だけでした。
物語はウィンストンがビッグ・ブラザーの愛に気づいたところで幕を下ろします。
現実を疑う能力を奪われた社会、その恐ろしさ
1984、本当に恐ろしい話です。
以下はオブライエンがウィンストンを拷問している中で出た言葉です。
「心なき服従でも、最大限に卑屈な降伏でも、我々が満足することはない。いずれ君が降伏するときには、君の自由意志でなくてはならん。我々は、異端者が反逆するから破滅させるんじゃない。抵抗を続けるかぎり、破滅させることはない。我々は彼らを変容させるのだ、内なる心を捕えるのだ、彼らを再形成するのだ。心にはびこる邪なものと妄想を燃やし尽くし、我々の側に導くのだ。うわべではなく真の、腹心の同胞としてね。殺してしまう前に、我らの一員にするということさ。
〜
我々によってここに連行され、最後まで抵抗を貫いた者は誰もいない。ひとり残らず綺麗に浄められたのだよ。君が無罪と信じた哀れな反逆者三人も、つまりジョーンズ、アーロンソン、ラザフォードの三人も、最後は我々にひれ伏したのだ。私自身が尋問に加わった。徐々に心をすり減らし、泣きごとを漏らし、ひれ伏し、涙を流す連中の姿をこの目で見てきたんだよ……最後には、苦痛のせいでも恐怖のせいでもなく、純粋に後悔の念からそうなるのさ。尋問が終わるころには、連中はもはや人間の抜け殻になっていた。心の中にあるのは、自分たちがしてきたことへの悲しみと、ビッグ・ブラザーに対する愛情だけだ。彼らがいかにビッグ・ブラザーを愛しているか目の当たりにするのは、実に感動的なものだったとも。自分の心がまだ清らかなうちに死んでしまえるよう、今すぐ射殺してくれと必死に乞うんだよ」
ウィンストンがその後どうなったのか、本作では明言されていません。しかしこのオブライエンの言葉を見るに、ビッグ・ブラザーへの狂信的な愛に目覚めた彼の頭に最後には銃口が向けられたのでしょう。
究極の服従を得た後の抹殺。考えただけでもゾッとします。
社会における恐怖とは何でしょう。
暴力、差別、強制労働、貧困。これらはすべて確かに恐ろしい現実です。が、1984が描く最も深い恐怖は「現実を疑う思考能力を奪われた社会」にあると感じました。
真理省による歴史の改ざんがそれを代表する行為でしょう。情報そのものを捻じ曲げることで、人々の思考の基盤を破壊していく。真理省の行なったこの支配は極めて巧妙でした。
しかし情報の改ざんはフィクションの中にのみ存在している訳ではありません。
真理省による情報の改ざんは、旧ソビエト連邦が行った写真修正、レーニンとトロツキーの写真から人物を消し去った行為を想起させます。旧ソビエト連邦のプロパガンダ担当者たちが、失脚した政治家たちや、特定の状況において存在していると好ましくないと判断された人などを写真から削除していたことは有名です。
人間の判断や学習は、すべて情報を基にしています。その情報自体が歪められているとすれば、私たちは何を信じ、何を基準に考えればよいのでしょうか。情報を奪われた人間は実に無力なのかもしれません。
人々から思考能力を奪い、党の思い通りに支配する。そのために党は「テレスクリーン」による監視、「二重思考」による認識の歪曲、「ニュースピーク」による言語の制限などを通じて、人々から思考能力を奪っていきます。
徹底的な監視と洗脳、ディストピアの中枢を担うテレスクリーン
私がこの本を読んでフィクションと思えない程のリアリティを感じたのがこの「テレスクリーン」という装置です。
もはやディストピアそのものと言っても過言ではないほど、その力は絶大でした。
この装置は市民を監視し、洗脳するための道具です。そこから流される情報は、プロパガンダや戦勝報道、経済成長の虚像など、真偽の定かでない情報の連続です。
「支配し、そして支配し続けるには、現実感覚を狂わせることが不可欠である」。作中に登場するこの一文が示すように、テレスクリーンは人々の現実認識を歪めるための装置として極めて有効に機能していました。
「二分間ヘイト」という番組も特徴的でした。この二分間ヘイトは国家の敵とされるゴールドスタインを国民が一斉に罵倒する時間です。これは現代のテレビやSNSで見られる集団的な批判や誹謗中傷の狂騒を予言するかのようです。
リーガルハイというドラマにこんなセリフが出てきます。有名なセリフですね。
「本当の悪魔とは巨大に膨れ上がったときの民意だよ。自分を善人だと信じて疑わず、薄すぎたない野良犬がドブに落ちると一斉に集まって袋叩きにしてしまう。そんな善良な市民たちだ。」
まさにこれを思い出しました。
1949年、インターネットもスマートフォンも存在しない時代に書かれた本作1984。
しかし、そこで描かれたテレスクリーンの機能はテレビにも似ますが、現代の私たちが手にする端末と驚くほど重なり合います。
常に接続され、常に情報を受け取り、そして知らず知らずのうちに私たちの行動を記録し続ける装置。便利さと引き換えに、私たちは自らの意思で「テレスクリーン」を持ち歩くようになったのではないかと思ってしまいます。
特に危険なのは、SNSで時折発生する集団的な攻撃性です。それはまさに「二分間ヘイト」の現代版と言ってもいいのではないでしょうか。
特定の個人や集団への憎悪が瞬く間にネット空間を席巻していく様は、本作で描かれた光景と重なります。
そして最も恐ろしいのは、私たちがこの状況に気付きながらも、もはやこの装置なしでは生活できなくなっているという現実かもしれません。
常に画面から与えられる情報に依存し、それによって知らず知らずのうちに思考が誘導されているのではないか、と感じてしまいます。
70年以上前に書かれた小説がこれほどまでに現代のテクノロジーの闇を言い当てていることに、恐ろしさを感じます。
真実ではない情報、これまでと異なる情報を信じ込むための二重思考
人間の記憶、それは本来最後まで改ざんできないはずのものでした。
しかし1984の世界では、「二重思考」という恐ろしい概念が存在します。おおまかに表現すると以下のようなものです。
- 特定の事実が改ざんされたら、新しい事実を正しいと思い込め
- 元々あった記憶は消去しろ
情報が改ざんされれば、それを正しいと思い込み、元の記憶を消去する。この非人間的な思考法を、党は強制します。
一般大衆は、メディアを通じた情報操作に気付かないまま洗脳されていきます。しかし党員たちは、その改ざんの事実を知りながら、自らの記憶を書き換えることを強いられるのです。
この二重思考は、決して架空の概念ではありません。
第二次世界大戦中の日本を例に取れば、アメリカに対する認識の劇的な変化がありました。
敵国として攻撃の対象だったアメリカが、降伏後は一転して友好国となる。人々はその急激な方向転換を、驚くほど素早く受け入れたことは広く知られています。
マッカーサーの陸軍省宛報告書には「推定1800万人の生徒、40万人の教師、4万の学校は、占領政策の道具である」とありました。
この意図に沿った指令として、GHQの検閲により不適切と判断された情報は容赦なく書き換えられるか、墨塗りされました。教科書に国家主義や戦意を鼓舞する箇所があればそこを黒塗りにし、黒い線が引かれ、時にはページのほぼ全行が抹消されることもありました。
これは、まさに1984の真理省による歴史の改ざんを想起させます。
教育現場での価値観の転換もあったでしょう。
それまで外国への敵意を教えていた教師たちが、突如として民主主義を説き始める。「A」という視点での解釈を強制されていた事象が、一夜にして「B」という解釈を強制される。この急激な転換は、生徒たちに大きな混乱を与えたに違いありません。
まさに二重思考のような不自然さを感じます。
この歴史的事実は、思想や価値観の強制的な書き換えが、決して小説の中だけの出来事ではないことを示しています。私たちの社会でも、権力による記憶の操作は確かに、身近に存在し得るのです。
私たちは自分の記憶や認識を、本当に自分の意思で保持しているのでしょうか。それとも、知らず知らずのうちに、外部からの情報によって書き換えられているのでしょうか。この問いは、現代を生きる私たちにも重要な示唆を投げかけています。
言葉を奪われる恐怖、ニュースピークによる思考の支配
党は言葉そのものを破壊し、新しい言語体系「ニュースピーク」を作り出します。その原理は実に単純明快でした。
それは「表現するための言葉が存在しないものは、考えることすらできない」ということ。そして、それにより思考の範囲を狭めていくということ。
この原理により、人々の思考範囲を意図的に制限していきます。
人間の思考は言葉によって形作られます。私たちは言葉を使って考え、コミュニケーションを行います。
言葉は考えるための、意志を疎通させるための手段であり道具です。
ではその言葉自体が使い物にならないものだったとしたらどうでしょう。ニュースピークは言葉を破壊し、思想の根幹を破壊するものでした。
思想を表現する言葉が無くなる世界。まさにディストピアです。
巻末に付録として「ニュースピークの諸原理」という章があります。これは一見すると単なるおまけように見えてしまいます。そのため、アメリカでの出版時にこの部分は削除したらどうかという意見もあったようですが、作者であるオーウェルはそれを拒否したとされています。
それほどこの部分には重要な意味が込められており、学術書のような完成度の高さに驚かされます。
その中の例として、「自由な」を意味するfreeという単語について挙げられています。
ひとつだけ例をあげよう。『自由な/免れた』を意味するfreeという語はニュースピークにもまだ存在していた。しかしそれは「この犬はシラミから自由である/シラミを免れている」(中略)といった言い方においてのみ使うことができるのである。「政治的に自由な」或いは「知的に自由な」という古い意味で使うことはできなかった。なぜなら、政治的及び知的自由は、概念としてすらもはや存在せず、それゆえ、必然的に名称がなくなったのだ。明らかに異端性を帯びた語が禁止されたのは当然として、それに加えて、語彙の削減それ自体がひとつの目的であると看做され、絶対に必要不可欠とは言えない語は生き残ることを許されなかった。ニュースピークは思考の範囲を拡大するのではなく、縮小するために考案されたのであり、語の選択範囲を最小限まで切り詰めることは、この目的の達成を間接的に促進するものだった。
「自由な」という言葉と共に使えるのは「シラミ」だけ。私たちは「自由な」の後に続く言葉を考えてくれと言われればたくさん考えられます。
しかし1984の世界ではそうではないのです。
この極端な言葉の制限により、自由についての思考そのものが制限されていくのです。
さらに深刻なのは、過去との断絶です。言葉が書き換えられることで、過去の文献に記された「自由」の概念すら理解できなくなる。たとえ古い文献が残っていたとしても、ニュースピークしか知らない世代には、その真の意味を理解することすら不可能になってしまいます。
党は意図的に人々の思考や抵抗の可能性を秘めた言葉を消していきます。「名誉」「正義」「道徳」「国際主義」「民主主義」「科学」「宗教」などなど、多くの言葉が姿を消します。
なぜならばそんな概念は1984の世界に存在しないからです。
これらの言葉が消えていくということは、それらの概念について考えること自体が不可能になることを意味します。
言葉を失うことは、思考する自由を失うこと。そして思考の自由を失うことは、人間性そのものを失うことに等しい。ニュースピークは、人間の精神を根本から支配する、極めて巧妙で残酷な装置だったのです。
現代はもうディストピアなのではないか
気づいたらどんどん言葉がなくなっていき、思考ができなくなってしまう世界。過去に接続できなくなり、何も学べない世界。特定の人を常に攻撃し続けることに疑問を持たない世界。改ざんされた情報に溢れた世界。思考できなくなったことで間違った情報を盲目的に信じることだけでしか生きていけない世界。
そしてその社会を疑った瞬間徹底的な暴力により排除される世界。
そんな人としか繋がっていけない世界。
1949年に描かれた「1984」の世界。
もし私たちがこんな社会に生きているとしたら。考えただけでも恐ろしいものです。そして最も恐ろしいのは、ディストピアの住人が誰もその事実に気付いていないという点です。
本作で描かれた恐怖は、現代においてより巧妙な形で実現されているのかもしれません。
テレスクリーンはスマートフォンとなり、二重思考はメディアの報道として日常に溶け込んでいます。
1984の世界と同じように、私たちもまた自分たちが生きるこの世界がディストピアだと気付いていないだけなのかもしれません。
便利なツールやルールが増えるほど、人々は喜んで支配に従います。考えることを放棄した頭で作られた情報が蔓延し、オンライン上でのつながりが増えるほど逆説的に人は孤独になっていく。私たちは利便性と引き換えに、人間としての本質を徐々に失ってしまってはいないでしょうか。
2025年。
デバイスやメディアの発達は、確かに生活を豊かにしました。しかし、それらが発信する情報が真実とは限りません。むしろ、改ざんされた情報で溢れている可能性すらあるのです。
皆が一様にスマートフォンを見つめる風景。その画一的な表情の中に、私たちは人間性の喪失を見出すことができるのかもしれません。
個人の幸せ、自己の本質、社会や世界の真理。これらの問いに向き合い続けることなしには、私たちはいつの間にか自我を失い、真のディストピアの住人となってしまうのではないでしょうか。
1984は警告でした。
しかし、私たちは既にその警告を超えた世界に生きているのかもしれません。